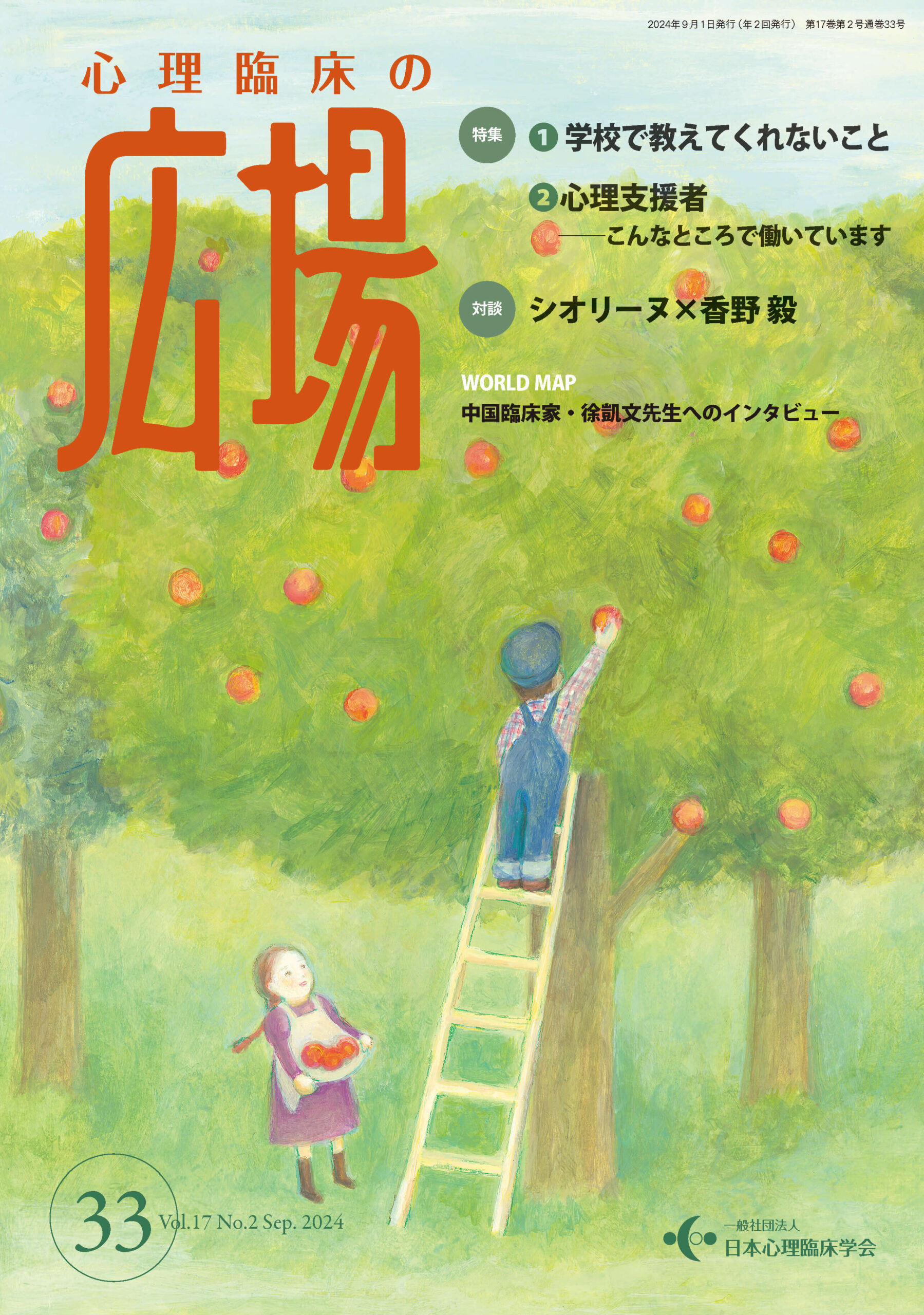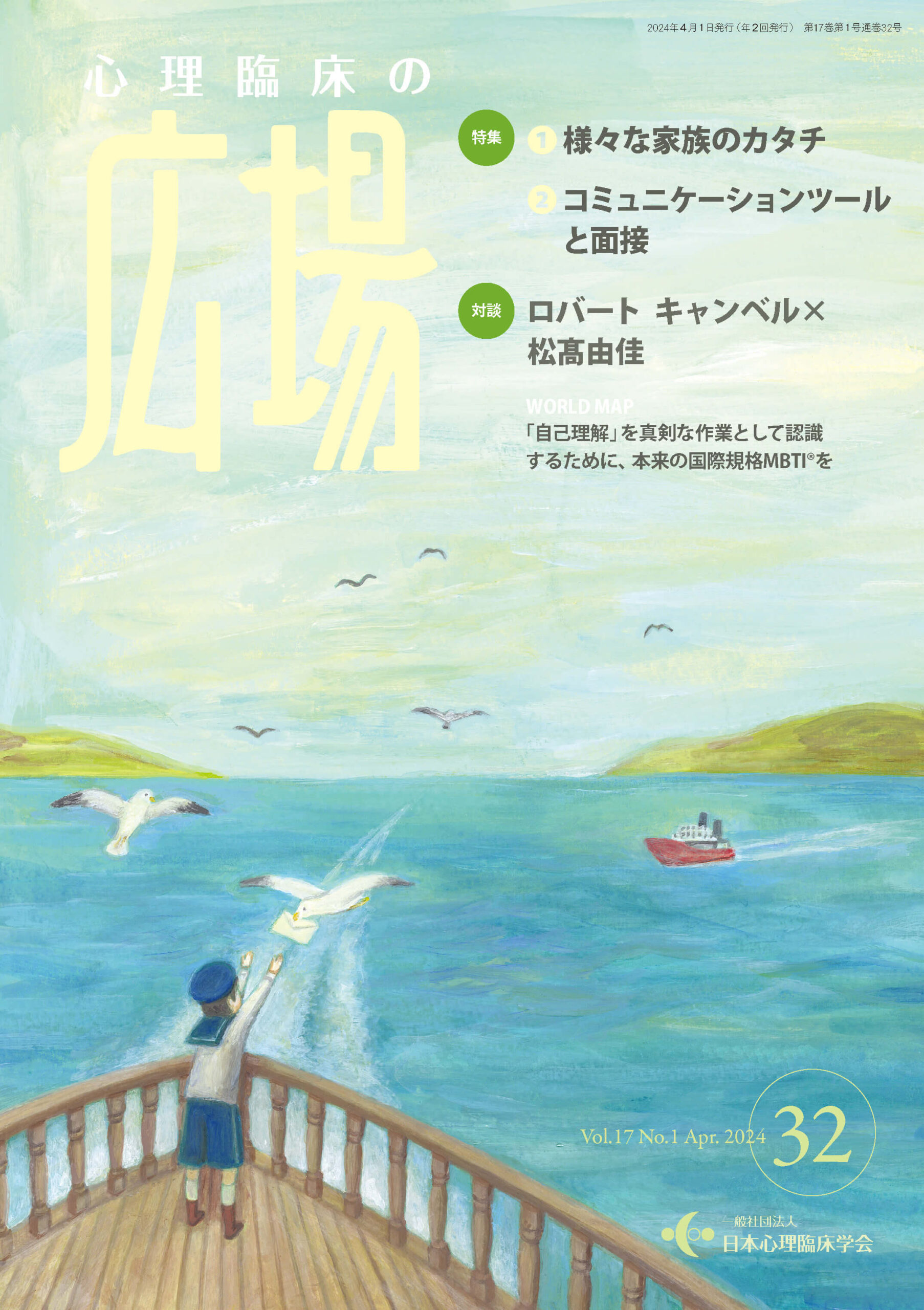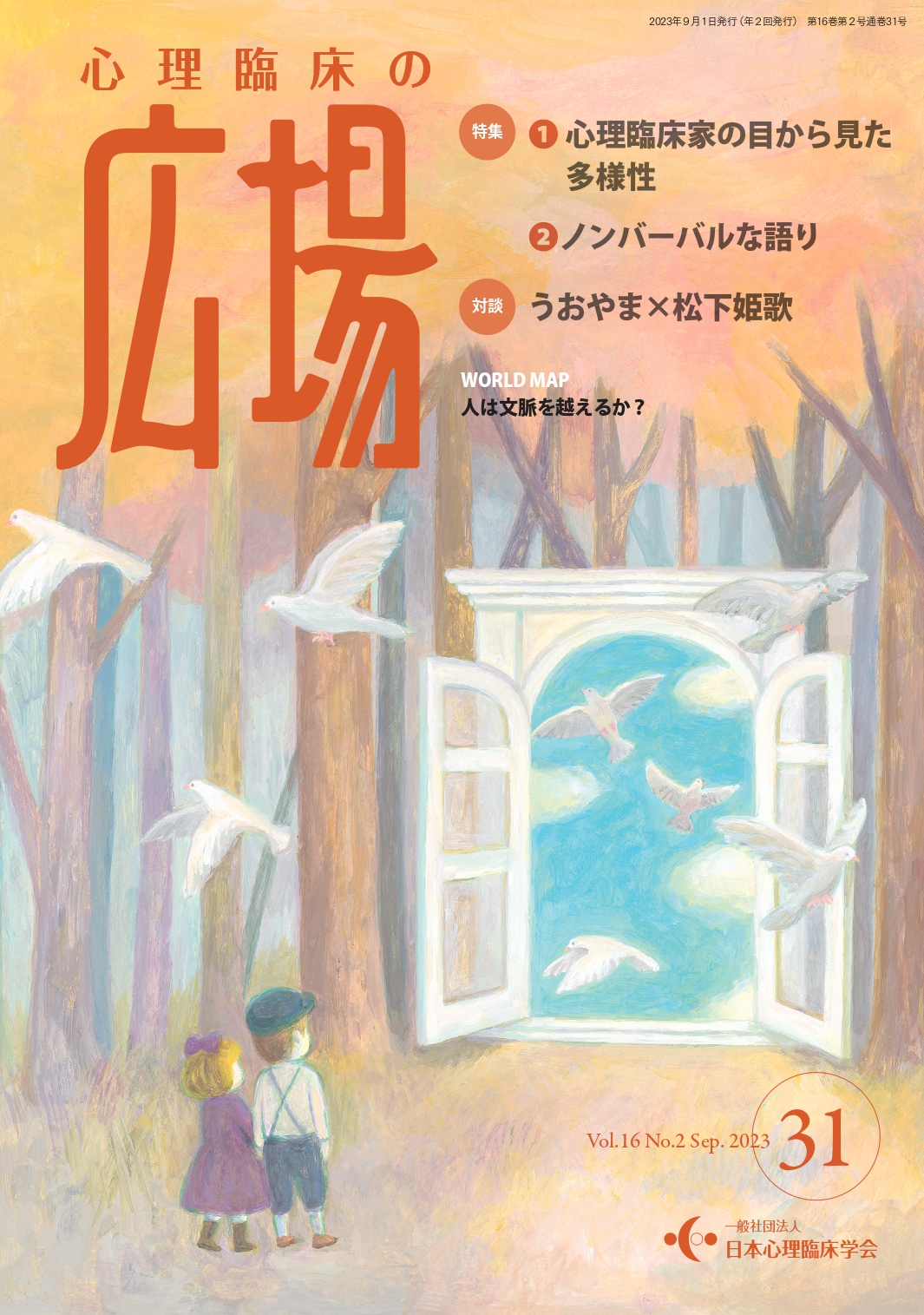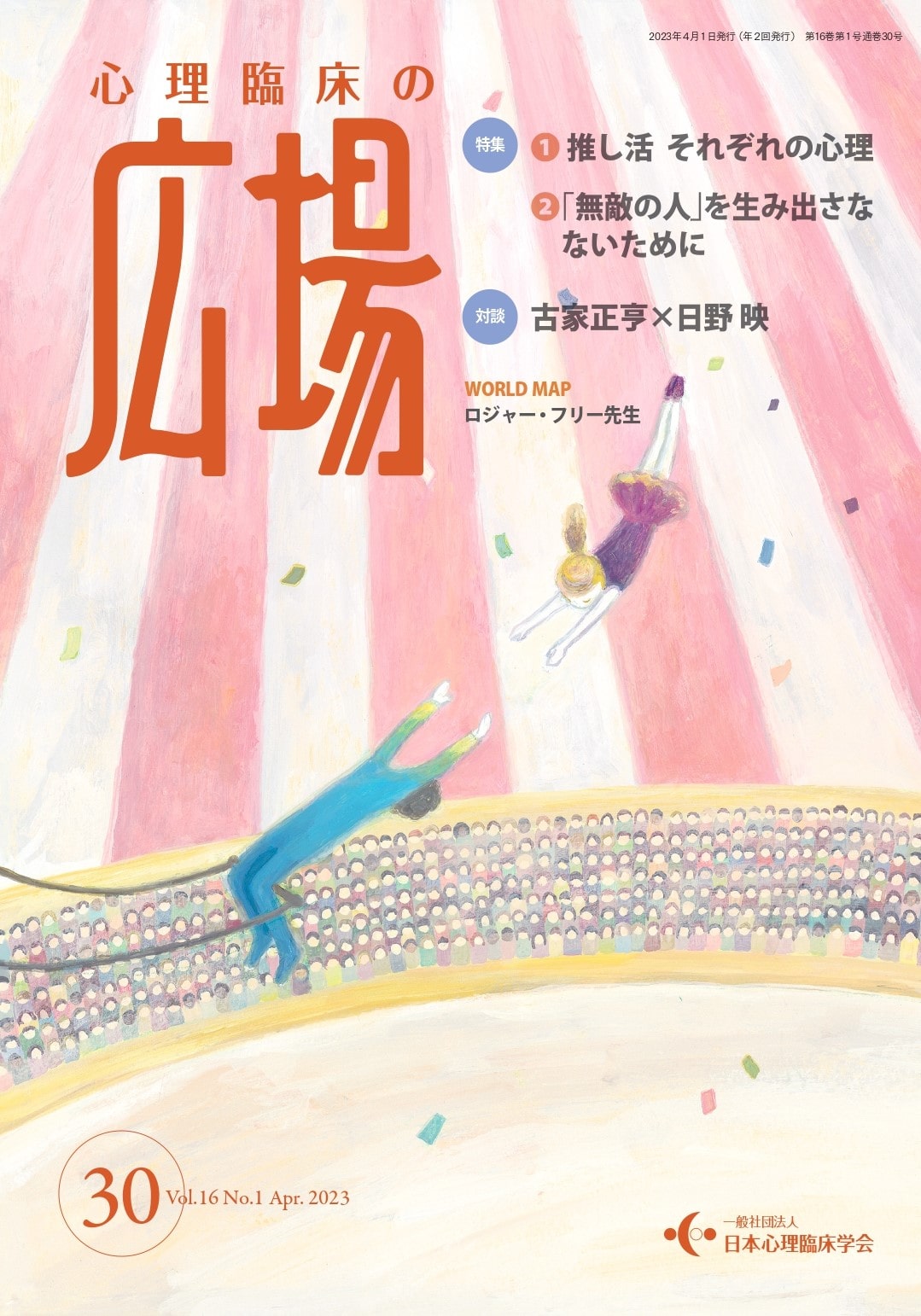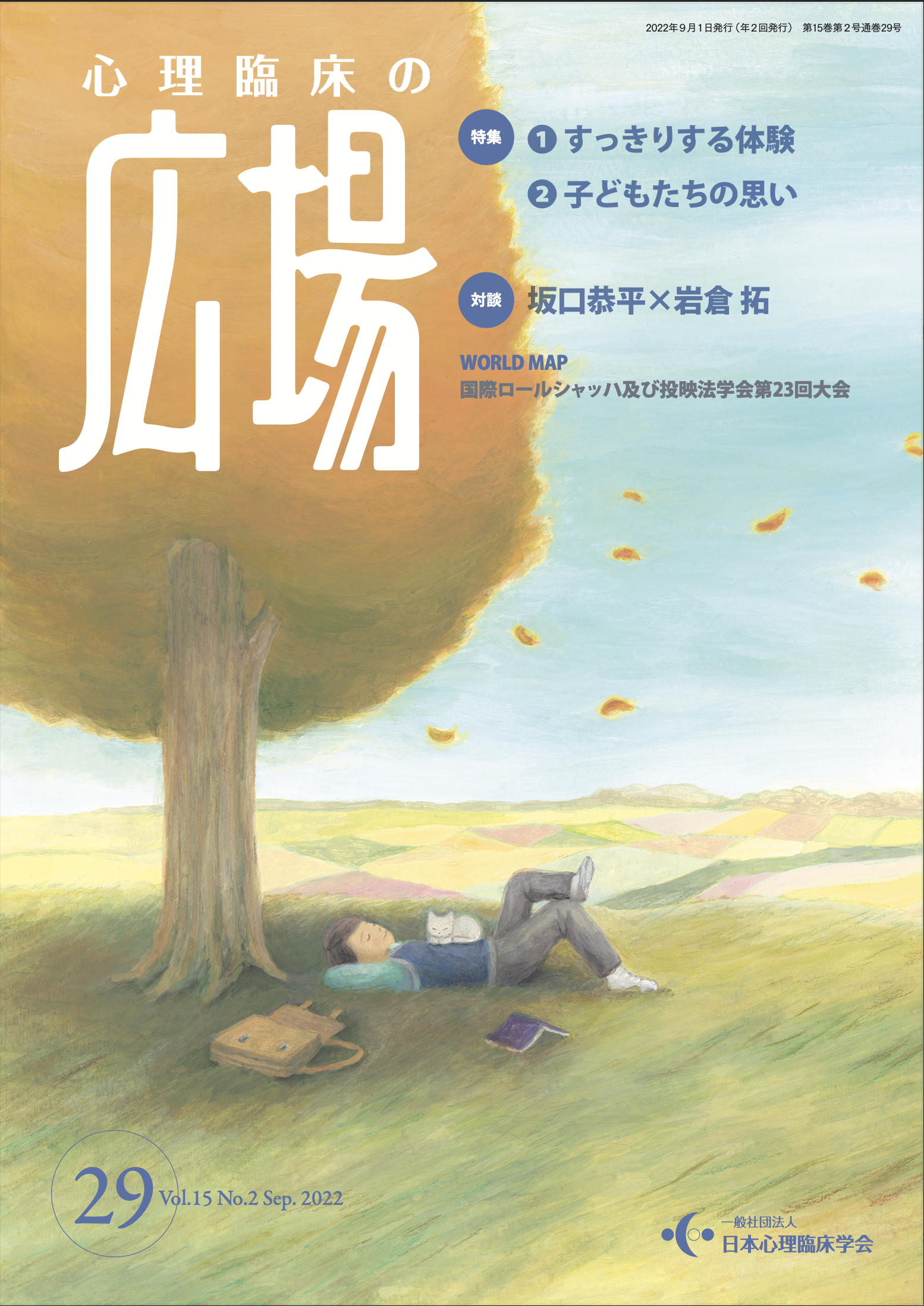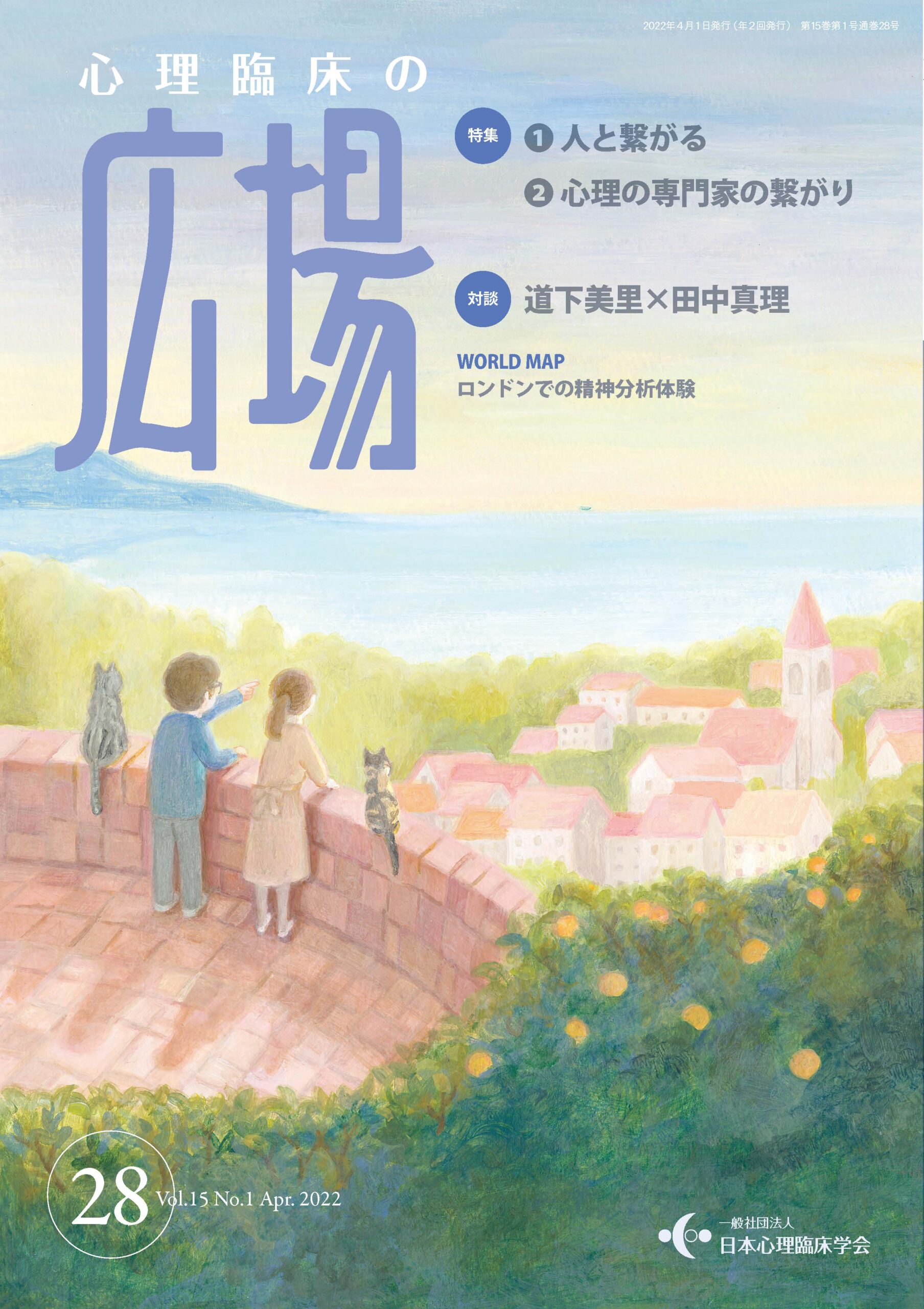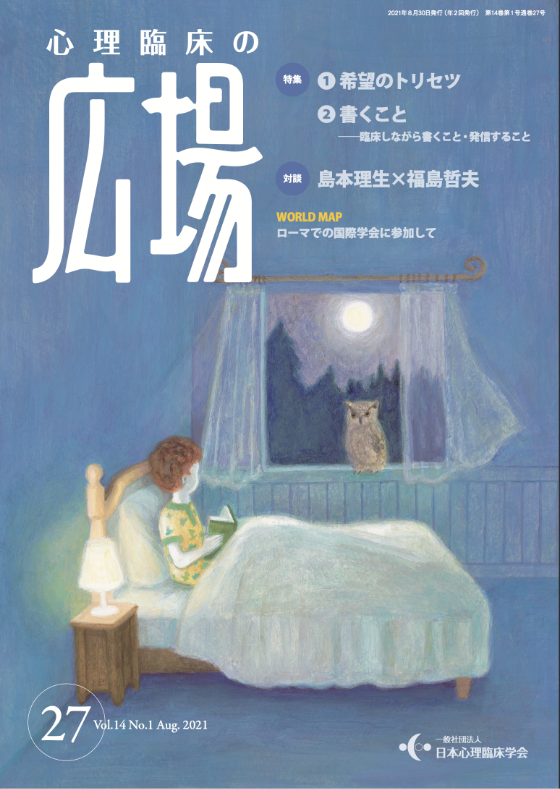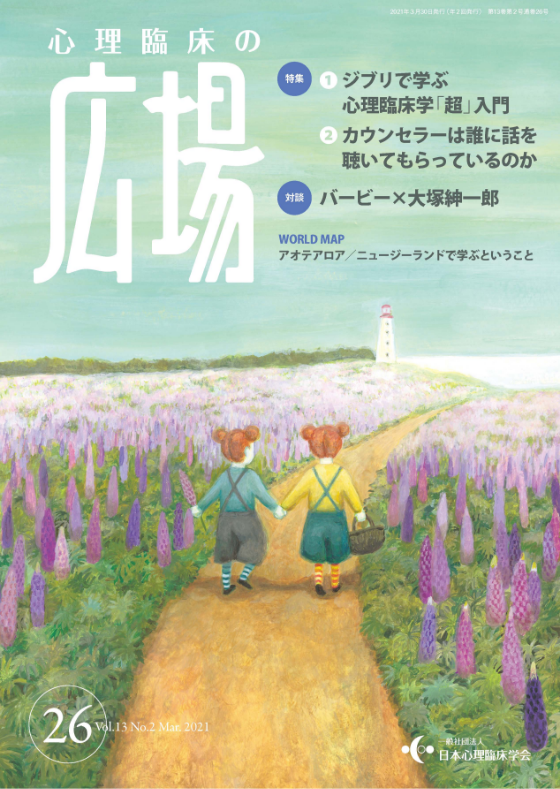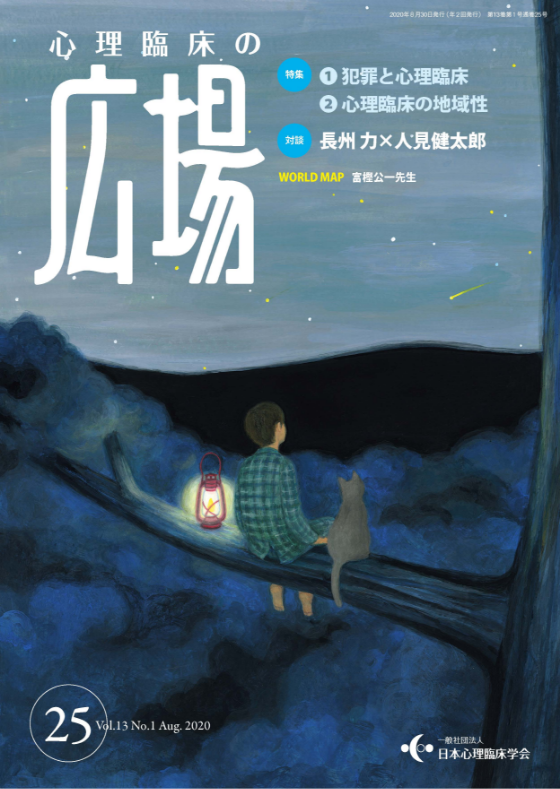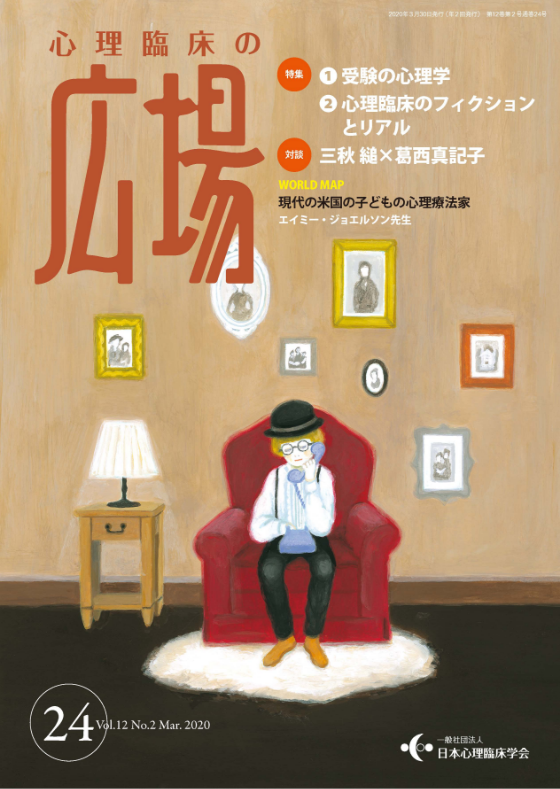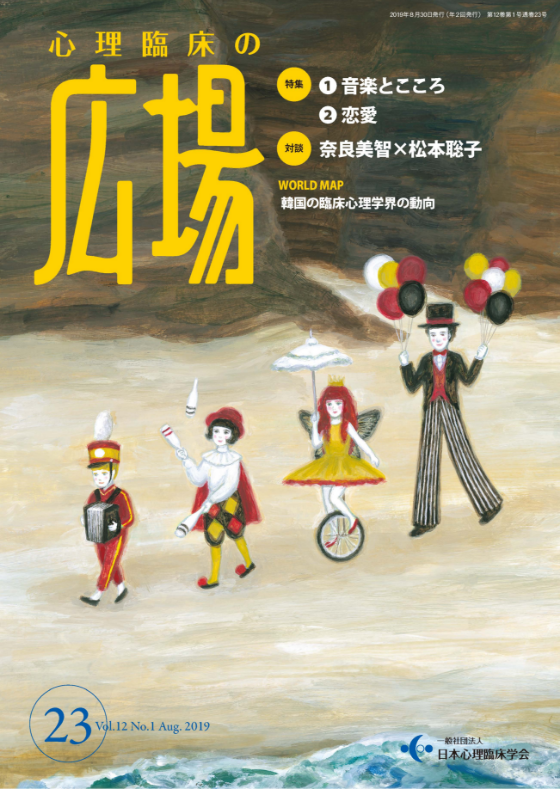大学院生だった頃、論文や本を書いたり、授業や講演をしたりしていると、臨床が下手になる、と周囲では盛んに語られていた。頭ばかりを使っていると、心が使えなくなり、大人数を相手にしていると、目の前の個人がわからなくなる。机上の空論によって、面接室の現実が見えなくなる。真の臨床職人は寡黙である、と饒舌に語られていた。
当時の私は「まったくそうだなぁ」と思っていたし、今でも一理あるとは思うのだけど、年を重ねる中で、別のリアリティ「も」あることがわかってきた。本を書いたり、授業をしたり、あるいはSNSで呟いたりすることで、クライエントに伝わる言葉が少しずつ増えているような気がしているからだ。
みんなそうだと思うけど、私もいつもビクビクしながら文章を書いている。今もそうで、書いては消してを繰り返しながら、少しずつ前に進んでいる。
ビクビクするのは、自分の言葉が読者の心の傷ついた部分にどう響くかを想像するからだ。「炎上を恐れる」という俗な言い方もできるが、炎上とは傷つきの存在に無知なままに、傷つきに触れたときに起きることであるのだから、ビクビクは臨床家のベーシックな感性であり、知性だと思う。
言いたいことを言うだけではなく、受け取ってもらえるように言うこと。その勇気ある試行錯誤の中で言葉は鍛えられていく。思えばそれは、面接室で私たちが日々やっていることでもあるはずだ。
言葉とは、風に乗った紙飛行機のように、コントロールできずに、見知らぬ遠くまで届いてしまうものだ。だからこそ、どこに届いても責任を取れる言葉を紡ぐ必要がある。
厄介で、苦労の多い仕事だけど、その報酬はある。臨床で使える言葉が増えるだけではなく、それは社会を小さく変えうる。届いた言葉を受け取った誰かが、自分の傷つきと、あるいは周囲の傷つきと、しばし一緒に居られるようになるかもしれないからだ。その積み重ねで、社会にはケアのための余白ができていく。
そのために、私たちはスクールカウンセラー便りを書き、本を書き、SNSで呟き、そしてこのような広報誌を作る。ビクビクしながら作った柔らかい言葉たちを、風に向かって、放つ。もちろん、ビクビクと風を読みながら。