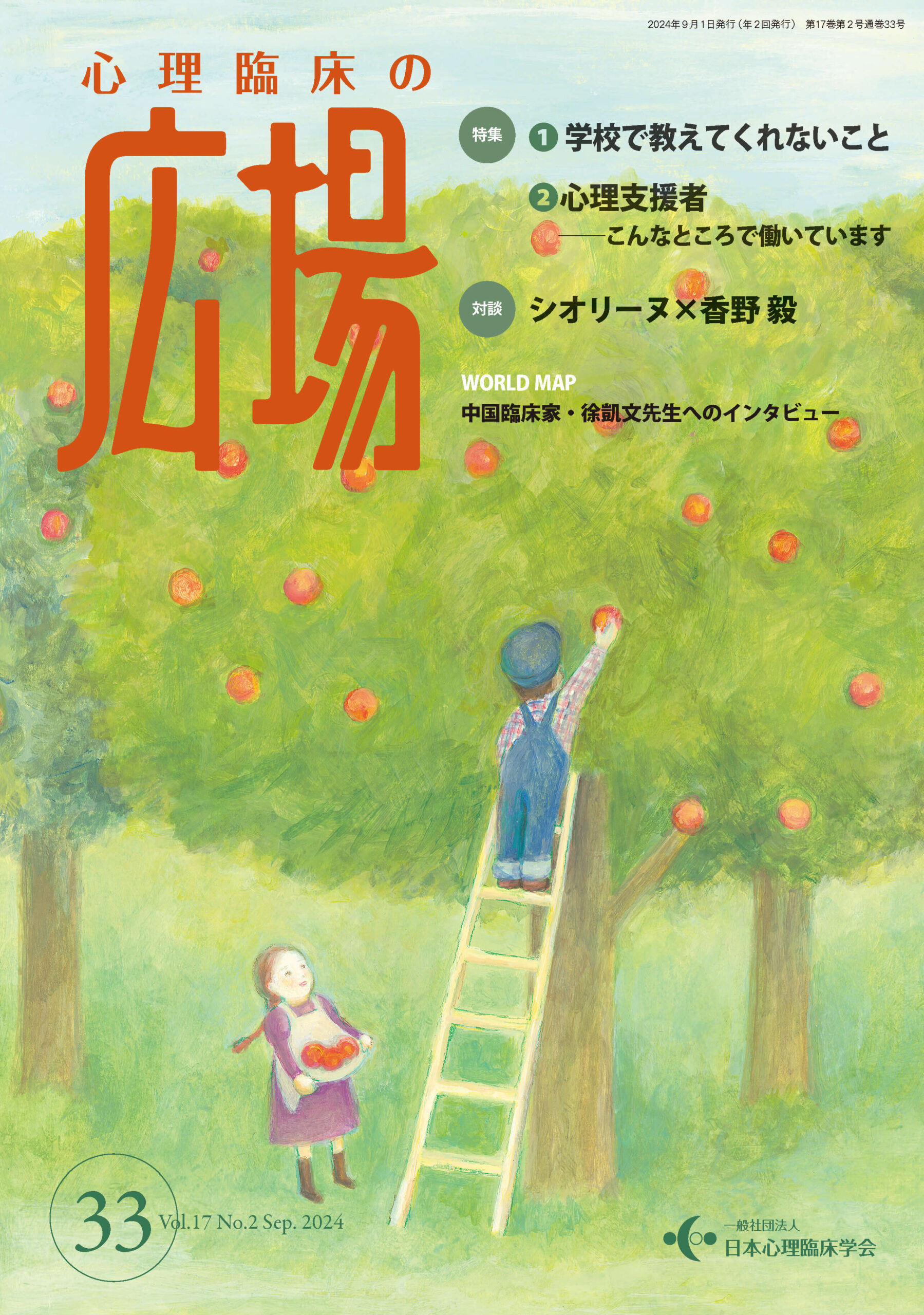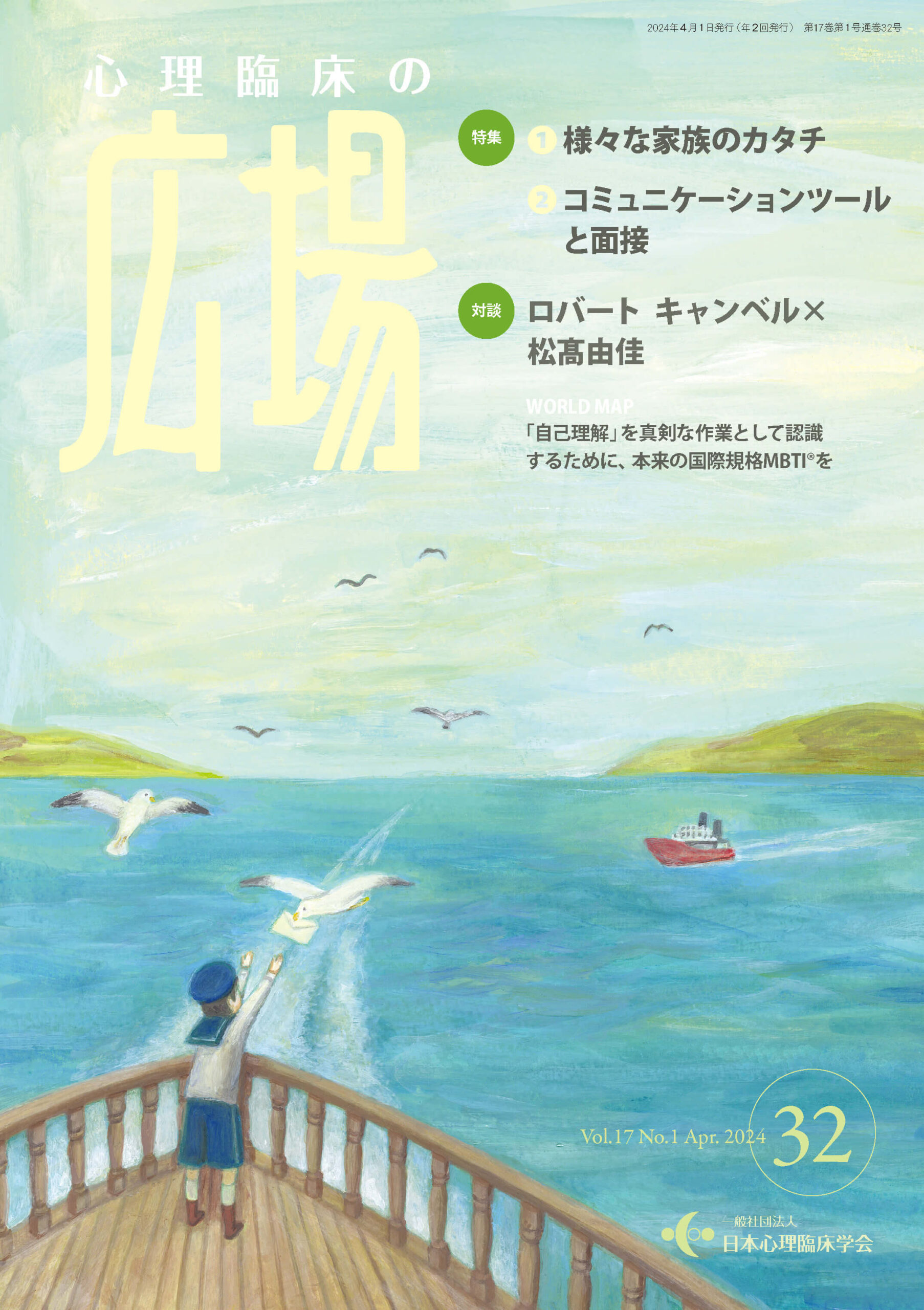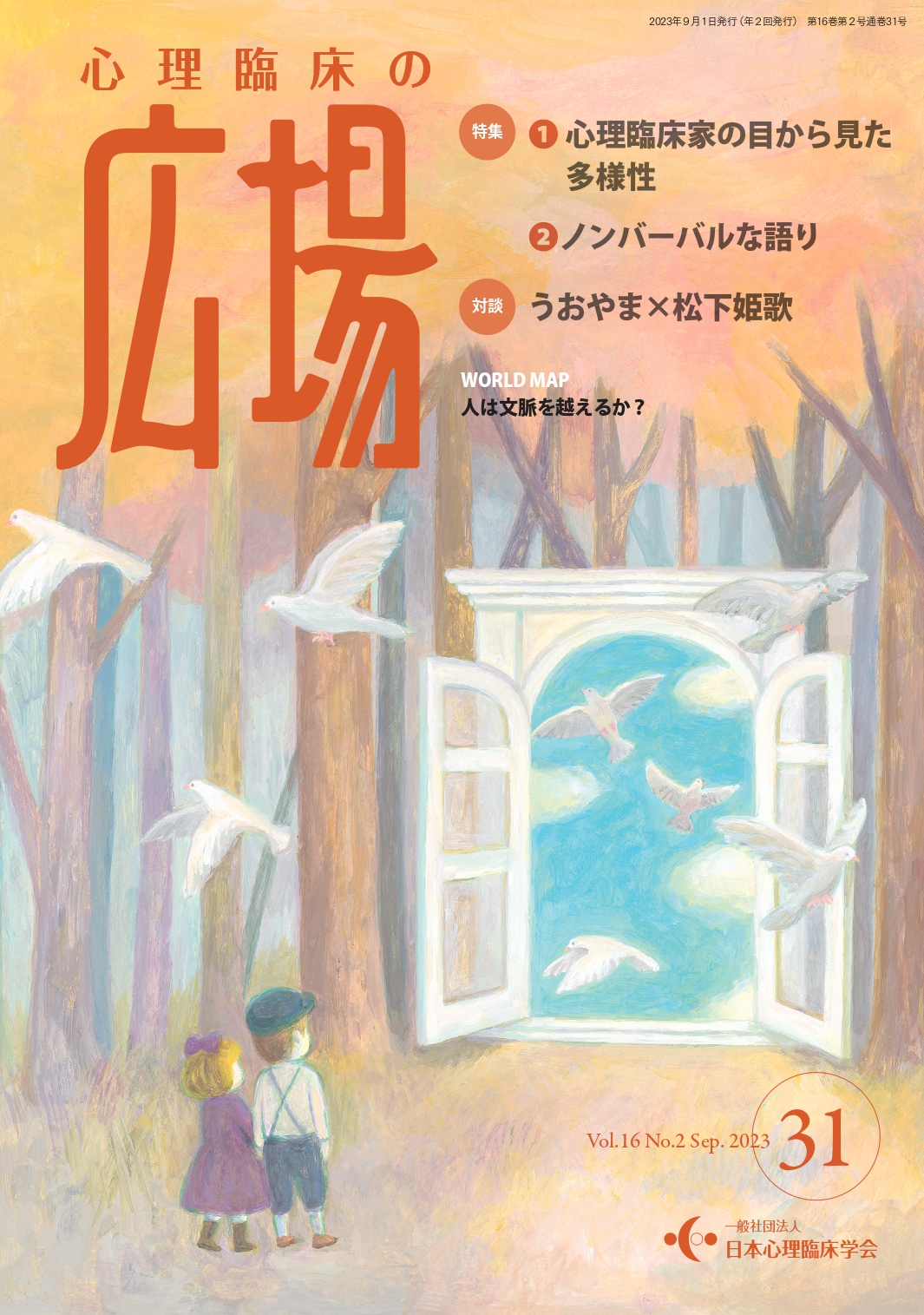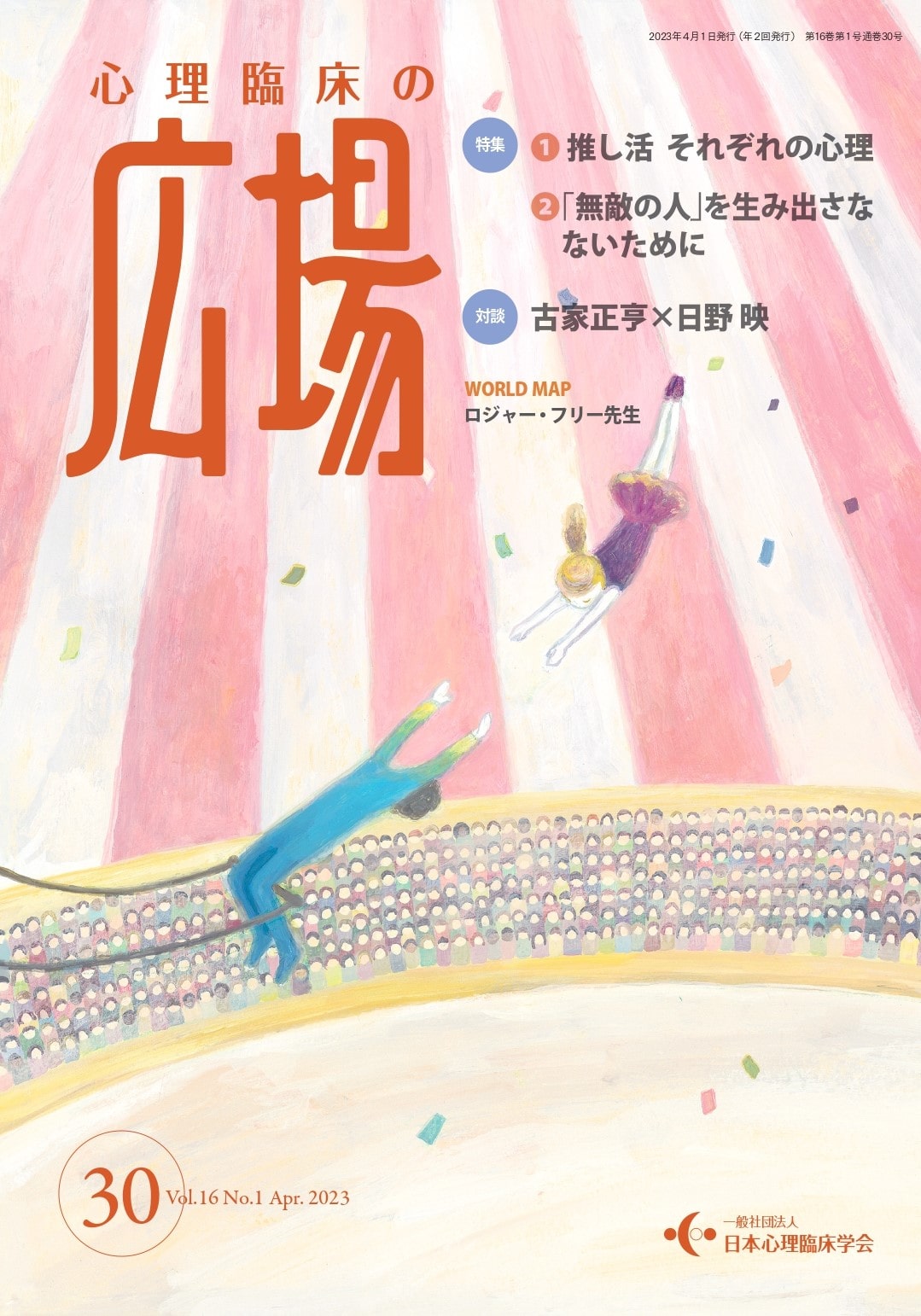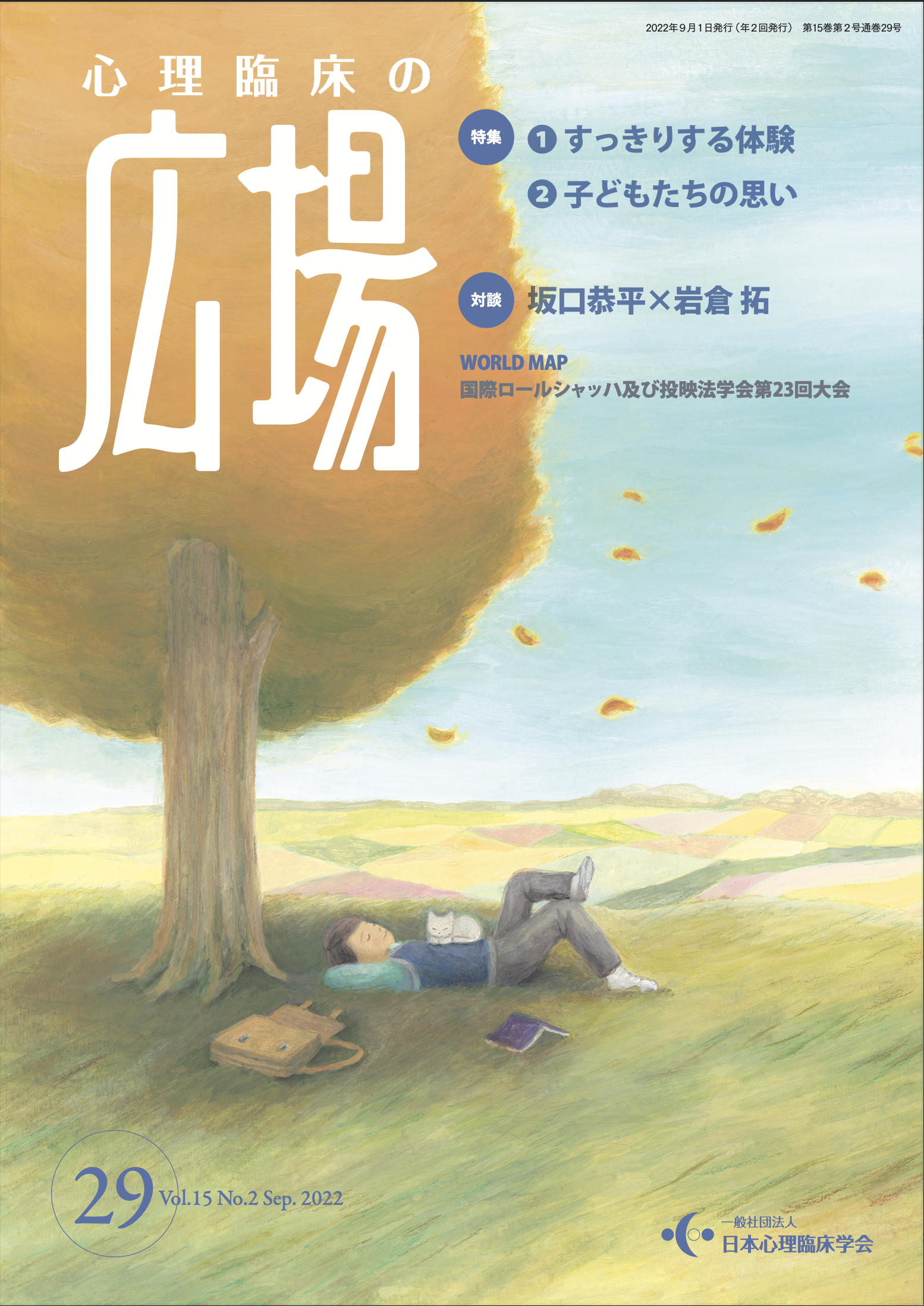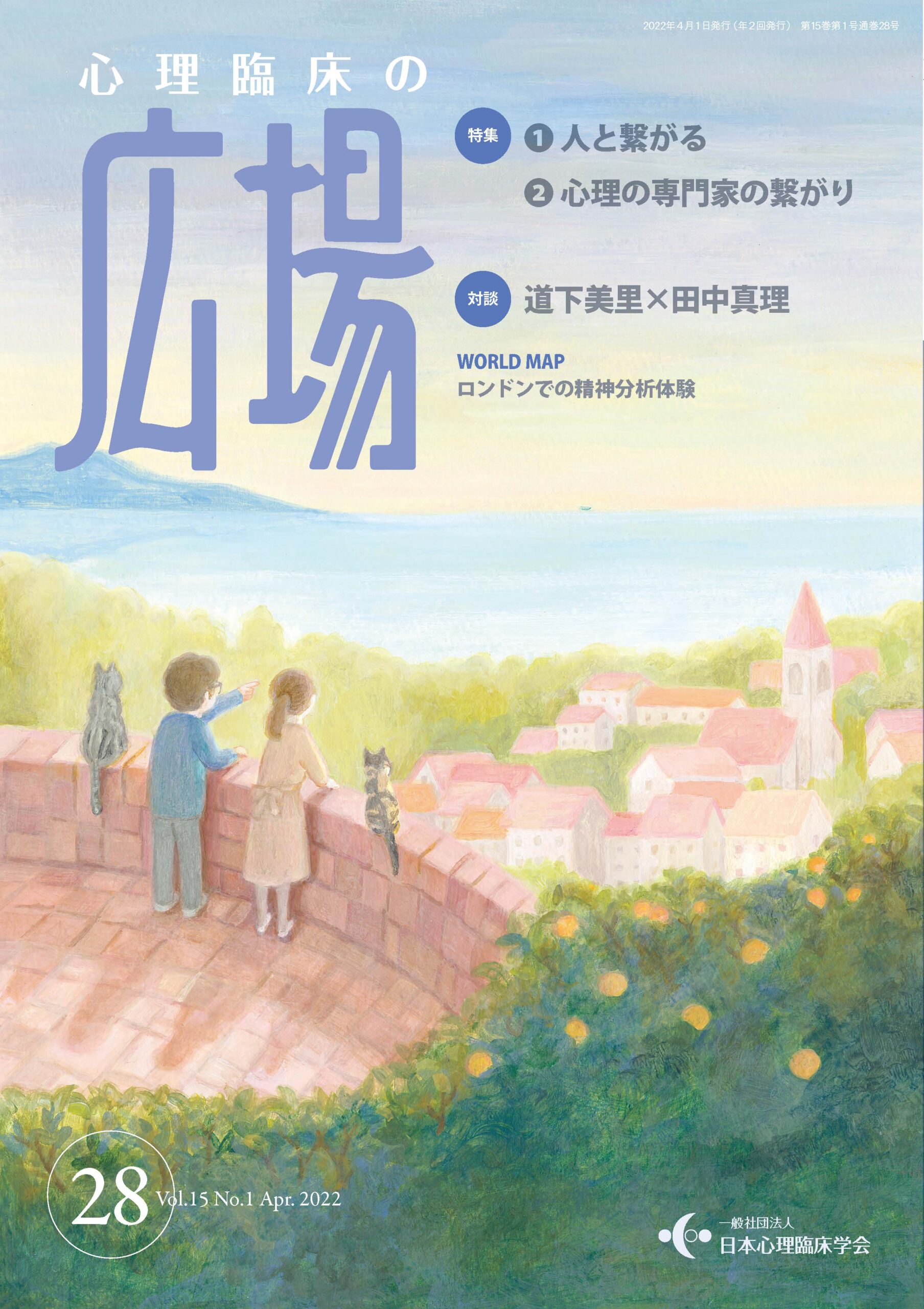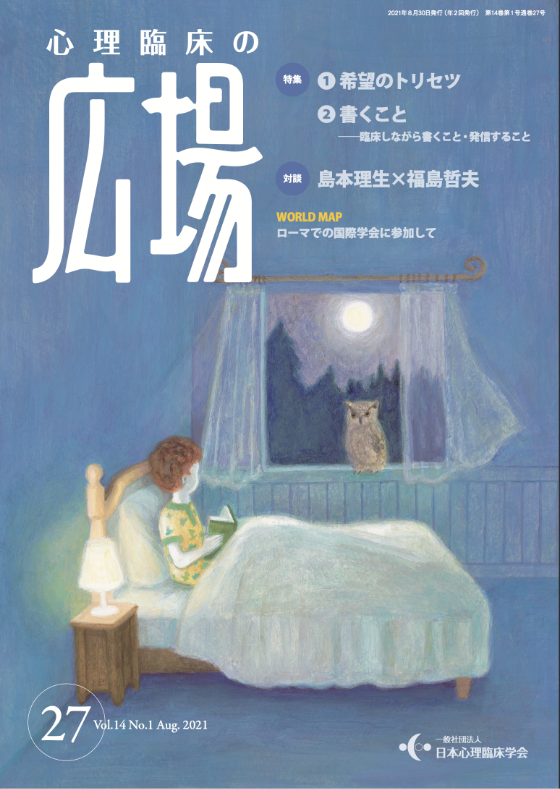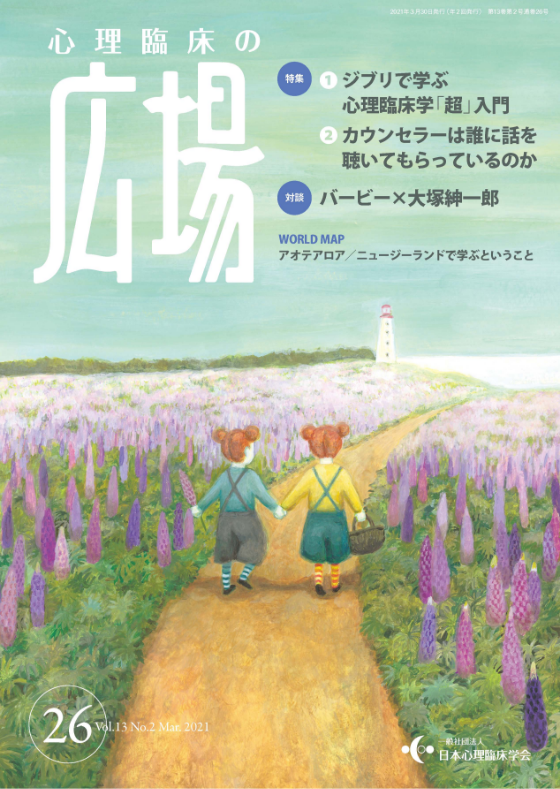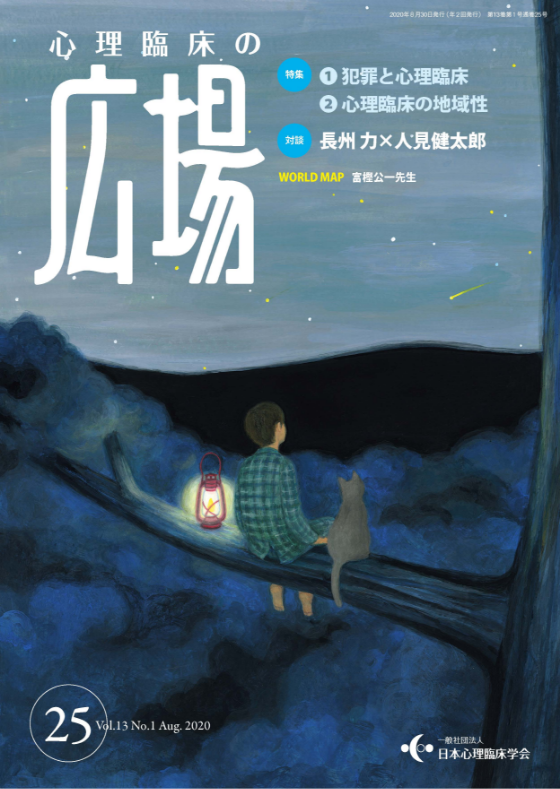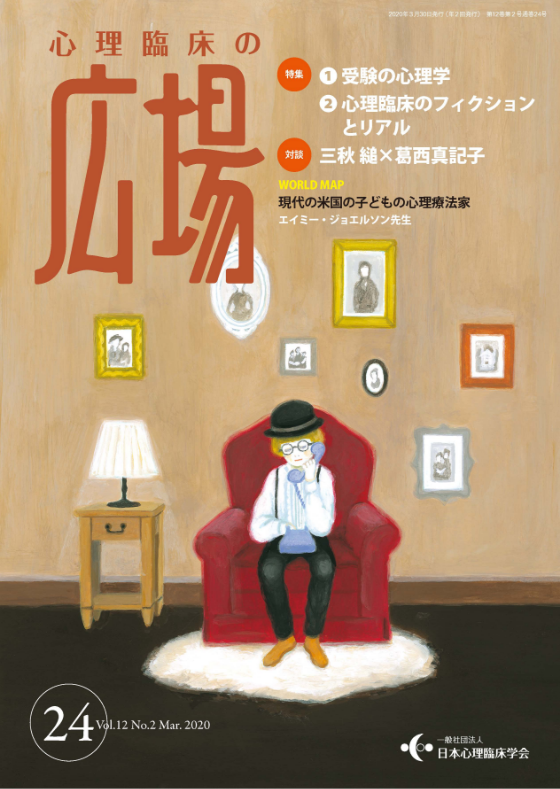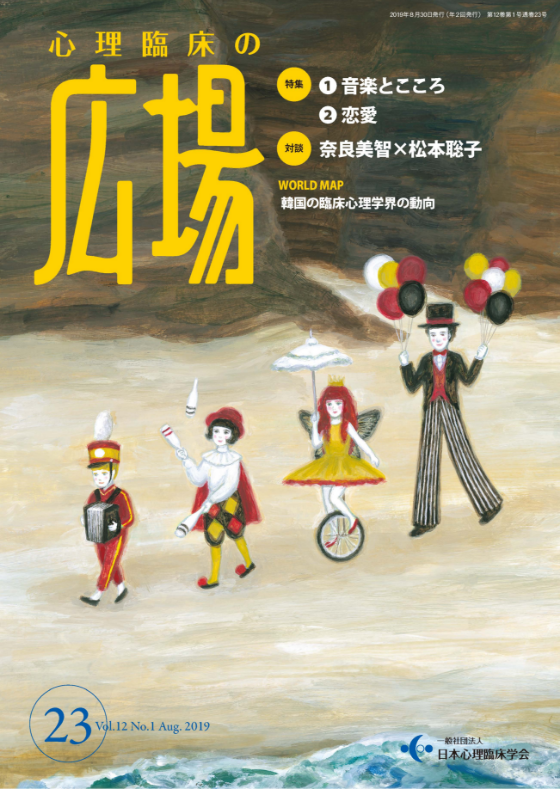編集後記・事務局だより
編集後記
今号では自分も関心をもっている日常の世界に関するテーマを選ばせていただきました。心の専門家だけでなく、広い読者層を対象とした本誌の特集を担当させていただくことはとてもやり甲斐があり、楽しい役割となりました。巻頭対談では、ランニング系ユーチューバーとして活躍される三津家貴也さんからお話を伺いました。走ることを通して身体の健康に向かうだけでなく、人とつながって、喜びを共有し、オンラインとオフラインのコミュニティーが作られていくという世界観に大きな魅力を感じました。
特集1では、食べることと心のつながりを掘り下げました。食べることに関心をもたない人は少ないでしょう。食についての情報が日常に氾濫して、お腹が減っていないときでも「今日は何を食べよう」と考えてしまい、食と離れることはあるんだろうかと思うほどです。本特集が「食」と「こころ」に関する日々の疑問について答え、さらに食べることを豊かなものにするきっかけとなれば幸いです。
特集2は、様々な傷つきからどう立ち直っていくのかということに着目しました。こころの怪我は、本人にも周囲の人にも傷ははっきりと見えません。目に見えないからこそ、傷の痛みや深さが本人さえもつかめず、その上にさらに傷を負うようなこともあるでしょう。この特集が自身の、そして周囲の人たちの傷に気づいて、それを癒すための手がかりとなると幸いです。「当事者のための心理教育」のコーナーでは「恥(シェイム)」を取り上げました。恥ずかしいという感情に悩まされることは多くあります。その一方で、恥ずかしいという気持ちは自分のプライバシーを守るという重要な役割ももっています。そんな「恥」と付き合っていくためのヒントがたくさん詰まった記事になりました。
本誌の記事作成にご協力くださった皆様に感謝申し上げます。そして、多くの読者の皆様が本誌を手に取り、これらの誌面から日常のこころのあり方について新たな気づきを得ていただければ嬉しく思います。
(広報委員 岩壁 茂)
事務局だより
2025年度もあと半年になろうとしています。皆様には新しい職場で、あるいは、引き続きさまざまな現場での活動にまい進されていることと思います。本誌「心理臨床の広場」は、学会員に留まらず心理臨床に関心をお持ちの皆様にお読みいただけるように、年に2回発行してきました。早いもので、今号で第35号となります。本誌がお手元に届く頃には、日本心理臨床学会第44回大会の開催の頃と思います。多くの学会員の皆様にご参加を頂きたく思います。
さて、わが国の経済状況といえば、コロナ禍からのいくらかの回復はしたものの、国際情勢を反映して、未だ不安定な状況にあります。このような生活状況における多角的な支援が必要となっています。こころの支援も同様です。国際的には、社会的脆弱性をえる人びとに対して、暴力や子育て上の問題も含めて喫緊の課題が山積みです。今年度の大会では、「心理臨床にとって伝承とは何か――学問的に対話する」というテーマをもとにして、私たちが先達から受け継いで来た「心理臨床のこころ」について、再考できる機会になればと思っております。特に、布柴靖枝先生(文教大学/国連NGO国内女性委員会副委員長)には、「社会的脆弱性をかかえる人々への支援――家族支援から国際連合(国連)の活動を通して」と題して、特別講演を頂きます。一般公開になっていますので、是非世界情勢を知り、子どもたちの未来について、そして社会的脆弱性を抱える人びとに対しての支援を考えられたらと思っております。
今後も私たち日本心理臨床学会の会員が、学術雑誌や本誌を通して、大会の会場やオンラインで、共に討議できるように、藤原勝紀理事長をはじめとして、理事一同励んで参りたいと思います。また、学会運営にお気づきの点などがございましたら、事務局にご一報いただけますと幸いです。そして本誌に対しましても、ご意見を頂けましたら幸甚に存じます。
(財務担当理事/大会委員長 髙橋靖恵)
広報委員会より
前号(34号)の巻頭対談の中で出てくる架空事例について、「架空事例である」という注釈を欠いたことに関して、編集段階での確認が十分でなかったことをお詫び申し上げます。以後、編集にさらに注意して参ります。