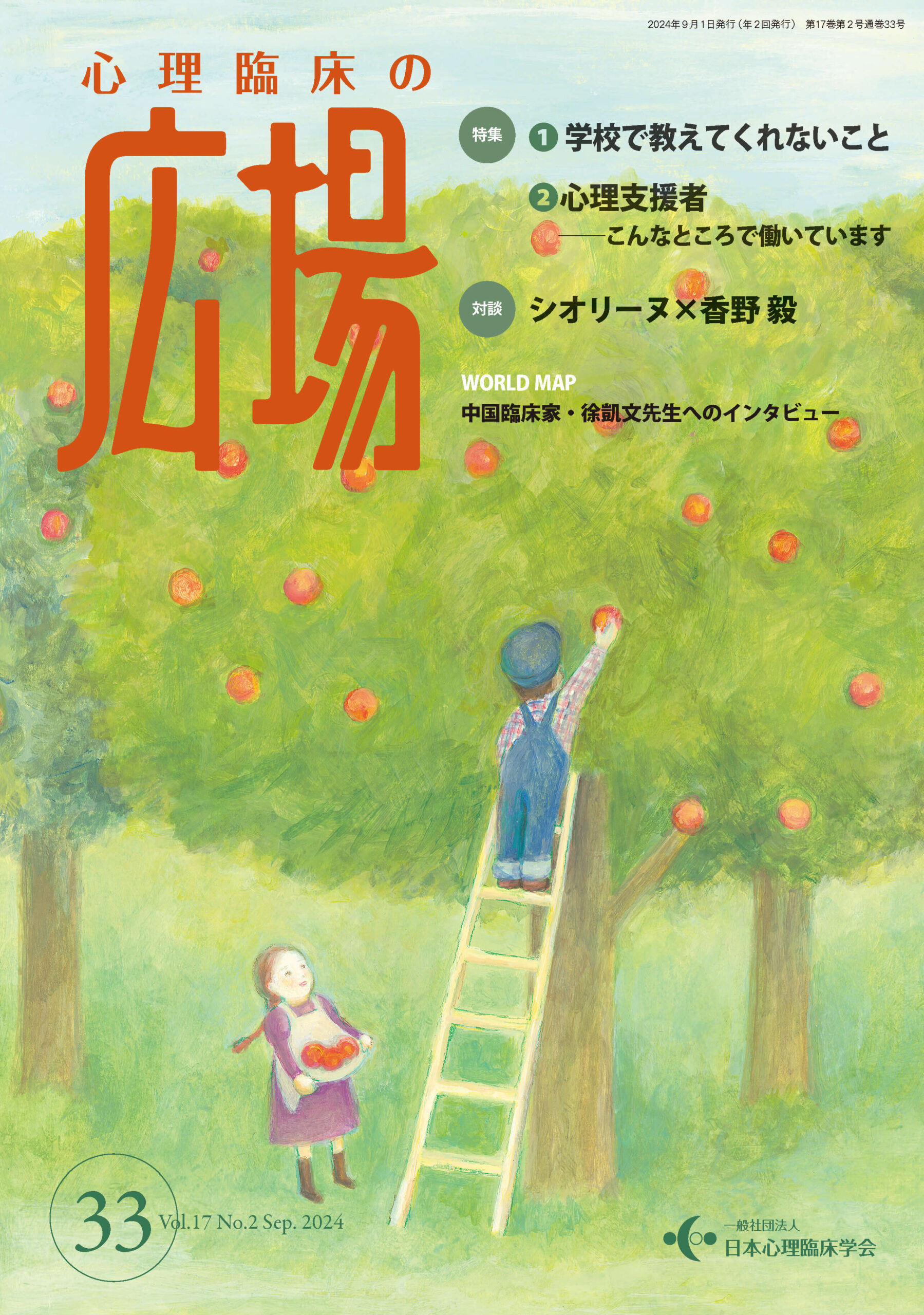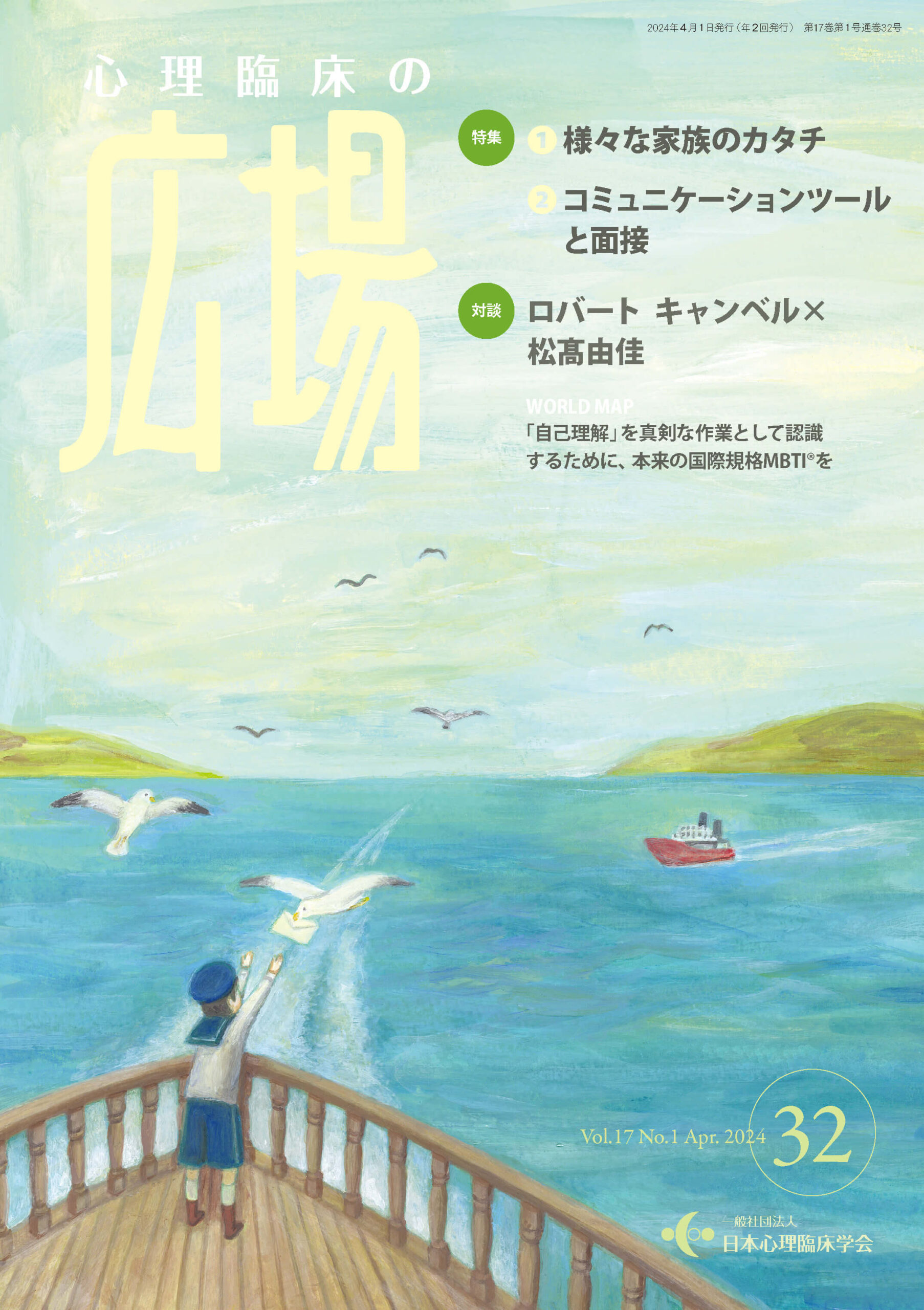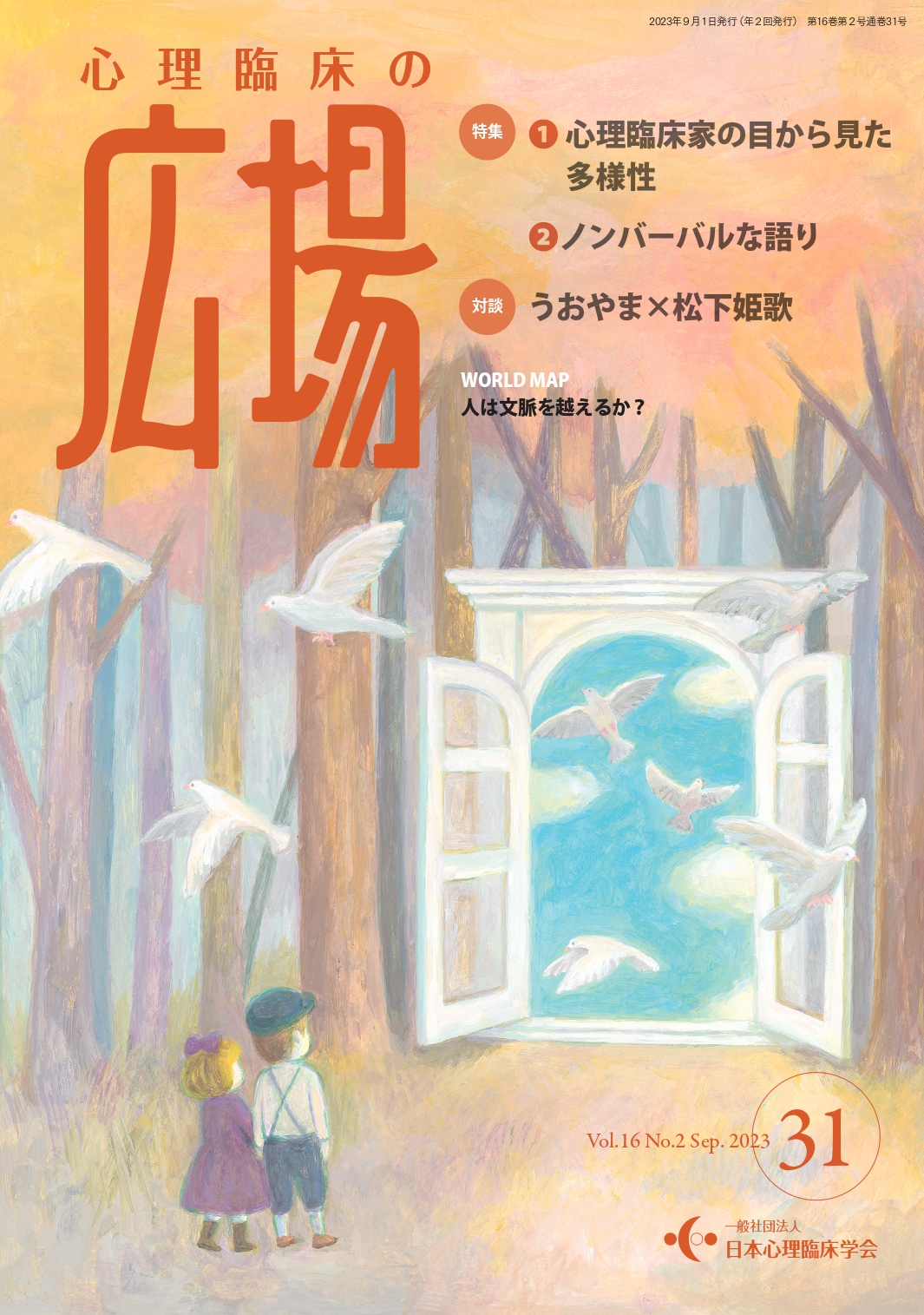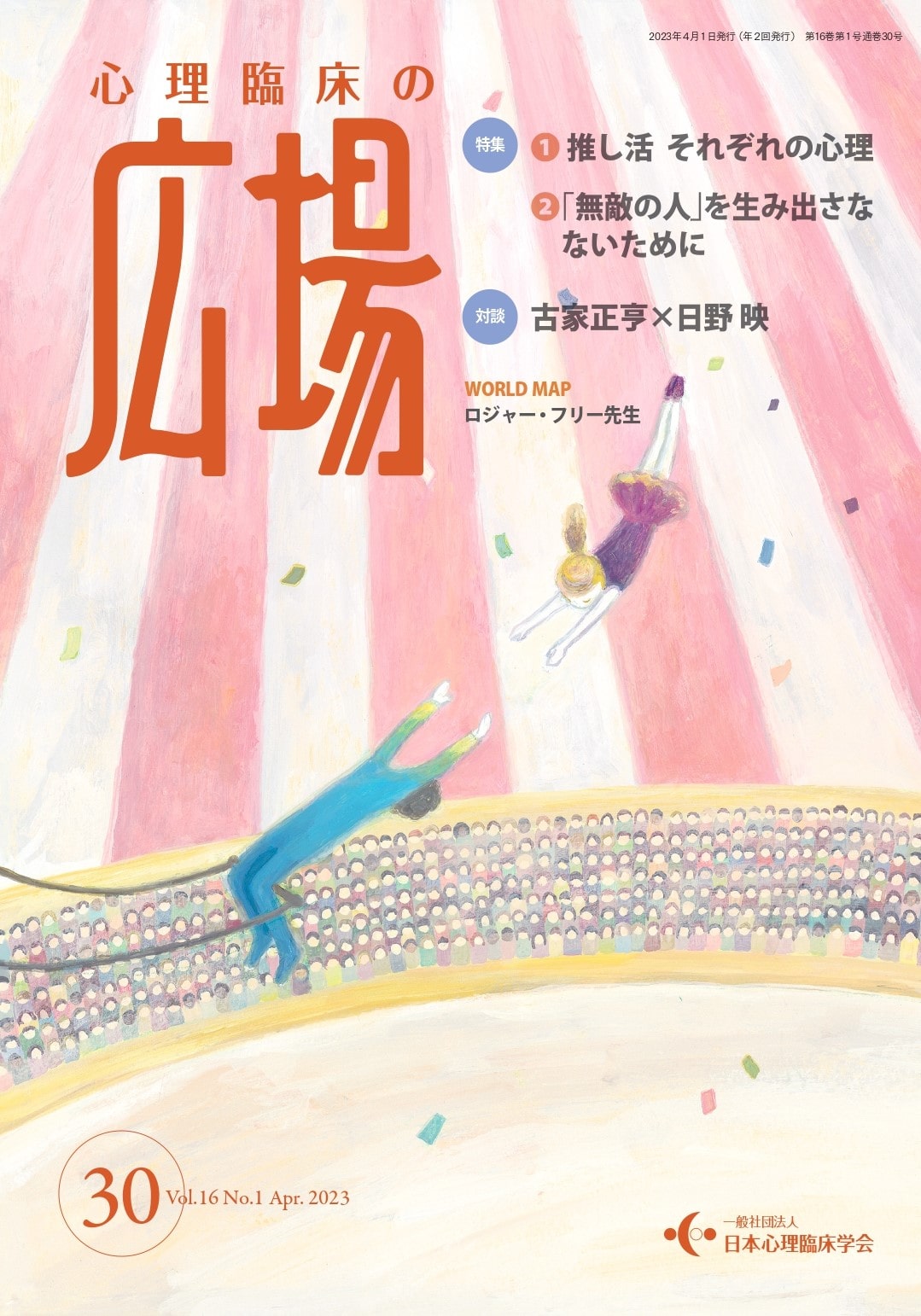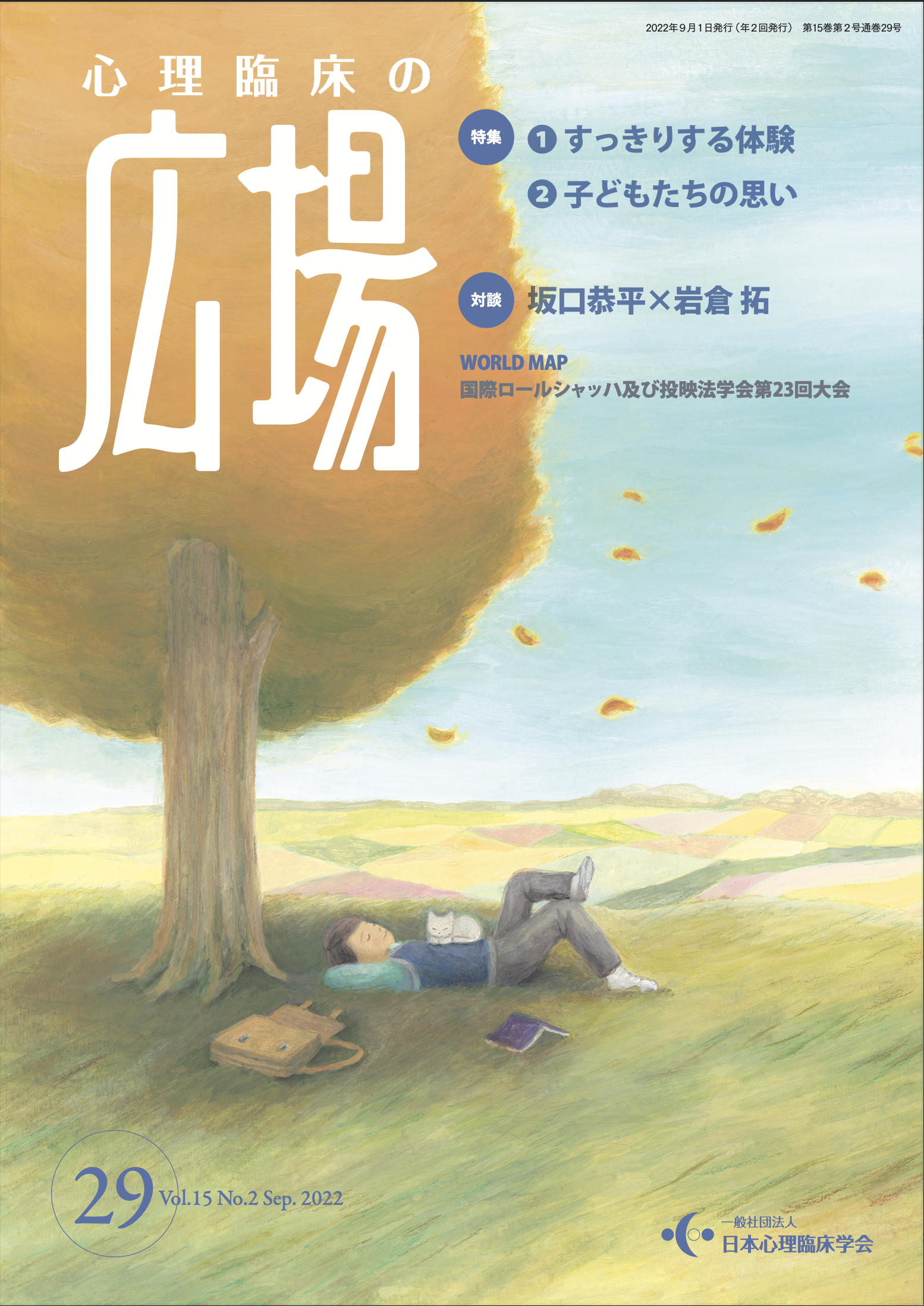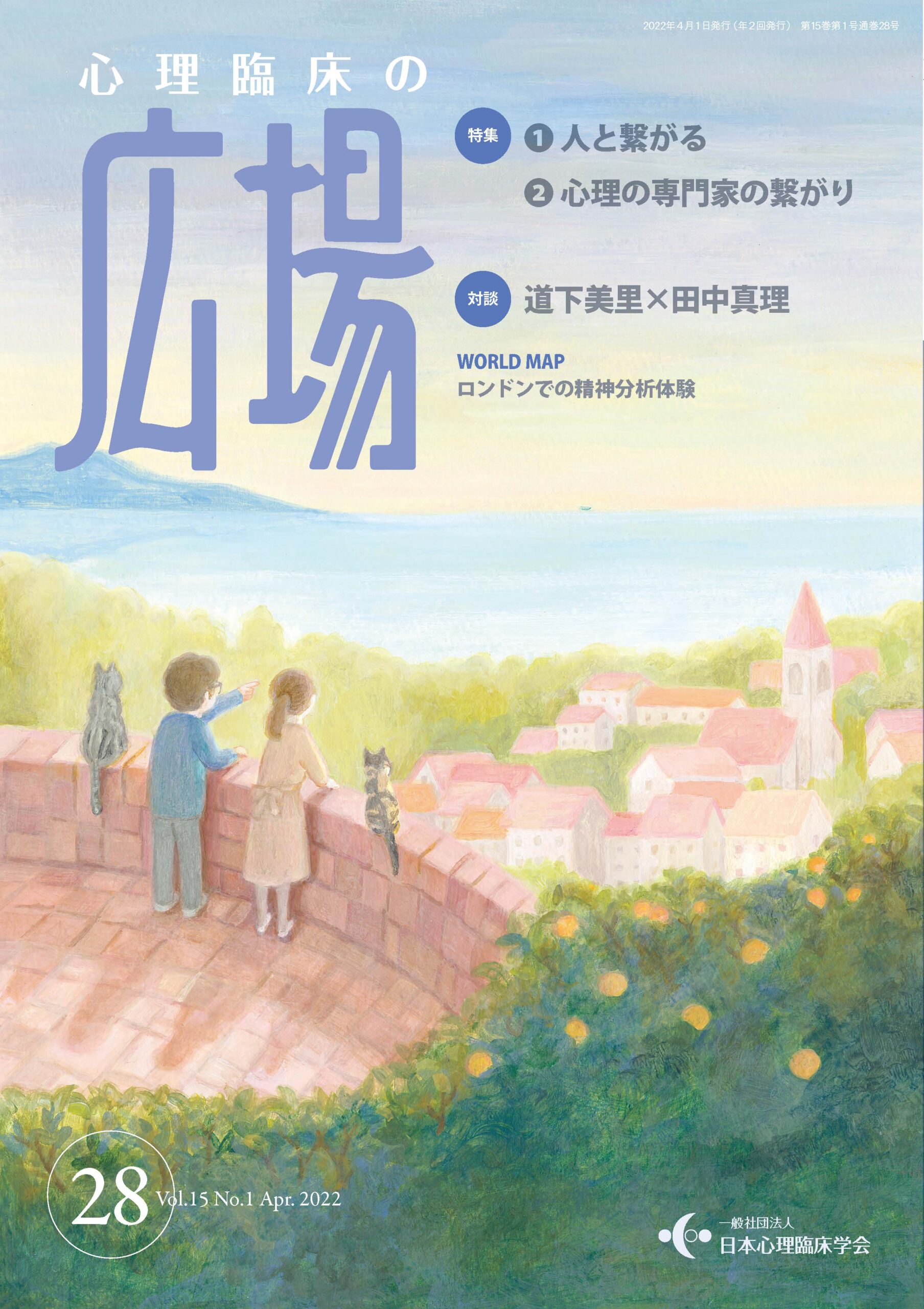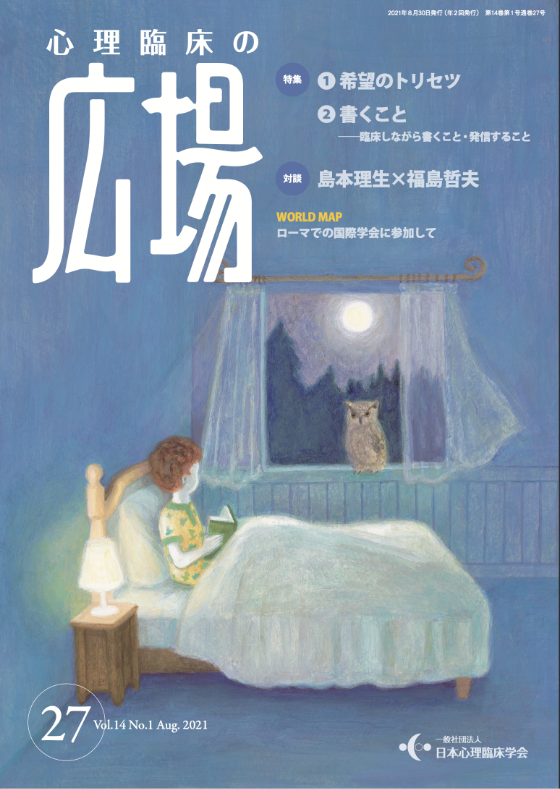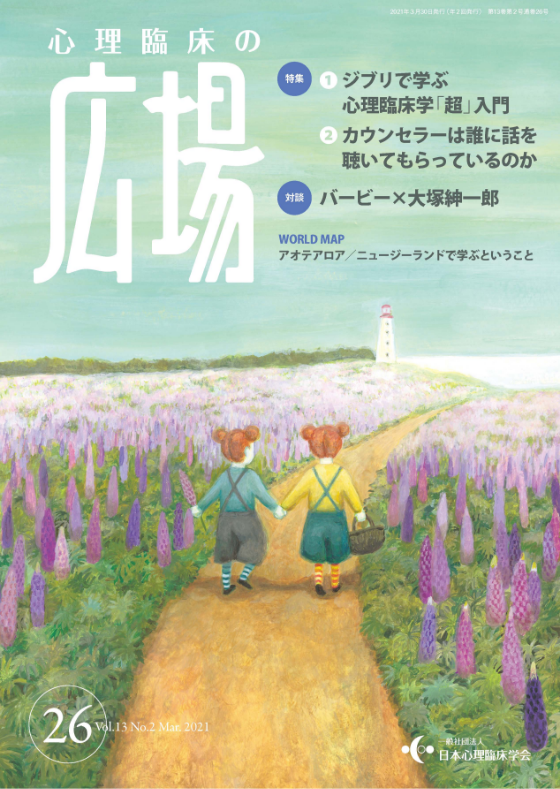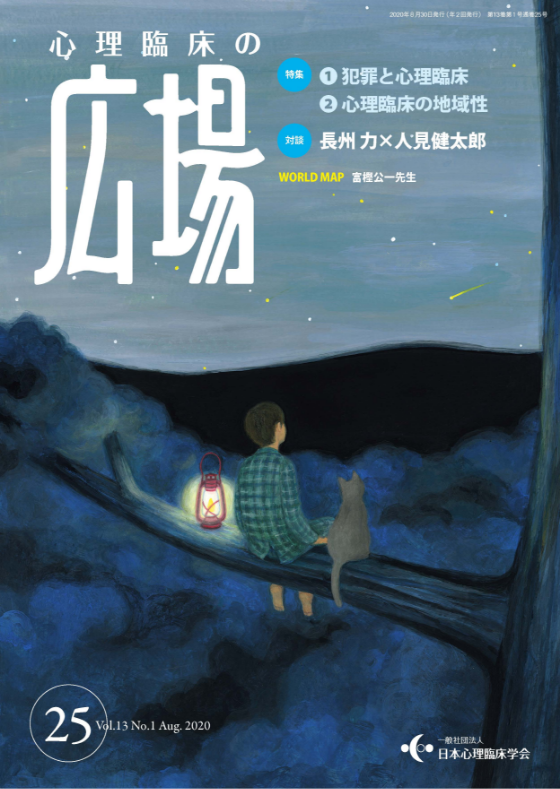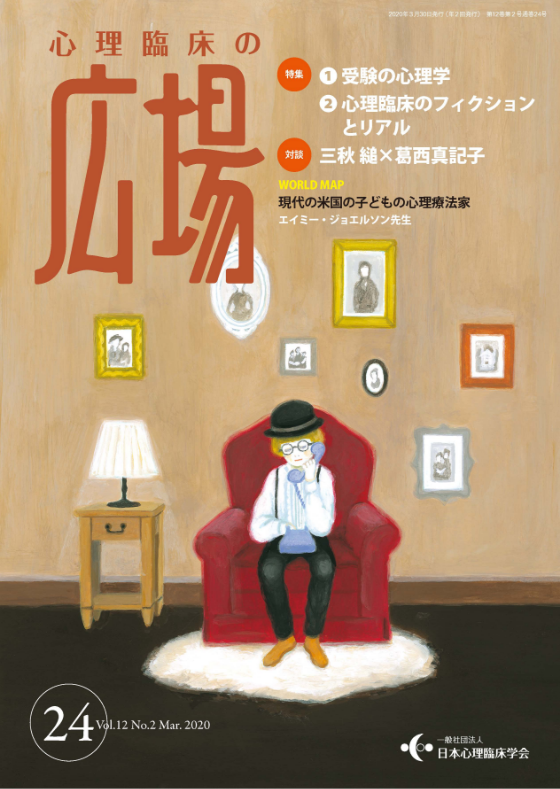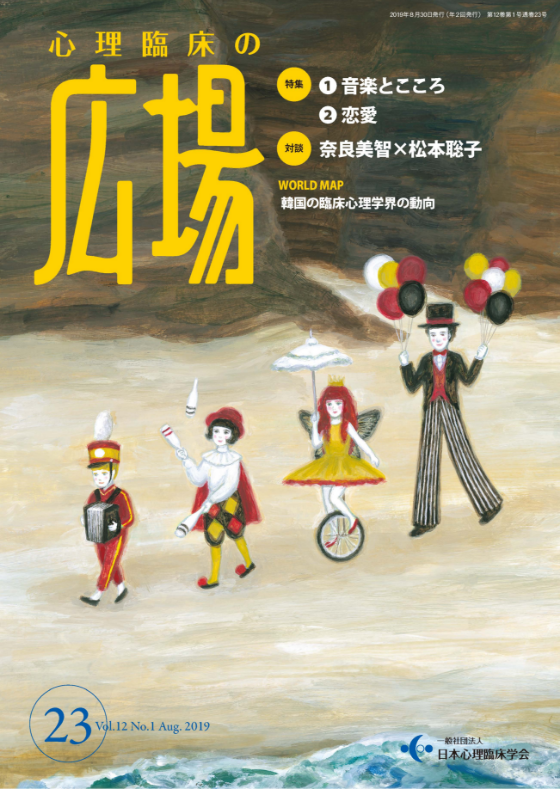ある日突然いつもが変わる
事故は予期せずにやってきます。信号を渡り始めた瞬間、あるいは家の階段を降りようとした一歩。どんな小さな日常の中でも「まさか」が起こりえます。それは、続いていた日常が突然途切れるような感覚をもたらすかもしれません。
事故前後のことをまったく記憶しておらず、気づいたら救急車や病院にいたという人もいれば、事故の瞬間がスローモーションのように鮮明に残る人もいるでしょう。
事故のあとに心の中で起こること
事故に遭うと、まず強いショックが訪れます。目の前の光景がぼやけ、「これは夢ではないか」と現実を受け入れられず、心身がふわふわと浮いたような感覚を覚えることもあります。
少し時間が経ち、ようやく事態を認識できるようになってくると、「なぜこんなことが起こったのか」「もっと気をつけていれば」といった後悔や、事故の関係者、周囲の人間、あるいは自分に対して怒りが湧き上がることもあります。
さらに、事故後は警察や保険会社とのやりとりが続き、場合によっては裁判になることもあります。そういう中で「自分は本当に被害者なのか」「こんなことを言っていいのか」と罪悪感や葛藤を抱くこともあります。事故について話すことを求められ、否が応でもつらい記憶に向き合わざるを得ません。それは大きな苦痛を伴うことになります。
事故に関する記憶がまったくない人もいます。心の防衛反応として、つらい出来事の記憶が無意識に封じ込められている場合もあれば、脳へのダメージによって記憶が失われることもあります。記憶がなければつらくないとは限りません。思い出せないこと自体が不安や混乱を生み、置き去りにされたような感覚や、自分の経験なのに他人事のように感じる苦しさを抱えることもあります。
また、「この出来事を他人にどう伝えたらいいか」といった悩みも生まれます。外からは見えない心の傷が周囲との距離を生むこともあります。人と話すのが怖くなったり、外出しづらくなったりすることもあるかもしれません。心の痛みは目に見えないからこそ理解されにくく、孤独感を深めてしまうこともあります。
身体が変わる、心も変わる
事故によって身体に後遺症が残ることもあります。思うように動けなかったり、痛みが続いたり、日常生活に制限がかかることは、単なる身体的な問題にとどまりません。「もう元の生活には戻れないかもしれない」という現実が、心にも深く影響を与えることがあります。「こんなはずじゃなかった」 と嘆く気持ちと、「でも、生きている」という事実との間で心は揺れ動きます。
また、事故の影響で脳に損傷を受けると、見た目にはわかりにくい認知機能や感情コントロールに関する困難が生じることがあります。これは「高次脳機能障害」と呼ばれ、記憶力や注意力の低下、気分の不安定さ、対人関係のトラブルなど、さまざまな形で現れます。周囲に理解されにくく、「怠けている」「わがまま」と誤解され、二重の苦しみを抱えることもあります。
社会復帰への不安や、周囲に迷惑をかけたくないという気持ちが積み重なり、目に見える痛みと見えない心の痛みが複雑に絡み合います。
支える人もまた、傷つく
事故は本人だけでなく、その家族にも深刻な影響を及ぼします。家族は、事故後の医療対応や保険手続き、職場や学校との調整など、実務的な負担に加えて、精神的なプレッシャーも抱えることが少なくありません。「もっとできることがあったのでは」と自分を責めることもあります。
また、家族にとっても事故は心の傷になります。「もっと早く気づいていれば」「自分が代わってあげたかった」と自責の念に駆られることもあります。本人に余計な負担をかけまいとし無理をして元気を装うことが、かえって本人にプレッシャーを与えることもあります。
心の支援を受けるということ
そんなとき、臨床心理士、公認心理師などの専門家による心理支援が、心の整理に役立つことがあります。事故後の不安や怒り、混乱などは、心が適応しようとする過程での自然な反応です。誰かに自分の気持ちを話すことで、少しずつ心が整理され、余裕が生まれることもあります。
また、必要に応じて、トラウマケアのための専門的な心理療法が行われることもあります。事故の記憶が強く残り、生活に支障をきたす場合には、こうした支援が役立つこともあります。どの方法が合うかは人によって異なり、必ずしもすべての人に必要なものではありませんが、選択肢の一つとして知っておくことが安心につながるかもしれません。
こうした支援を受けることに、ためらいを感じる人もいるかもしれません。「自分でなんとかすべきではないか」「こんなことで相談してもいいのだろうか」と思うこともあるでしょう。でも、誰かの力を借りることは、「弱さ」ではありません。それはむしろ、回復に向かって歩もうとする強い意志の表れであり、新たな一歩を踏み出すための力と言えます。
支援は本人だけでなく、家族にも必要です。家族もひとりの人間として幸せになっていいのですし、家族が精神的に余裕を持てることで、本人へのサポートも変わり、良い影響を与えることにつながります。
回復というプロセス
事故からの「回復」は、けがが治ることだけを指すのではありません。少しずつ自分の生活を取り戻していく過程そのものが回復と言えます。ただ、その道筋は一人ひとり異なります。昨日できなかったことが今日は少しできた。それだけでも大きな一歩です。
ある人にとっては「職場に戻ること」が回復かもしれませんし、また別の人にとっては「安心して眠れるようになること」や「自分を責めずにいられるようになること」が回復の形かもしれません。どうならなければならないということは決まっていません。
時には、回復の歩みが止まったように感じたり、後戻りしたように感じたりすることもあるでしょう。でも、振り返ると、少しずつでも進んできた道のりがあることに気づく瞬間があるかもしれません。
回復に「正しい形」はありません。それぞれのペースで進む中で、痛みを抱えながらも、少しずつ前を向ける日がやってくる。その過程で、これまでとは違う価値観やつながりに気づくこともあります。回復とは、ただ元に戻ることではなく、傷ついた経験の中から、自分なりの意味や強さを見出し、新たな自分を育てていく営みなのかもしれません。