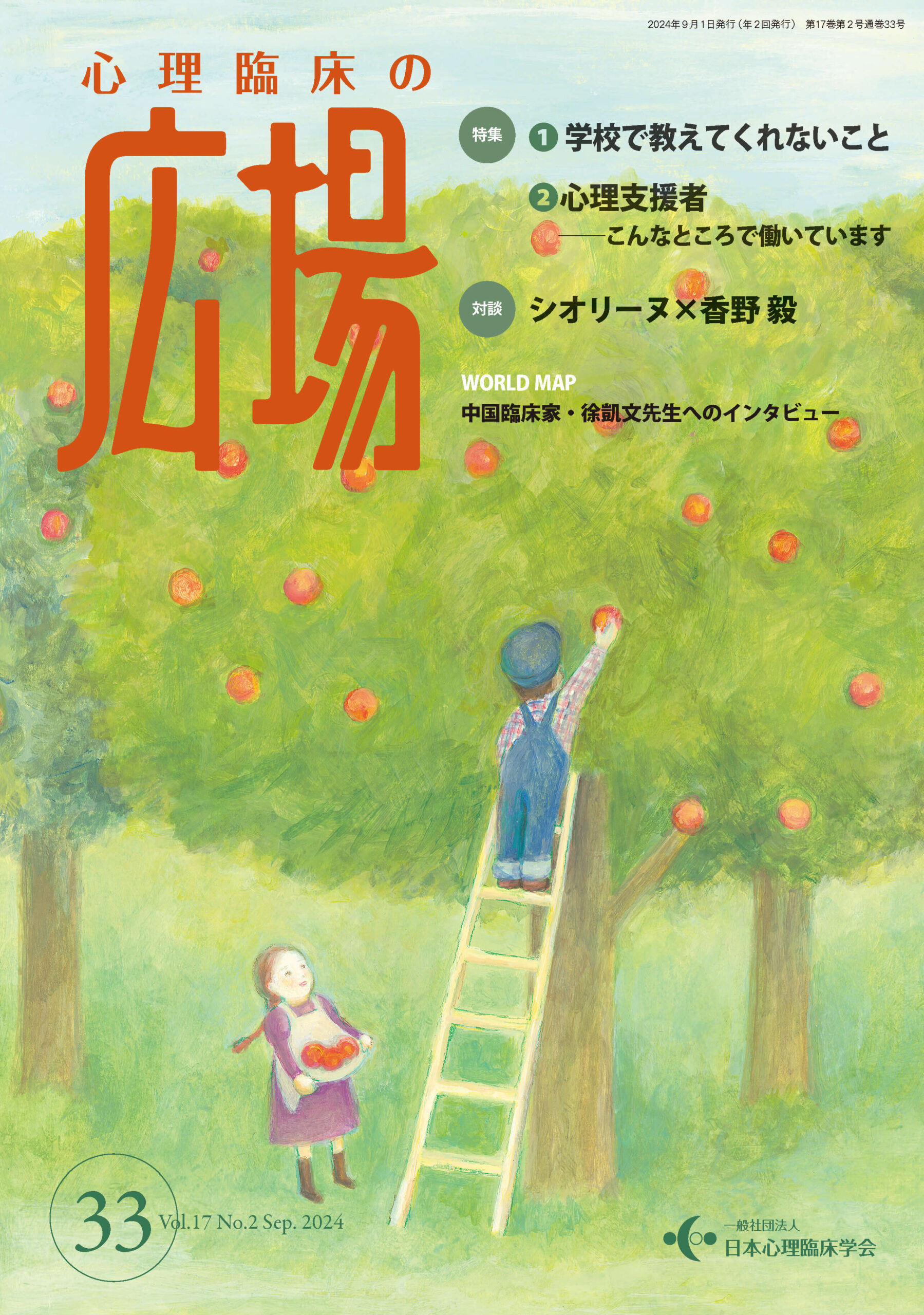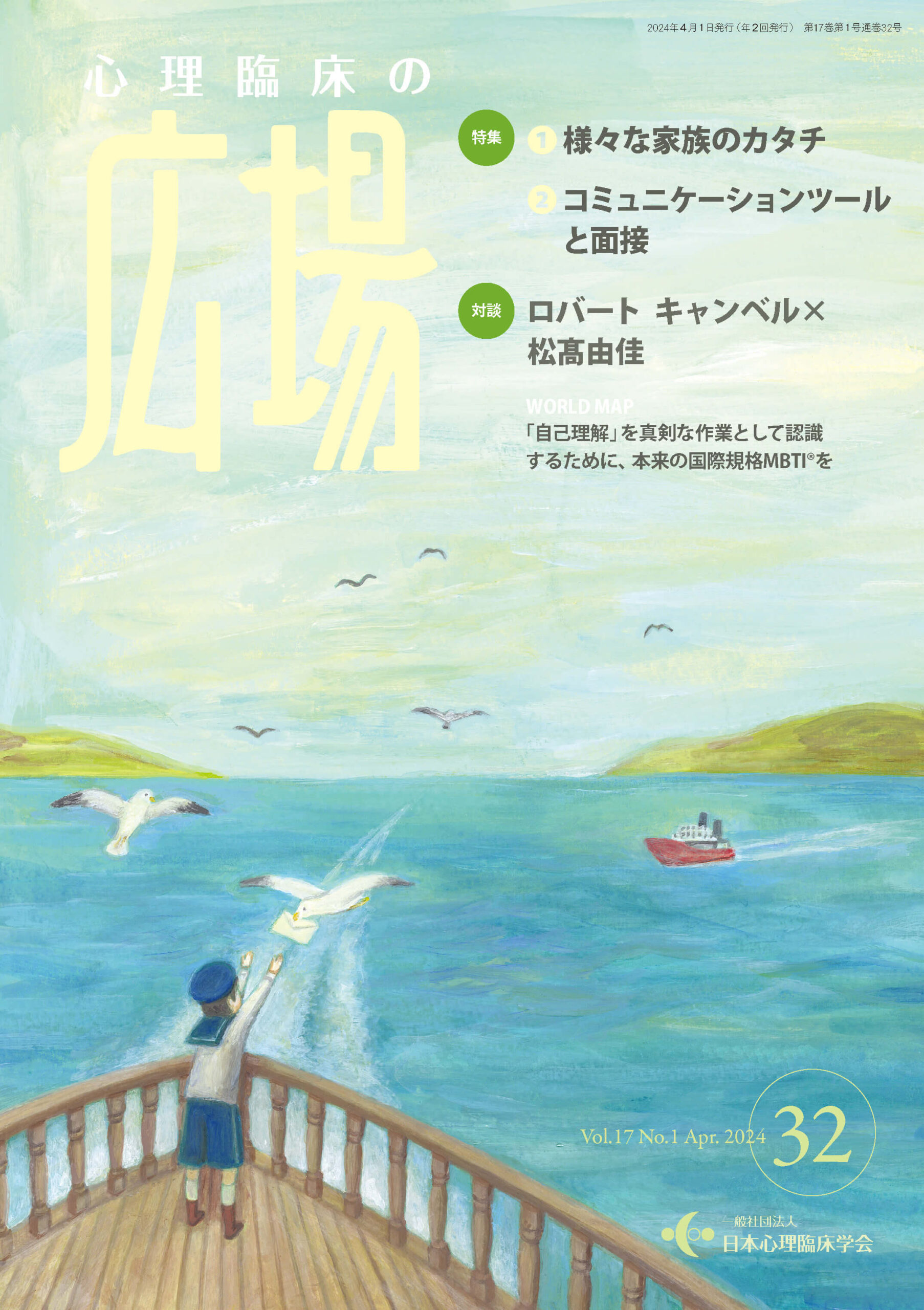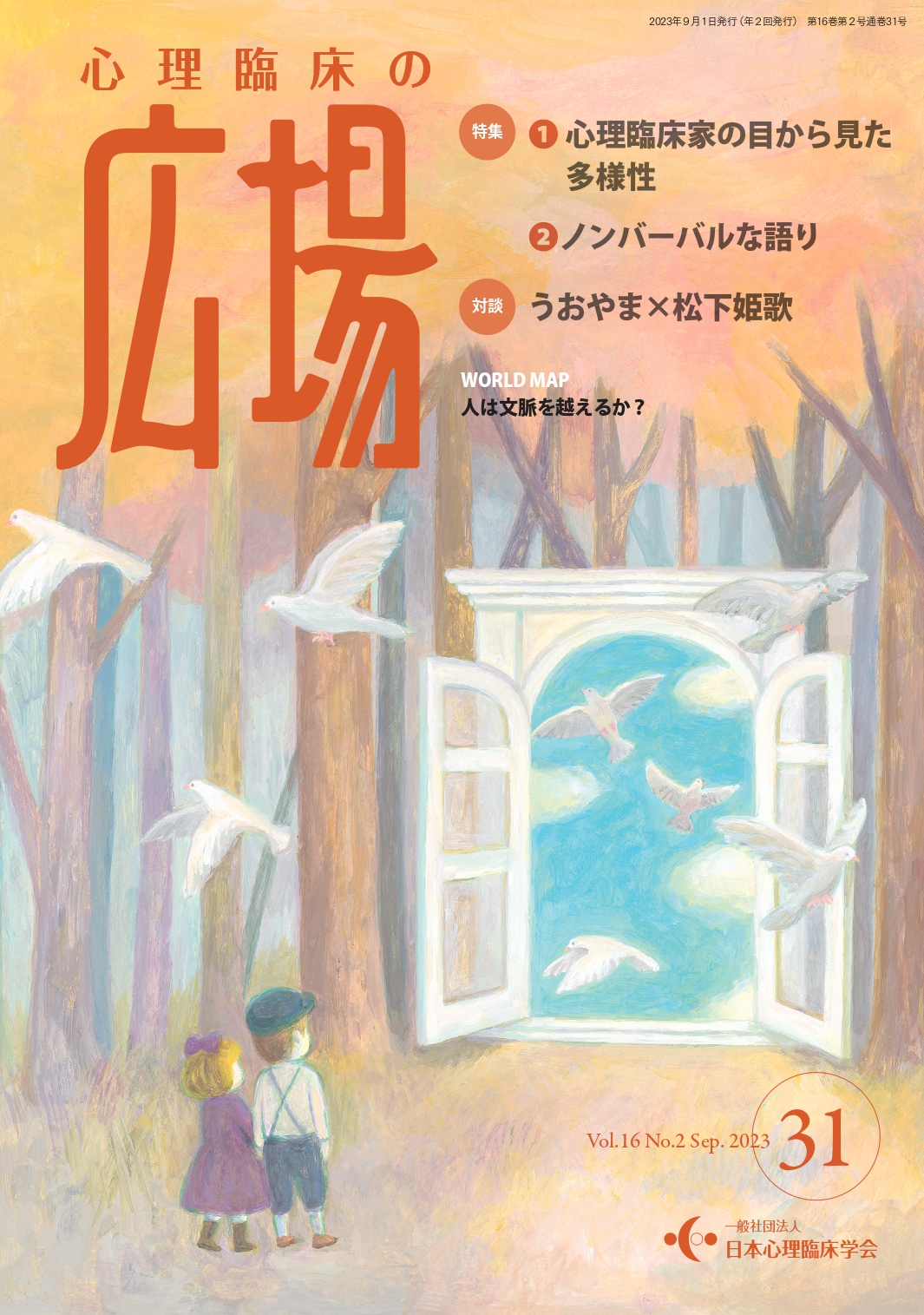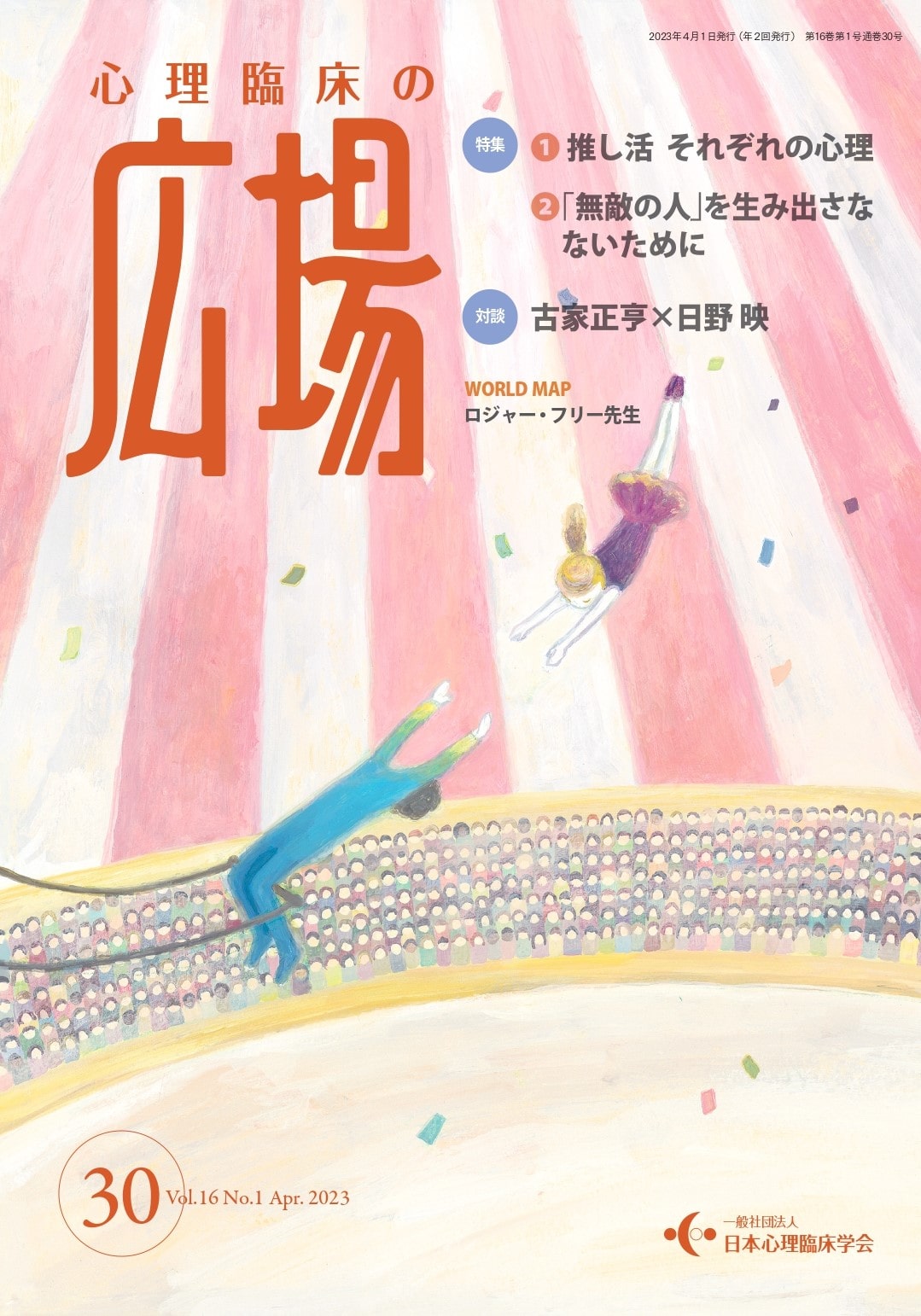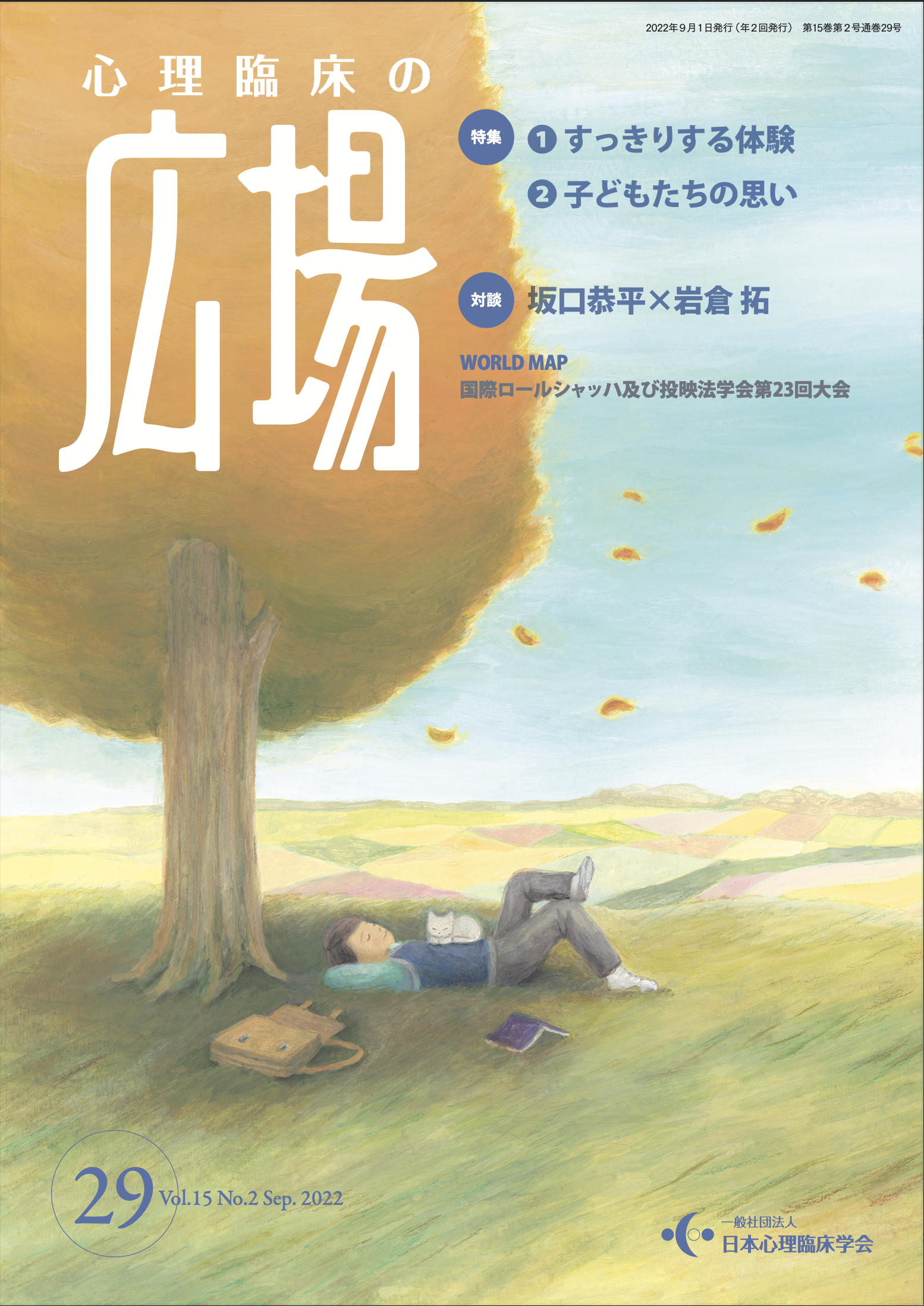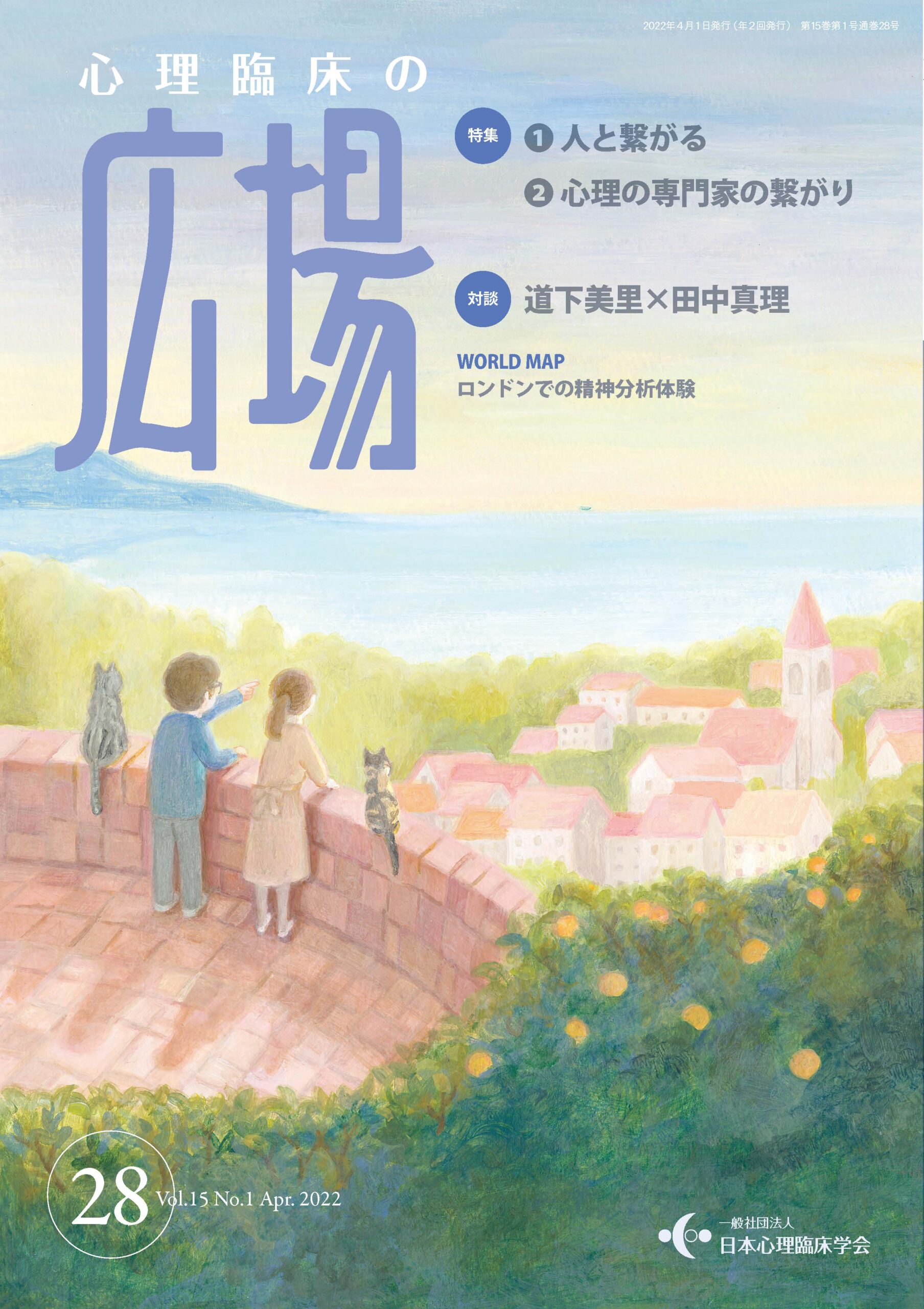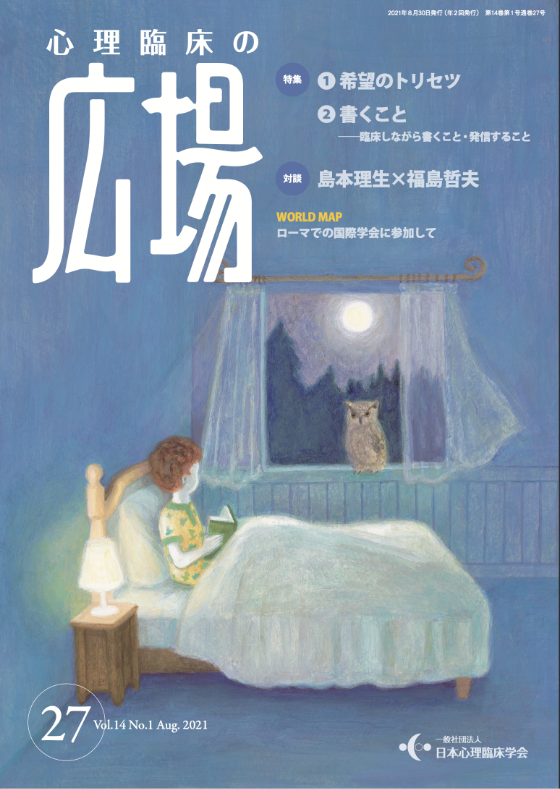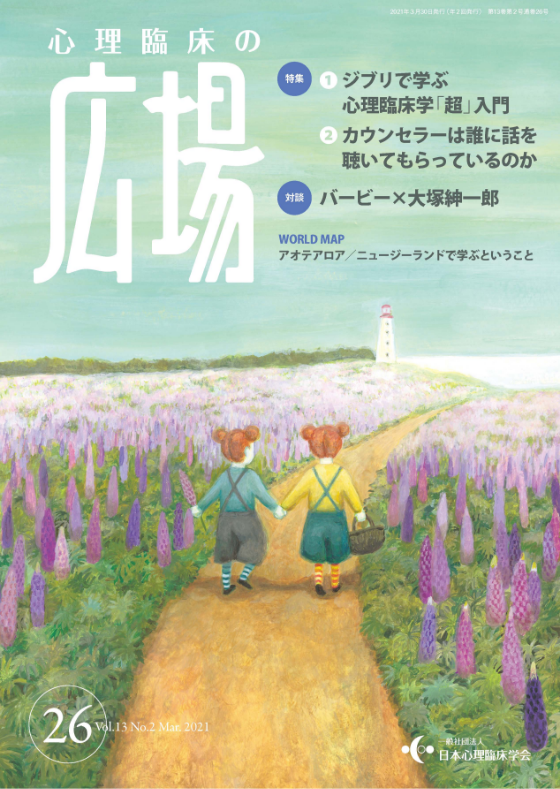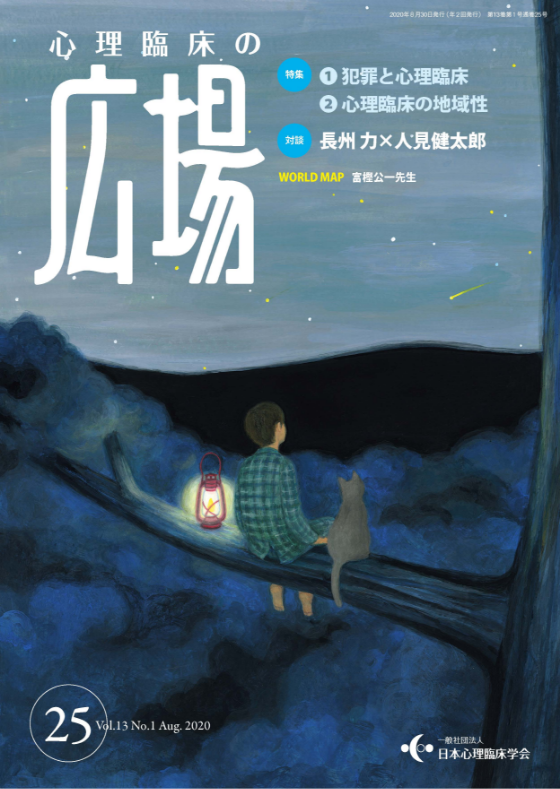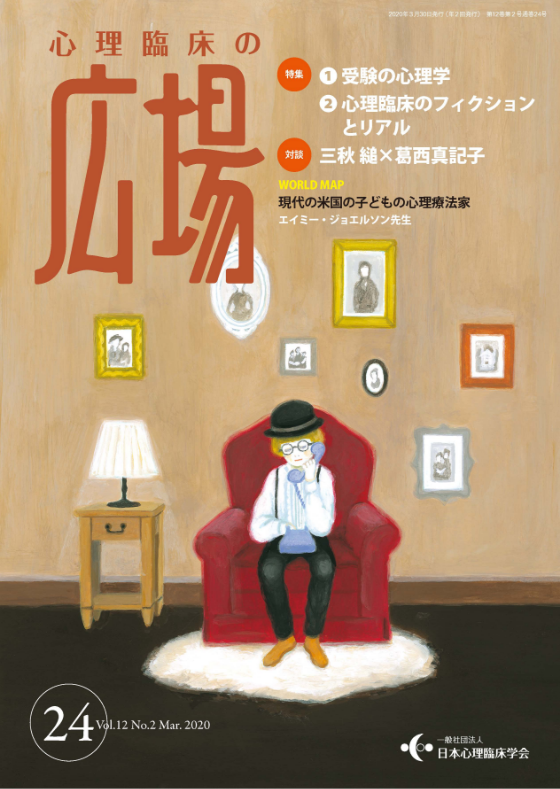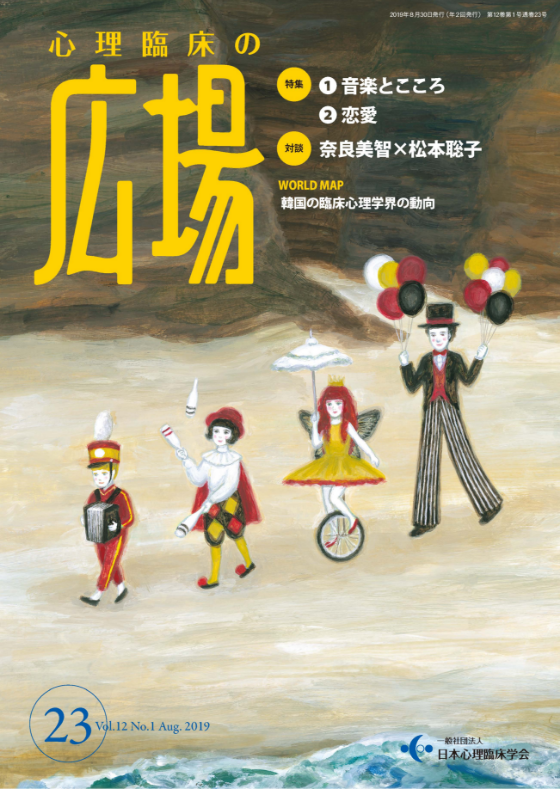心理学の研究・教育・相談業務をしています。これまで、スーパーや百貨店で野菜全般(例えば、人参・ブロッコリー・白菜)や果実的野菜全般(例えば、いちご・メロン・すいか)、果物全般(例えば、マンゴー・みかん・りんご)の魅力を生活者様に伝えてきました。現在も、インターネット上でUsako’s Kitchenを主宰し、野菜の料理レシピや健康にまつわる情報を配信しています。野菜の消費量を上げるとともに、生活者の健康増進、農業の活性化や地域振興に関心を寄せています。日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエプロの資格を取得してからは、より一層活動の幅を広げることに努めております。
野菜ソムリエプロとして、店頭で「美味しい果物を選んで」と生活者様にご依頼されたとき、美味しい野菜・果物を選ぼうとすると、野菜や果物のほうから「私、美味しいよ」と教えてくれます。そうして、その野菜・果物を、生活者様にお渡しすると、生活者様は、とても喜んでくださいます。野菜や果物は、自力で根を張り、実を結び、力強く生きています。そして、他者に喜んでもらうこと、運んでもらうことと食べてもらえることに、植物としての喜びを感じているのではないかと思います。野菜・果物にとって、食べられることは、種を運んでもらえますから、とても幸せなことです。野菜・果物の喜びが伝わり、受け取る側・食べる側にも喜びが広がるのだと考えています。
野菜・果物と心を通わすこと
野菜・果物をはじめ植物には、妖精がついていて、「育て。育て。」と励ましているそうです。野菜・果物などを育てるとき、穏やかな気持ちになるのは、「妖精がいるから」という理由もあるのかもしれません。育てるとともに、育てられているのでしょう。
よく、人前で話すのに緊張することに悩む人に、「聴衆者を、かぼちゃだと思って!」とアドバイスされることがありますが、実は、かぼちゃ一つひとつにも、個性があります。皮がごわごわして実がぎゅっと詰まっているものや、皮がつるつるしているもの、水分の多めのものや少なめなもの、お料理によって、水分がどれくらいのかぼちゃを使うかを考えます。そうやって、野菜と対話をしながら、日々の献立を考えていると、毎日をとても丁寧に生きている気がして、自分のことも、繊細に、大切にできるようになってきます。そのかぼちゃも、中をくり抜くと、ハロウィンのお化けになるのですから、野菜とは、不思議な存在です。生活に追われていると、忘れてしまいそうになることもありますが、野菜は生きています。そして、私たちは、毎日、いのちをいただいています。
菜食と「こころ」と「からだ」
野菜を育ててみたり、美味しい野菜・果物の見分け方が分かってくると、野菜などは調味料を使わずに、そのまま食べても美味しいことが分かります。また、調味料を使わずとも、たとえば、「すだち」や「かぼす」の絞り汁を調理に使うと、減塩になりますし、ビタミンCやカリウムといった栄養素を摂取することができます。私たちの健康にとって、風邪を引きにくくなったり、高血圧を予防したりすることが期待できます。
第7の栄養素というのが注目されています。フィトケミカルともいわれる野菜・果物の色素などの成分(例えば、トマトのリコピン・茄子のアントシアニン・人参のβ-カロテンなど)は、抗酸化作用や免疫力アップといった働きがあり、私たちに元気を与えてくれます。心と体はつながっていますから、体が元気になると、心も元気になります。
きのこに多く含まれるビタミンDは、精神疾患の予防・改善に有効だという研究が、栄養学で多く明らかにされてきているようです。
野菜は「赤、黄、オレンジ、緑、紫、黒、白」といった色があります。そのうちの1色だけでなく、いくつかの色を1日の食事に取り合わせると理想的ですね。私たちの日常や食卓に、野菜・果物は、彩を与えてくれます。色を見るだけでも元気がもらえます。厚生労働省の「健康日本21(第二次以降〜第三次)」においても1日に350グラムの野菜を食べるように掲げられており、量を摂ることと、バランスよく摂取することが大事なようです。また、「毎日くだもの200グラム運動」が、果物の小売業者、生産団体、関係機関等により、知識の普及啓発活動としてなされています。1日に、野菜350グラムと、果物200グラムとはかなりの量ですが、がんばって摂取したいですね。
野菜の調理の仕方がわからなかったり、包丁の使い方がわからなかったりするかもしれません。それでも大丈夫です。青ネギは、ハサミで切ることができますし、レタスやキャベツは、手でちぎると食べやすい大きさにすることができます。あとは、洗ってヘタをとるだけのミニトマトと、お好みのドレッシングがあれば、彩り豊かなサラダの完成です!
Usako’s Kitchenにおいて、冷蔵庫の中にある食材と、台所にある調味料で作ることのできる、野菜・果物のレシピを、インターネット上に載せています。ぜひ参考になさってみてください!
手作りの料理には、愛情がこもっています。特に、野菜の料理は、「切る」「煮る」「焼く」「茹でる」「盛りつける」といった工程のほかに、野菜を加工する際の「洗う」という工程が加わりますから、その分、作り手のパワーが込められています。野菜たっぷりの料理の並んだ食卓を、家族で囲むなどということは、幸せの象徴です。それでも、ひとりで食べなければならなかったり、インスタント食品に頼ってしまったり、また、最近では、「お昼ご飯がアイスクリーム」という話も聞き、やるせない気持ちになります。心理学に携わる者として、また、野菜ソムリエプロとして、国民が心身ともに健康で、家族が安心して食卓を囲める社会になってほしいと願っています。
野菜と心理について、科学的に検証するために、日本の30〜59歳を対象に、「野菜」などを刺激語としたSCT(文章完成法)と宗田・岡本(2013)の「個としてのアイデンティティ」尺度および「関係性にもとづくアイデンティティ」尺度などを用いて、調査をしています。野菜の栽培や調理法は、地域によって異なり、歴史や食習慣などともかかわっています。私たちの民族としてのアイデンティティも、菜食の歴史とともに社会的・文化的に発達してきたでしょう。
野菜を摂取することで、身体的・心理的・社会的に、幸福な存在としていられるウェルビーイングな社会を実現するために、これからも研究を続けてまいります。
●引用文献
宗田直子・岡本祐子(2013)「アイデンティティにおける「個」と「関係性」をとらえる尺度作成とその短縮版の検討」青年心理学研究25:13-27.
Usako’s Kitchen(野菜ソムリエ☆うさこのキッチン)https://vegefru-usako.amebaownd.com/