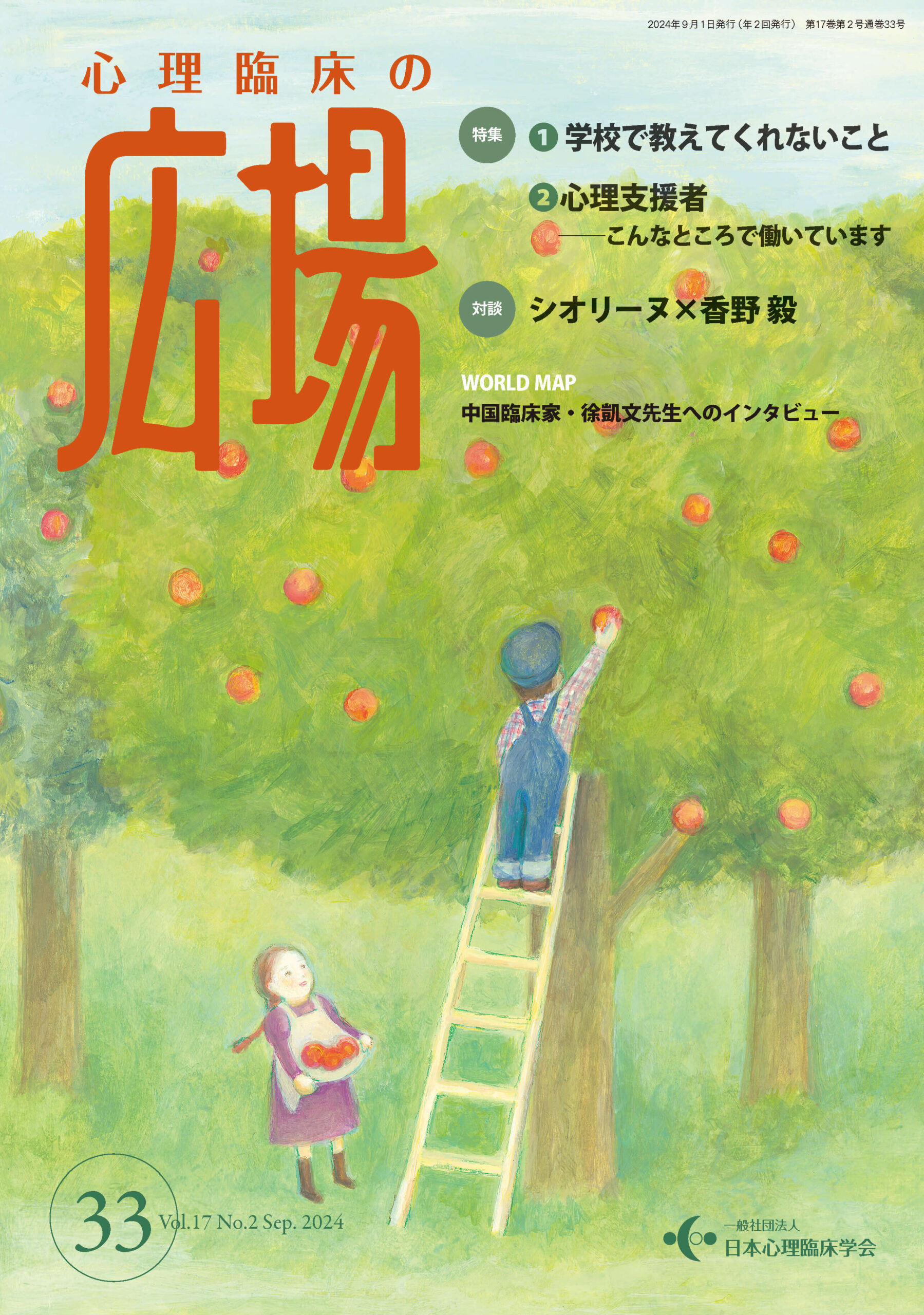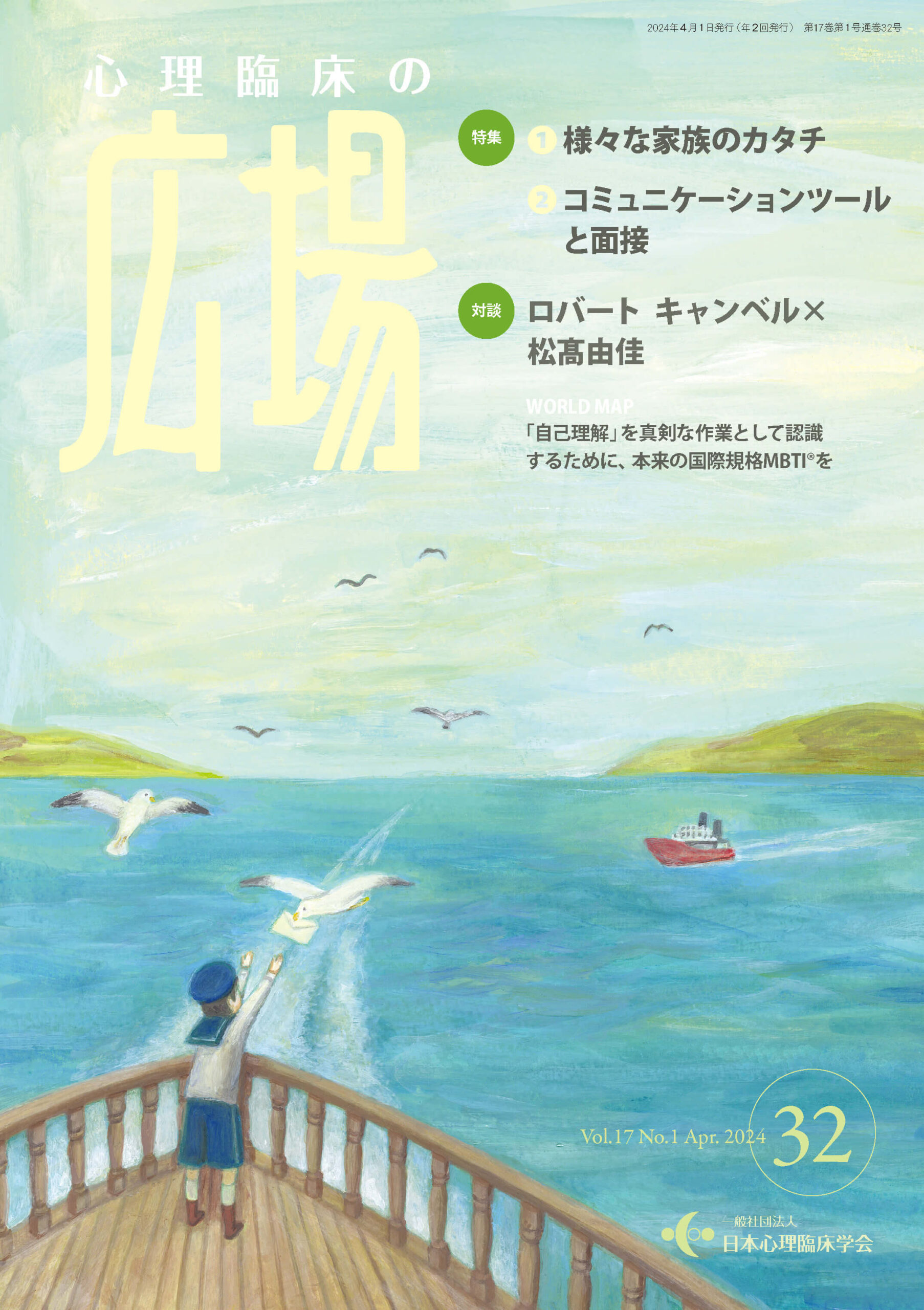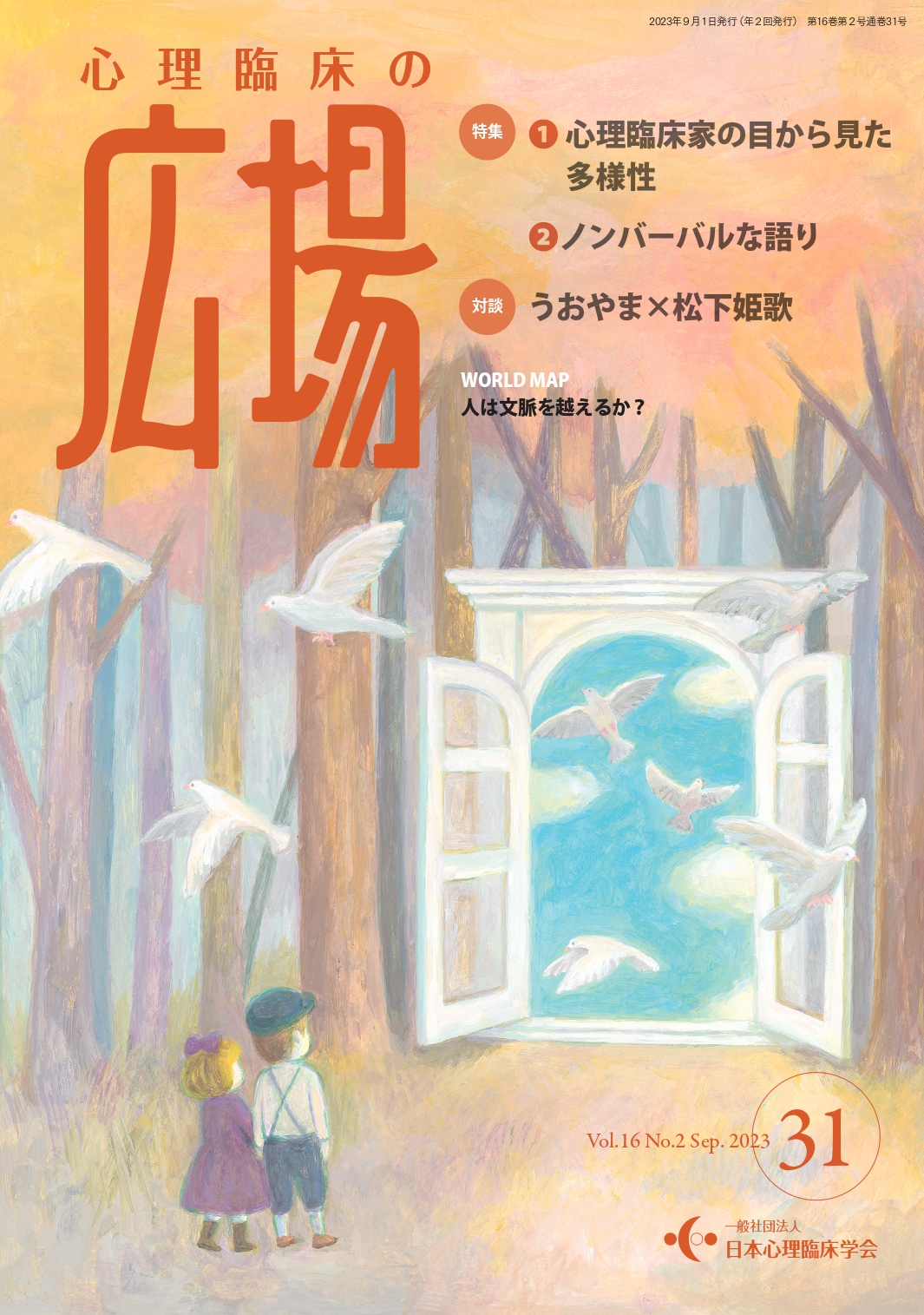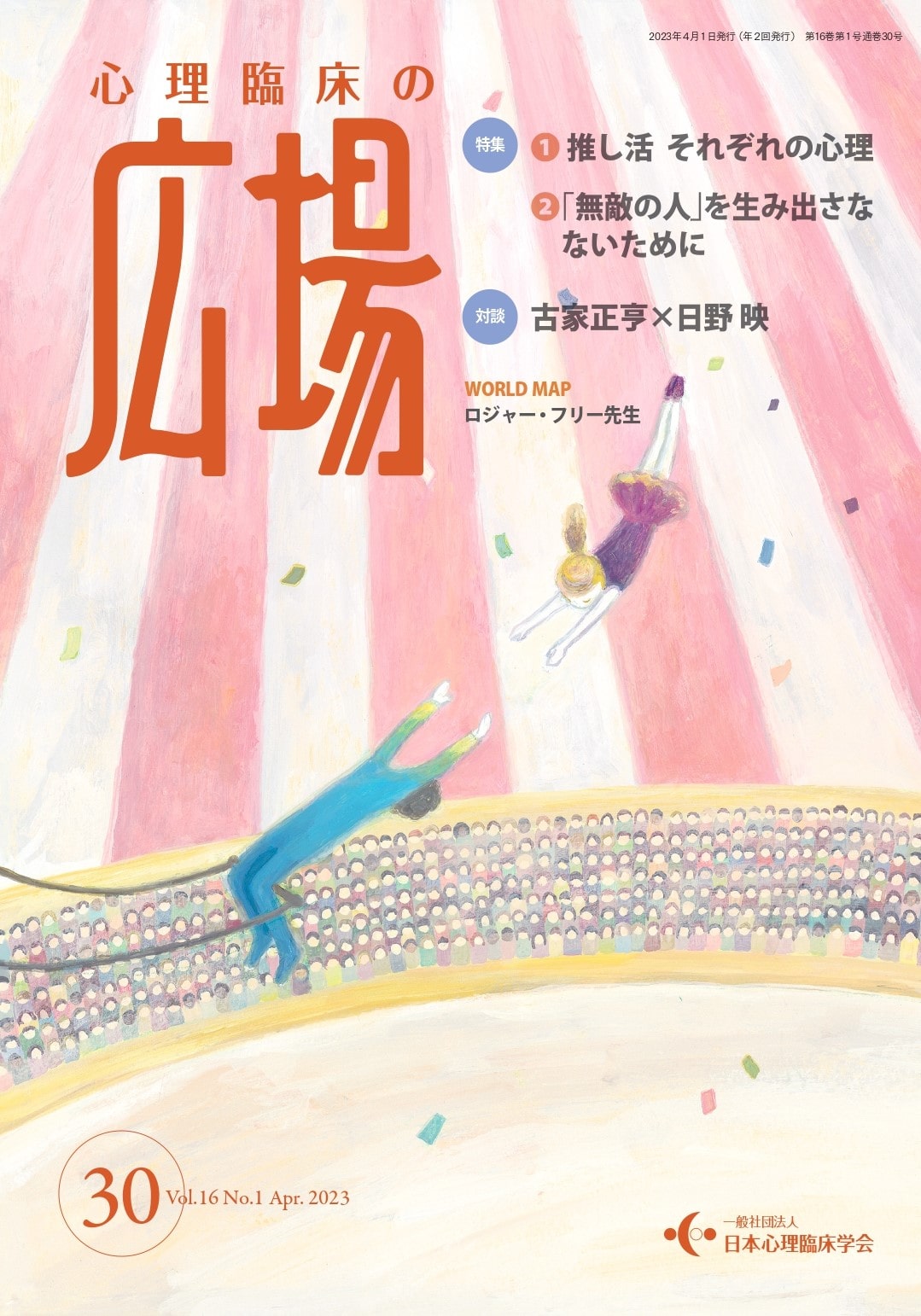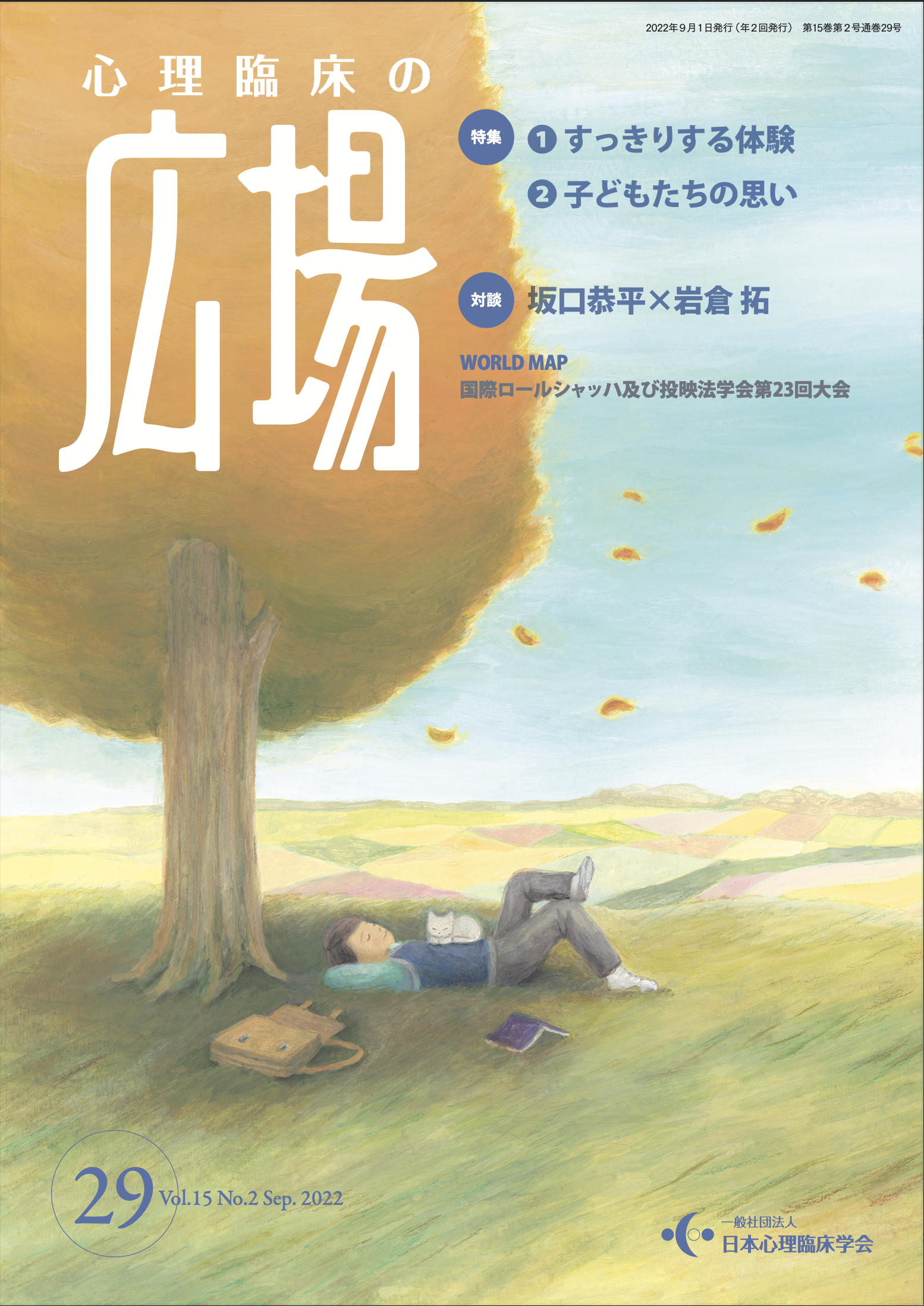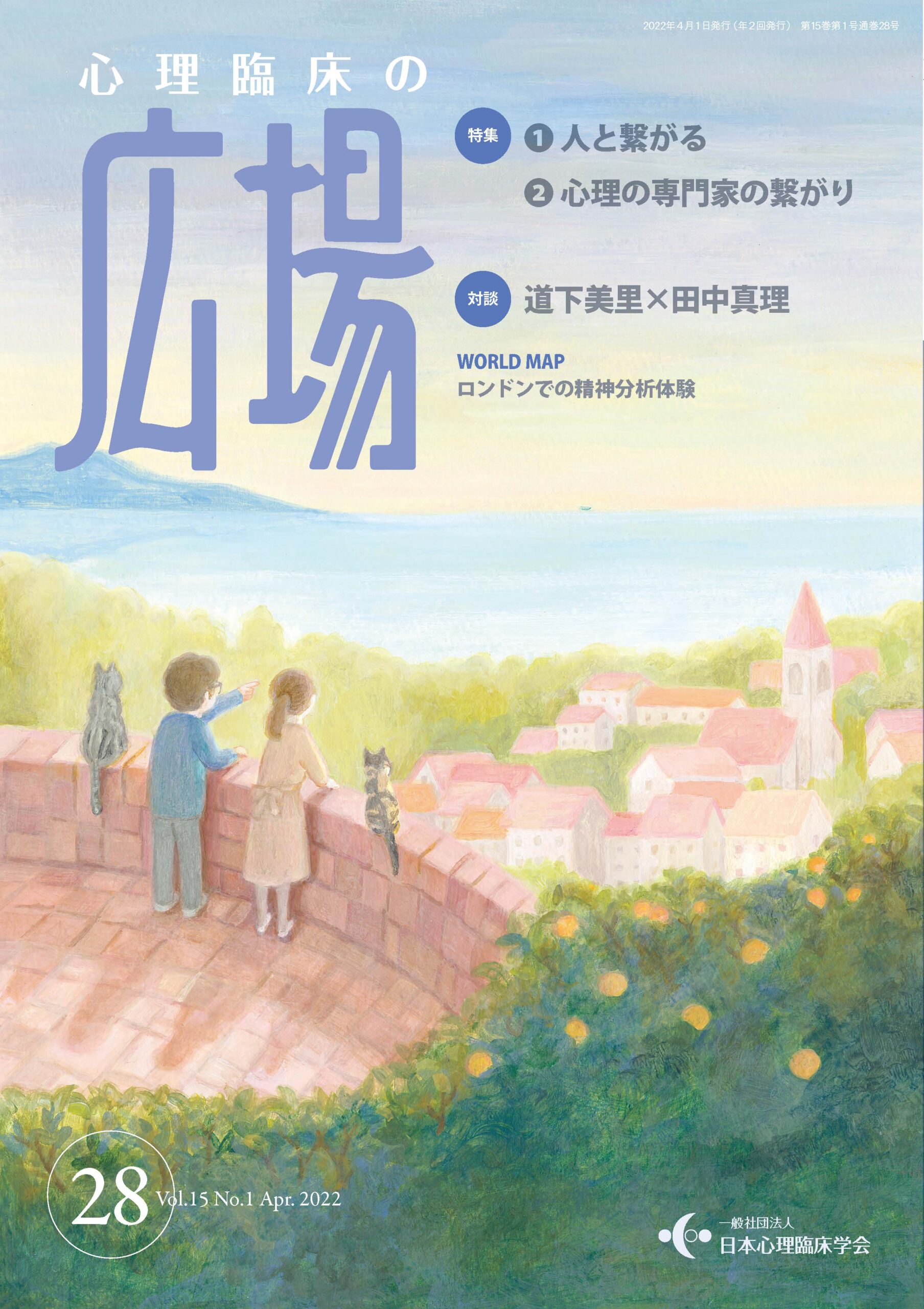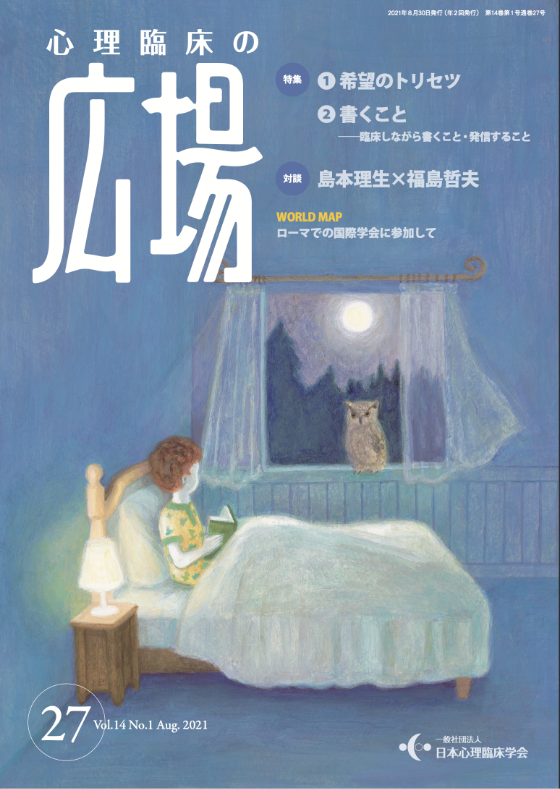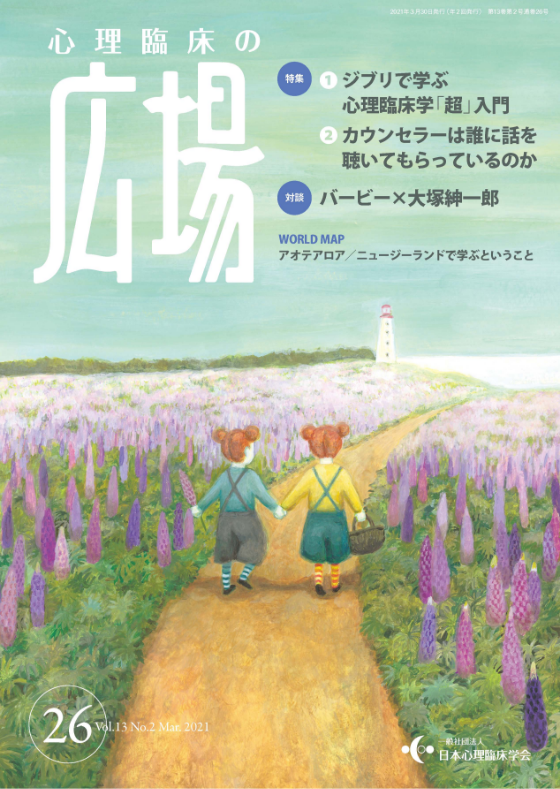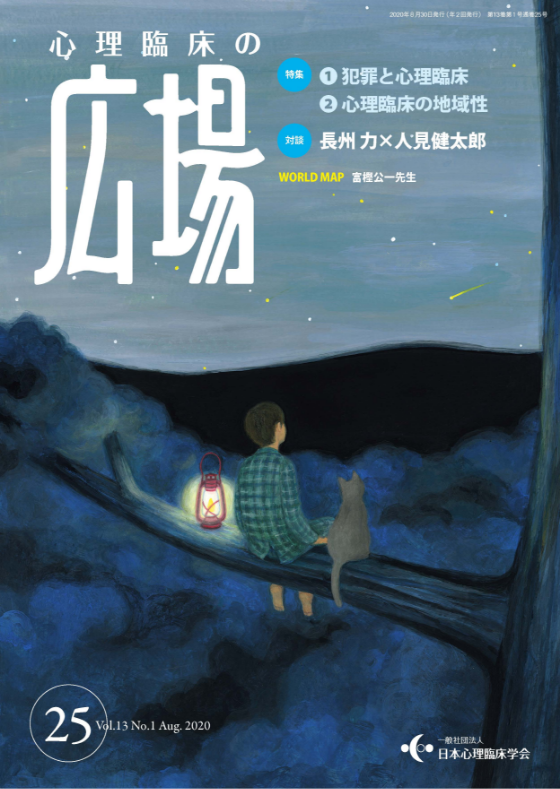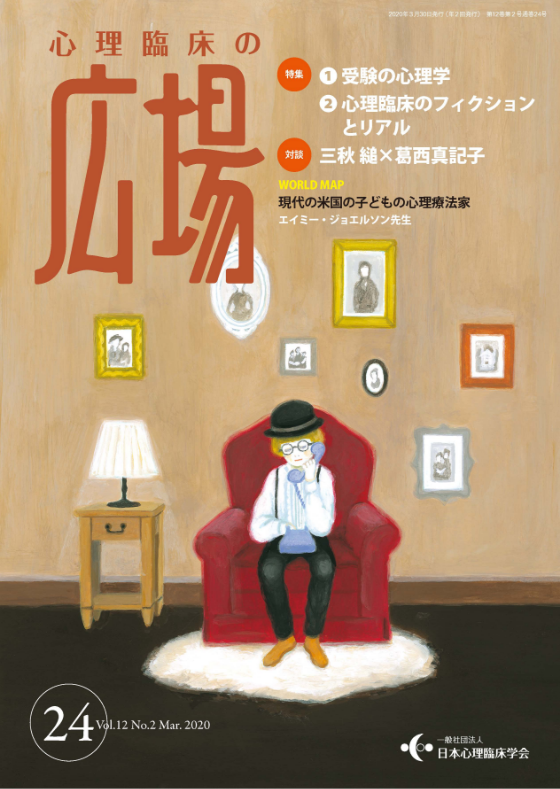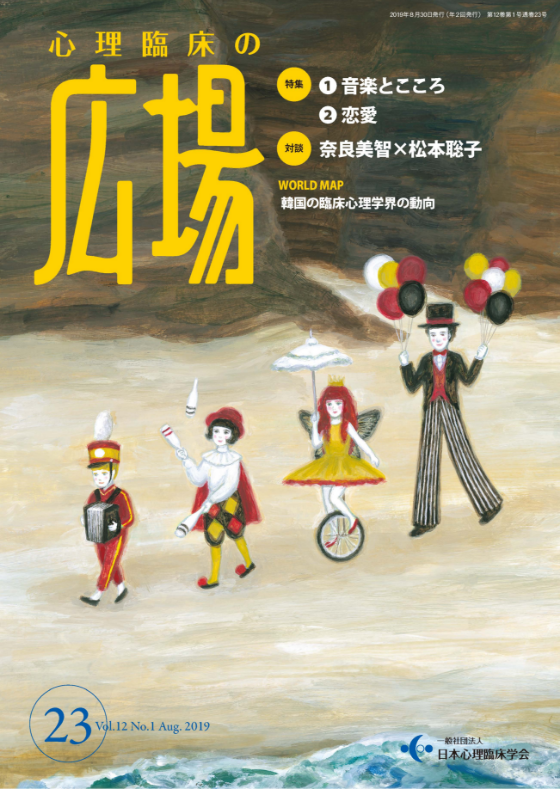皆さんは普段、どんなふうに食事をしていますか?「何を食べましたか?」という質問にはすぐに答えられても、「どんなふうに食べましたか?」と聞かれると、ちょっと戸惑うかもしれませんね。
最近では、「何を」食べるかだけでなく、「どのように」食べるかも大切だと考えられるようになってきました。たとえば、スマホを見ながら食べたり、ぼんやり考えごとをしながら食べたりして、「気づいたら食べ終わっていた」ということはありませんか?そうすると、「どんな味だったか覚えていない」「もうお腹がいっぱいなのに、食べすぎてしまった」といったことが起こりやすくなります。こうした「ながら食べ」をすると、満腹感を感じにくく、食べすぎにつながることがわかっています。
「どのように」食べるかというスタイルは、実は離乳食を食べる赤ちゃんの頃から始まっているとも言われています。ある研究では、乳幼児期に「どのように」食べるかが、生涯の食事への向き合い方に影響することが示唆されています*1。たとえば、幼少期に親から食べることを強要されていた人は、本来であれば自然に感じることのできる空腹感や満腹感に気づきにくくなり、成人後も食行動の問題が続くという指摘があります。
マインドフルイーティングという考え方
こうした「自動的な食べ方」をやめて、五感(見る、触る、においをかぐ、味わう、聞く)を使って、食べるという体験そのものに意識を向けていくことが大切だとされています。それが「マインドフルイーティング」という考え方です。マインドフルイーティングとは「今この瞬間の食べる体験に、ていねいに意識を向けること」です。
この方法は、もともと仏教の瞑想から生まれた「マインドフルネス」という考え方をもとにしています。マインドフルネスは1970年代から医療や心理の分野にも広まり、ストレスケアや心の健康のためにも使われるようになりました。
普段からマインドフルイーティングを心がけている人は、肥満になりにくく、気持ちが安定しやすいことが研究でわかっています*2。また、ストレスからくる食べすぎ(感情的な食行動)も減り、自分の体の声に気づけるようになるとも言われています。こうした変化は、一度に起こるものではありませんが、毎日の小さな気づきを積み重ねていくことで、少しずつ育っていくものです。
日々の食事に取り入れるために
では、どうすればマインドフルイーティングを練習できるのでしょうか。マインドフルイーティングの練習方法はいくつかありますが、代表的なやり方として、「レーズンエクササイズ」を紹介します。これは、ひと粒のレーズンを使って、「今ここ」の感覚に気づく練習です。レーズンが手元にあれば、ひとつ手に取ってください。もしなければ、チョコレートやナッツ等でも大丈夫です。
①見てみる
まずは、レーズンをじっと見てみましょう。色はどうですか?形は?どんなところにしわがありますか?あたかも初めてレーズンを見るような気持ちになって、「これはどんなものかな?」とゆっくり観察してみます。
②触ってみる
次に、指でそっと触ってみましょう。やわらかいですか?かたいですか?どんな感触がしますか?手で転がしてみたり、軽く押してみたりして、手の感覚に意識を向けてみます。
③においをかいでみる
つぎに、レーズンを鼻に近づけて、においをかいでみましょう。どんなにおいがしますか?甘いですか?少し酸っぱいですか?
④口に入れてみる
それでは、レーズンをゆっくりと口に入れてみましょう。すぐに噛まずに、しばらく舌の上にのせて、どんな感じかを感じてみます。口の中の温度や、レーズンの重さにも気づいてみましょう。
⑤ゆっくり噛んでみる
次に、ゆっくりとひと噛みしてみましょう。味や感触がどう変わるか、よく味わってみてください。何度か噛みながら、じっくり味わいましょう。どんな味がしてきますか?どんな音が聞こえますか?噛むことで、口の中に唾液が分泌されていることに気づくかもしれません。
⑥飲み込んで、余韻を感じる
飲み込みたくなったら、ゆっくり飲み込んでください。飲み込んだあとの口の中の感覚にも、しばらく意識を向けてみましょう。
やってみてどうでしたか?たったひと粒を、こんなふうにじっくり味わうのは、少し不思議な体験かもしれません。でも、こうして注意を向けることで、ふだん見落としている「今」の感覚に気づくことができます。
このエクササイズは、心理臨床の現場でもよく用いられており、摂食障害の治療やストレスケアの一環として取り入れられることもあります。実際に行ってみた方の中には、「ひと口の大切さに初めて気づいた」「食べることへの罪悪感が少し減った」と話される方もいます。こうした気づきは、食だけでなく、日常生活のさまざまな場面にも波及していきます。
また、マインドフルイーティングは、特別な道具がいらず、いつでもどこでもできるのがいいところです。毎日の食事の中で、「最初のひとくちだけでも味わってみよう」「香りに気づいてみよう」といった小さな工夫をするだけでも、変化を感じられるかもしれません。
さらに、友だちや家族との食事の場面でも、「この料理、どんな味がする?」「どんな香りがする?」といった会話を取り入れると、ただの食事が、楽しい時間へと変わっていきます。
ここまで、「どのように」食べるかの大切さとマインドフルイーティングのやり方について紹介してきました。もちろん、栄養バランスなど「何を」食べるかもとても大切ですが、それと同じように、「どのように」食べるかも、心や体の健康に深く関わっているのです。
忙しい毎日でも、ひと口を丁寧に味わうことで、心と体の声を聴く時間を持つことができます。そしてそれが、自分自身を大切にする習慣へとつながっていくのです。
*1 Batsell, W. R., Jr., Brown, A. S., Ansfield, M. A., & Paschall, G. Y. (2002). “You Will Eat All of That!”. A retrospective analysis of forced consumption episodes. Appetite, 38, 211-219.
*1 Ellis, J. M., Galloway, A. T., Webb, R. M., Martz, D. M., & Farrow, C. V. (2016). Recollections of pressure to eat during childhood, but not picky eating, predict young adult eating behavior. Appetite, 97, 58-63.
*2 Warren, J. M., Smith, N., & Ashwell, M. (2017). A structured literature review on the role of mindfulness, mindful eating and intuitive eating in changing eating behaviours: effectiveness and associated potential mechanisms. Nutrition research reviews, 30(2), 272-283.
*2 Winkens, L. H. H., van Strien, T., Brouwer, I. A., Penninx, B. W., Visser, M., & Lähteenmäki, L. (2018). Associations of mindful eating domains with depressive symptoms and depression in three European countries. Journal of affective disorders, 228, 26-32.