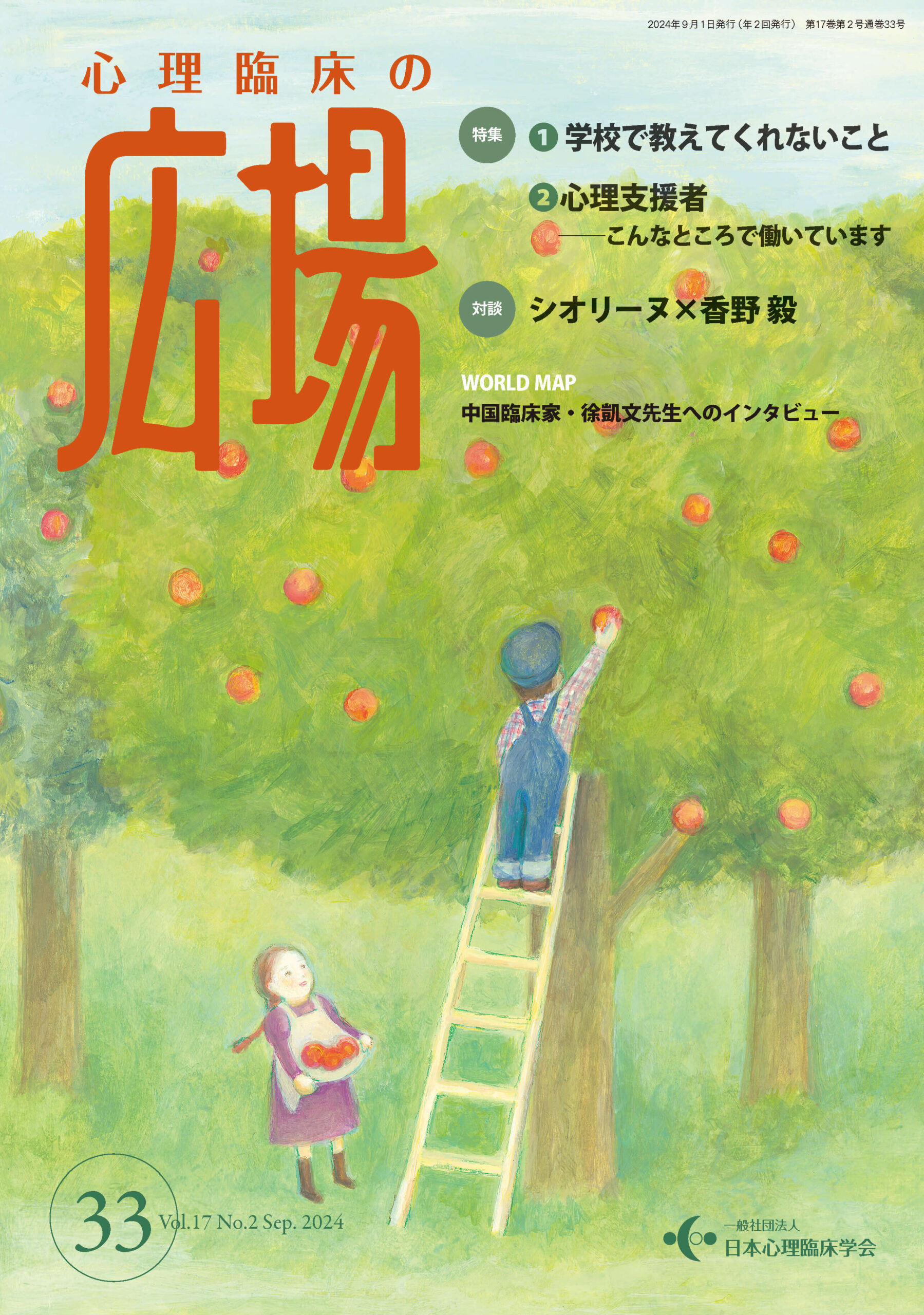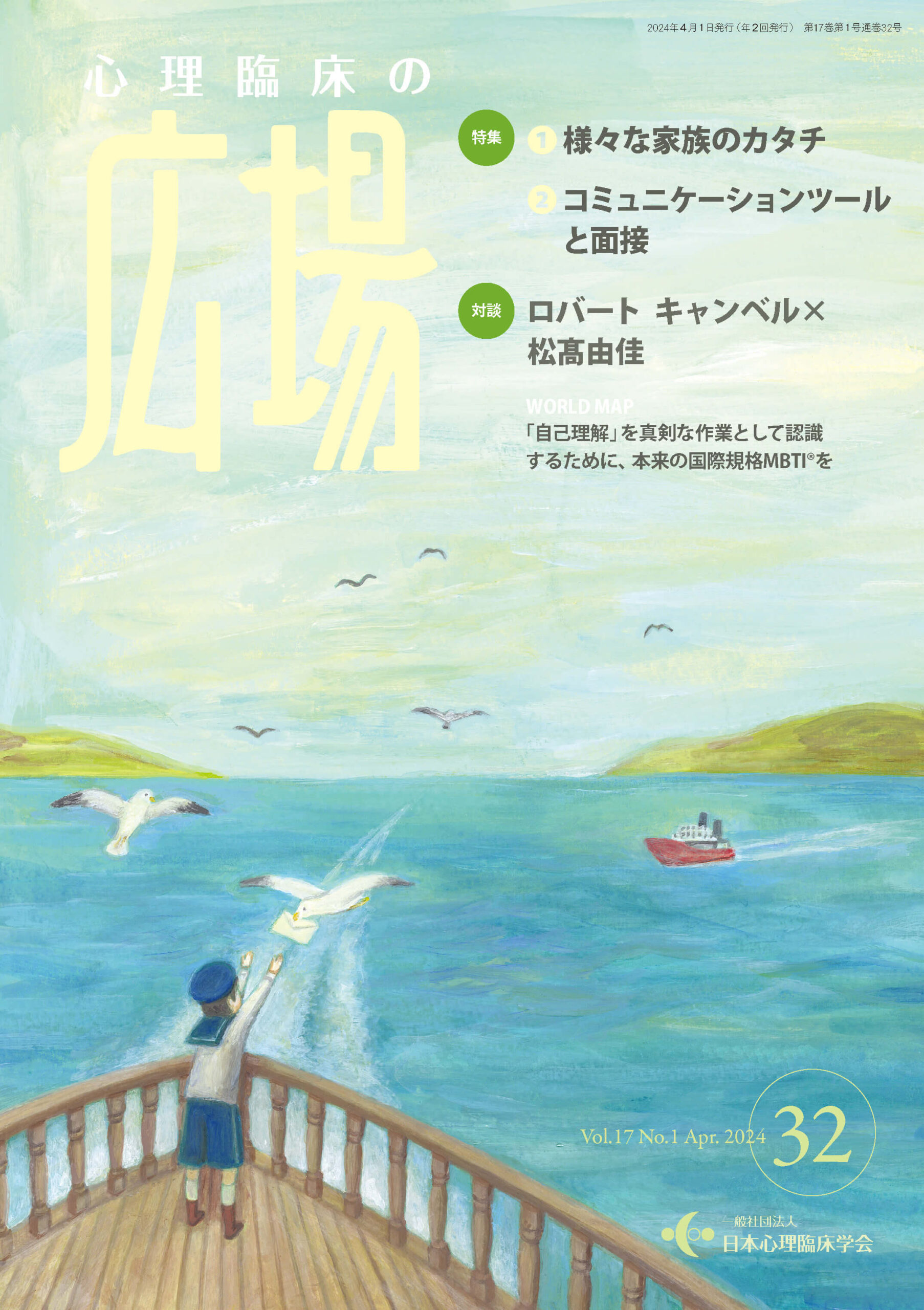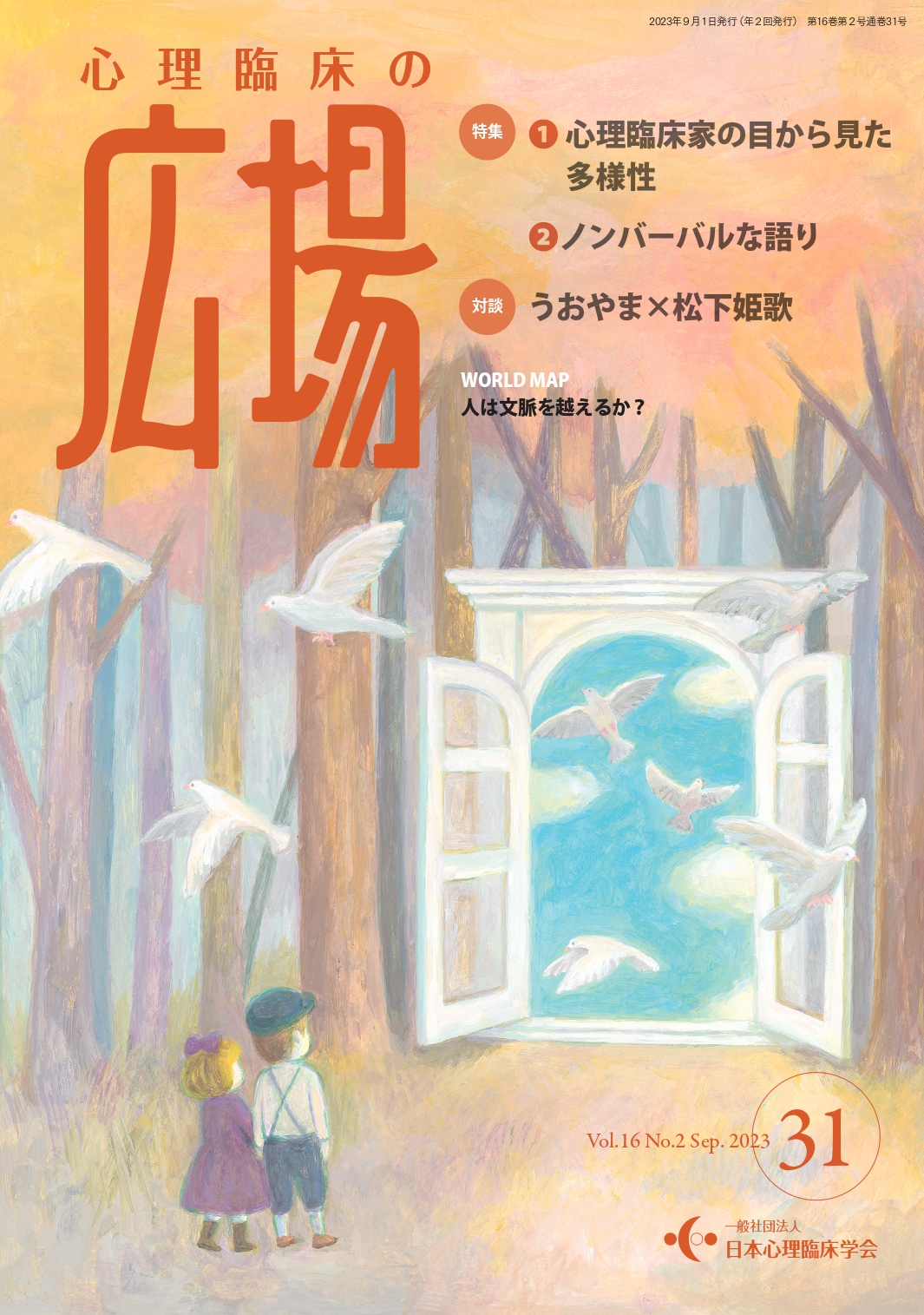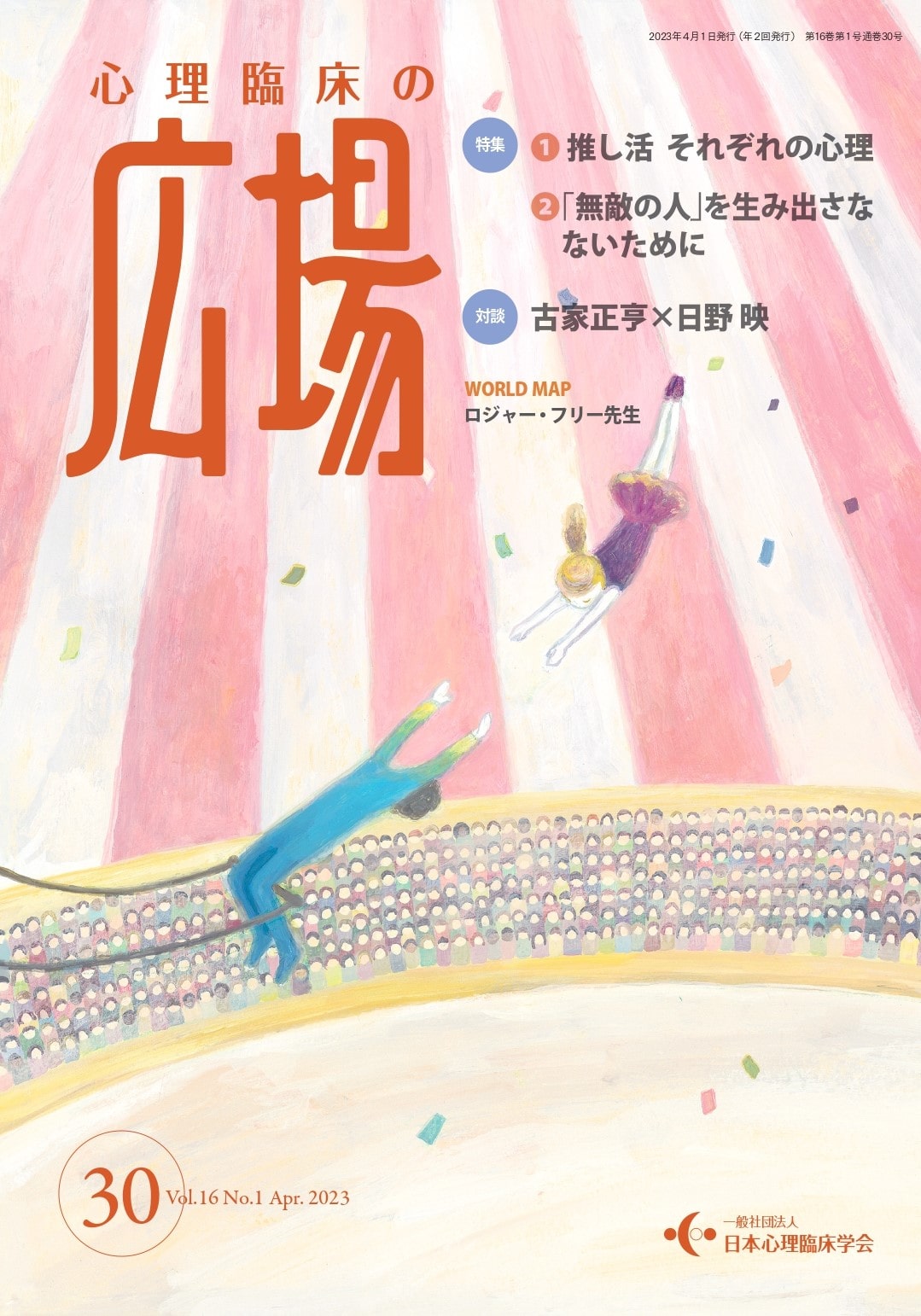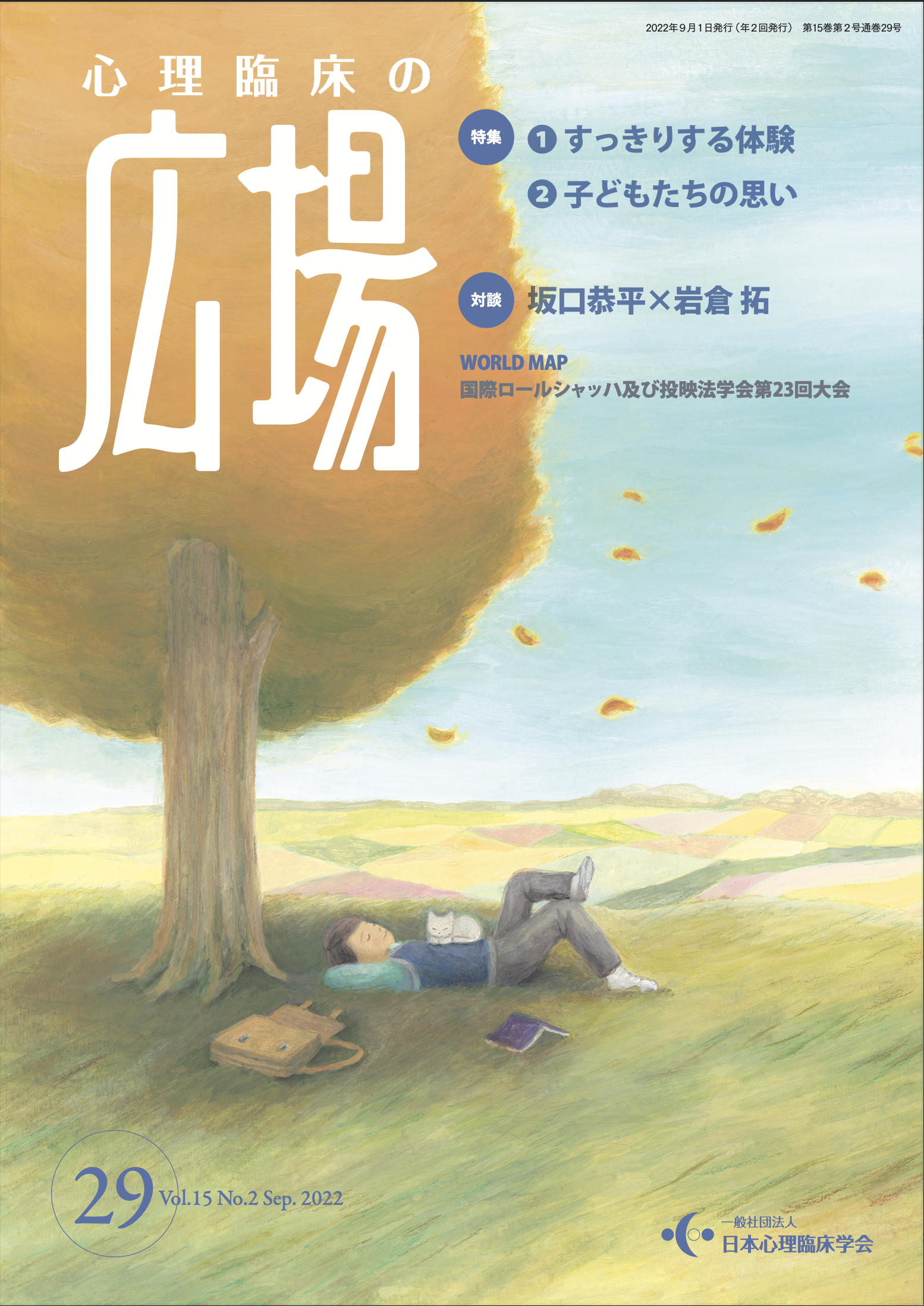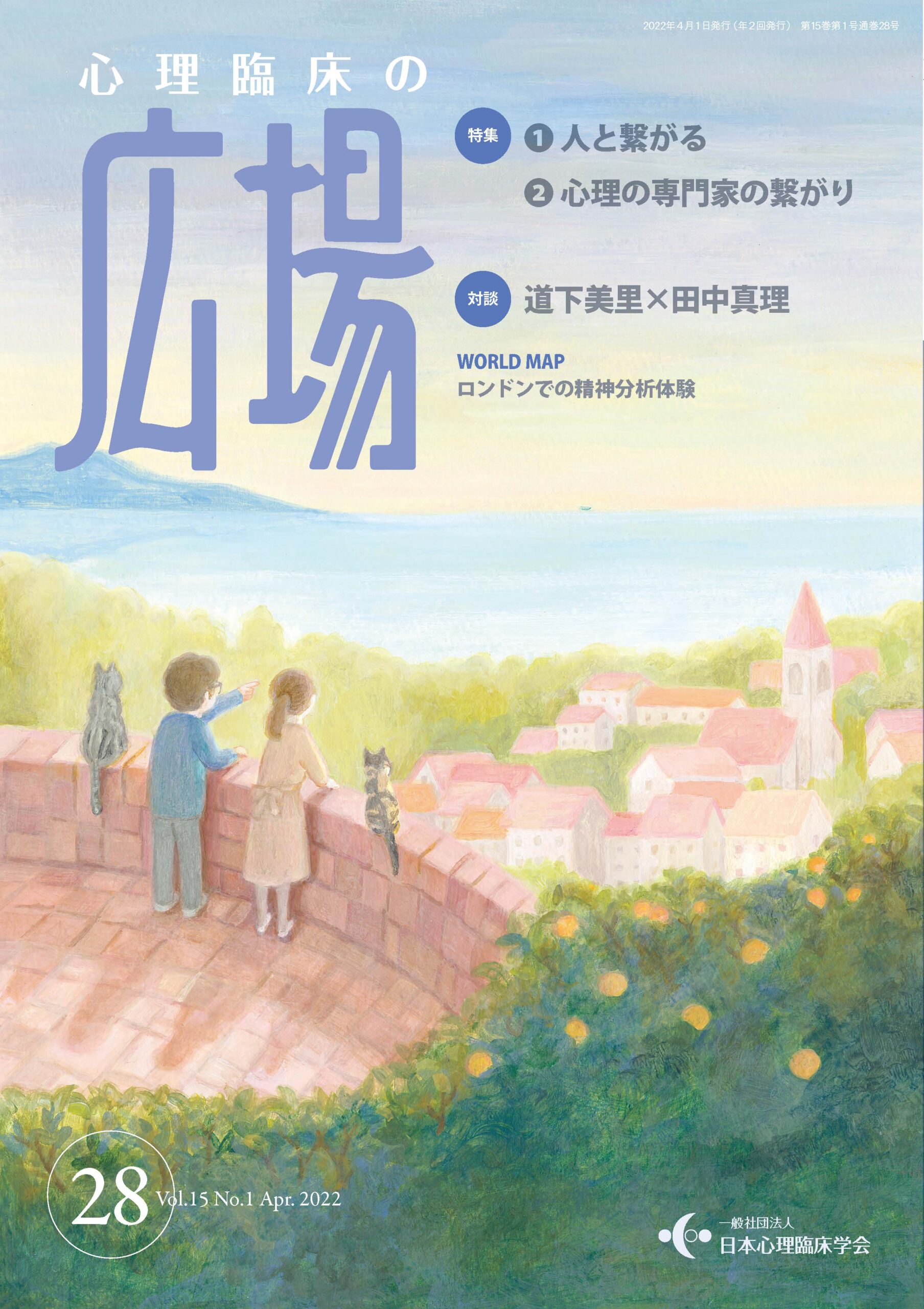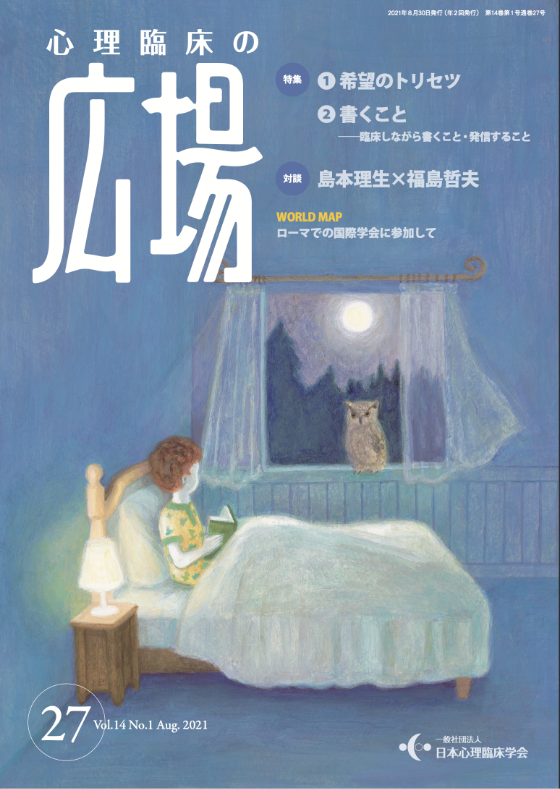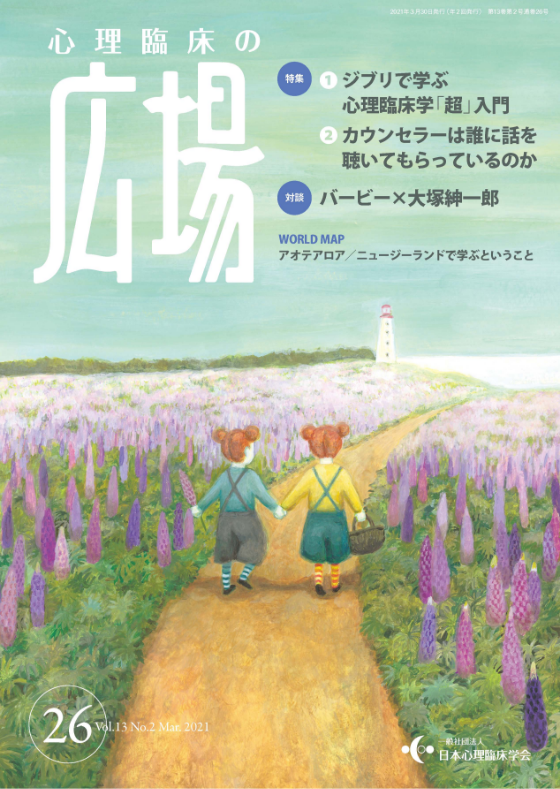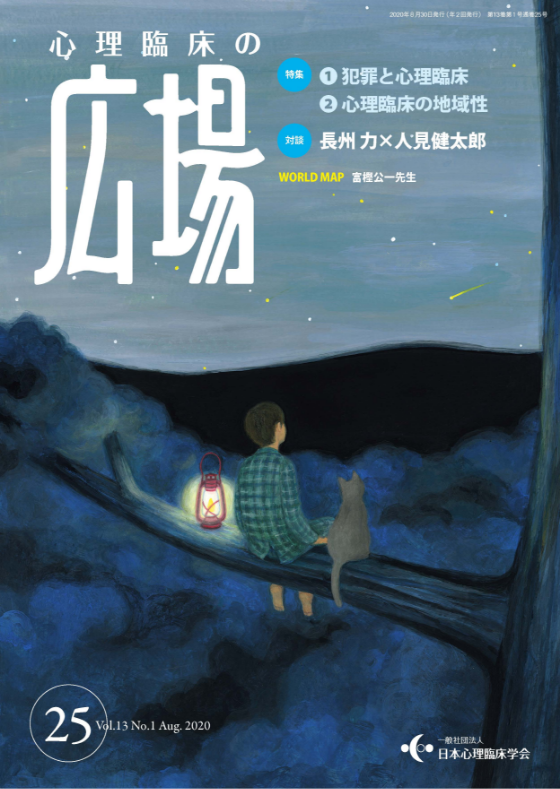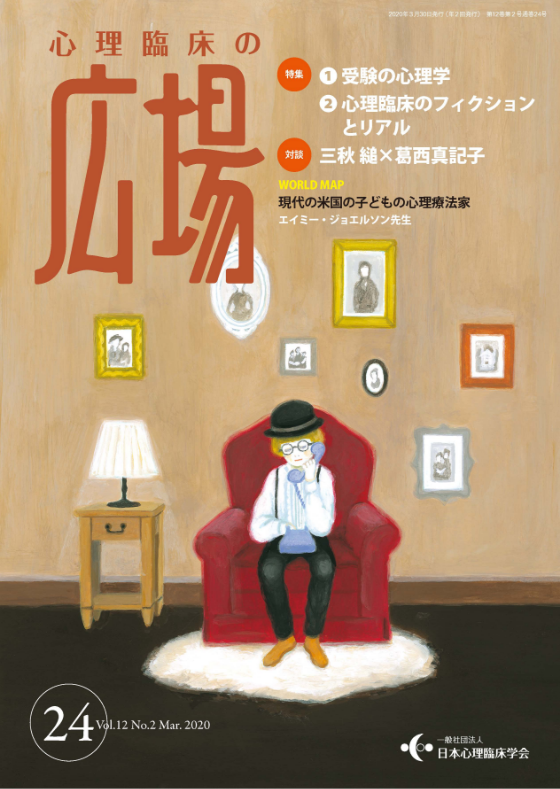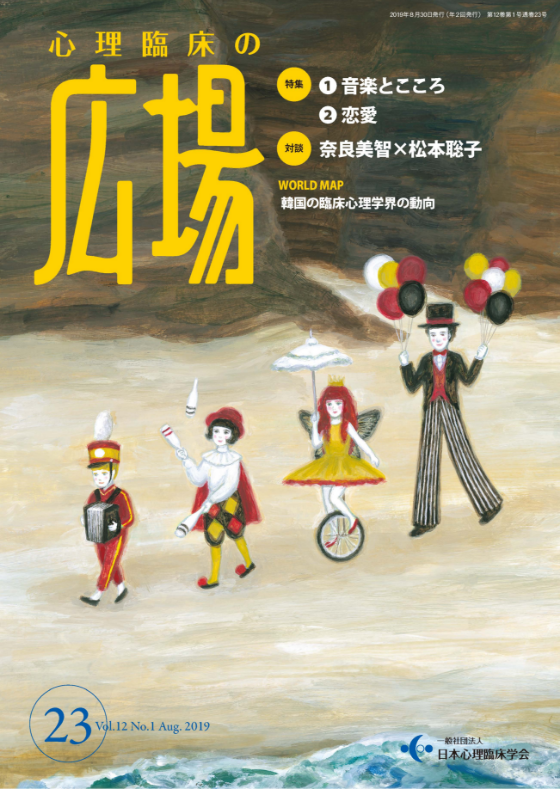はじめに
コンビニエンスストア(以下、コンビニ)が日本に誕生したのは、高度経済成長期(1955〜1973年頃)が終わろうとしているときでした。三大コンビニといわれるファミリーマート、セブン・イレブン、ローソンは、それぞれ1973年、1974年、1975年と、連続して相次ぎ誕生しました。今では、コンビニは、全国に広まり、約5万5000店舗あるといわれています。
経済産業省によると、コンビニは、「飲食料品を扱っている」「セルフサービス方式を採用している」「売り場面積が30㎡以上250㎡未満である」「営業時間が14時間以上」と定義されています。しかし、現在のコンビニは、商品の販売だけではなく、銀行・金融、行政、郵便・宅配サービスなど、多岐に渡っています。この他に、年中無休、24時間営業という特性を活かして、地域の安全・安心を見守る活動も行っています。
コンビニが招いた不健康な食習慣
コンビニは、その名前の通り、便利(convenience)な店(store)です。コンビニは、私たちの時間と費用と手間を減らし、日常生活における利便性を究極的に高めました。距離と時間の利便性は、私たちの食行動に大きな影響を及ぼしました。用もないのに、コンビニの前を通ると寄ってしまう。刺激―反応理論にあてはめると、コンビニが刺激になり、食べるという行動を引き起こしていると、説明できます。歩きながら食べている人をみかけるようになったり、決まった時間に食事をとらず、食べたい時に食事をとるという人も増えてきました。これは、コンビニが広まった、すなわち、「食べる」刺激が増えたという結果だといえます。
コンビニの出現は、私たちの食事の「食べ方」だけでなく、食事のそのものにも、影響を与えました。それが「中食」です。中食とは、家庭外で調理されたものを持ち帰って食べる食事を指します。中食が広まった背景には、物流の発展が関係しています。コンビニができた当初は、1日1回の店舗への配送でしたが、1980年代終わりに1日3回、温度帯別に配送ができるようになりました。このことにより、食品衛生や味の観点からも高品質の商品を販売することができるようになりました。
物流の発展により、高品質な商品の販売は可能になりましたが、コンビニ弁当を含む中食弁当には、栄養バランスの観点から課題があります*1。中食弁当の野菜量を調べた研究によると、平均野菜量は1食あたり35gであり、全体の25%の弁当が野菜量0〜8gであったと報告されています。野菜の摂取目標量は1日あたり350g以上と定められていることから、1食あたり120g程度が必要になります。1食あたり約10gの中食弁当では、野菜不足の可能性が出てくるといえます。
コンビニには、弁当だけでなく、カップ麺や清涼飲料水といった加工食品が多く陳列されています。これらには、食塩や砂糖が多く含まれていることから、摂り過ぎは健康への悪影響が懸念されます。たとえば、カップ麺の食塩相当量は1個あたり4〜7gであり、1個で1日の目標量(男性7.5g未満、女性6.5g未満)の半分以上を摂取することになります。
コンビニで商品陳列を変えることで、カップ麺の選択行動が変わるかという実験的な研究があります*2。これは、ナッジ(nudge)を用いた研究です。ナッジは、人間は直観に基づいて意思決定をする傾向にあるというヒューリスティックの特徴をふまえ、無意識のうちに選択を誘導する手法のことを指します。この研究では、カップ麺の食塩が少ない商品を目の高さに、そして、食塩の多い商品を目につきにくい下の方へ移動させ、カップ麺の売れ行きを検討しました。その結果、取組み前5カ月間の売り上げ上位3位は、6g台(カップ麺全体の販売の31.6%)、7g以上(27.0%)、5g台(23.9%)であったのに対し、取組み後の5カ月間では、4g台(37.5%)、2g台(22.7%)、5g台(21.8%)に変わり、含有量の少ない商品割合が有意に増加したと報告されています。ナッジでは、「選択の自由」を妨げないという前提があるため、食塩を多く含む商品の販売を禁止するという方法はとれません。しかし、この研究では、食塩の多い商品の販売禁止をせずに、売り上げも客単価もあがったことが報告されています。顧客を健康な食行動へ自然と誘導し、コンビニにとっても良い結果となった事例です。
コンビニが家庭の代わりになるのか
食事には、誰かと一緒に食べることで、人間関係を深めるという機能もあります。誰かと一緒に食事をすることを、「共食」と呼び、共食は精神的・心理的な健康に寄与するだけでなく、栄養バランスのとれた食事の摂取にも寄与します。
共食の反対である「孤食」が日本で問題になってきたのは、コンビニができて10年ほど経ったときでした。1982年にNHKが「こどもたちの食卓〜なぜひとりで食べるの〜」という番組を報道し、孤食の課題が注目されるようになりました。この番組で登場する食事がコンビニ食だったというわけではありませんが、コンビニから普及した中食弁当は、孤食を後押ししたと考えます。他に、コンビニができてから、保護者が留守をするときの作り置きから、お金を置いて好きなものを買わせる家庭も出てきていたといわれています。コンビニの普及により、家庭の味を通じた親子の関係が途絶えてしまうような事態も起きています。
一方で、コンビニが人との交流の場となっているという話もあります。たとえば、ラジオ体操を終えた後、近所のコンビニの飲食スペースで、友人とコーヒーを飲んで帰る高齢者がいたり、団地にあるコンビニが住人のつながりを生む場になっているという話もあります。一人世帯が増える現代、コンビニが人と人をつなぎ、家庭のような役割を担っているといえます。
終わりに
コンビニの出現は私たちの生活をきく変えました。その変化は、悪い方向だけではなく、良い方向のものもあります。肝心なことは、私たちが「どう活用するか」です。仕事や勉強でがんばったあと、コンビニに寄って、スイーツを買う。この頻度が高かったり、量が多かったりすると、健康への問題が生じます。しかし、頻度と量をコントロールできるなら、モチベーション維持やストレスマネジメントとして、コンビニが活用できます。心理学の知見を用いて、行動をコントロールし、コンビニと上手くつきあうことが今後さらに求められるでしょう。
*1 谷内ななみ他(2025)「市販の弁当に含まれる野菜等食材の特徴」栄養学雑誌83 p.140-150
*2 川畑輝子他(2021)「医療施設内コンビニエンスストアにおけるナッジを活用した食環境整備の試み」フードシステム研究27 p. 226-231