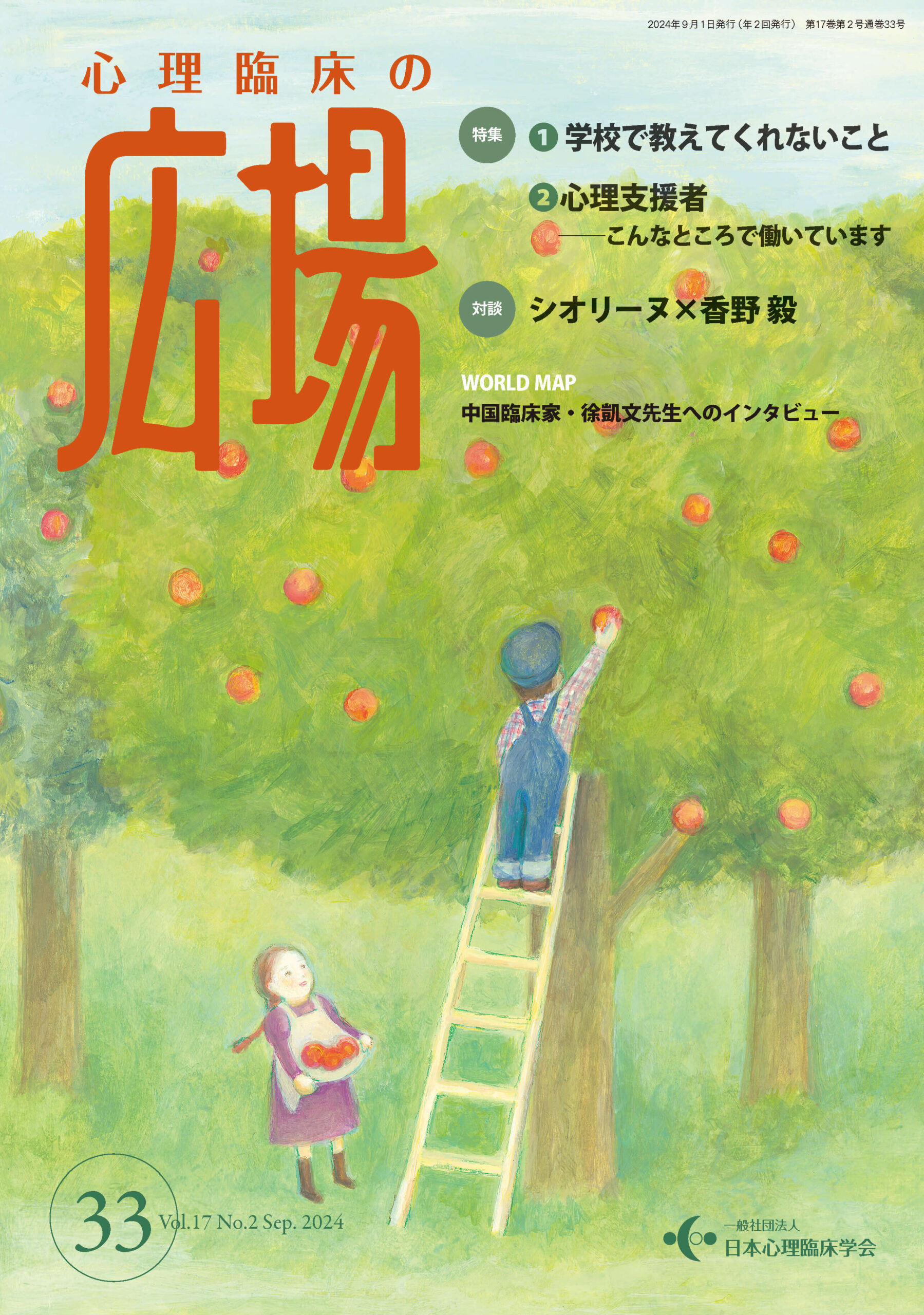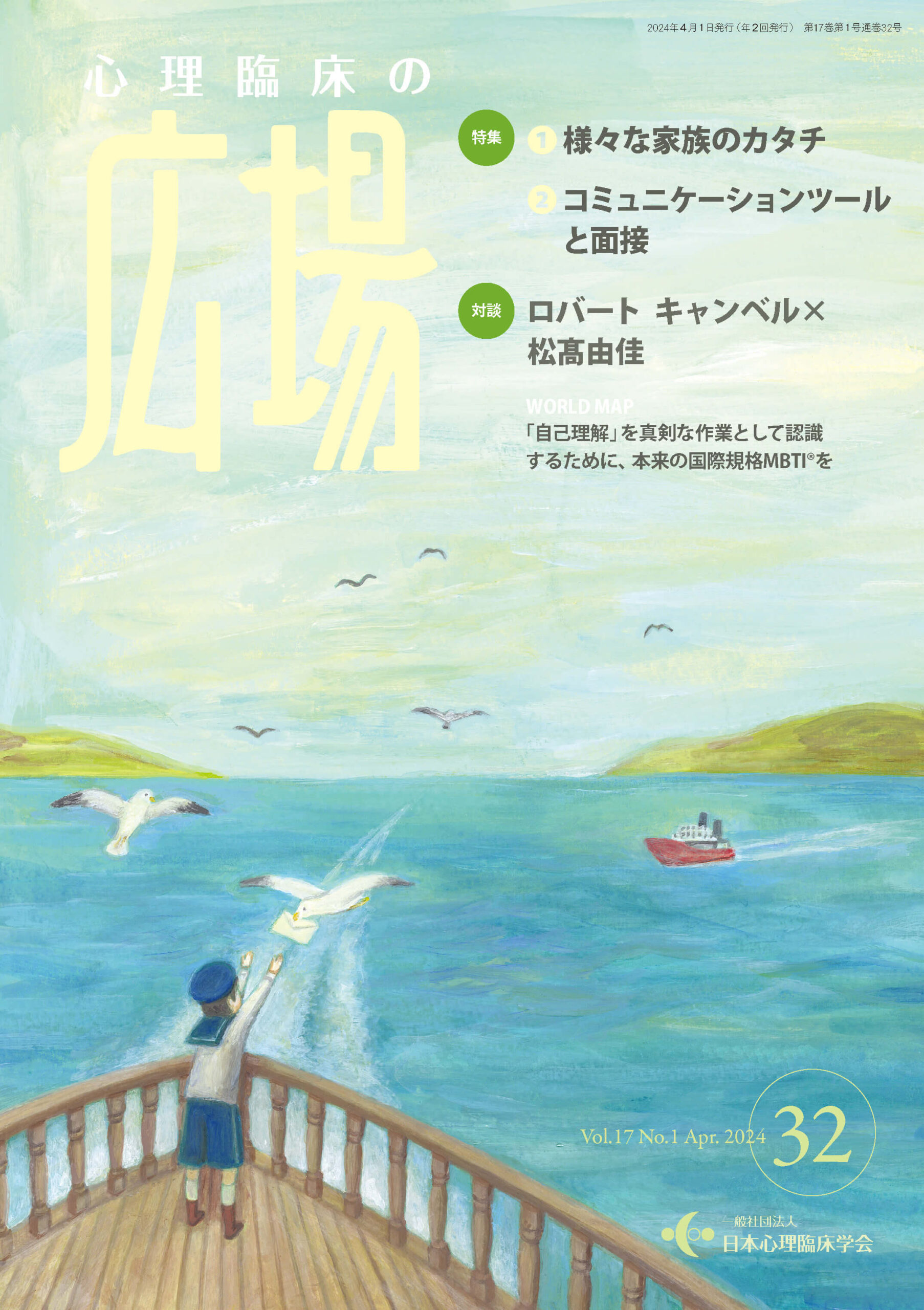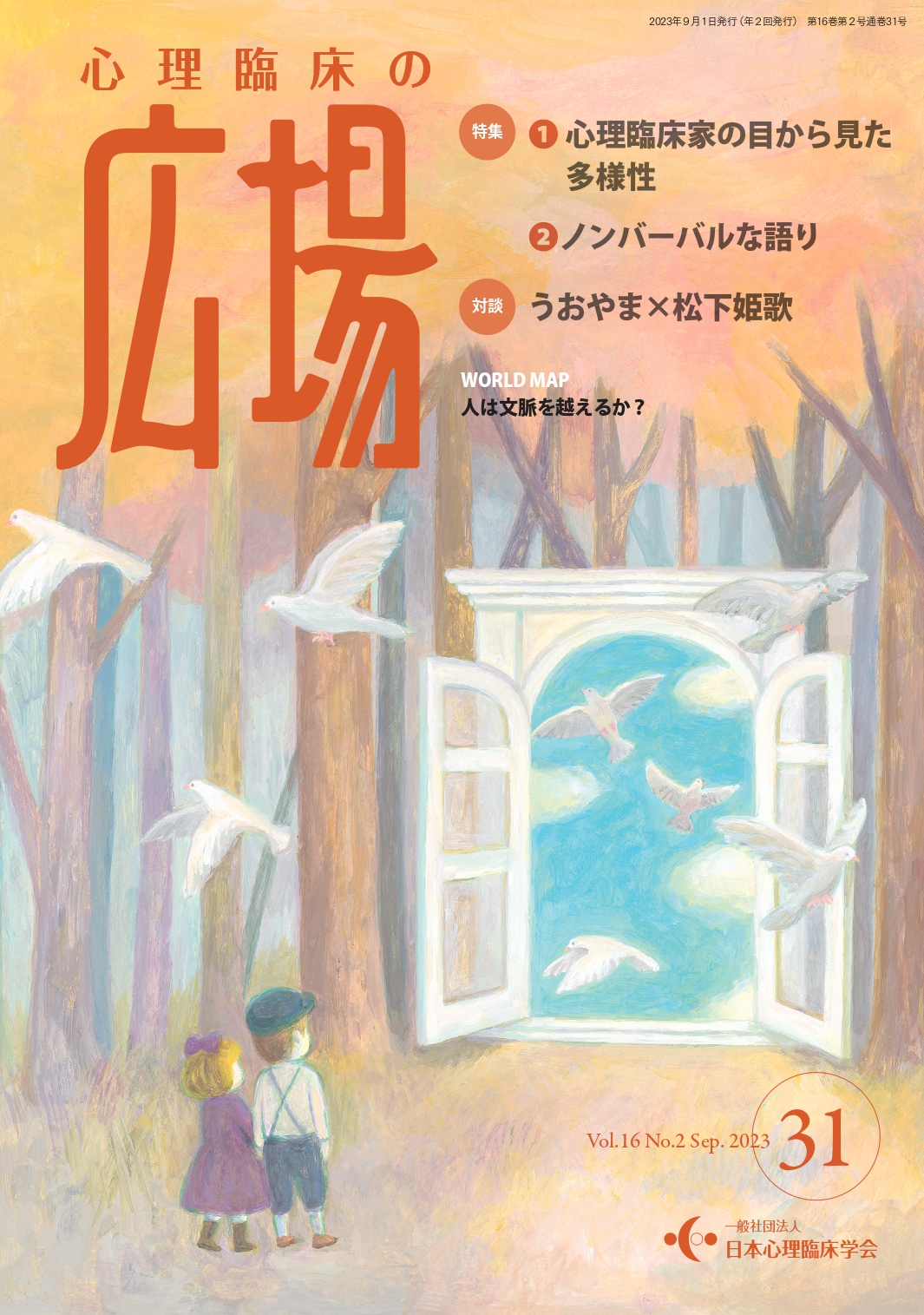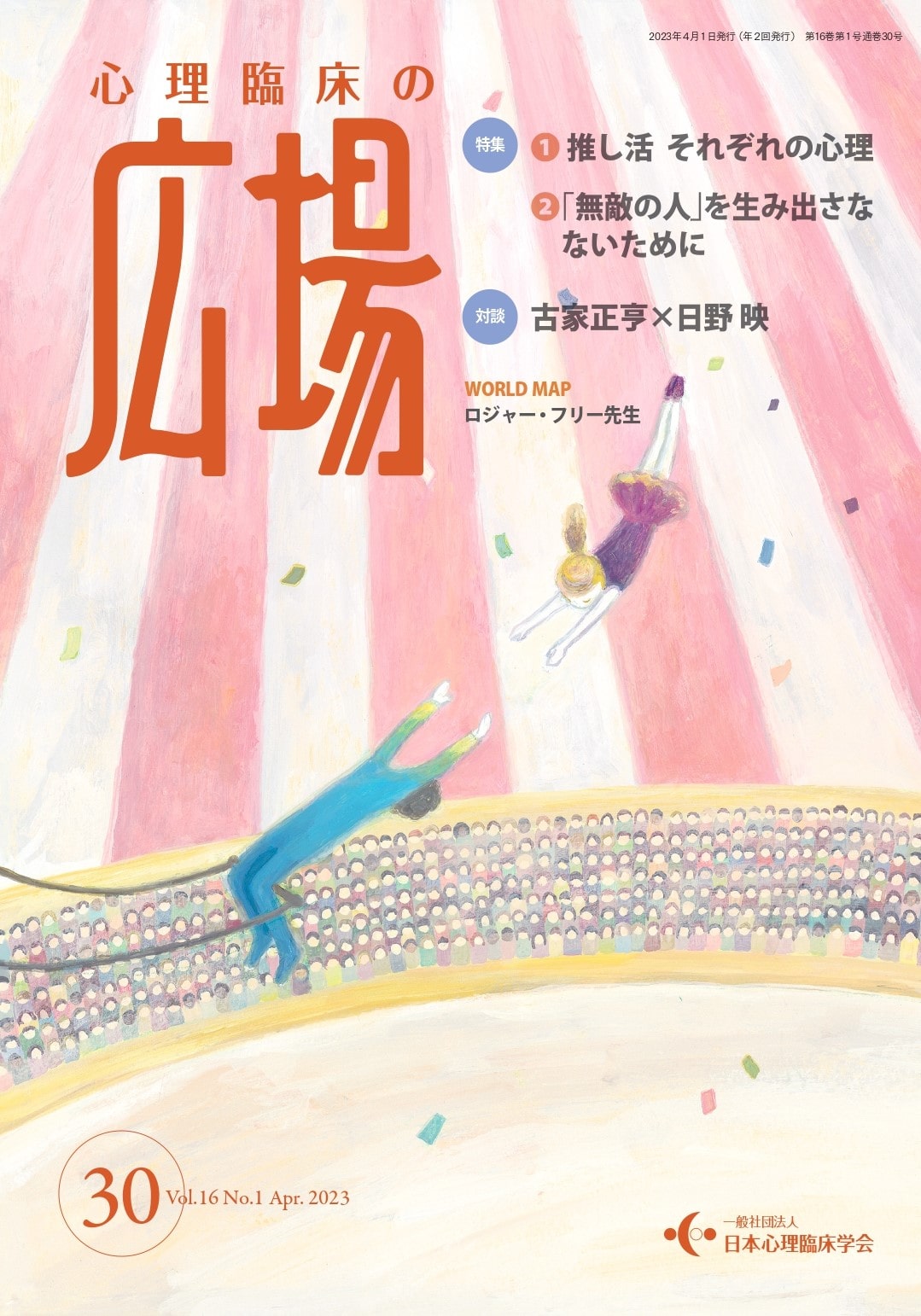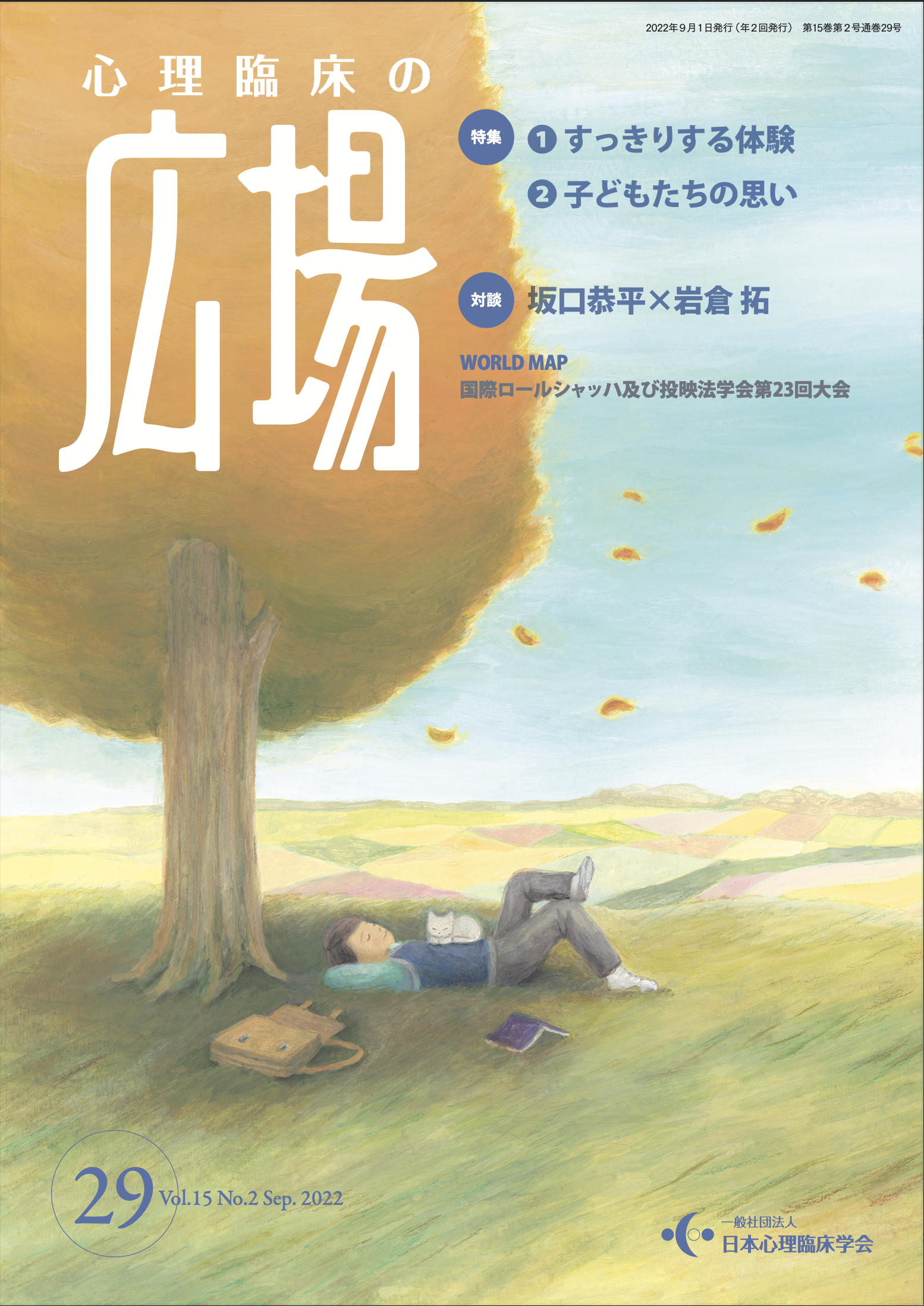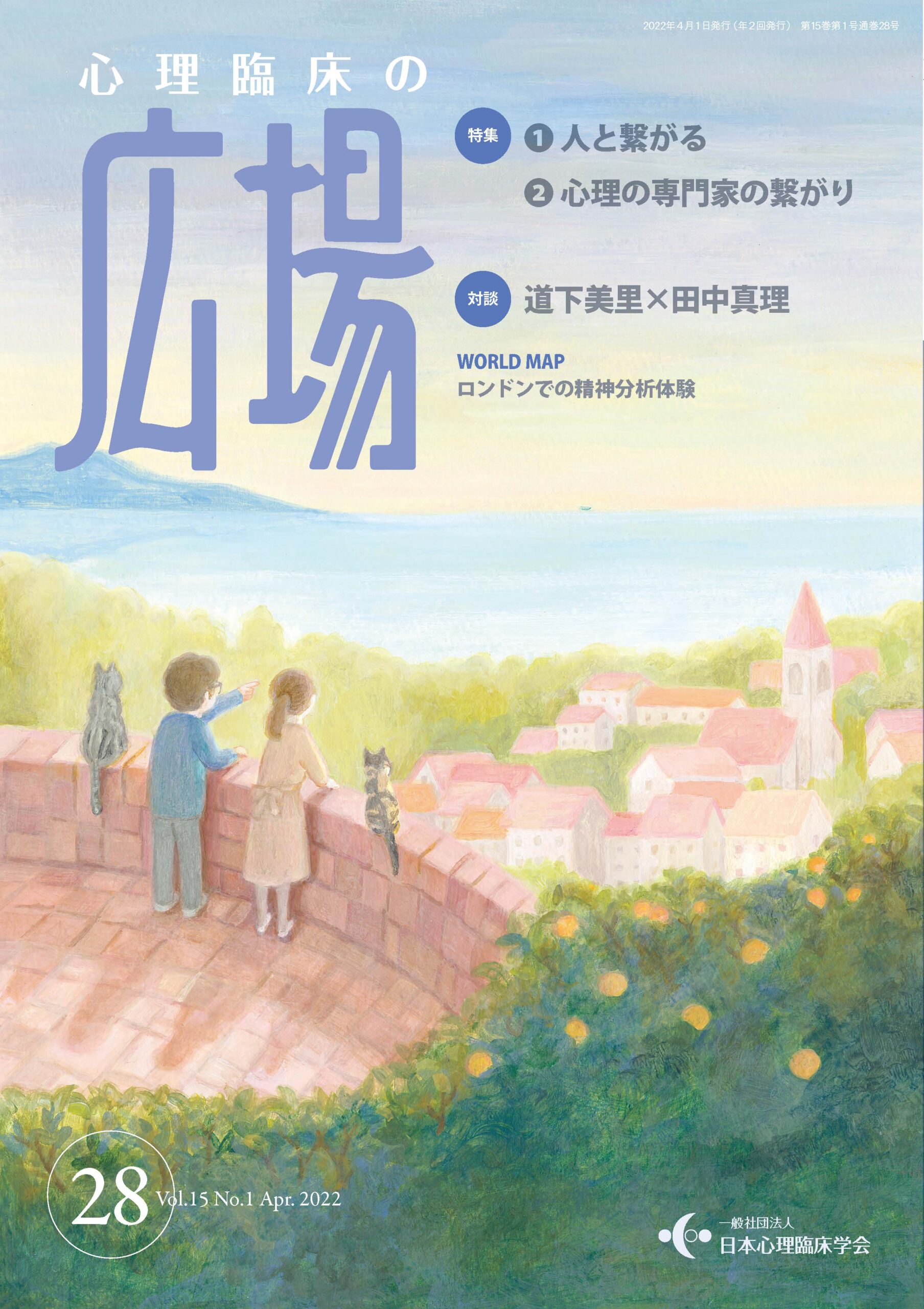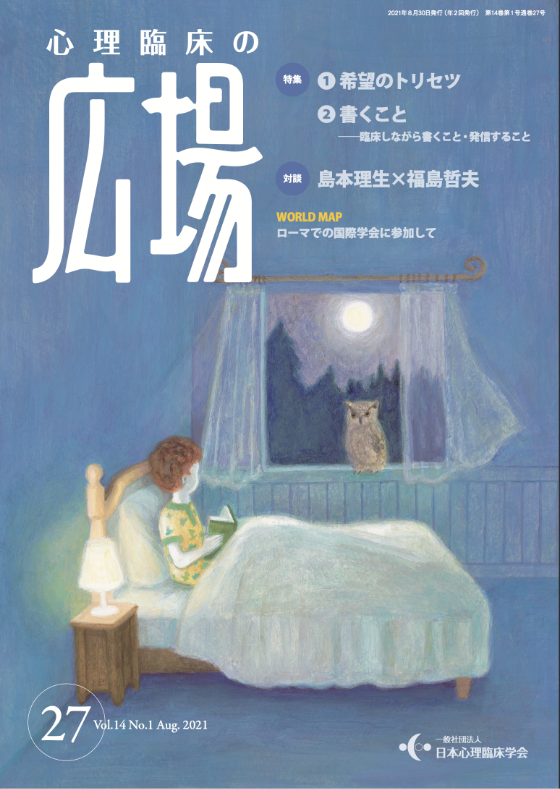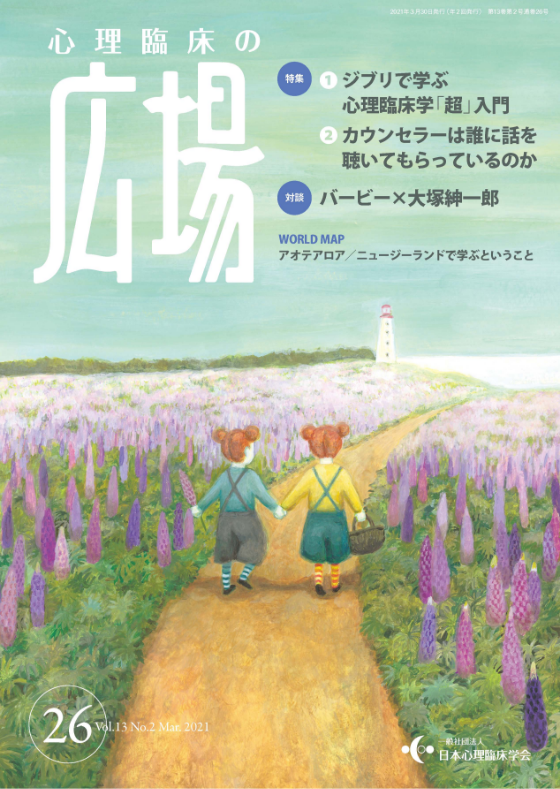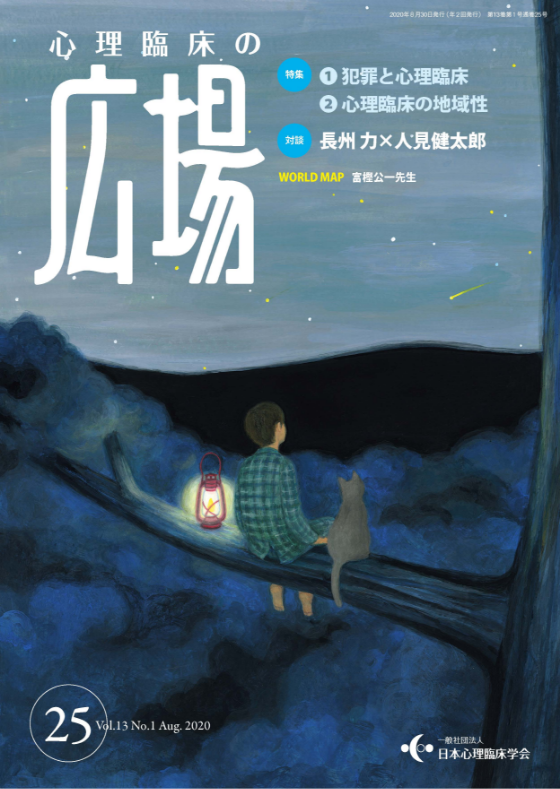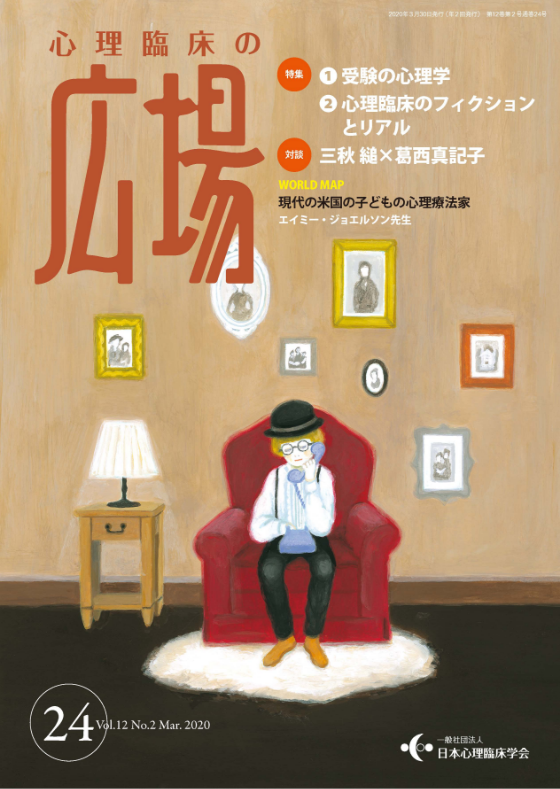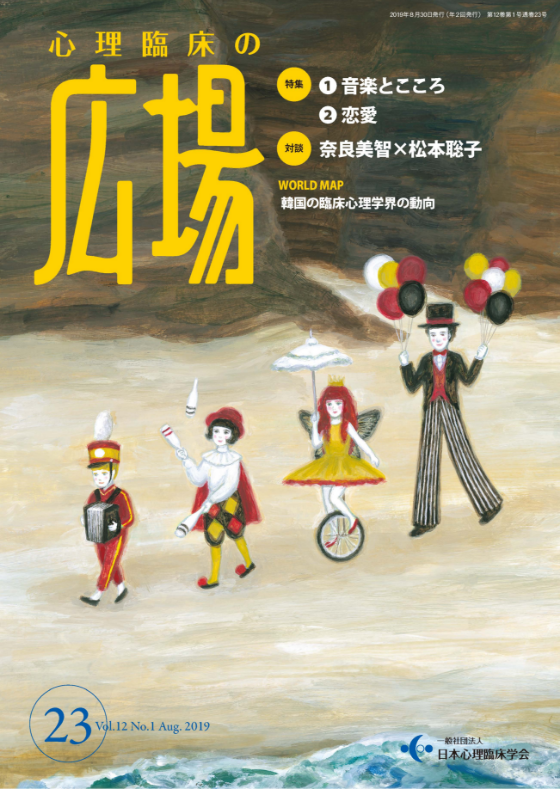トイレで食事をする若者
筆者は以前、「便所メシ」という言葉を取り上げて論じたことがある。この言葉は2009年に朝日新聞で、最近の大学生のなかに昼休みにトイレのなかで昼食を食べて過ごしている者がいるということが取り上げられたことから始まったと言われている。その時は最近の若者に見られる特徴的な行動として取り上げたのであるが、それからもう10年以上がたった。当時、この記事に対しては「都市伝説に過ぎない」などの批判もあった。実際、筆者が勤めていた大学の学生たちの多くがその存在に懐疑的であった。しかし、しばらくして実は自分もトイレで食事したことがあるという学生が、何人か現れて驚いたことを覚えている。
トイレで食事をする理由は、一人きりで食事をしている姿を知人に見られたくないからだという。一人でいると、友人がいないと思われるのではないかと恐れ、そのような姿を人前に晒したくない一心でトイレにこもるのである。なかには自分の場合は昼食を食べないで我慢しているという学生もいたが、家の人がお弁当を持たせてくれた場合などは、捨てるのも忍びない気持ちから、やむをえず人目につかないトイレでの食事を摂ることもあるのだと想像された。
筆者にとっては驚きの現象だったのであるが、それから数年のうちに、これは珍しくない現象として認識されるようになっていった。その背景には日本のトイレが目覚ましく清潔になり、ほとんど無臭の空間になったこともあるだろう。確かに、筆者などの研究室より、大学のトイレの方が清掃も行き届いていて快適である。今やトイレはくつろぎを演出するスペースになっているといえるだろう。
「ぼっち」と「いつメン」
このような現象の背景には、「ぼっち」を恐れるという心理がある。「ぼっち」 というのは 「ひとりぼっち」のことで、これも随分前から若者たちの間でのスラングとして用いられている。
このような「ぼっち」を恐れる心性は、「いつメン」と呼ばれる集団との関係で理解することができる。この「いつメン」もまた若者たちのスラングで、「いつものメンバー」「いつもの面子」 を意味するものである。「いつメン」は、よく遊ぶ親密な仲間であることも多いが、なかには必ずしも親密ではない者たちがグループになっていることもある。「いつメン」の存在感が大きくなるのは、自由なグループで行う学校行事、例えば修学旅行などのときである。また昼食の時や休憩時間も「いつメン」がいないと「ぼっち」になってしまう。「ぼっち」は、意図的な仲間はずれによってだけ生じるのではなく、それぞれが「いつメン」で固まったときに所属集団がはっきりしないものが自然に孤立してしまうという場合もある。
岩宮(2025)は以前は女子に見られた「いつメン」に固執する傾向が、近年は男子にも見られると述べ、次のように指摘している。これまでとちがい、同じ集団に所属するからといって自然に「共同体」が成り立つわけではなく、自力での共同体を作らなくてはならなくなっているというのである。「いつメン」へのこだわりも、基本的な生活を守るための「共同体」を整えるプロセスとして理解する必要があるだろう。
「おひとりさま」
「ぼっち」になることを恐れ、トイレで食事をするまでに追い込まれていく若者たちがいる反面、「おひとりさま」とも呼ばれるように、ひとりで食事をすることはライフスタイルとして確立されてきている側面もある。
株式会社電通の「食生活に関する生活者調査2024」によると、「おいしいものは一人でなく、誰かと一緒に食べたい」「家族との食事は、ストレス緩和になる」「友人との食事は、ストレス緩和になる」と答えた人の割合は、2022年から2024年にかけて減少している。これらはコロナ禍から始まった調査ではあるが、コロナ禍が収束して会食の喜びが復活するのではなく、むしろ孤食が常態化してきている印象を受ける。
これらの調査結果は、「おひとりさま」というライフスタイルが広く定着してきていることを意味していると考えられる。コロナ禍を経て飲食店の多くに衝立が出現したことによって、拍車がかかった部分もあるだろう。会食することが(感染などの)リスクとして認識されたことも影響していると考えられる。
また、家庭内でも「孤食」「個食」が増加しているという。「孤食」はひとりで食事することであるが、「個食」とは家族がそれぞれ別の食事をとることである。これらは共に「共食(家族や友人と一緒に食事をすること)」という文化の危機であるとされているが、その背景には共食したくともできない状況があることも忘れてはならない。今や両親がともに仕事をしていることは当たり前となっており、家族で食事の時間を合わせることが困難になっている。
個々人の生活リズムがばらばらになっていき、生活共同体の結びつきも希薄化していることが孤食化の背景にあるといえるだろう。つまり「おひとりさま」もトイレで食事をすることも、極めて現代的な食事のスタイルなのである。
新しい食事のスタイル
それでは現代の若者たちがみな「孤食」を理想としているのかといえば、そうとも言い切れない。
筆者は数年前、一人暮らしをしている学生が「毎日、あるおじさんが夕食を作って食べている実況動画を見ながら、僕もご飯を食べるんです」というのを聞き、とても興味深く思った。それからしばらくして、韓国で「モッパン(モクバン)」と呼ばれる、配信者が食事をしながらリアルタイムに視聴者とやりとりをする動画が人気になっていると耳にし、新しい食事の風景が生まれつつあることを確信した。
これに関連した興味深い研究がある。海和(2024)は、大学生30名に、1日につき1回、共食、孤食、インターネットを介した食事のいずれかの条件で食事をしてもらい、食後すぐにアンケートに回答してもらうという実験を行った。結果として、食事のおいしさは、孤食、インターネットを介した食事、共食の順に有意に高くなり、その他、食事内容の満足感や楽しさなどの項目でも同様の結果が得られたとのことであった。
筆者は必ずしも「人と食べること(共食)」を絶対視するわけではないが、人と食べることによって親密性や感受性が育つことは認めたい。「共食」が難しくなっているなかで、心と心を結んでいくために、新たな食事のスタイルが生まれても良いのではないかと思っている。
●参考文献
岩宮恵子(2025)『思春期センサー―子どもの感度、大人の感度』岩波書店
株式会社電通(2025)「食生活に関する生活者調査2024」
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2024/1030-010797.html
(2025年5月11日最終確認)
海和美咲(2024)「COVID-19がもたらした食事とデジタルの共生社会」生活協同組合研究579巻 p. 38-45