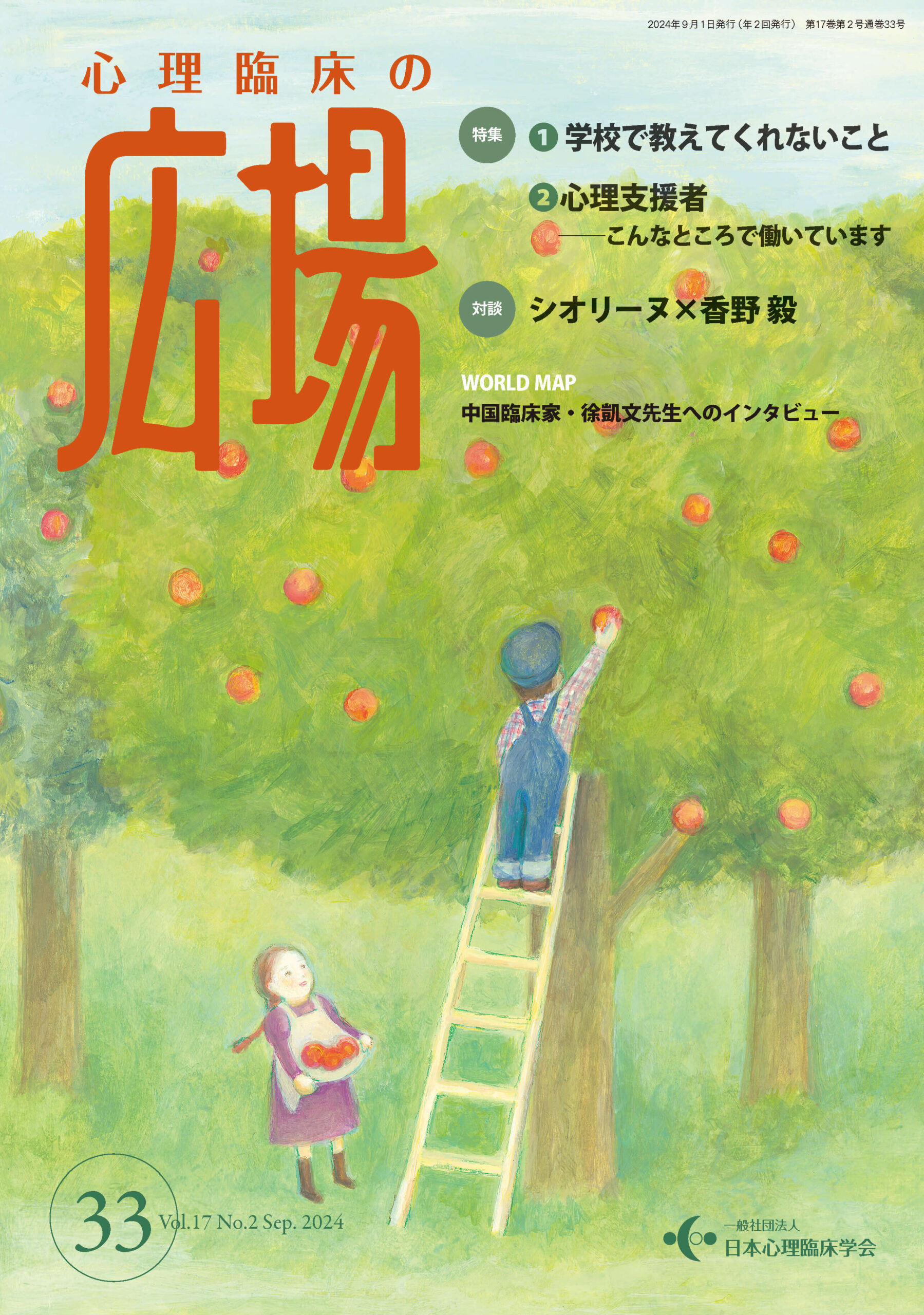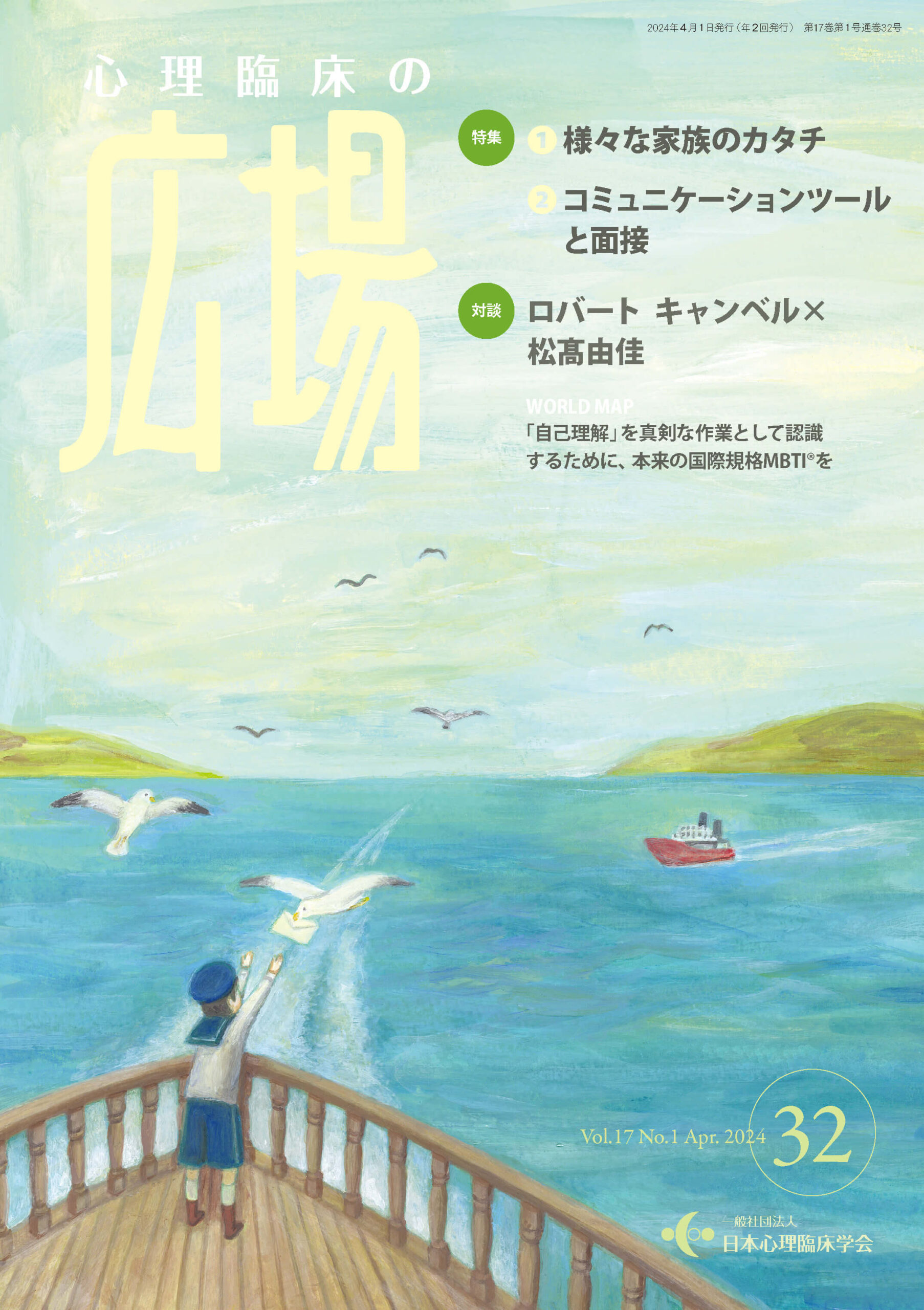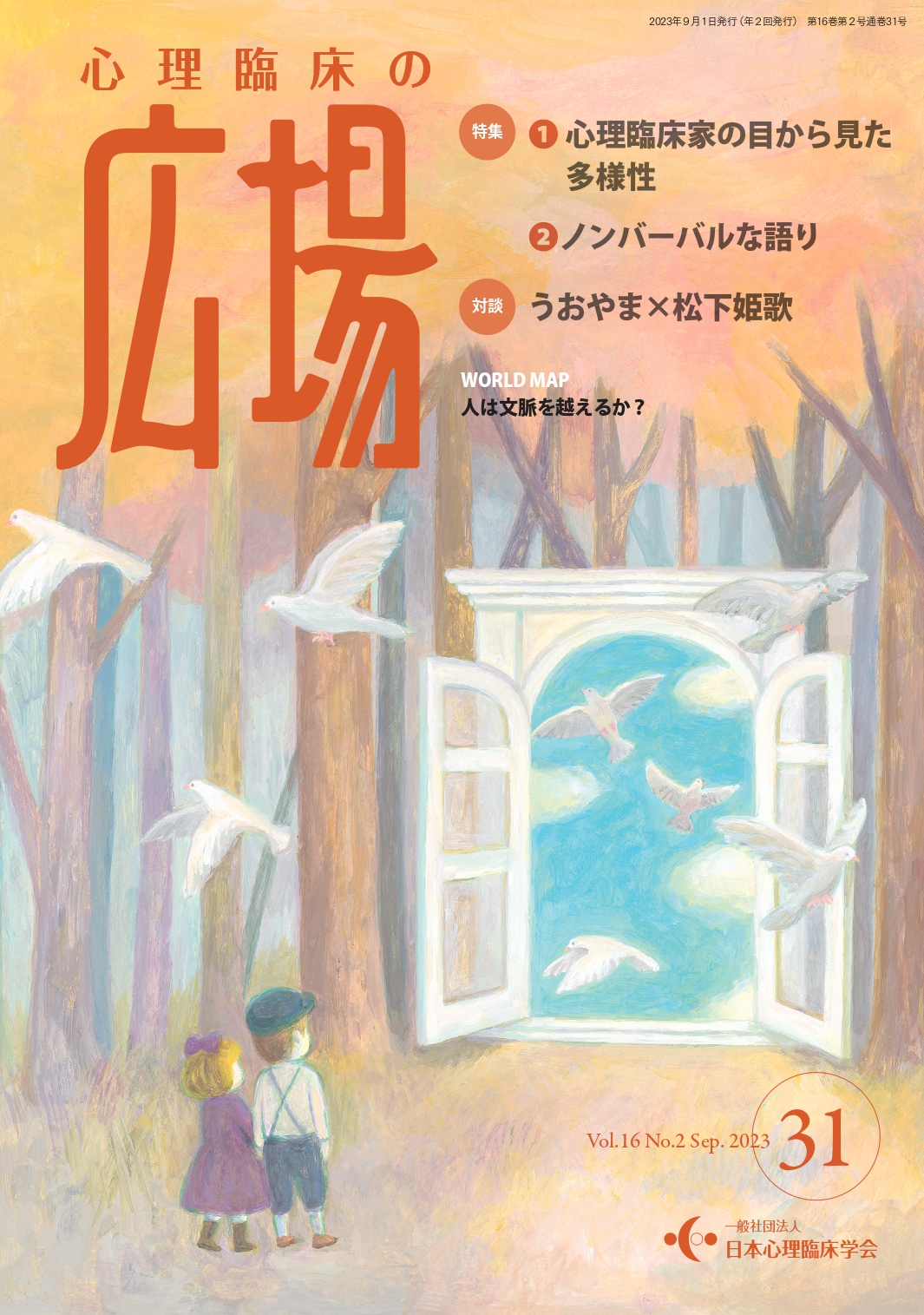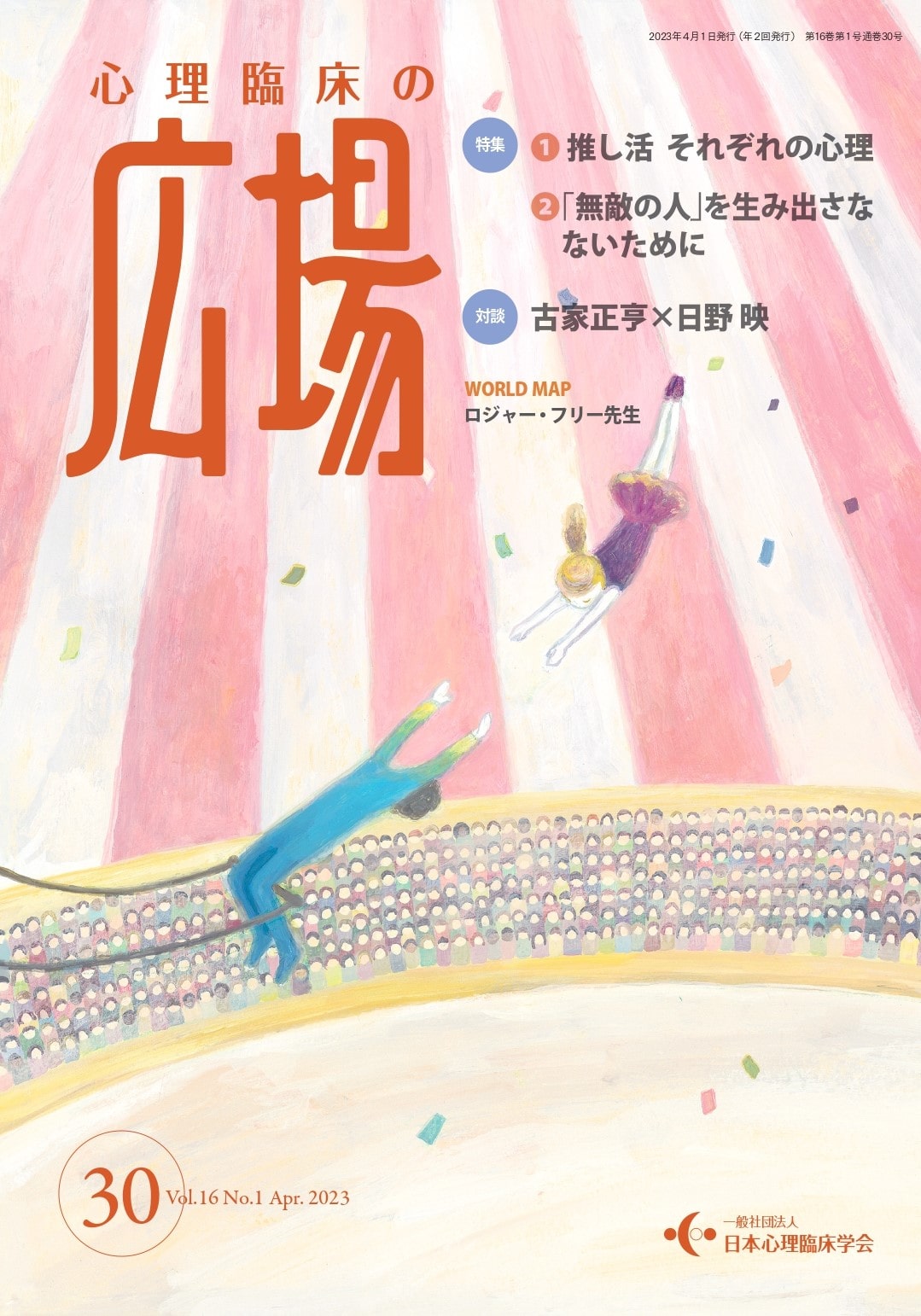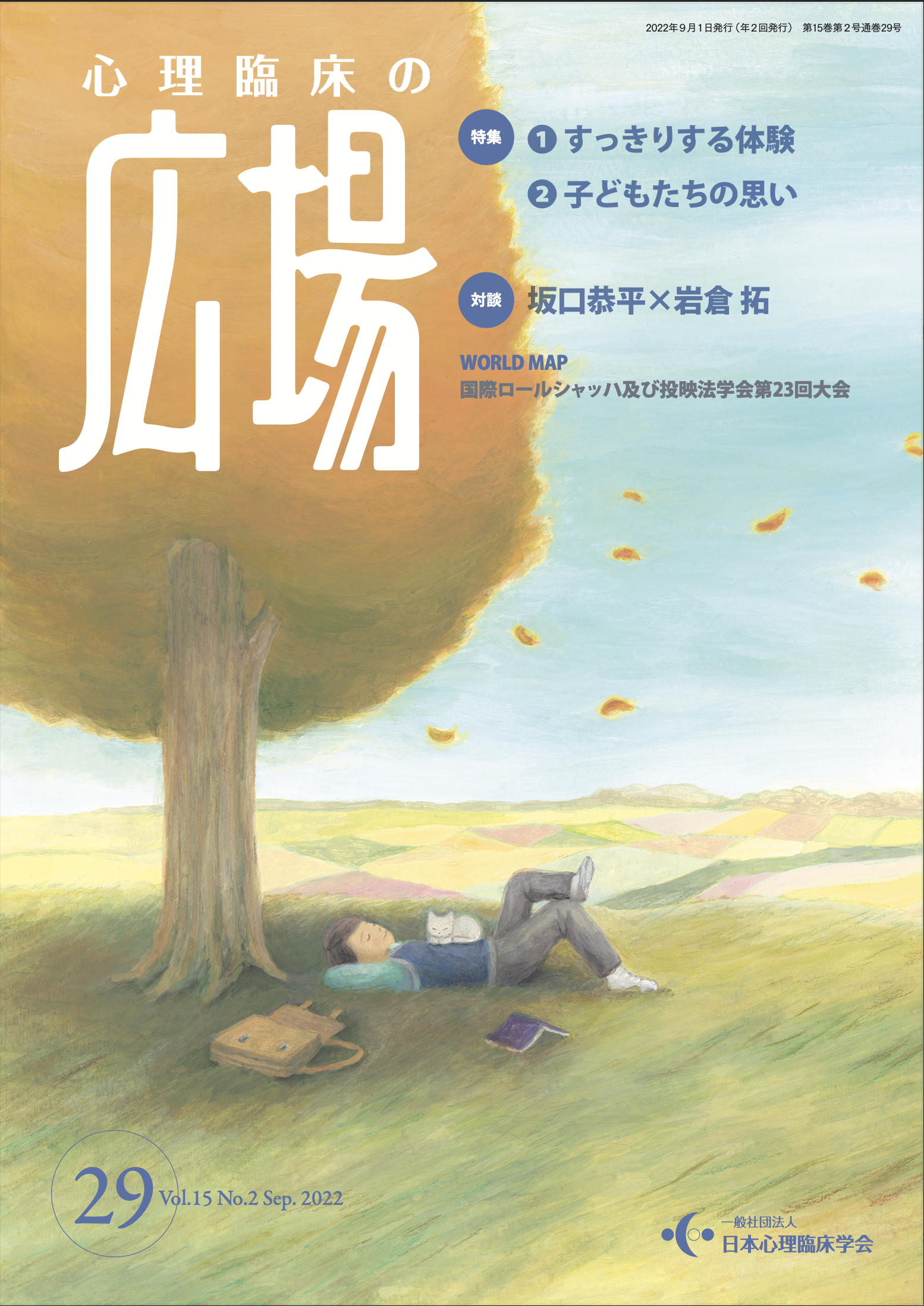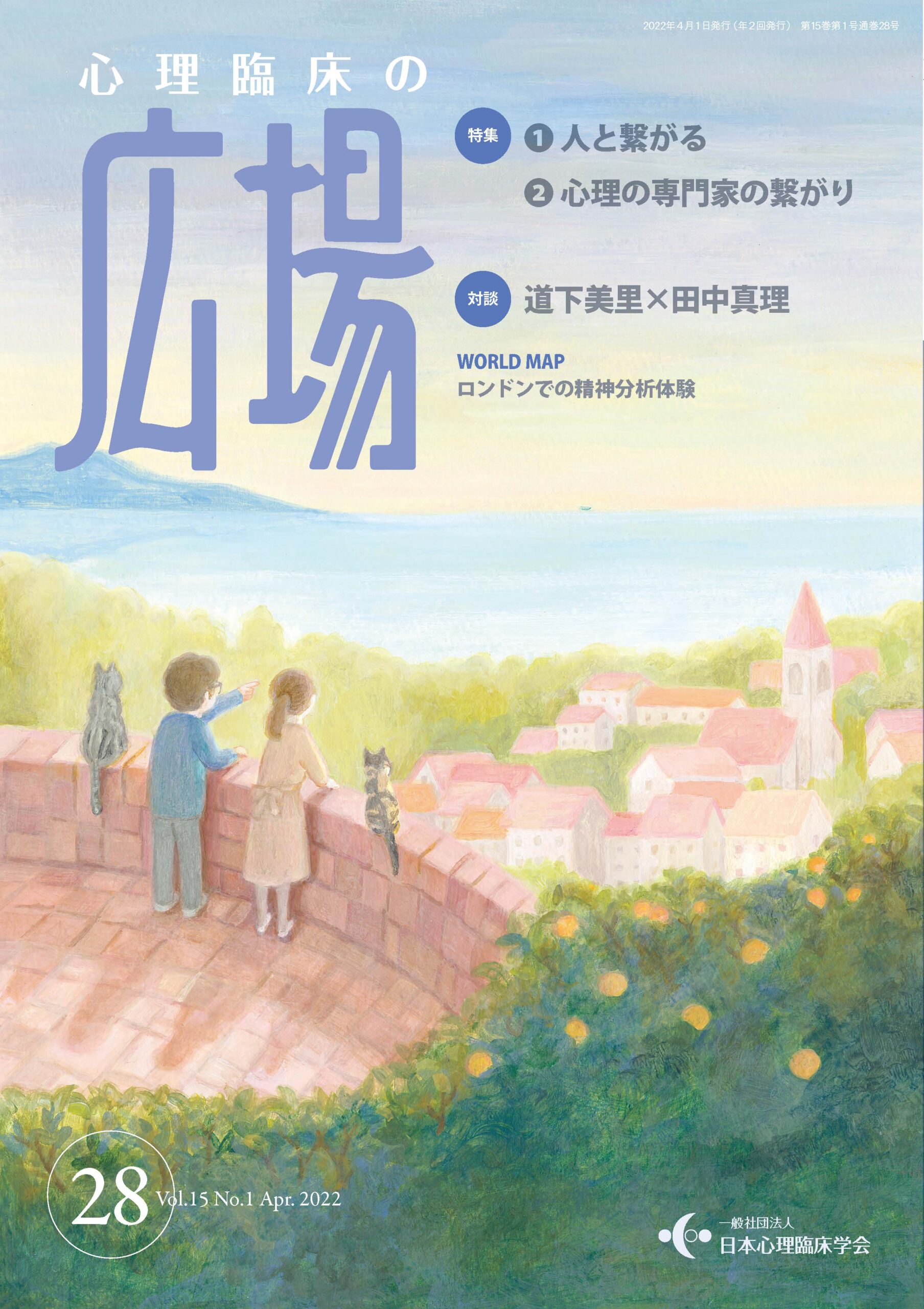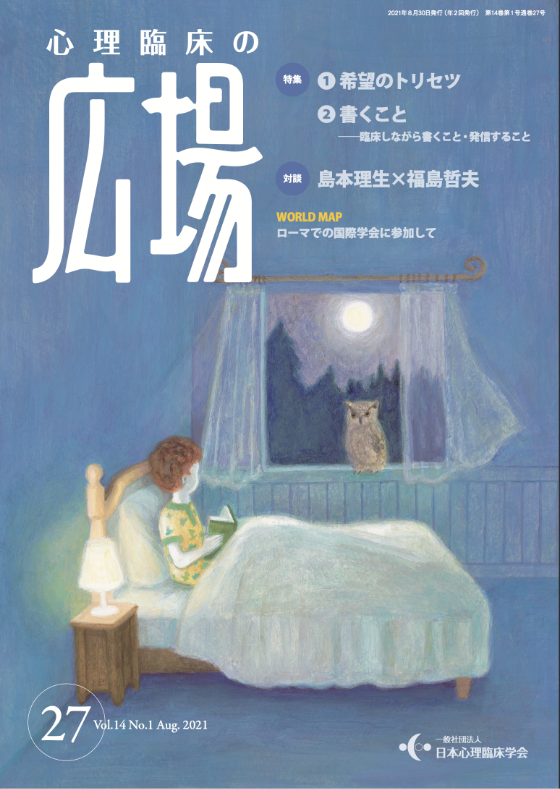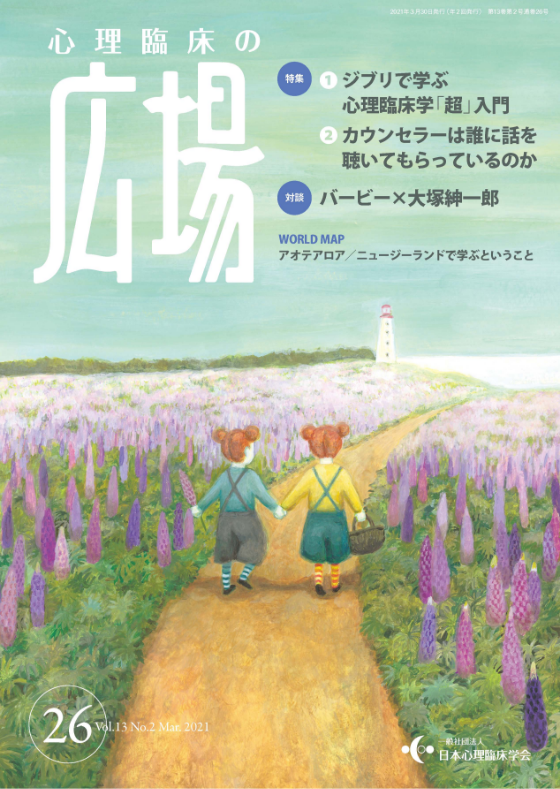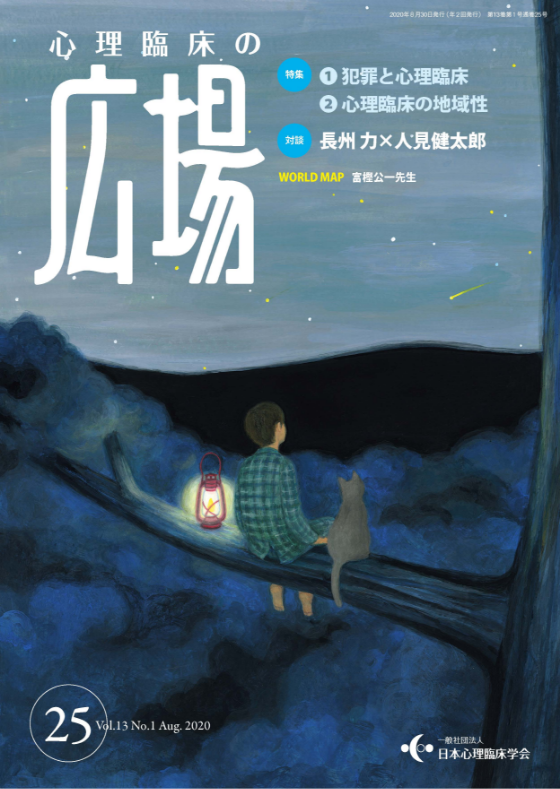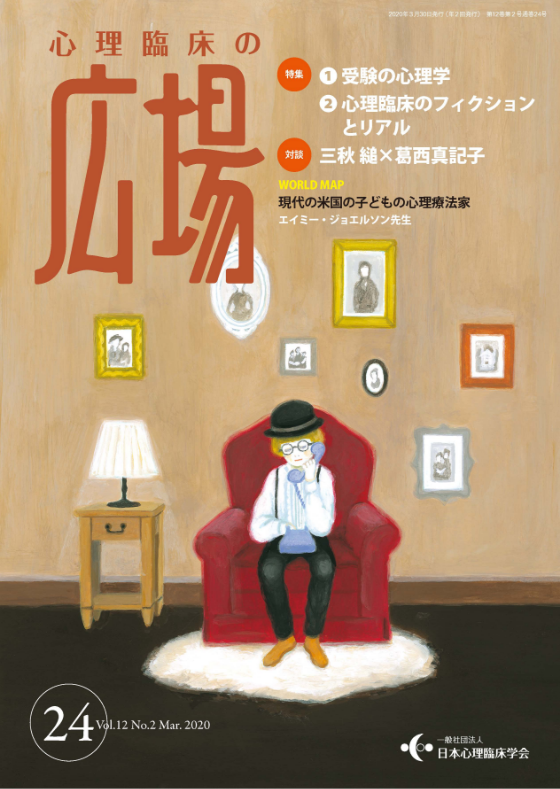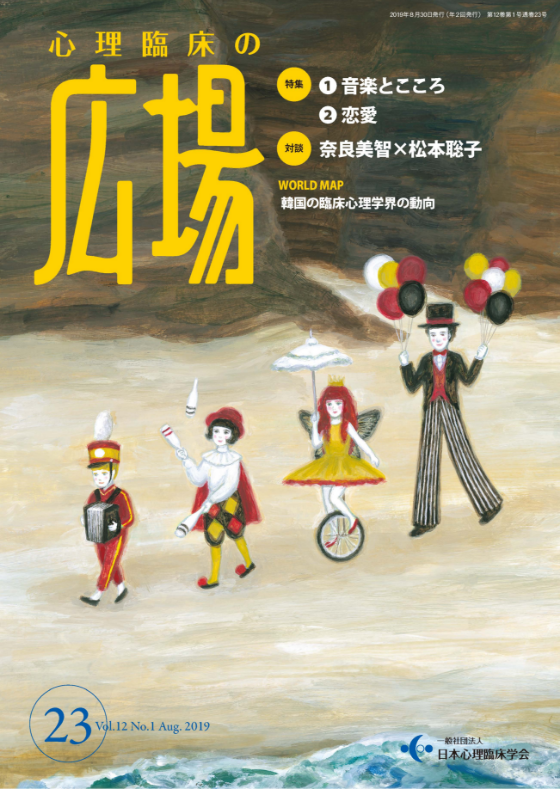毎日のように口にする食べ物は、お腹を満たすための「食糧」です。しかし、「これ、おいしいなあ」と感じると、気持ちまで明るくなったり、一緒に食べている人たちとの会話が弾んだり、幸せな気分になったりするでしょう。おいしさとは、食に関わる快感情ですが、食事は快感情を日常的に味わうことができる貴重な機会ともいえます。そうなると食べ物は単なる食糧を超え、私たちのサステイナブル(持続的)な幸福にも関係しているそうです。
マズローの欲求階層説と食
心理学には「マズローの欲求階層説」という考え方があります。アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱したもので、人間の欲求を5つの層に分け、ピラミッド型で示しています。下から順に、①生理的欲求(食べる・寝るなど命を維持する欲求)、②安全の欲求、③所属と愛の欲求(誰かとつながっていたい)、④承認の欲求(認められたい)、⑤自己実現の欲求(自分らしく生きたい)と続きます。基本的には、下の階層がある程度満たされて初めて、上の欲求に関心が向かうとされています。
ここでは「食べること」は一番下の生理的欲求に位置づけられていますが、冒頭のように考えると、食はそれだけにとどまらず、上位の欲求すべてにも深く関わっているといえるでしょう。例えば、誰かと一緒に食卓を囲むことは所属欲求に応えますし、誰もがうらやむような贅沢な食事を楽しむことは、承認欲求を満たすことにもつながります。そしてヴィーガンのように、自分の世界観や信条を食行動で表現することは、まさに自己実現の一つとも言えるでしょう。つまり、「食べること」は、人のさまざまな段階の欲求にかかわるのです。
アリモンとニュリチュール
人と食の関係については、フランスの味覚教育の創始者ジャック・ピュイゼも興味深い視点を示しています。彼は、フランス語には食べ物を表す言葉が複数あり、それぞれが異なる側面を表していると述べました。第一には「ニュリチュール(nourriture)」――命を支える栄養としての価値を指し、食事全体、食糧を抽象的に捉える語。もう一つは「アリモン(aliment)」――感覚を刺激し、精神を養う価値を含む、個別の食品や食体験、感覚・身体で味わう快に結びつきます。大切なのは、これらは別々の食べ物を現すのではなく、一つの食べ物の中に両方の側面が込められているという点です。忙しい朝にトーストをかじるときも、友人とケーキを分け合うときも、私たちは食べ物を通して、身体と心の両方に働きかける経験をしているのです。
「アリモン」としての側面は、食を文化や芸術として捉える際に重要な鍵になります。例えば、日本の和菓子には季節のうつろいや自然のかたちが美しく表現されていますし、お正月のおせち料理には、健康や豊作を願う意味が一品一品に込められています。食べるという行為を通じて、私たちは自然や歴史、そして誰かの想いとつながっているのです。
スイーツとウェルビーイング
最近、私はある企業のスイーツについての調査を監修しました。学術研究というよりも、マーケティングや啓蒙的な意味合いが強いのですが、今回のテーマに関連しそうなので少し紹介します。そこから見えてきたのは、甘いものを楽しむ時間が、単なる「おやつ」以上の意味を持っていることでした。例えば「仕事や勉強を頑張った自分へのご褒美」や「気分を切り替えたいときのひと息」といった意味を持たせる方が多かったようです。スイーツは糖質や脂質を多く含むため、ダイエットなどの観点からはネガティブに捉えられがちですが、一方で日々の達成感や自分をいたわる気持ちを可視化するような役割を果たすことができます。そうした時間を誰かと分かち合ったり、感覚を集中して一人で味わったりすれば、その楽しさや満足感はより大きく広がるでしょう。スイーツを食べる習慣がない方よりも、ある程度食べている方の方がポジティブ感情が高いことも示されました。こうした体験は「ウェルビーイング(well-being)」――人が健やかに、いきいきと生きるための基盤と深く関係しています。ウェルビーイングは3つの側面から整理されることが多いです。まず、身体が健康であること(医学的ウェルビーイング)。次に、「おいしい」「楽しい」といったポジティブな気分を味わっていること(快楽的ウェルビーイング)。そして、そうした良い状態が自分らしく、長く続いていること(持続的ウェルビーイング)です。
栄養のある食事は医学的ウェルビーイングを支えますし、おいしさや楽しさを感じる時間は快楽的ウェルビーイングに直結します。さらに、それが誰かとのつながりや文化の中で大切にされてきた味覚体験、あるいは日々の生活リズムと結びつくことで、人生の豊かさ――すなわち持続的なウェルビーイングへと広がっていくのです。上述のスイーツについても、過剰摂取は医学的ウェルビーイングにとってネガティブな影響があるかもしれませんが、頻度や量を自律的にコントロールして楽しむことができれば、甘味や脂質による根源的な快楽的ウェルビーイングが、日々の幸福感を育む要素となり、持続的ウェルビーイングを高める可能性があります。
おいしさの拡がり
私たちが「おいしい」と感じることは、単に味覚だけの問題ではありません。例えばスイーツにおいては、生まれつき人間が好む甘味の存在に加えて、可愛らしい見た目やフルーティな香り、バニラの香気、ふわふわした食感や脂質の満足感など、五感や内臓感覚、能動的な咀嚼や呼吸の運動感覚が複雑に組み合わさって働いています。さらに、誰と、どんな気持ちで、どのような場面で食べたか――その体験全体が「おいしさ」の印象をかたちづくっているのです。「あのとき食べたご飯」や「あの人と一緒に食べたスイーツ」が、人生の節々に寄り添う記憶として残っていることも、少なくないでしょう。
そして今、世界的には、人口増加を支える蛋白質確保のための畜産飼料が不足し、動物性蛋白質の安定供給が難しくなる「タンパク質危機」が迫っています。そのため、植物性を中心とした代替蛋白質の開発が進められており、おいしいものも出てきています。それに伴い、アレルギーや宗教、倫理的信条の違いを越えて、より多くの人が共に楽しめる新たな食品が現れるかもしれません。「食を通じてダイバーシティを受け入れ、同じ食卓を囲む」ことの意味は、これまで以上に大きくなる可能性があります。
食べることは、生きるための営みとしてもっとも身近な行為です。ただ空腹を満たすだけではなく、感じ、思い出し、そして誰かとつながっていく人生の伴走者にもなりえるでしょう。今日のみなさんの食卓も小さな幸せとして思い出されることがあるかもしれません。