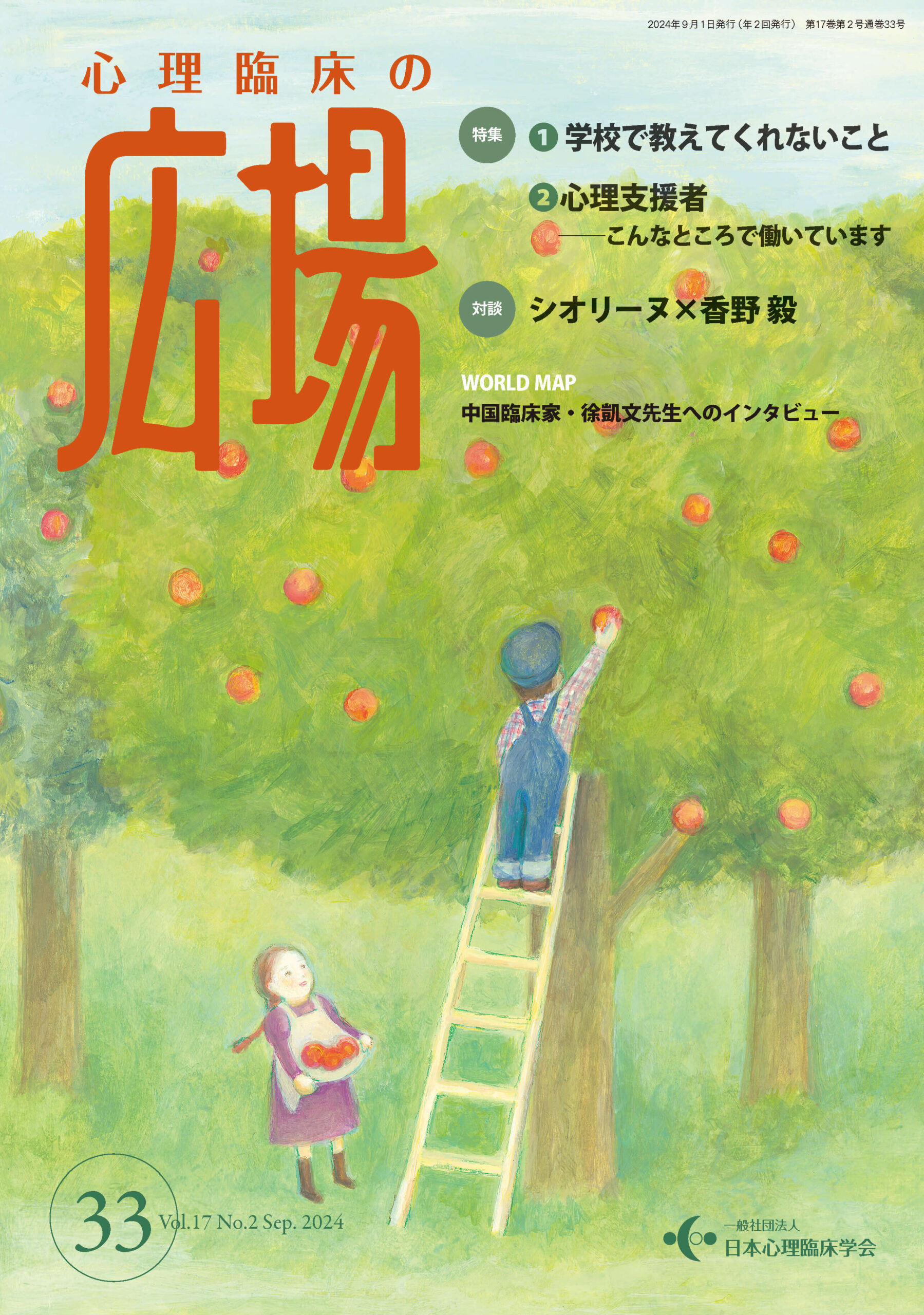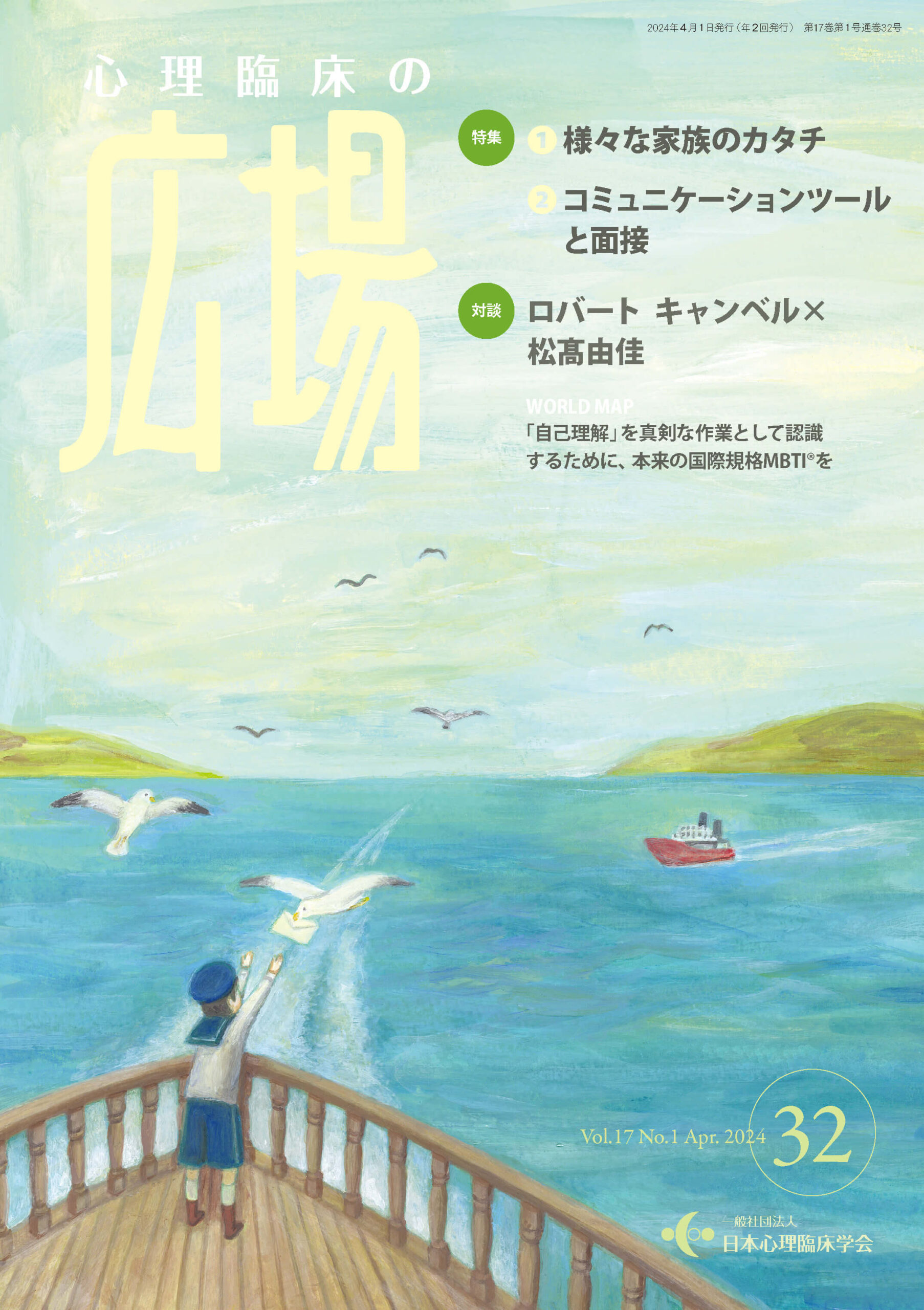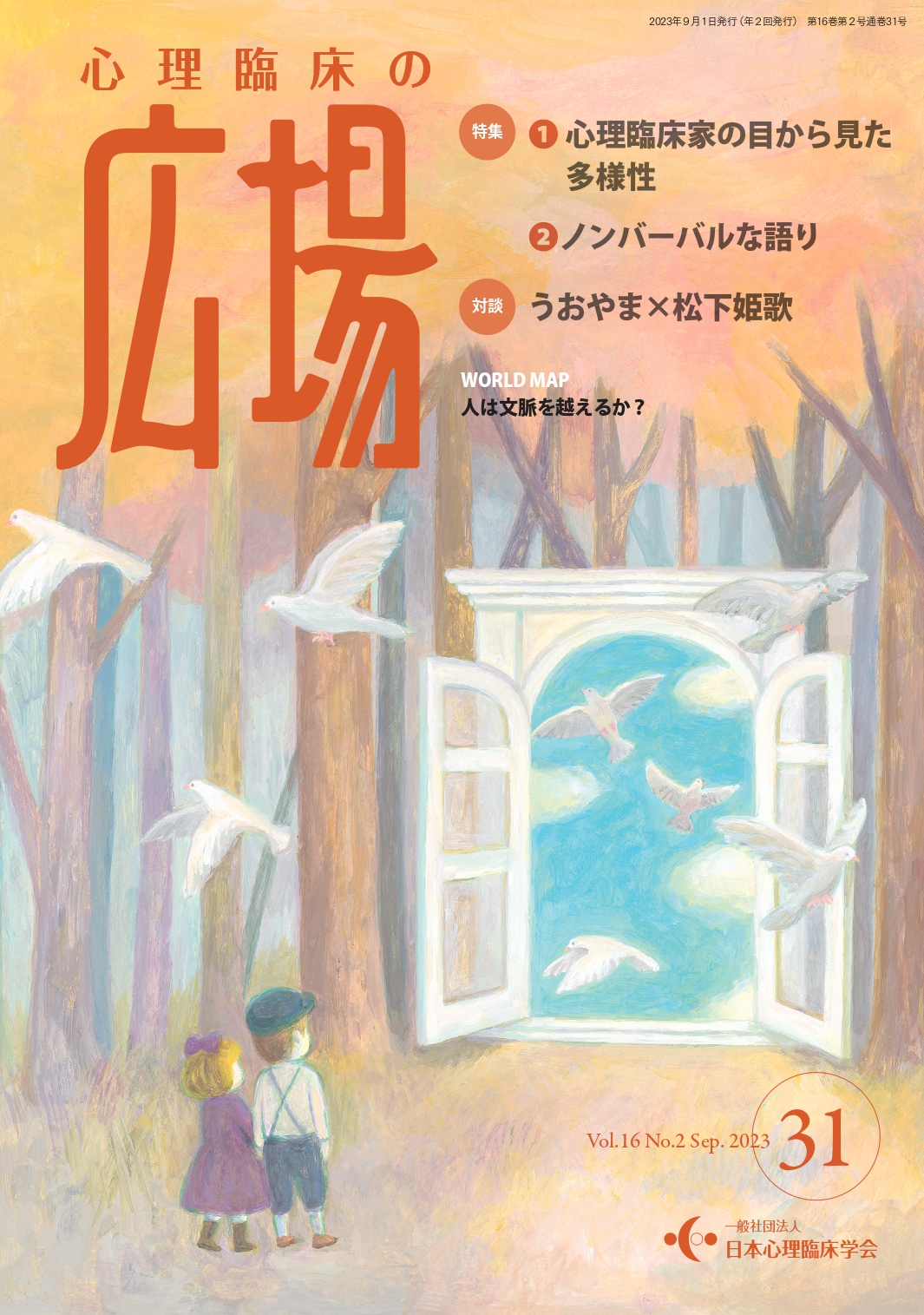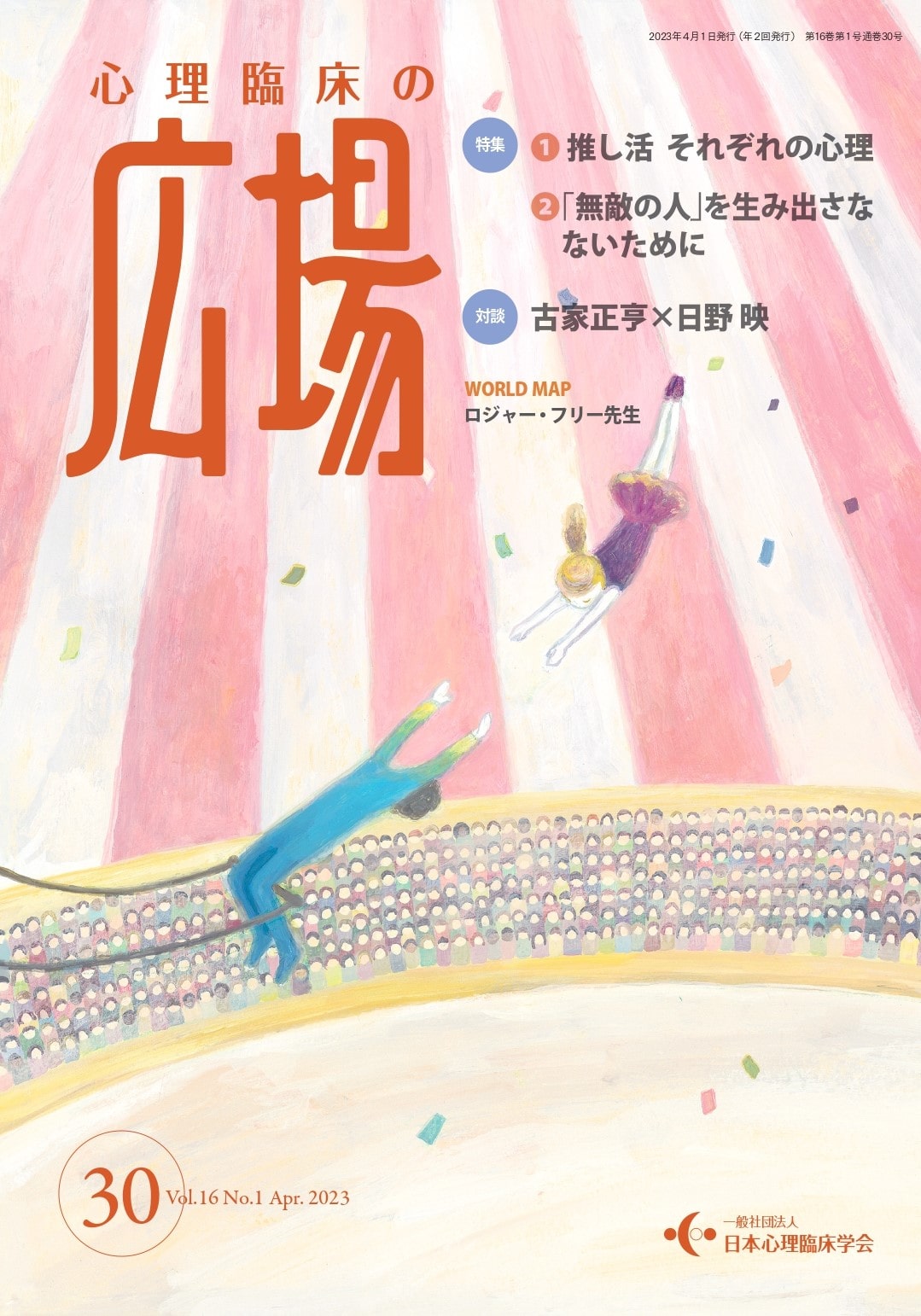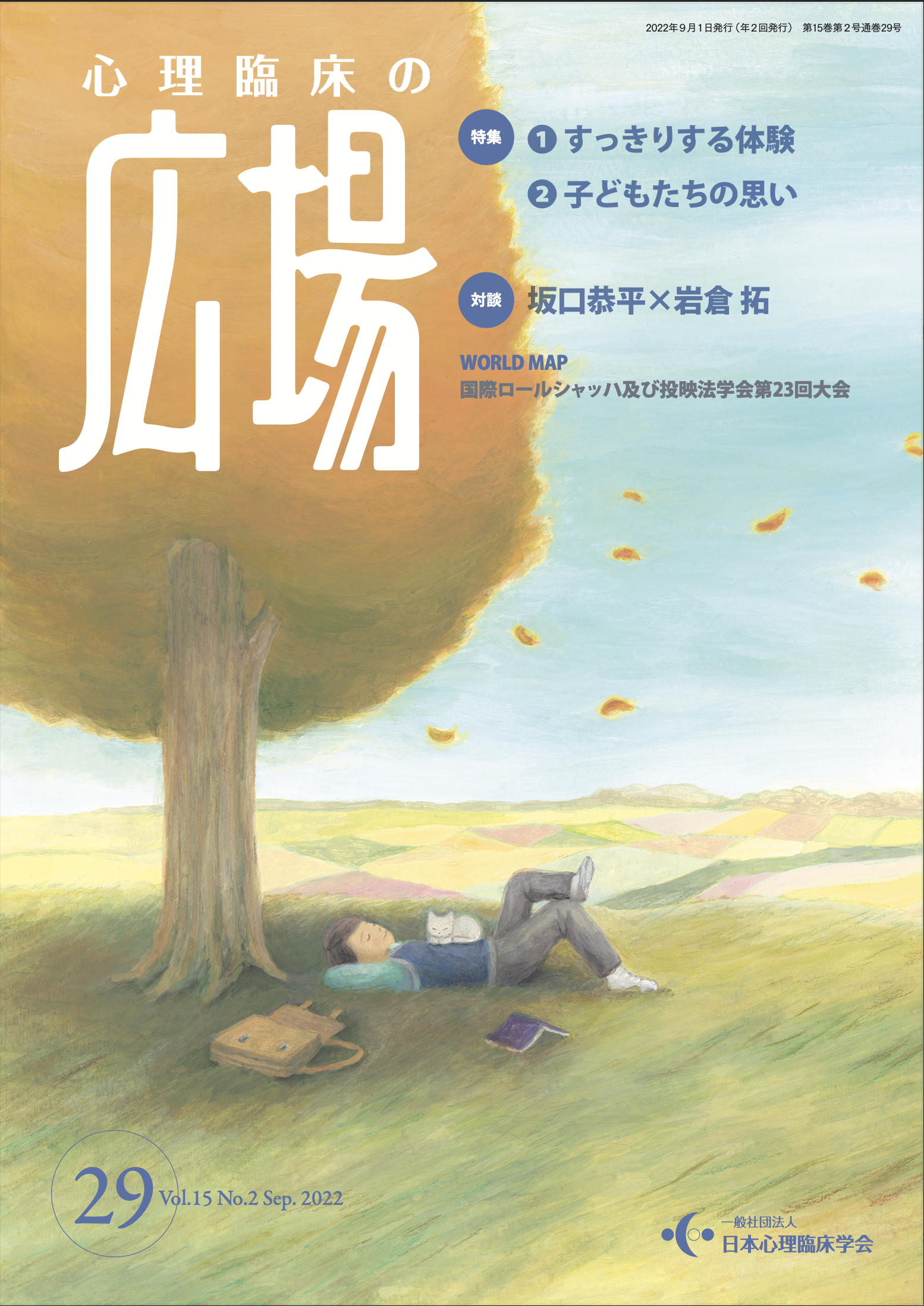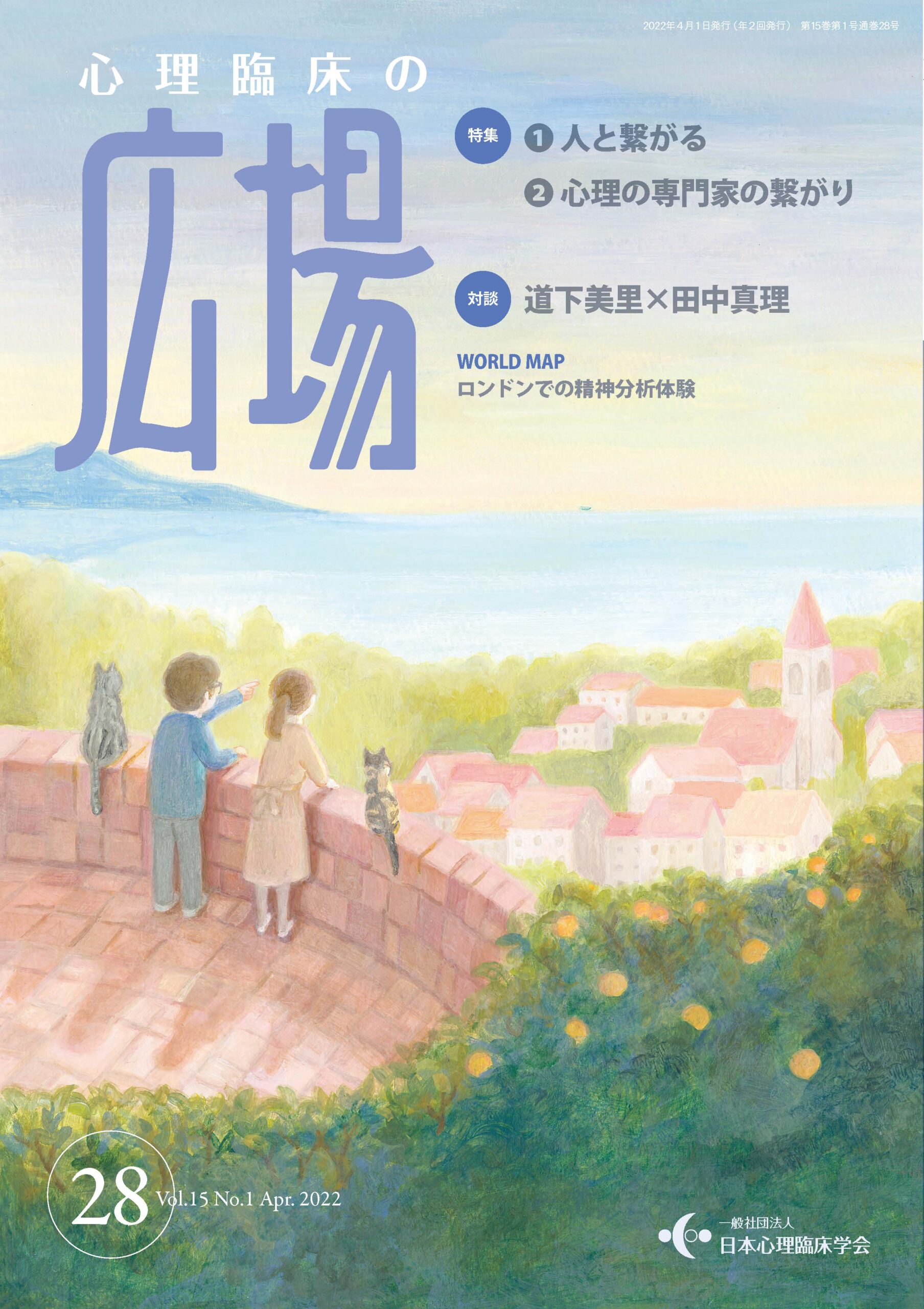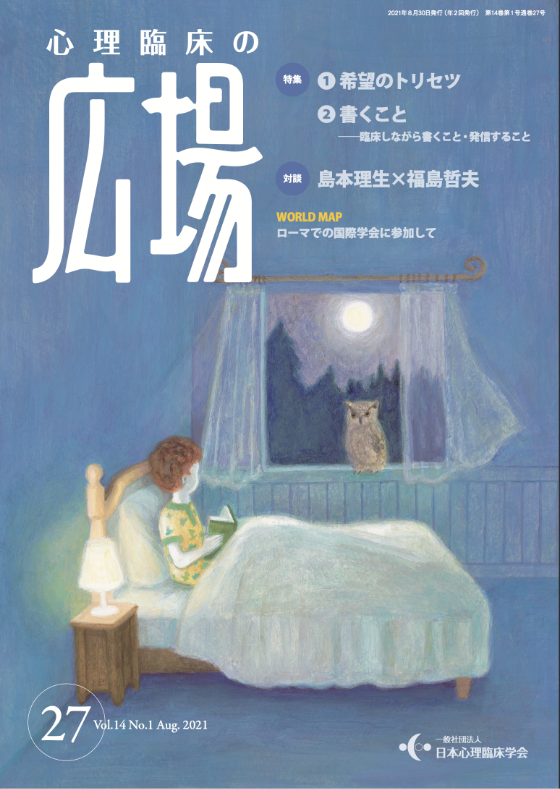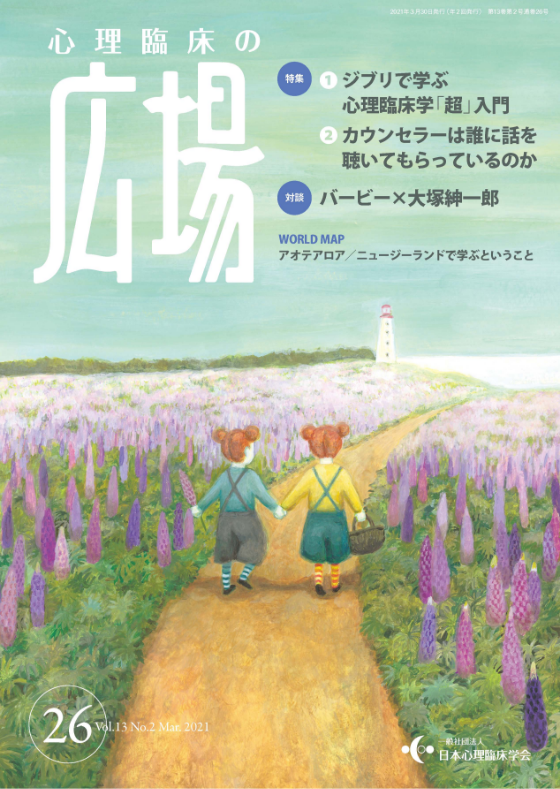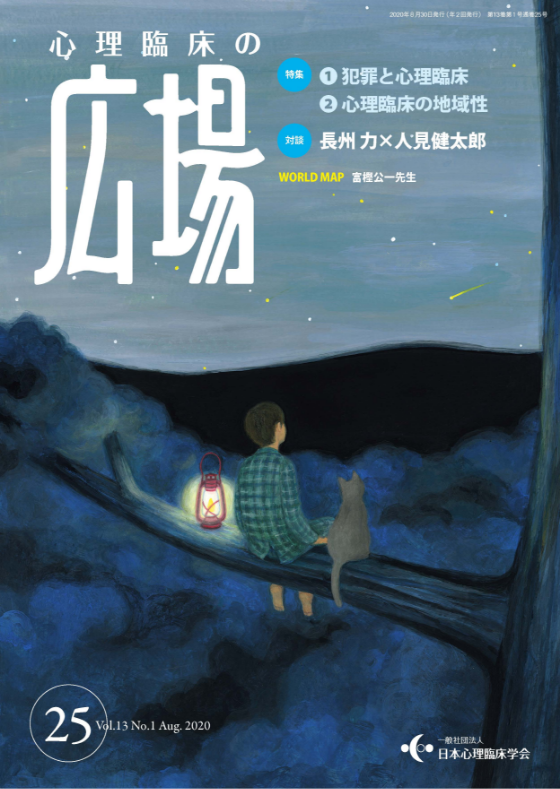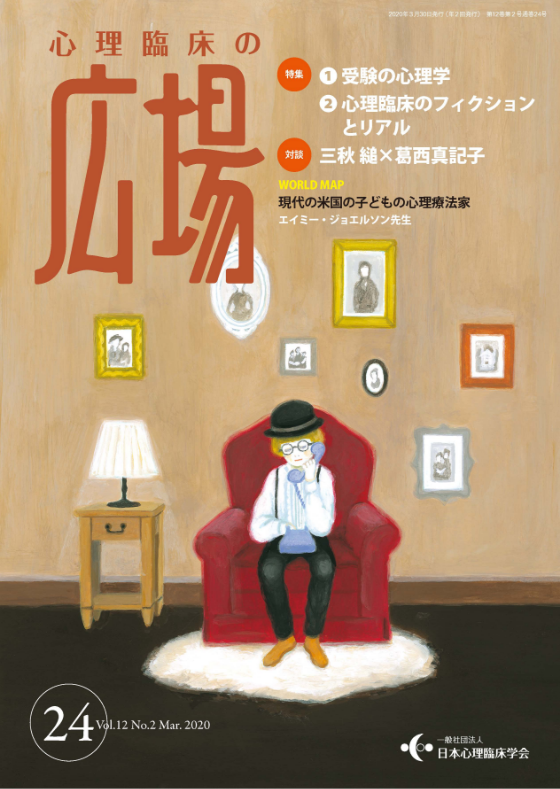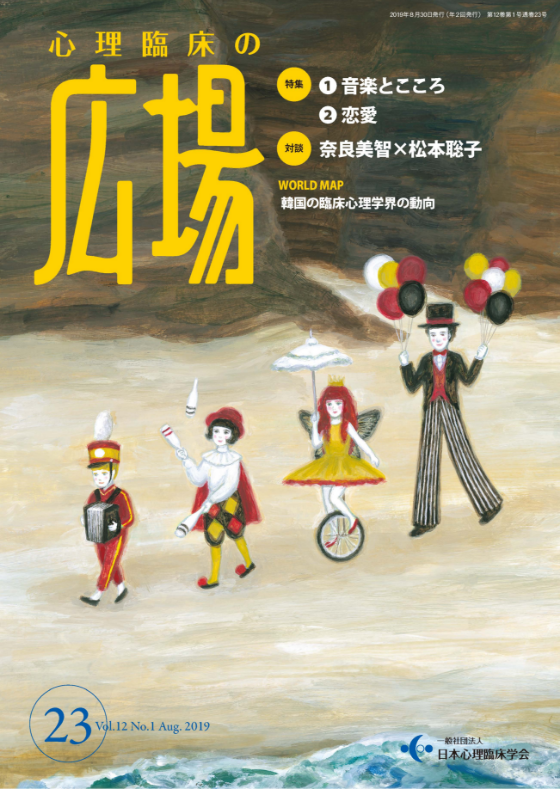私たちは、どのようにして心理臨床の実践を学んできたのでしょうか。現在、多くの学生が大学や大学院でカウンセリングや心理療法、心理支援の専門家となるべく、臨床心理士や公認心理師といった資格の取得を目指し、日々トレーニングに励んでいます。大学や大学院では、人間を理解するための多様な科目や、心理療法・心理支援に関する科目、さらには体験的な学びとなる演習や実習が、体系的なカリキュラムとして用意されています。
日常の会話と異なる「対話」の専門性
心理臨床の基本は、面接の仕方や他者、さらには自分自身とのかかわり方にあります。面接の仕方や相談者へのかかわり方には、学派などにより様々なアプローチがありますが、効果的な面接には面接者に共通した特徴があることも明らかにされてきています。心理相談は、カウンセリングや心理療法などいろいろな名称で呼ばれていますが、基本的には「相談者との対話」です。この対話は、日常会話とは異なる専門性が求められる一方、外見上は大きな違いがないため、その専門性は目立ちにくいものです。
専門的な会話とは、例えば「面接場面では、相談者の語りに丁寧に耳を傾け、その語りを聴きながら自分自身の内面にも意識を向け、語られた内容に込められた感情や意味、その背景などにも意識を広げながら、的確に理解しようと努め、相談者の福祉のために必要な応答を行うこと」であるといえるでしょう。
体験を通した理解のトレーニング
日常生活では、他者と会話をするときに自分の話し方や聴き方、相手とのかかわり方を意識的に振り返ることはあまりありません。また、相手の話を途中で遮らずにじっくり聴く機会も多くはありません。しかし、心理相談の場面では、これらの点が重視されます。相手にとって意味ある会話を実現するため、面接中の自分の会話やかかわり方をトレーニングし、意識的に振り返ることが求められます。心理相談は相談者の福祉に寄与するサービスであり、その目的を達成するための特別な会話やかかわり方が必須です。
カウンセリングの研修会で「話を聴くだけで良くなるのですか?」と質問を受けることがあります。実際の面接を知らない方からは「ただ話を聴いているだけ」に見えるのかもしれません。しかし面接では、相談者が自分自身を理解し、自ら変化できるよう、その作業できるよう、対話が組み立てられているのです。
資格取得のためのカリキュラムでは様々な知識を学びますが、それらは単なる知識として覚えておくだけではなく、実際の面接場面で目の前の相談者を理解するための「活きた知識」として使えるよう、体験的な学びが重視されています。相談者を理解するとは、多様な知識をもとに判断し理解するだけでなく、その知識を手掛かりに、対話の中での相談者とのやり取りを通して的確に把握していくことが求められます。
相談者が何をどのように語るのか、その語りを聴きながら自分がどう感じ、どのように理解していくのかをトレーニングしていきます。また、一回一回の面接の中で何が起こっているか、継続的な関係の中でどのようなことが展開されているかについても丁寧に検討していきます。面接の進み方を理解するためには、その時々で何に着目し、どのような言葉を使い、どんな態度で臨むかなどを繰り返し学び続ける必要があります。
逐語録とスーパービジョン
面接のトレーニングの初期段階では、会話のやりとりを記録した逐語録や録画などを用いることで、面接を細かく丁寧に振り返りかえることができます。「なぜこのように問いかけたのか」「この場面でどう感じ、どのように対応したか」などを検討し、自分自身の強みや課題、戸惑いや迷いにも向き合います。スーパービジョンを通じて他者からのフィードバックを受けつつ、自分自身の体験を振り返ることで、臨床的な力が養われていきます。
スーパービジョンは、単に知識や技術を伝えることではなく、実際の面接場面で生じている複雑な出来事や自分の内面にまで目を向け、臨床的な実践力や理解力、さらには、相談者自身の自己理解を支援する営みです。一般的な学問では知識は客観的に扱われますが、心理臨床では、自分自身の主観的な体験も思考の対象となり、理解を深めていきます。それゆえ、逐語録を使ったスーパービジョンや事例検討会などに丁寧に時間をかけて取り組むことが、心理臨床家養成の大きな特徴といえるでしょう。
大学院での学びと職場での成長
大学院を修了した後は、それぞれの職場で必要とされる知識やスキル、態度を身につけ、職域ごとに求められる、あるいはその職場で必要とされる専門性を高めていきます。数年前に、本学会の職能委員会で行った心理職の専門性や独自性をテーマにした一連のシンポジウムにおいて、このような知見が得られています。それゆえ、大学院では、心理臨床の基本的なことを体験を通してしっかりと学ぶことが大切であるといえます。この体験的な学びは、トレーニングの中で自分自身の嫌な点も見なくてはいけなくなり落ち込むこともあるかもしれませんが、それは、相談者の人生を豊かにするためのだけではなく、自分の人生も豊かにしてくれるものだと思います。
日本心理臨床学会の役割と養成の歩み
日本心理臨床学会が設立されたのが1982年で、臨床心理士の制度が始まったのが1988年です。本学会は、臨床心理士制度の創設に深く関わっていました。そして、それ以来、心理臨床の実践を学問として構築していくだけではなく、臨床心理士の育成や教育・研修にも寄与してきています。そして、2015年には公認心理師法が制定されましたが、本学会も資格制度や養成カリキュラムに関する多くの提言を行ってきています。例えば、2016年には「公認心理師養成に向けた日本心理臨床学会案」が出されています。その後も「公認心理師養成に向けた日本心理臨床学会からの要望・提言」や「公認心理師養成カリキュラムにおける実習についての提言」なども公表されています(本学会のホームページで公開されています)。また、2022年には「大学課程(学部等)/大学院課程カリキュラム提言」として、特に大学(学部等)のカリキュラムのさらなる充実に向けた提言が出されています。
今期カリキュラム委員会では、大学院カリキュラムを中心に心理臨床家養成の今後について議論が行われています。今後も本学会は、心理臨床家養成のあり方などについて知見を蓄積し、必要な提言を発信していきたいと考えております。
一般社団法人 日本心理臨床学会
https://www.ajcp.info