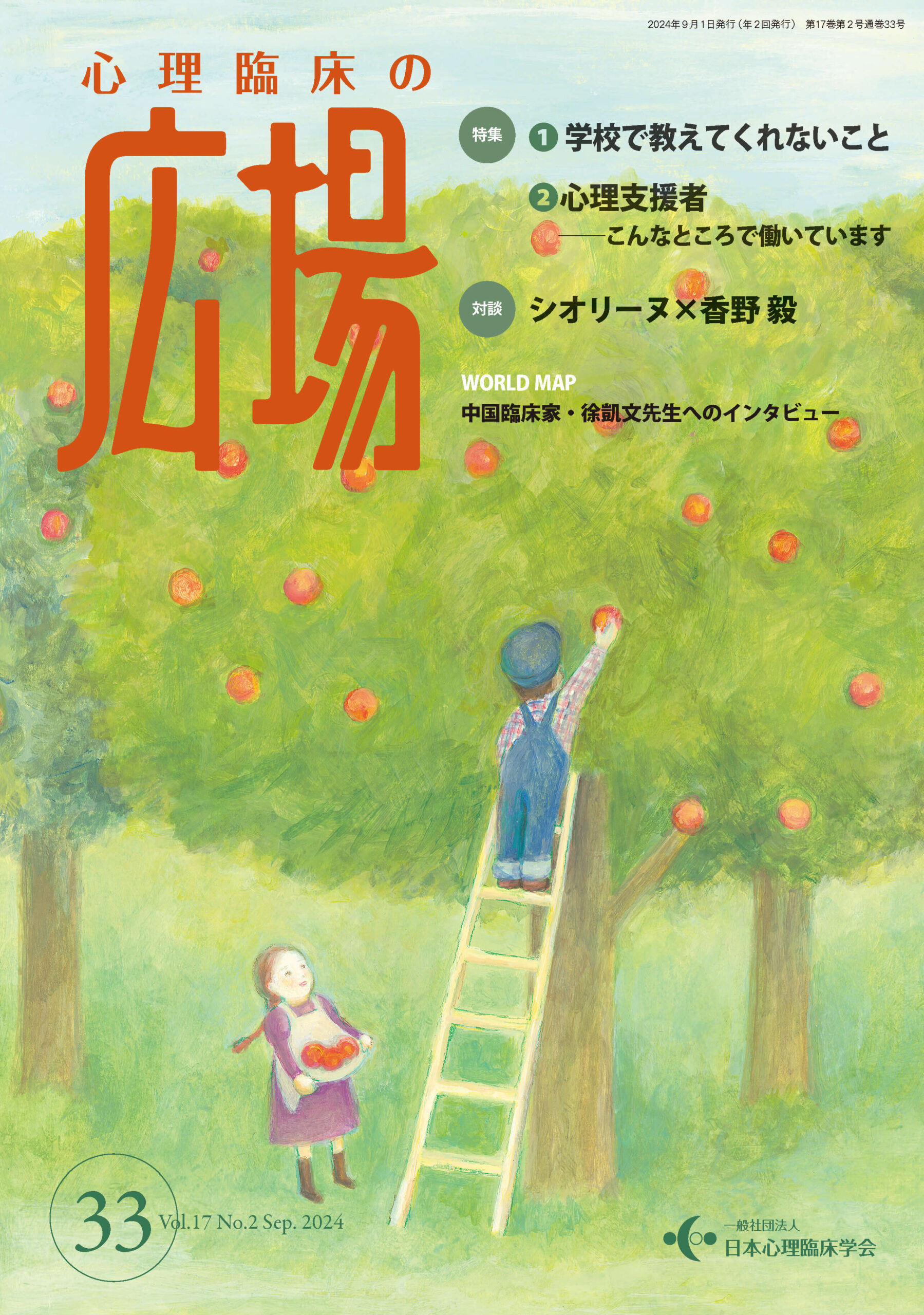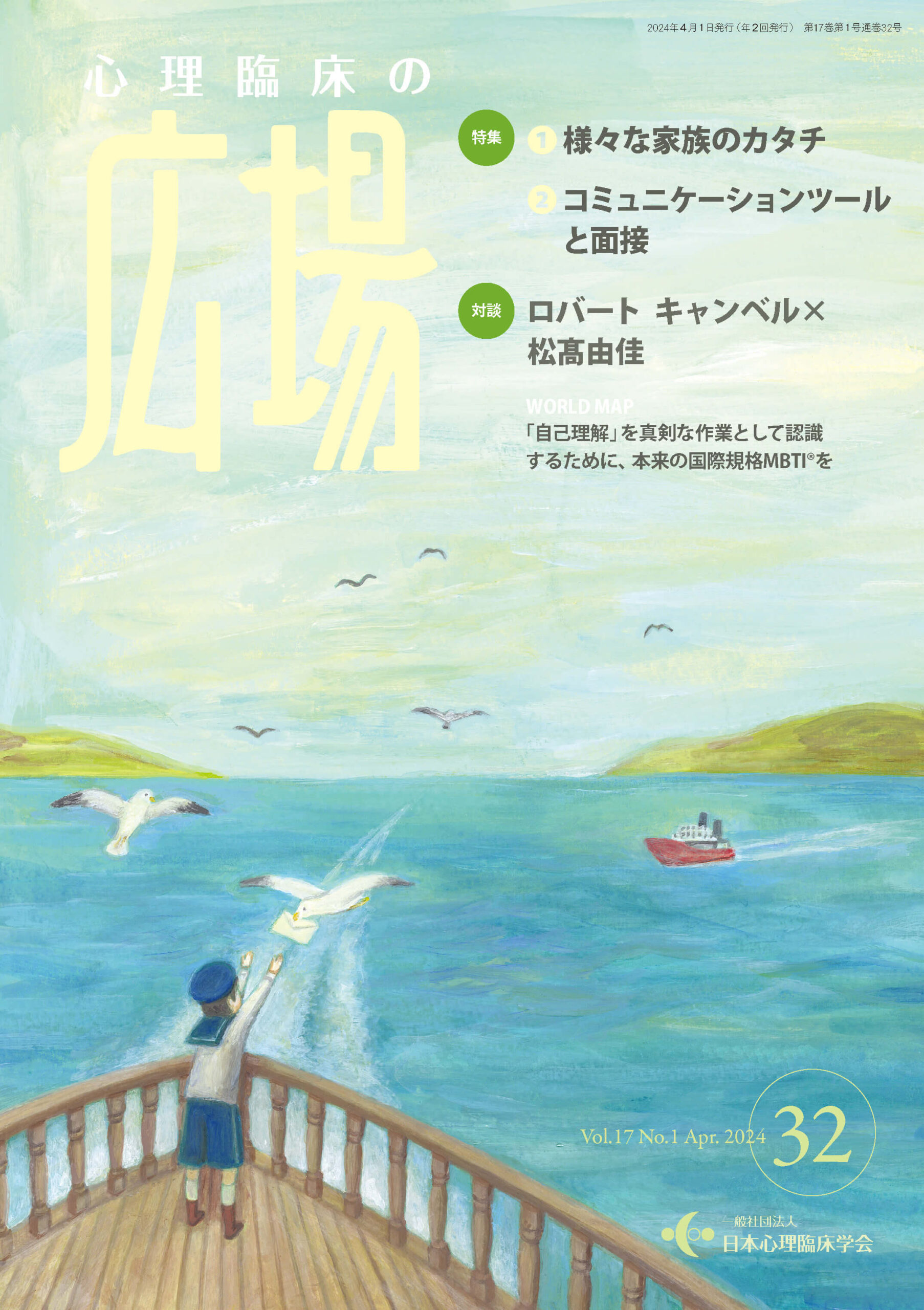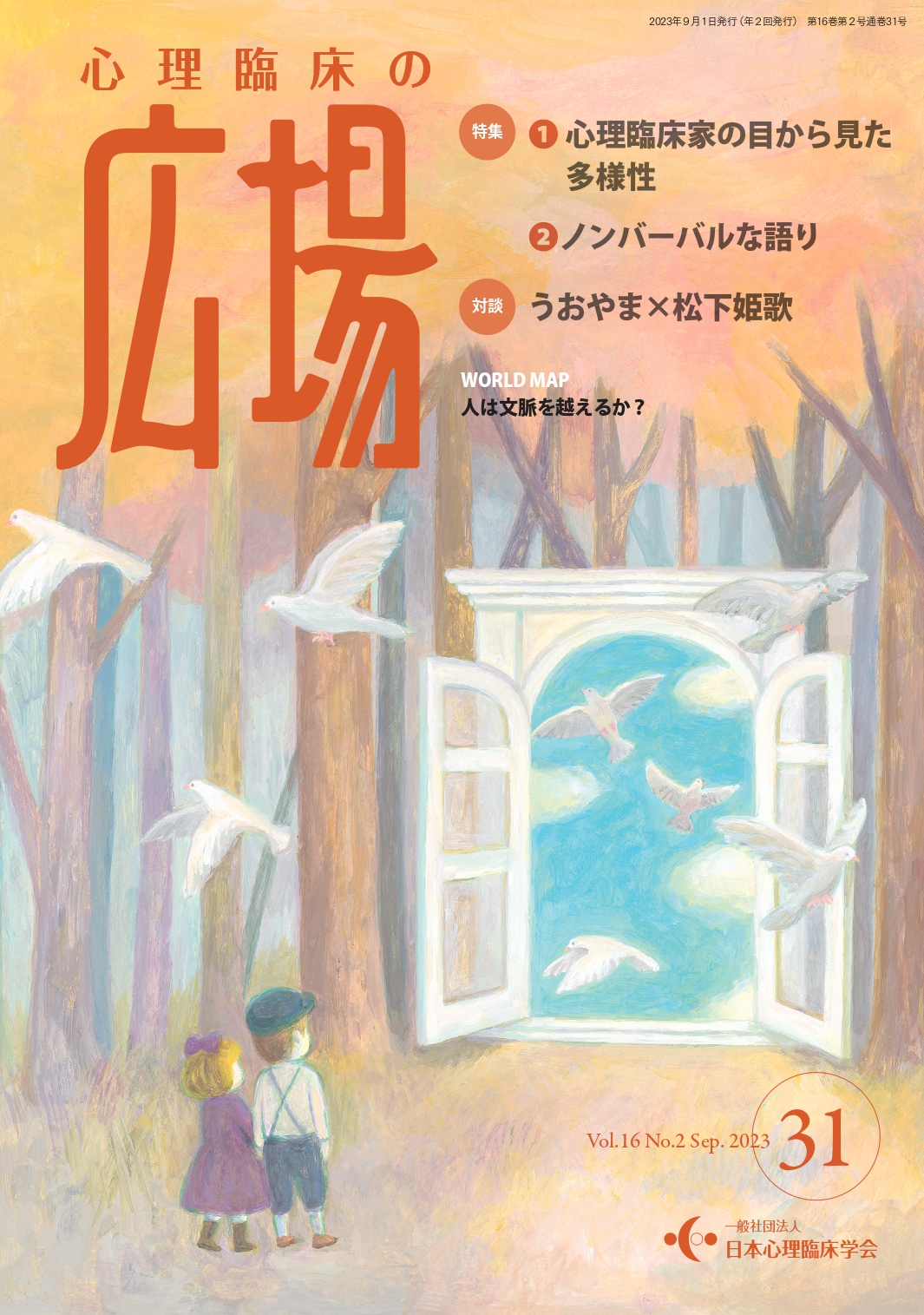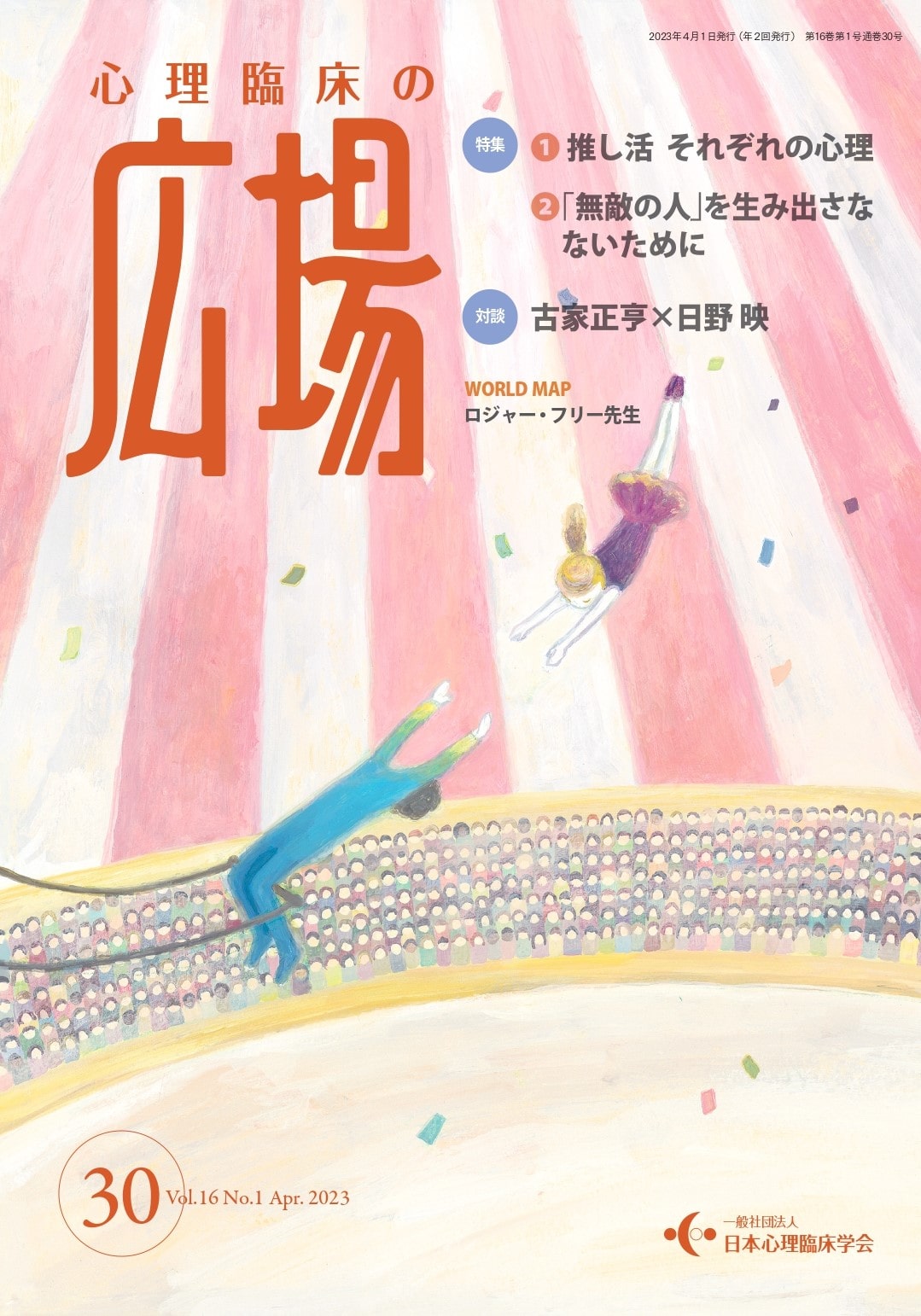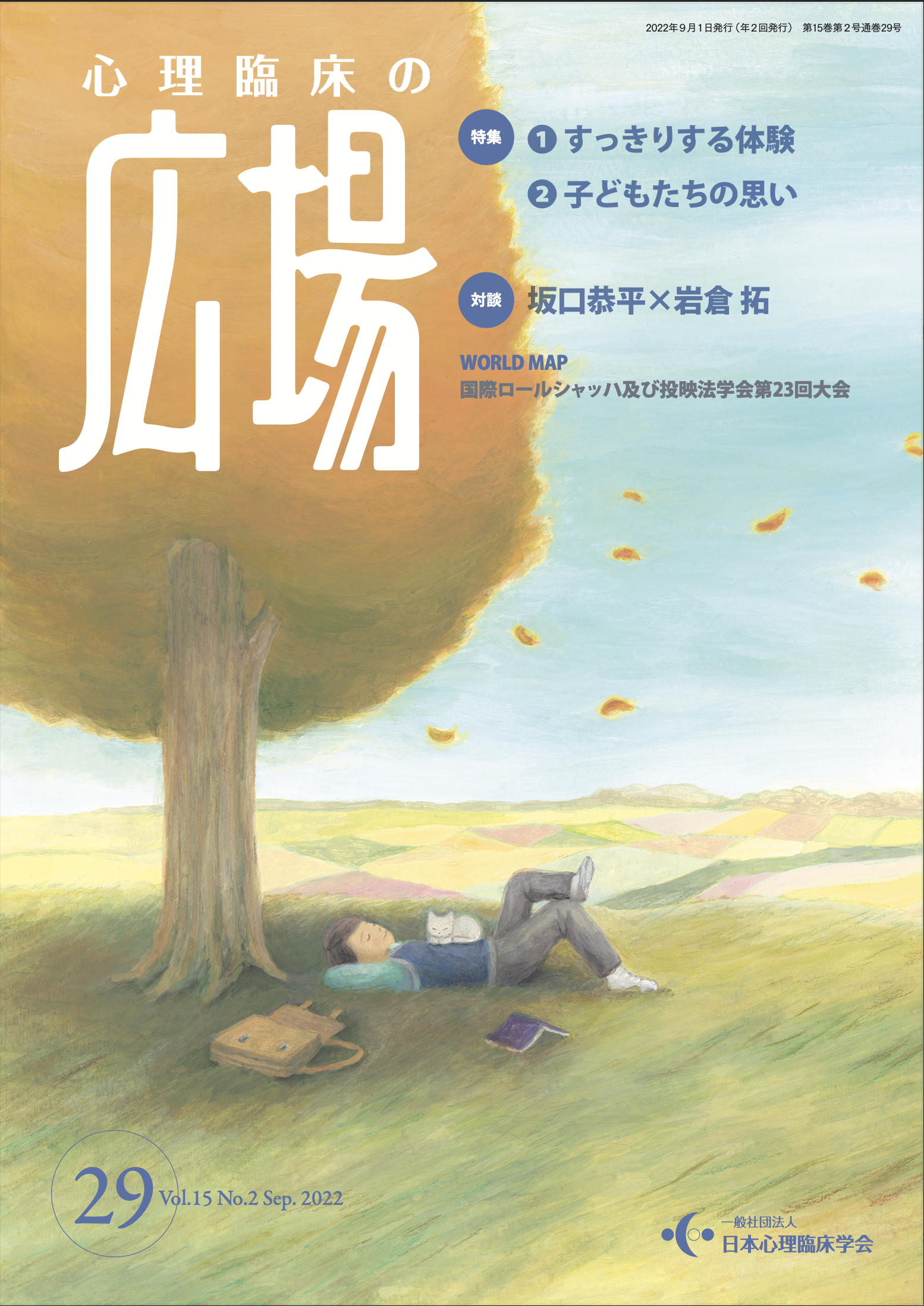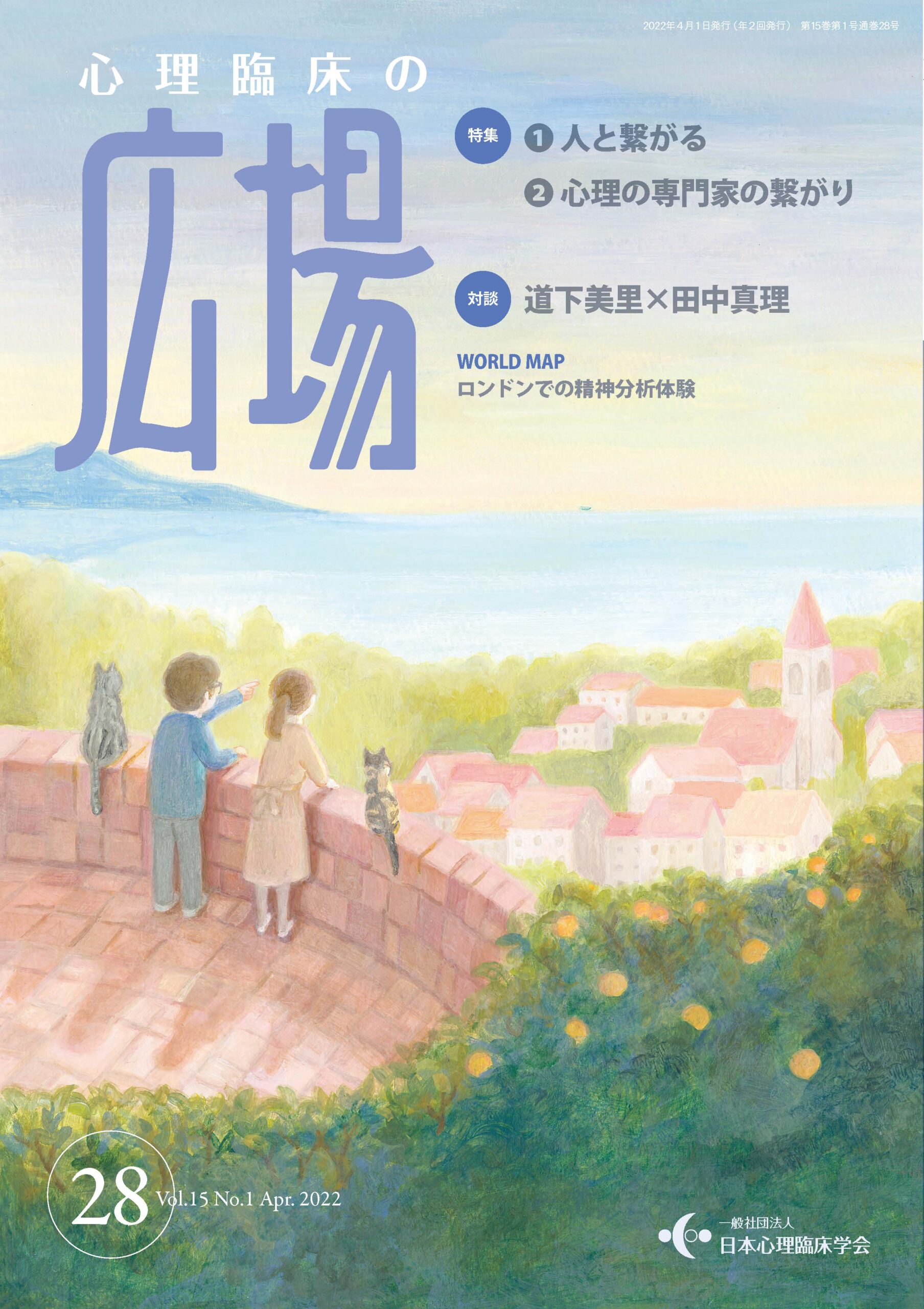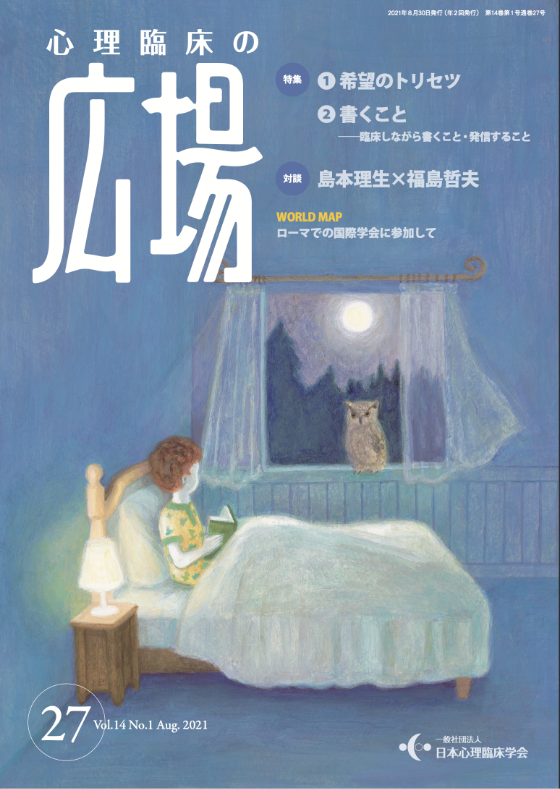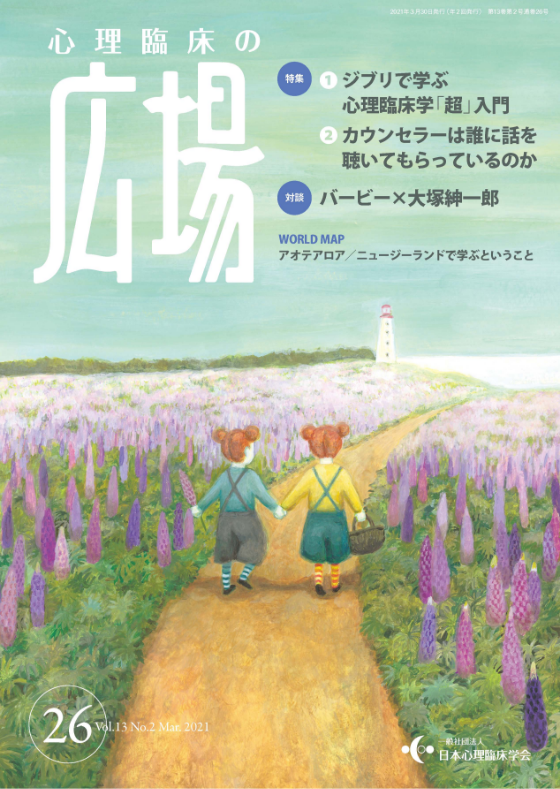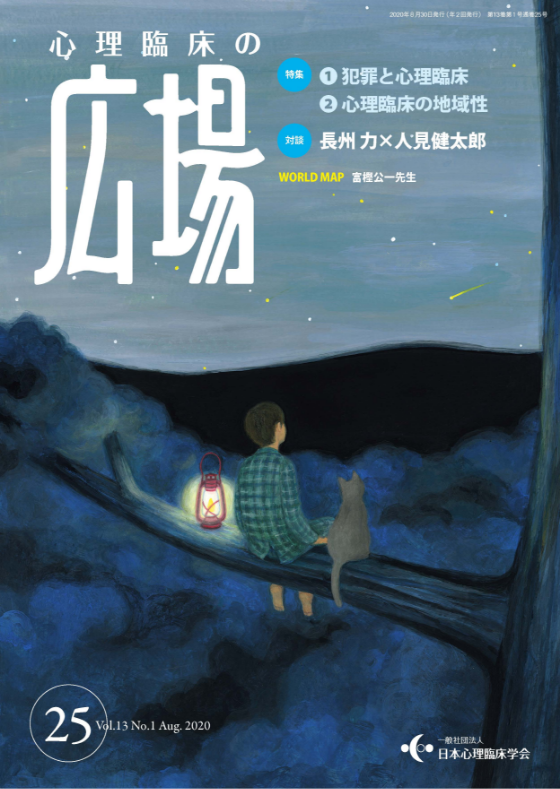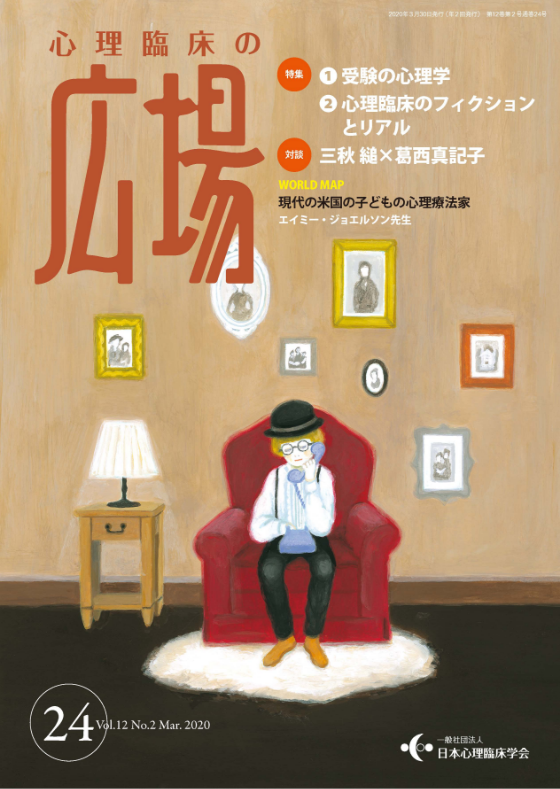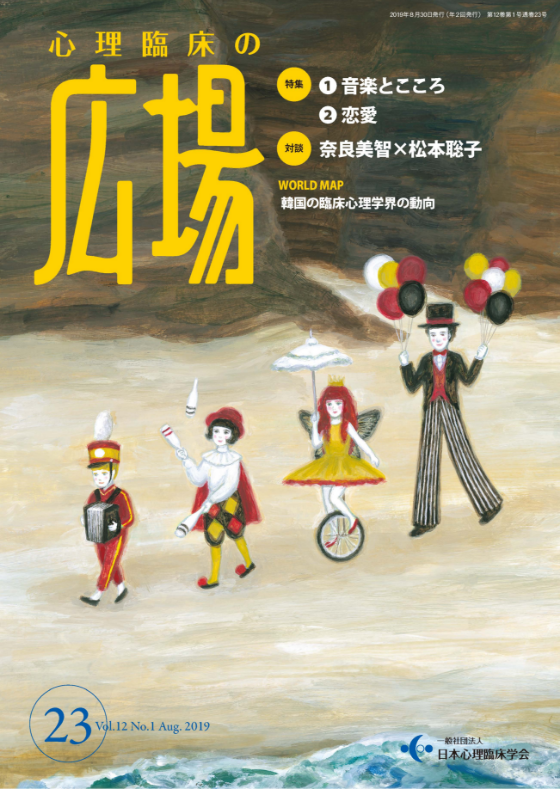Serial Articles #若手心理士の声 「えいや」と進む、心理臨床の道すがら
著者 大阪公立大学国際基幹教育機構特任助教 西 恭平
皆さんは、計画通りに物事を進めるのは得意な方でしょうか。私はもちろん、張り切って計画を立てるものの、夏休み最終日に慌てて「えいや」とやるタイプです。今の生活も、当初の計画とは少し違いますが、「えいや」と挑戦を続けてきたことで、今の自分につながっています。
これまで私は、主に学校や医療現場で心理職として働いてきました。同時に昨年、博士号を取得し、研究者としての活動や、大学での講義などにも取り組んでいます。毎日職場が変わり、臨床、研究、教育を行き来する日々です。
その中でも、中学校での臨床活動においては「自傷行為」が重要なテーマのひとつです。そしてこのテーマに向き合う中で、「友人」が大きな助けになる可能性に気づきました。そこで現在は、「自傷とは何か」「友だちとしてどう関わればよいか」を学ぶ中学生向けの教育プログラムの開発に取り組んでいます。
想定外の研究の道
こうして綴ると、元から研究者を目指していたようにみえるかもしれませんが、博士後期課程に進むことは、当時まったくの想定外でした。元々は、現場で心理支援を続けていくつもりで、研究をするとしても10年以上先だと考えていました。けれど、偶然見つけた仕事や人との出会い、社会情勢やプライベートの変化など、いくつものきっかけが重なり、「今しかないかもしれない」と思って、「えいや」と進学を決めました。
挑戦には、不安がつきものです。本当にできるのか、今の仕事を手放していいのか、そんな迷いもたくさんありました。でも、若手なりに一歩踏み出してみると、それまで見えていなかった景色が広がることもあります。実際に、多くの場面で「やってみてよかった」と思えています。
「えいや」で広がる、心理臨床の世界
例えば、博士後期課程に進学したからこそ、学校現場で生まれた問いを研究で掘り下げ、教育プログラムという形で生徒に還元することができています。さらに、大学での講義を通じて、将来学校現場を担う大学生に知見や経験を提供することもできています。
臨床活動を中心に取り組んでいる方にとって、研究は少し遠く感じられるかもしれません。しかし、現場で働いているからこそ、研究につながる大切な問いが浮かび、それが研究と結びついたとき、今度は臨床活動をより豊かにしてくれます。そのため、これらを共有し合える学会の場などはとても重要だと感じます。
心理臨床の道は、ときどき迷いながら進むものかもしれません。もちろん慎重になったり、他の人の意見を聞いたりすることは大切です。しかし、それでも決断しづらいことはあります。そんな時は「えいや」と一歩踏み出してみた先に、自分なりの意味を見出せるかもしれません。もし今、挑戦しようか迷っている方がいたら、その一歩がよい出会いや発見につながることを、心から願っています。