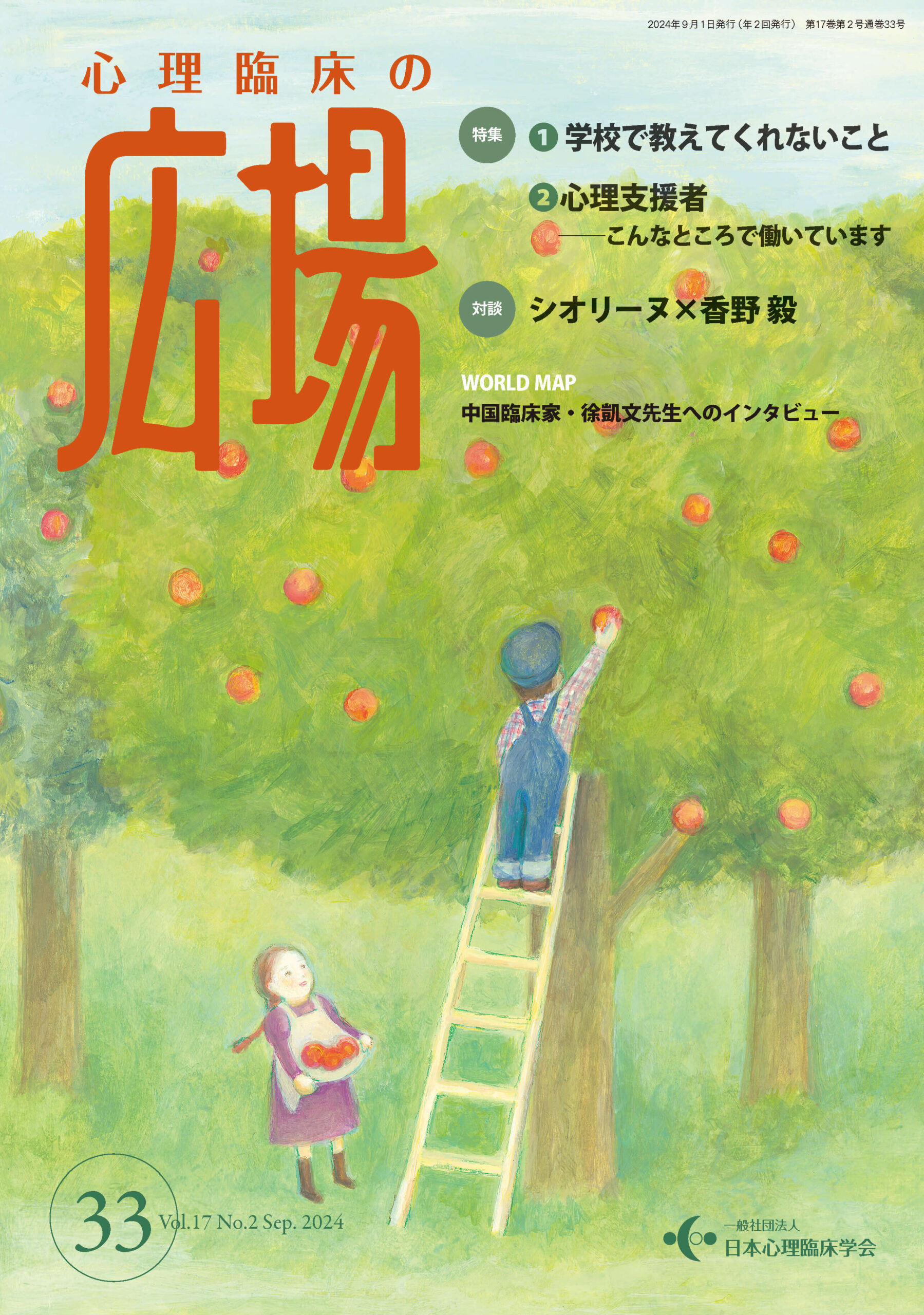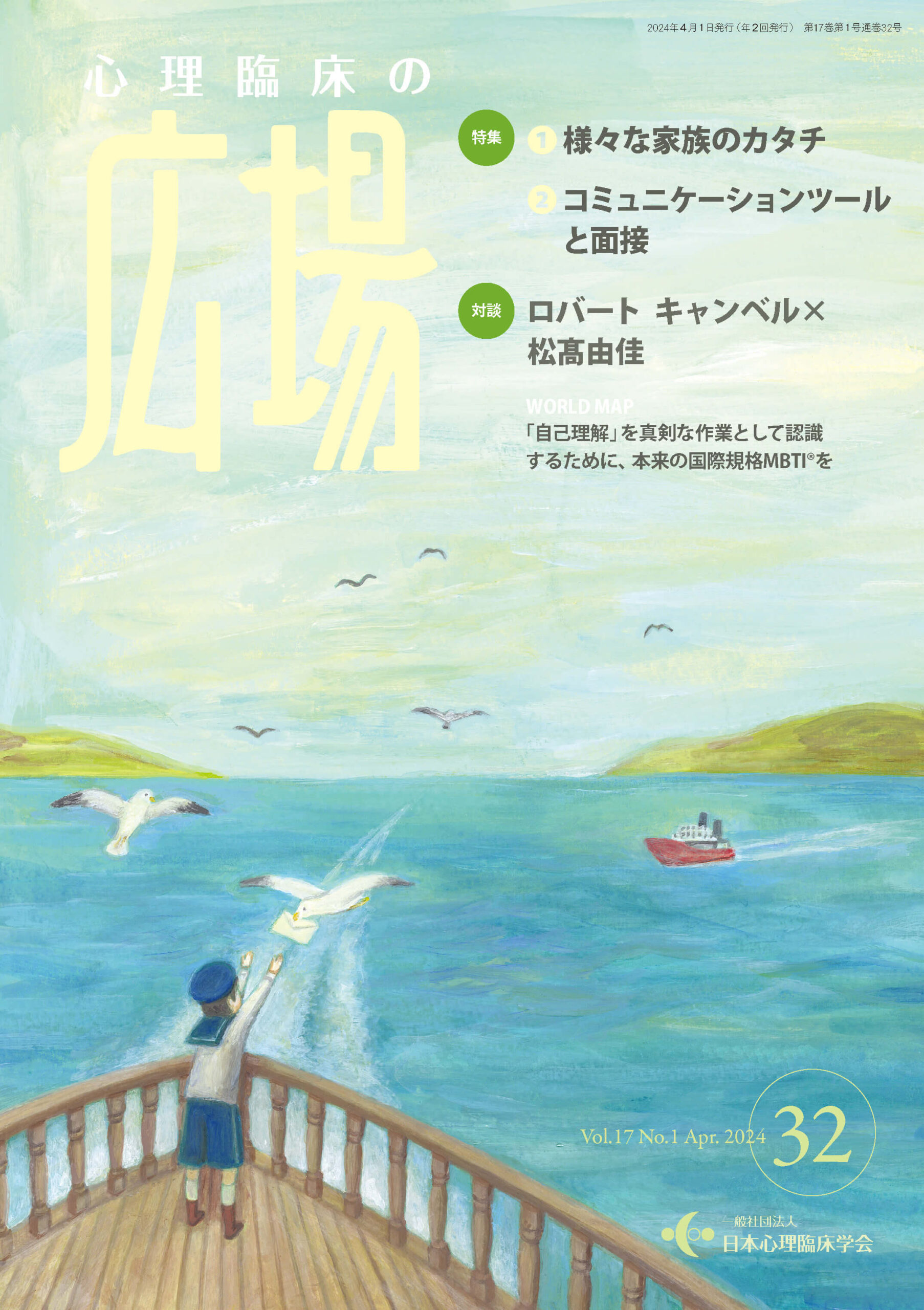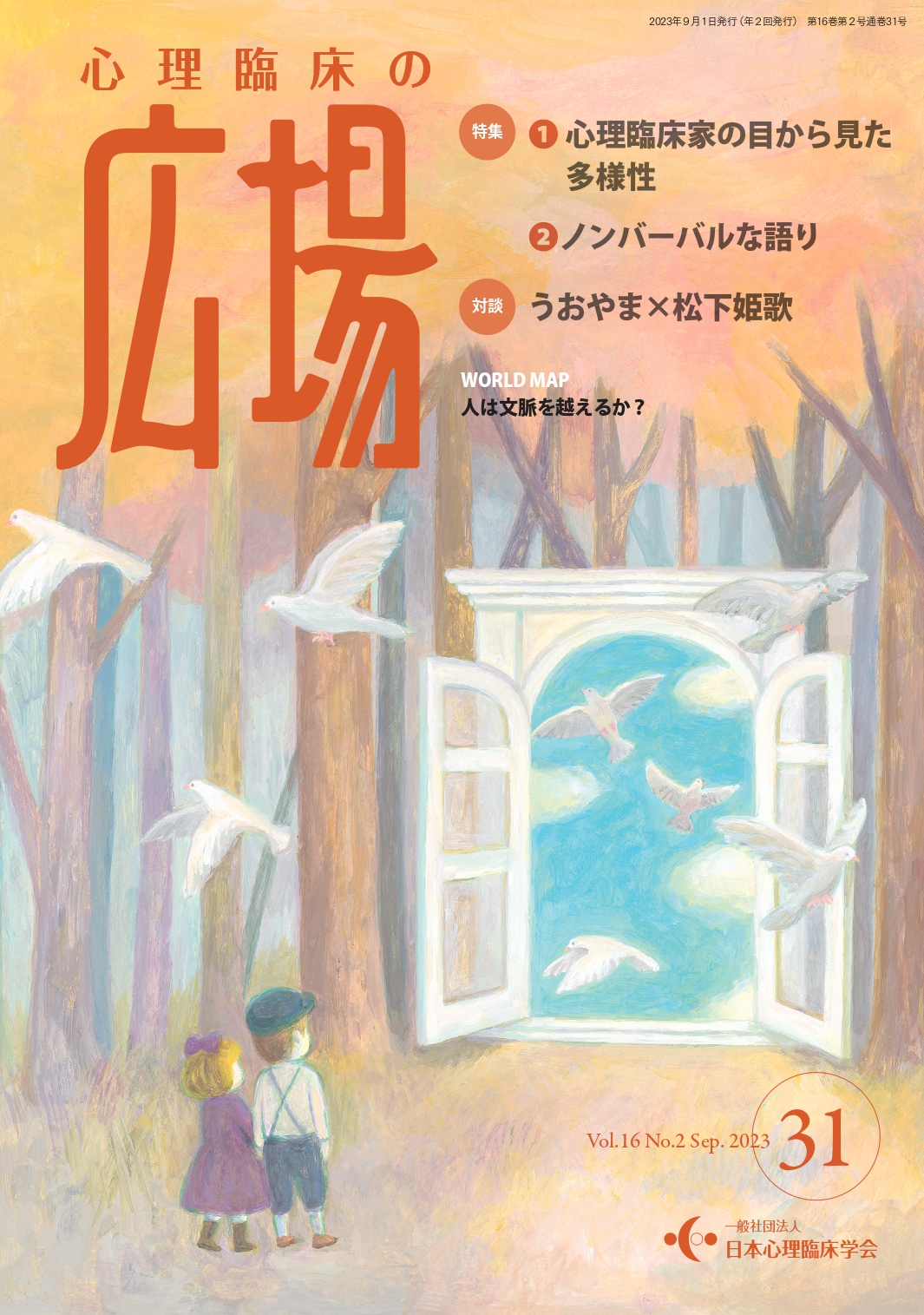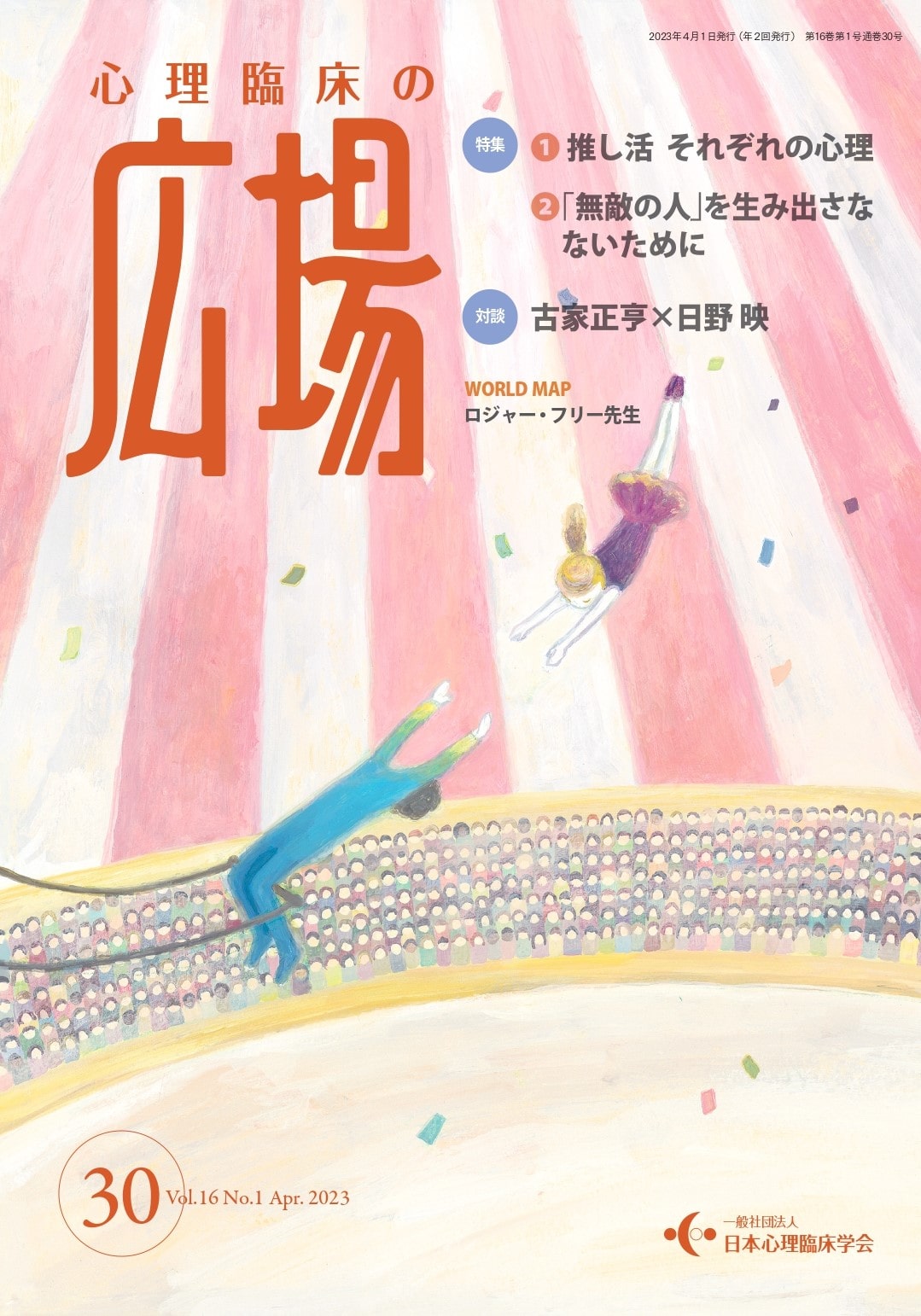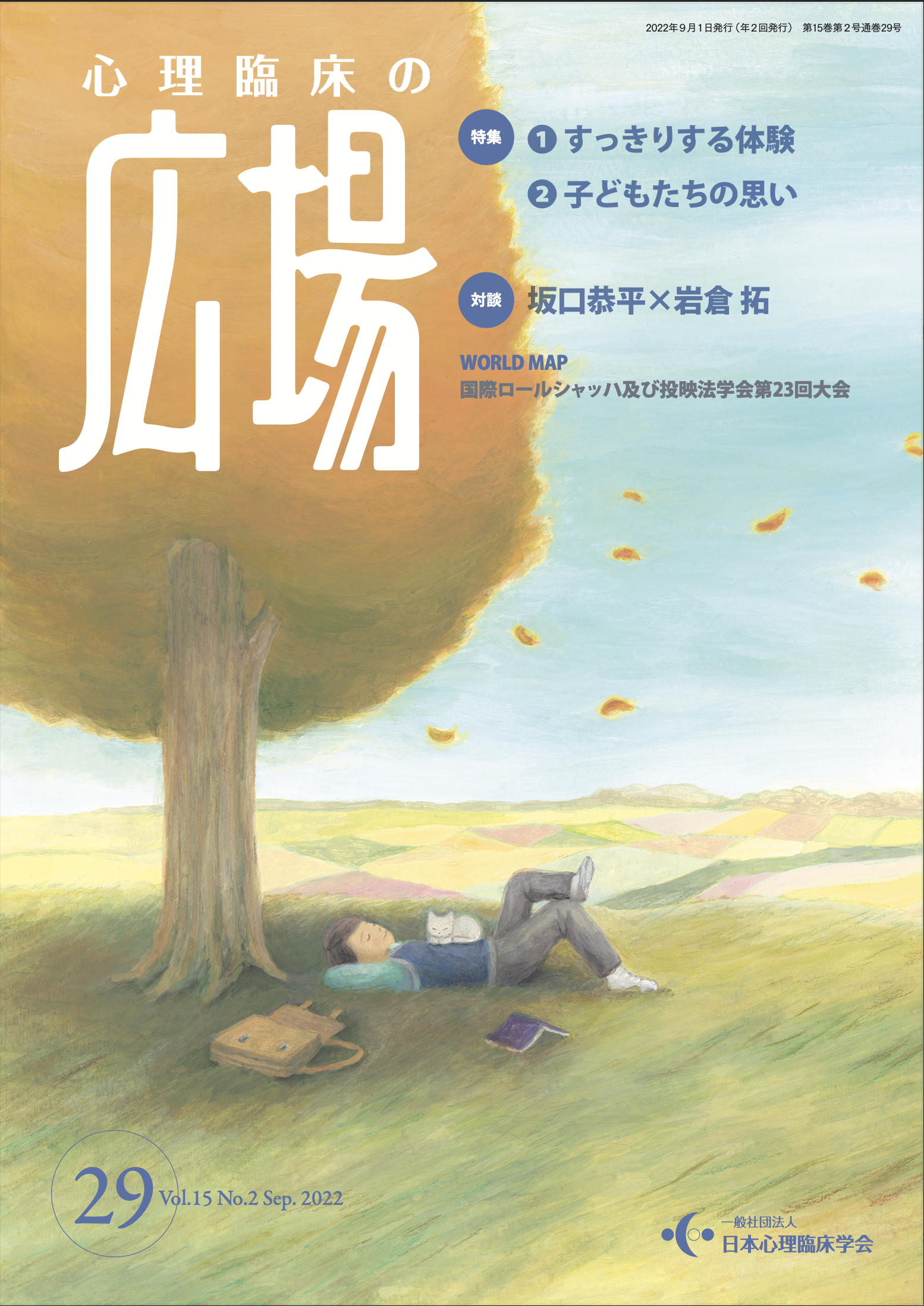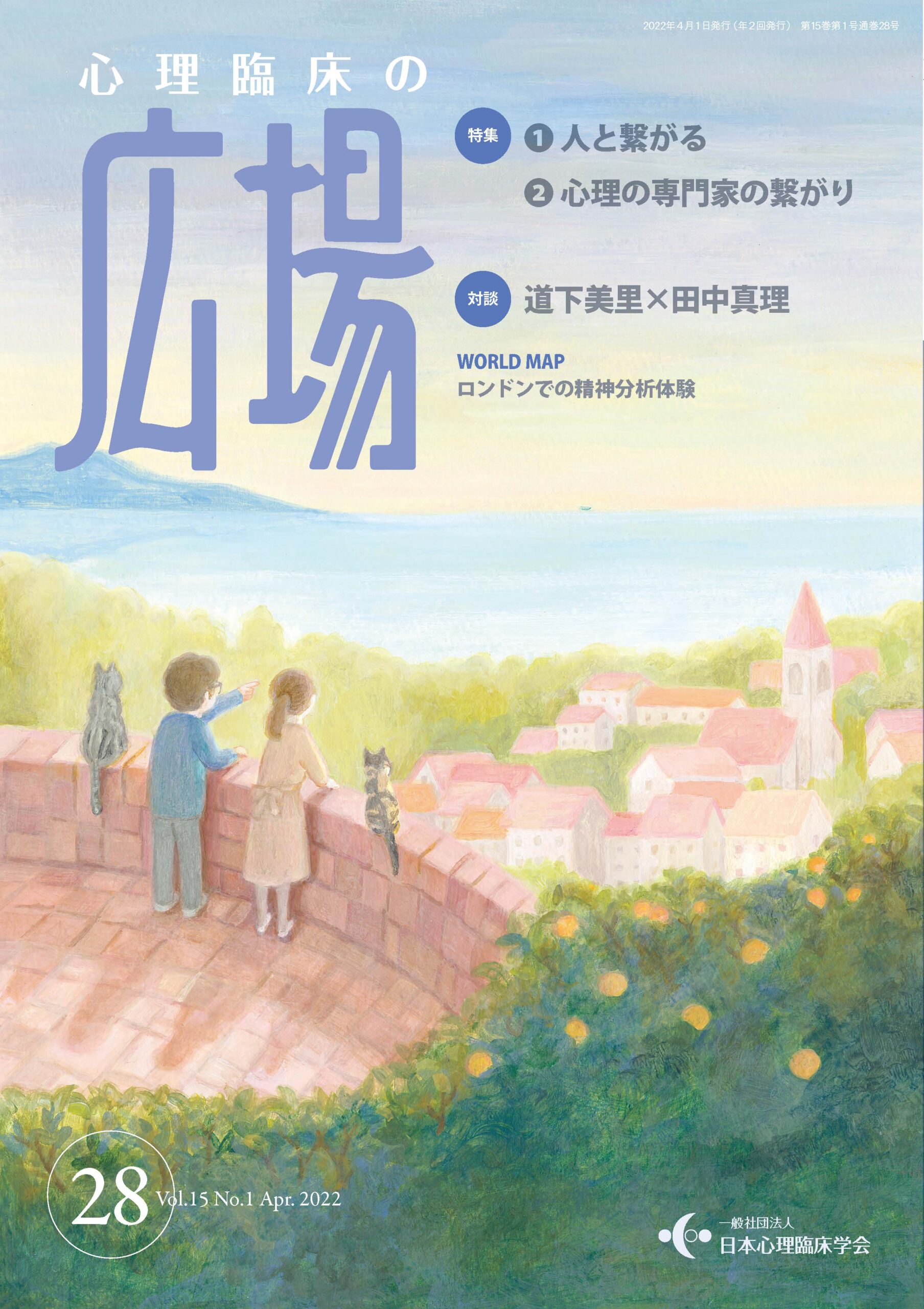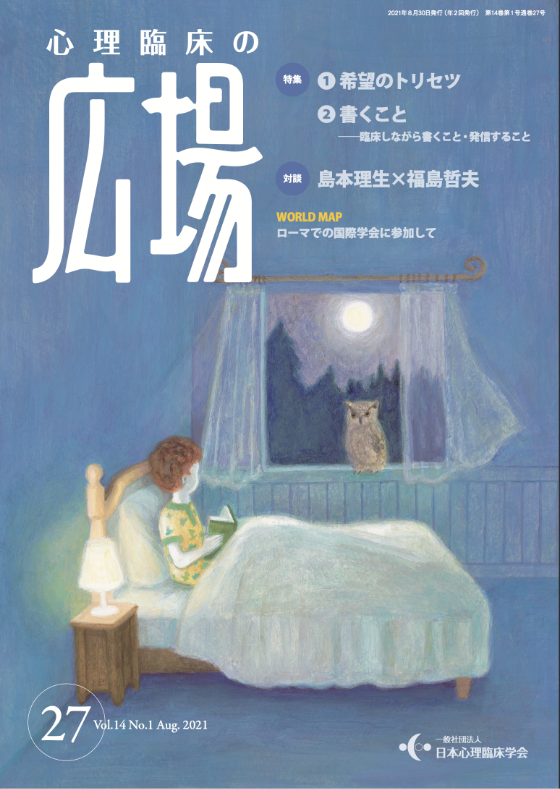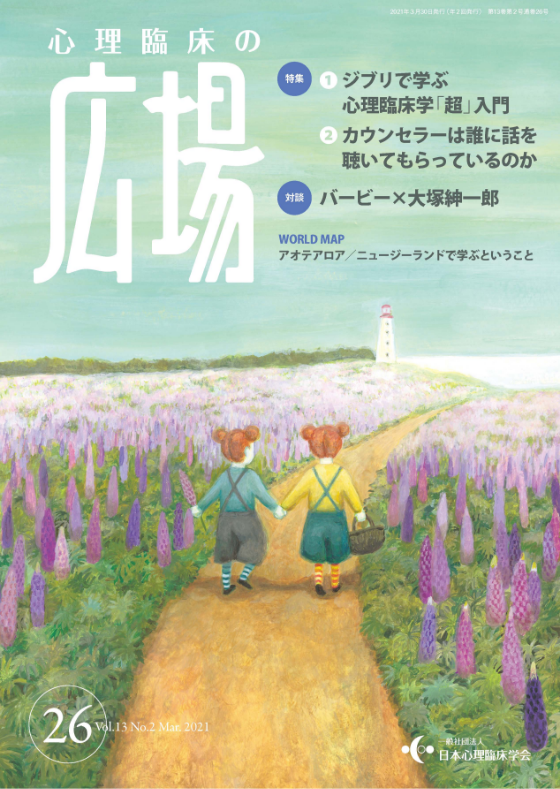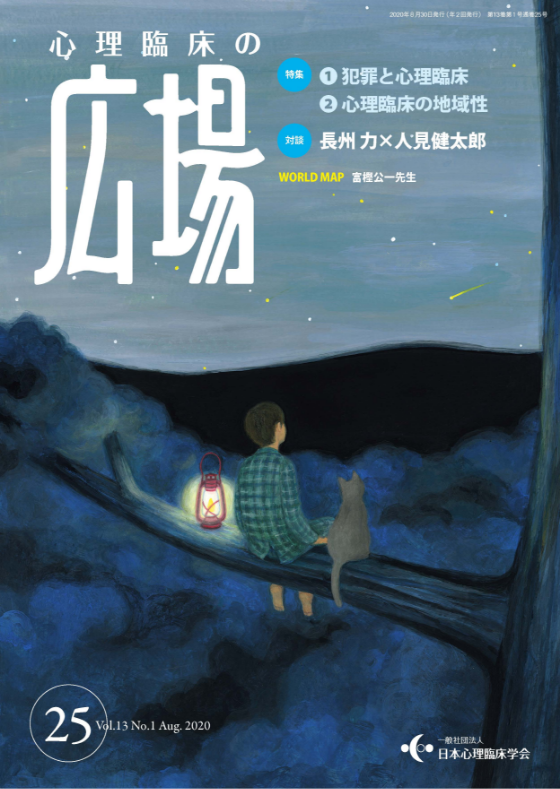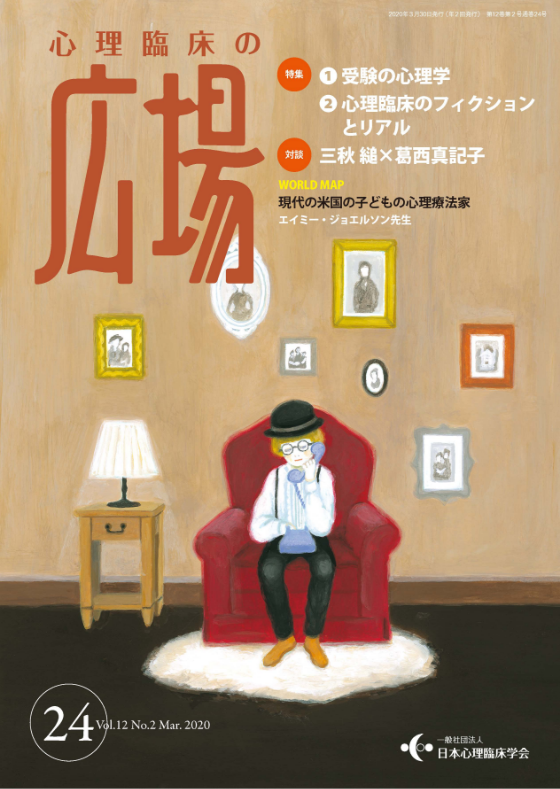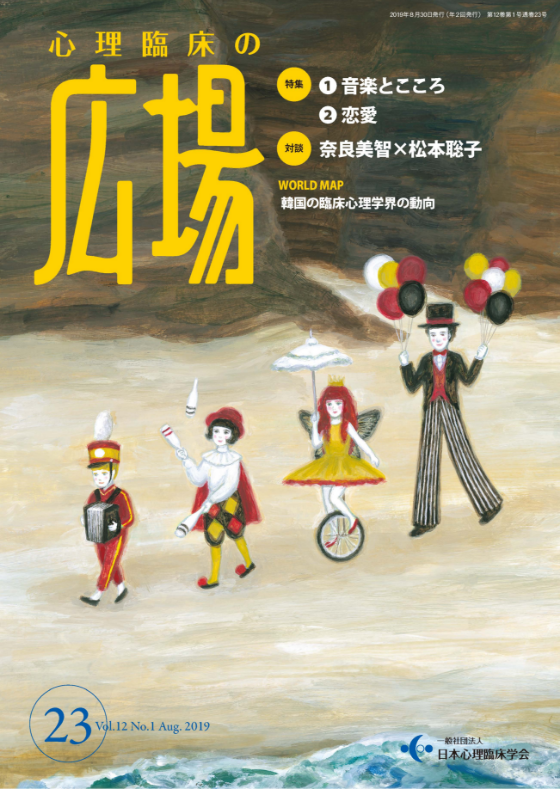釣りとの出会い
私の出身地である東京都稲城市が多摩川沿いにあったことや、江戸時代に造られた大丸用水という水路が身近にあったこともあり、小さい頃から魚やザリガニをとる水辺の遊びに親しんで育ちました。今にして思えば、小さい頃から水辺の自然からたくさんエネルギーをもらっていたのだと思います。小学生の頃(1990年代)、バスフィッシングを題材にした漫画雑誌が登場し、そこから友人達とルアーフィッシングに励むようになりました。高校時代以降は、陸からの釣りとあわせてレンタルボートに乗って湖上に出て釣りをする機会も増え、富士五湖・相模湖・霞ヶ浦・琵琶湖・榛名湖・房総半島のダム湖など、各地の釣り場に遠征して釣りを楽しんでいました。修学旅行の自由時間に訪れた九州地方の湖で、見たことのない大きさのブルーギルを発見して「アレは絶対、日本新記録のギルだ!」と同級生と大騒ぎしていた魚が、“ティラピア”という全く別の種類の魚であったことや(数年後、沖縄県の安里川で再会)、初めての学会発表のため前日入りした香川県で、ガチガチに緊張する私を気遣って同期生がバスフィッシングに連れ出してくれたことなど、振り返ってみると人生の様々な場面で楽しい釣りの思い出があります。
釣りをしている時に考えること・体感すること

朝靄に包まれながらボートで湖上に浮いている時や、レインウェア越しに雨粒の音を聞きながらリールを巻いている時など、ふとした瞬間に自然の中に自分が溶け込んでいるような感覚になる時があります。“あぁ、やっぱり自然の一部なんだなぁ”と思ったりしながら、また湖に溶け込んでボーッと自動運転のようにルアーを投じて巻いていると、ゴンッ!と強い振動が手元に伝わってきて我に返り、そこからは目の前の魚(主にブラックバス)とのやりとりが始まります。魚を取り込んで持ち上げたところで「ナイスフィッシュ!」と離れた場所からボートを寄せてきた釣り仲間に声をかけられることもあり、高揚感と共にスッと現実感覚が戻ってきます。ルアーフィッシングの場合は、釣った魚をリリースすることも多いため、各フィールドのルールにそって魚を湖へと帰します。水中へと消えていく魚を見送りながら、“何故このタイミングで、このルアーにバイトしたのだろう”と、ぼんやり魚の気持ちを考えてみたりすることもあります。こうした一連の流れを正午あるいは夕方まで繰り返して、ボート屋さんに戻ってきます。桟橋にボートを寄せてロープを巻き付けた所で、その日の釣りは終了となります。湖上から陸に戻り車を運転し始めると、ゆっくりといつもの世界が立ち上がってくる感覚になり、“さぁて、戻ってまた頑張るか”とエネルギーが充電されたような気持ちになることが多いです。
子どもたちとの水辺の探索
我が家の子どもたちも自然と触れ合うことが大好きで、多摩地域の水辺を探索しに出かける機会が多くあります。近隣の川や水路を巡って生き物を探索すると、ドジョウ・メダカ・モツゴ・ハヤ・コイ・フナ・ナマズ・ザリガニ・モエビ・サワガニ・ヤゴ等々、たくさんの生き物たちと出会うことができます。少しまとまった休みがとれた際には、大洗海岸(茨城県)や岩井海岸(千葉県)の海まで足を伸ばして生き物たちに出会いに行くこともあります。また最近では、息子がルアーフィッシングに興味を持ってくれたこともあり、湖でのボートフィッシングに同船してもらうことや、管理釣り場にニジマスを釣りに行くこともあります。大人にとっては見慣れた光景であっても、子どもの目にはとても新鮮に映るものがあるようで、水辺へと出かける度に新しいものに出会えた喜びを明るい表情や真っすぐな言葉で伝えてくれます。こうした子どもたちを介して体験する水辺の探索は、これまでとは異なるチャンネルから自然とつながる体験にもなっている気がしており、ヘトヘトになることもありますが、こころはとてもリフレッシュされているように思います。

水辺の自然に癒されて
大人になるにつれて、どうしても効率的に日々を過ごしていくことを考えるようになる気がします。ただ、時には非効率的な世界・時間軸の中に身を置くことも大切なのではないかと思っています。私の場合は、そうした世界が水辺にあり、その世界に触れるための手段として「釣り(ルアーフィッシング)」があり、「水辺の探索」があったのだと思います。学生であっても社会人であっても現実生活に少しへばった時に、全力で逃げ込める世界が一つ二つあると、とてもこころが軽くなるのではないかと思います。私自身も、「受験勉強」「対人関係」「卒業論文・修士論文の執筆」「病院実習」「学会発表」「就職活動」「資格試験」「心理職としての実務」など、様々なプレッシャーから解放されるべく水辺に逃走した思い出がたくさんあります。水辺に限らず「自然」の世界に足を踏み入れると、そこには「他者評価」のような価値観のない、「そのまま」の世界が広がっています。自然の中に在ることで、人が「そのまま」の世界の一部であることに気づけると、少しこころがリフレッシュされるのかも知れません。私自身もそうした感覚を大切にして、また水辺の自然たちとお付き合いしていきたいと思っています。