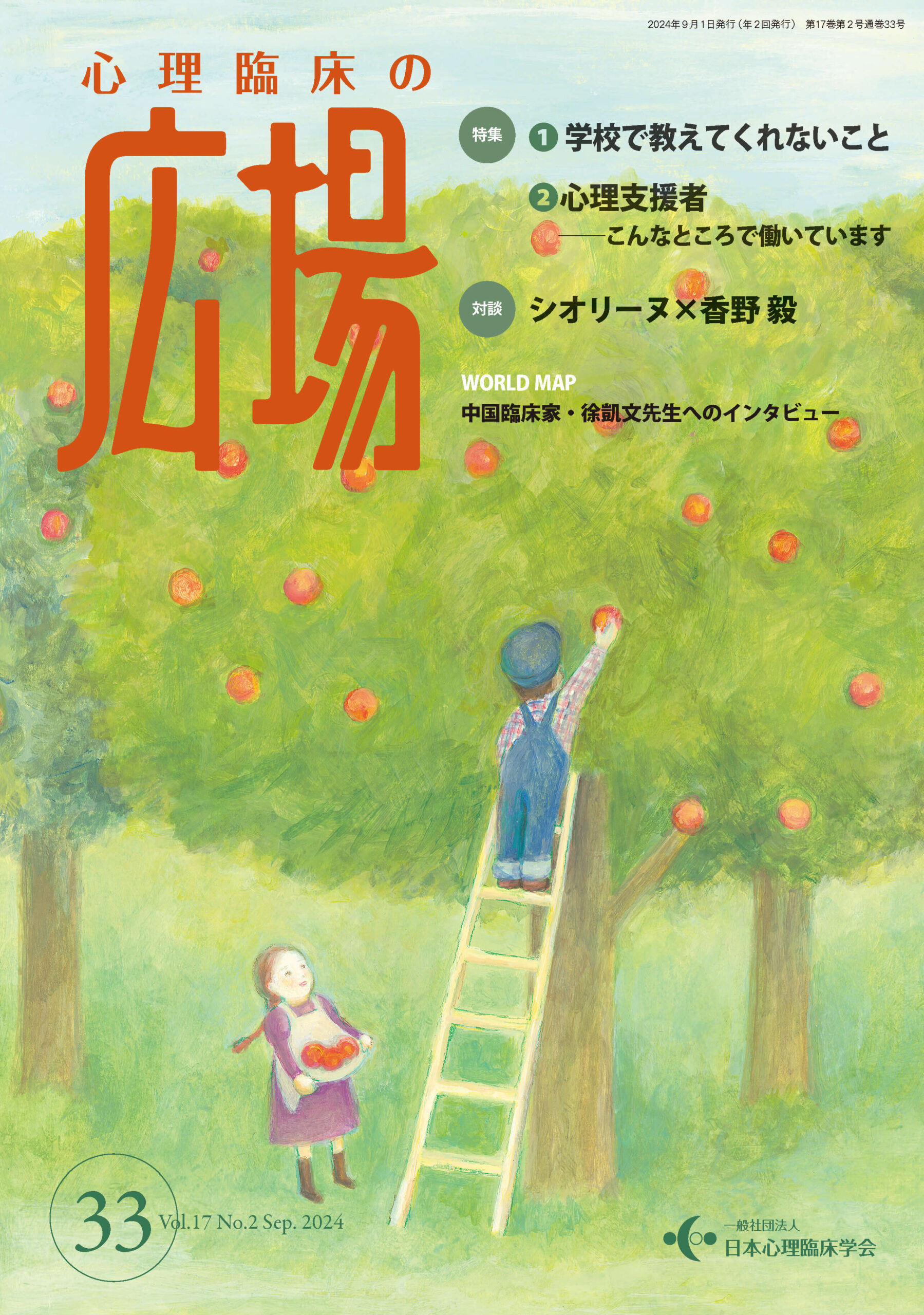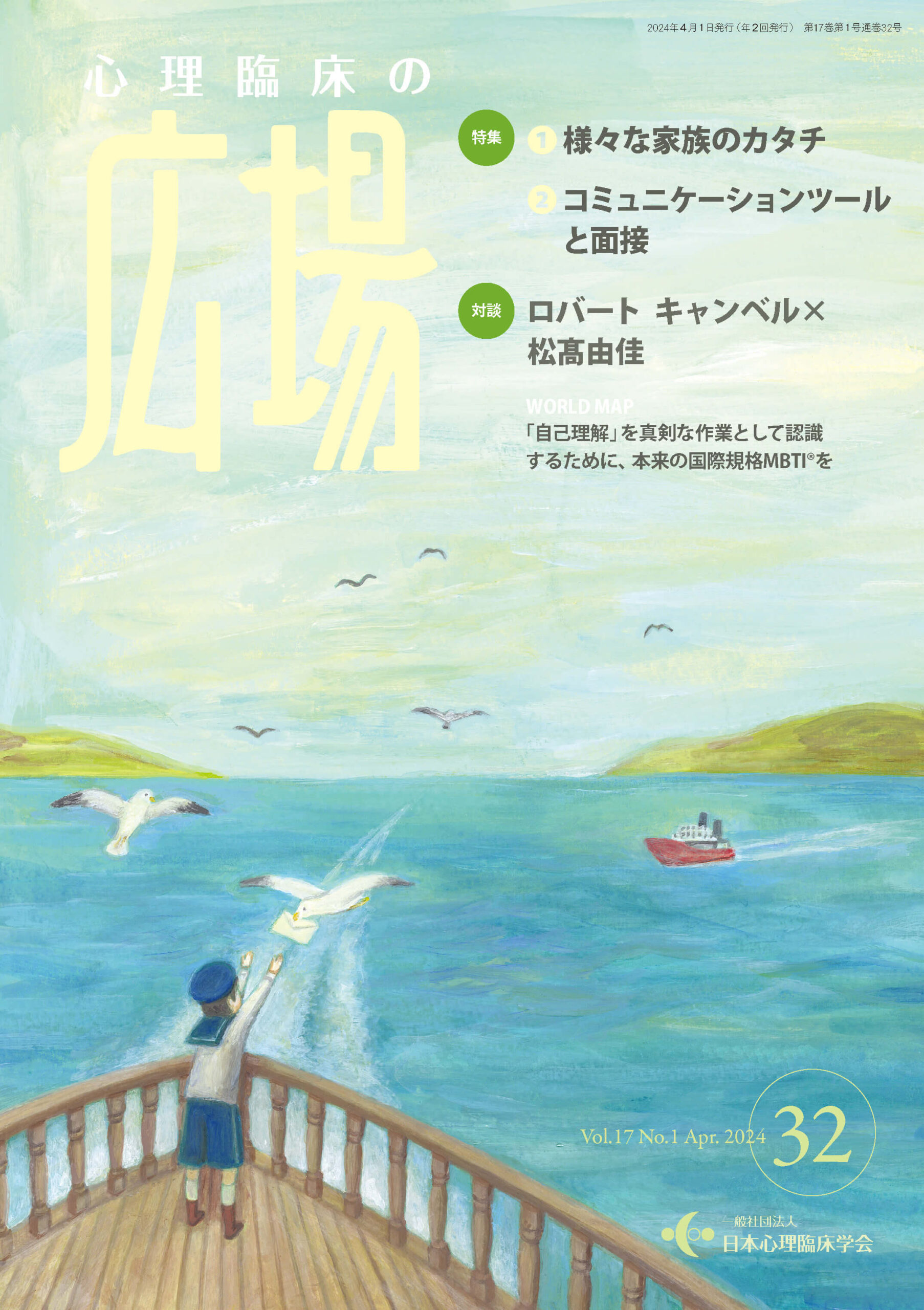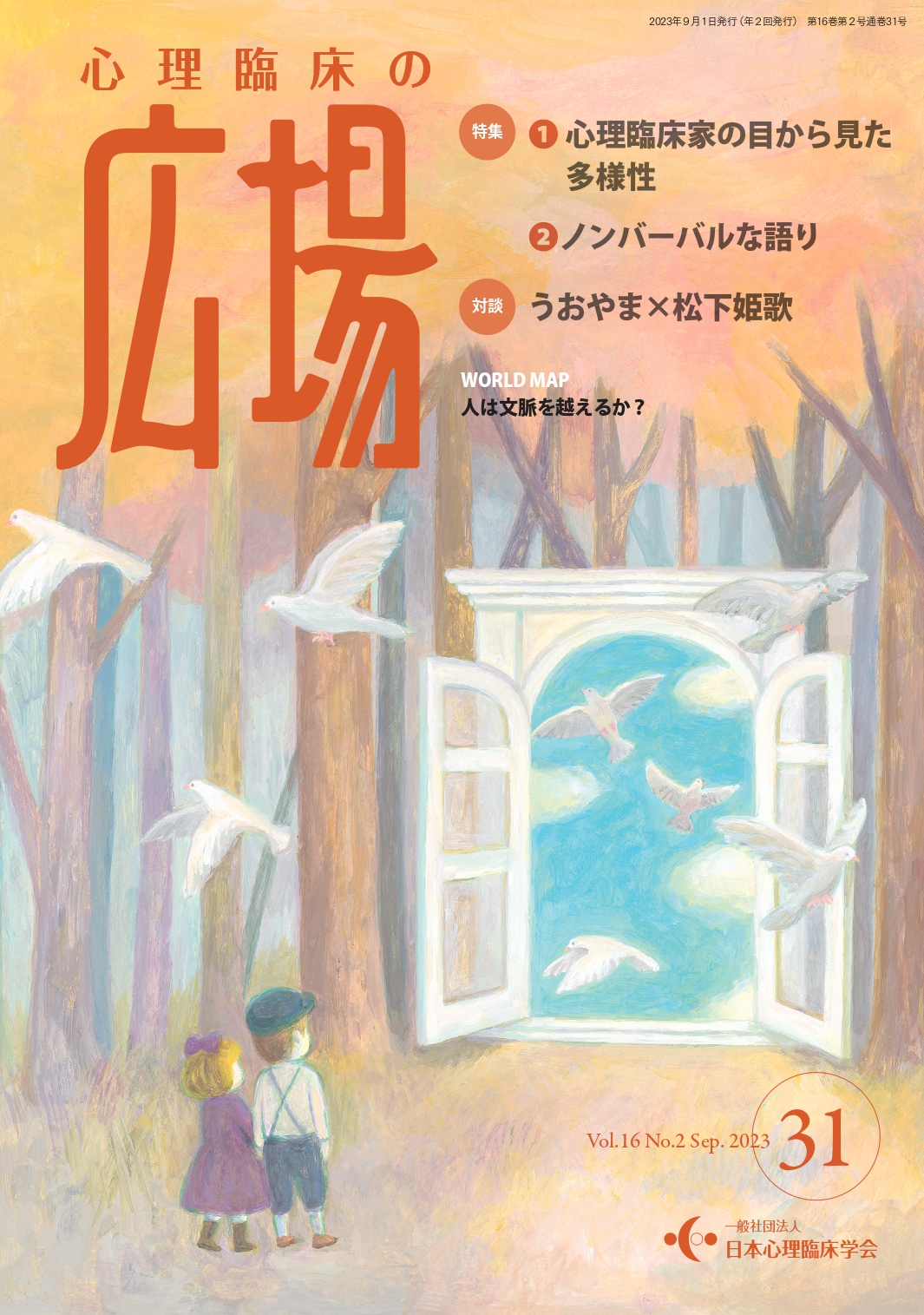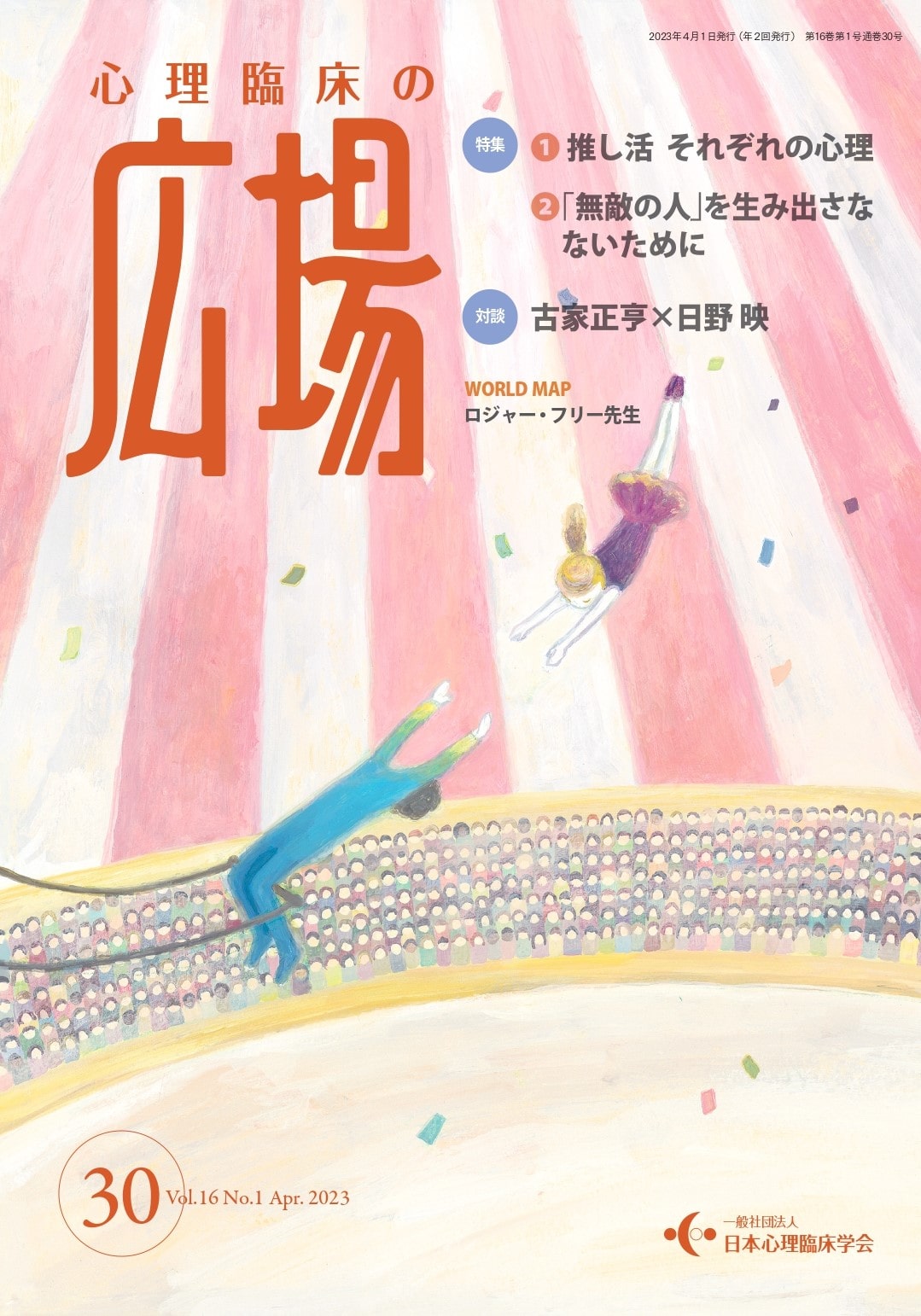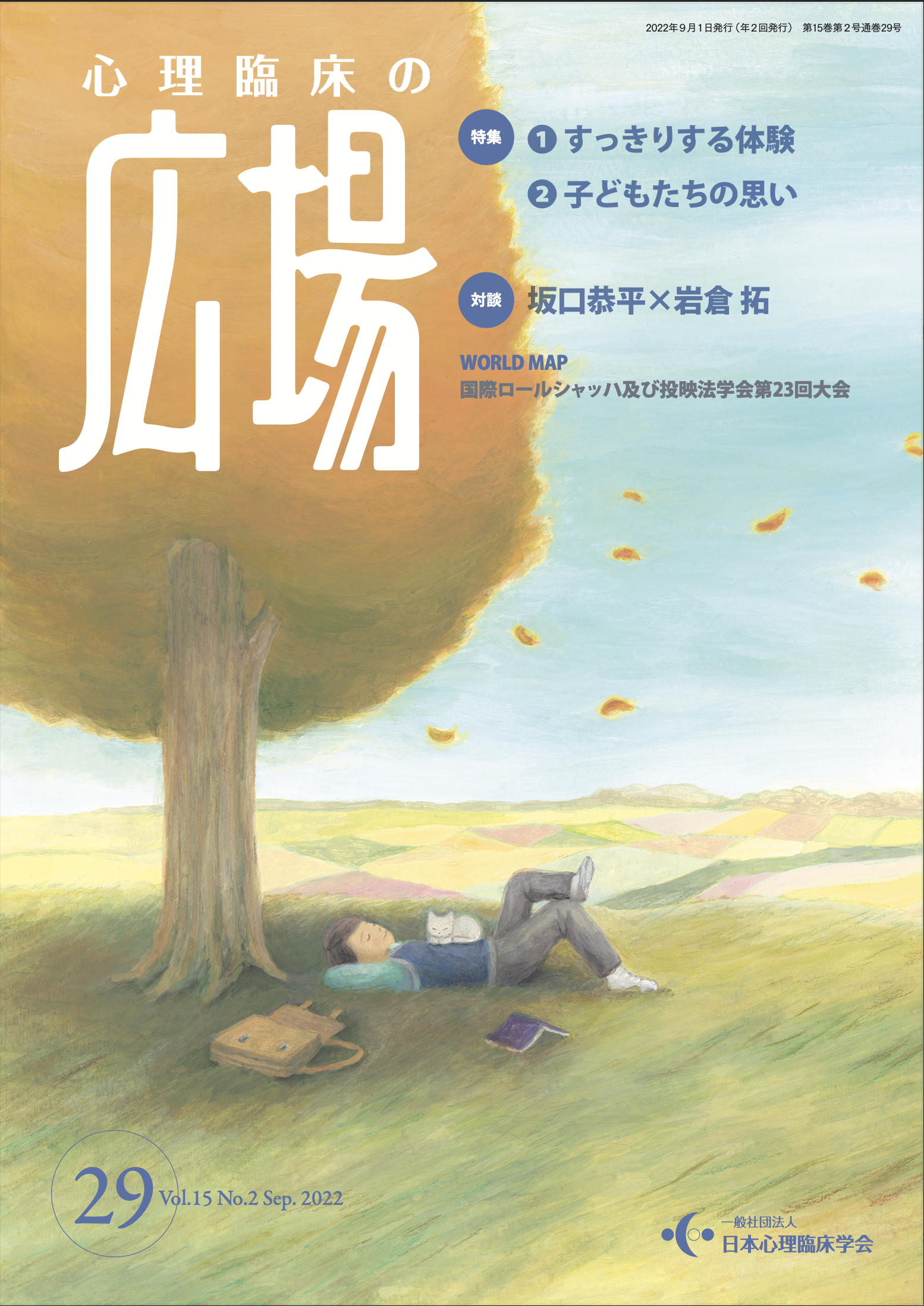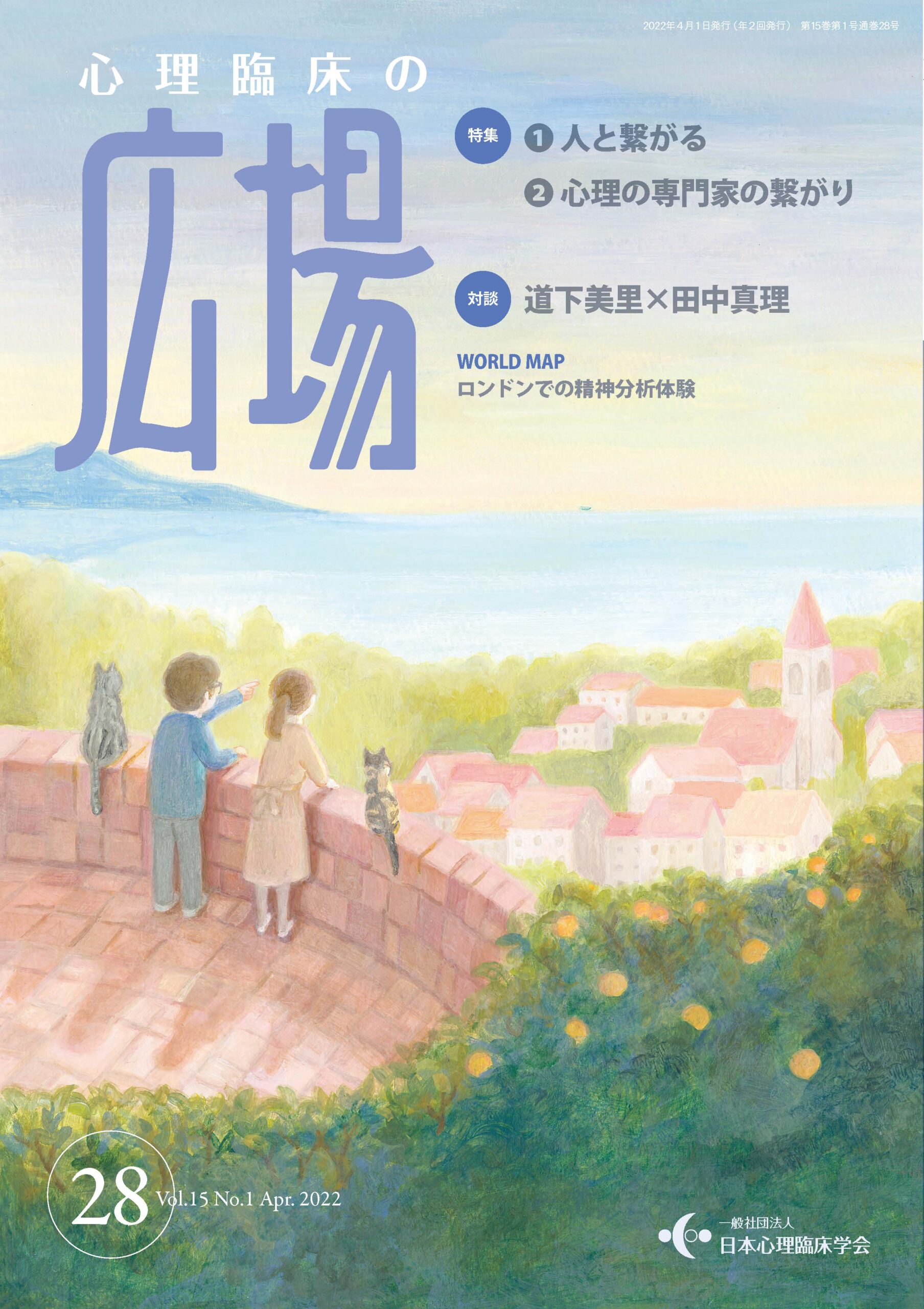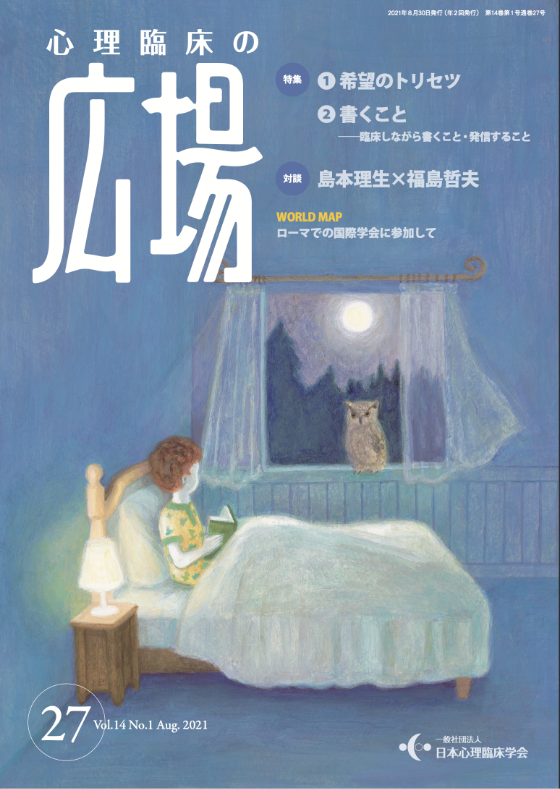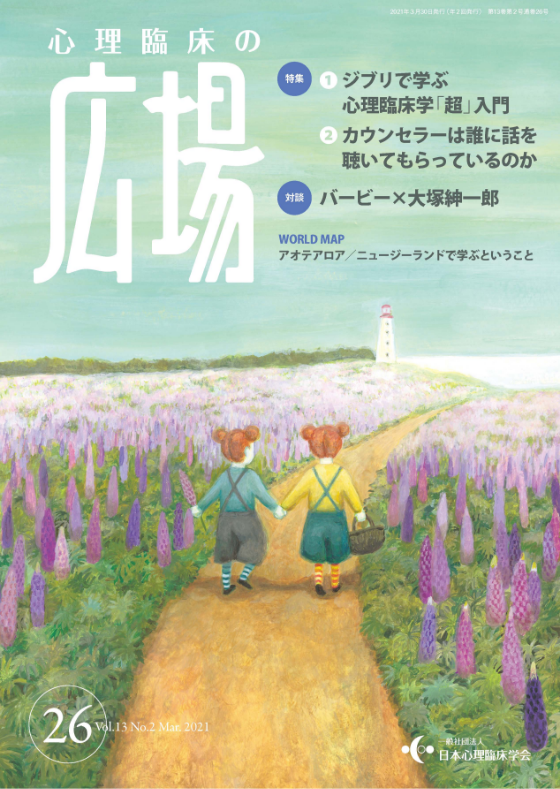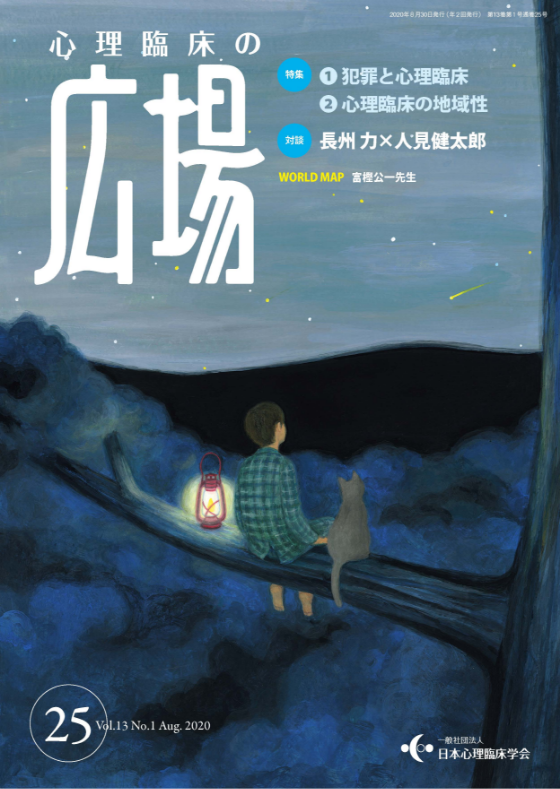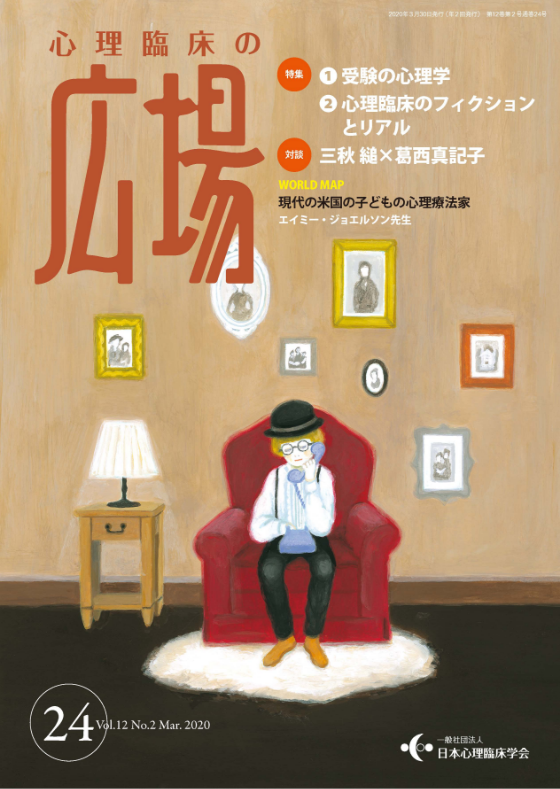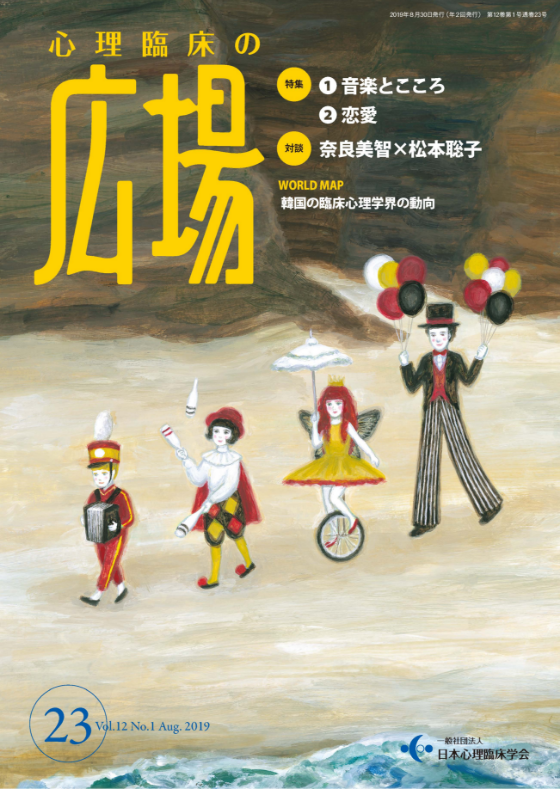Serial Articles WORLD MAP イタリアの難民センターにおける心理社会的支援
著者 Joel Nafuma Refugee Center/アトマスジャパン 滝 真樹子
私は現在イタリアのローマに住んでおり、オンラインでカウンセラーの仕事をしながら、ご縁があり難民センターで心理士としてお手伝いをさせて頂いています。過酷な環境にいる難民の人達を支援することの難しさや、活動の様子を紹介したいと思います。
難民支援を志したきっかけ
「難民」と聞くと、どこか遠い国の自分とは関係のない存在のように感じる人もいるかもしれません。でも、あまり知られてはいませんが日本にも庇護を求めて逃れてくる難民の人達はいるし、徐々に難民の学生を受け入れ始めている大学も出てきています。昨今のウクライナ侵攻における避難民受け入れでも話題になったように、日本でも難民という存在は身近になりつつあります。
難民の人達とはもちろん状況が違いますが、私自身も今までに住んだ国は今回のイタリアで5カ国目、引っ越しをした回数は覚えている限りで10回以上になります。移動が多い人生を送っていると、新しい環境での適応能力は比較的高くなったように思いますし、今ではそれを楽しめるようにもなりましたが、やはりどこにいても「よそ者」という感覚があります。そういった経験から、移住者のアイデンティティや難民・移民の心理支援に興味を持つようになり、学生時代に国際関係のサークルに所属していたこともあって、いつかは自分の専門性を生かして国際協力に携わりたいと希望していました。
修士論文も難民支援について執筆し、卒業後はイギリスのタビストック・クリニックで難民の心理支援や多文化カウンセリングについての授業を受けました。日本ではクリニックや学校で臨床経験を積んでいたのですが、いつかまた難民支援に関わりたいという気持ちがあり、家族のイタリア赴任が決まった際に色々と調べてローマにはたくさんの難民支援施設があることを知りました。そこで一つの難民センターにコンタクトを取り、お手伝いをさせて頂く機会を頂きました。
Joel Nafuma Refugee Centerにおける心理社会的支援について
イタリアには近年、北アフリカの密航業者の斡旋増加や政情不安の影響により、アフリカ各国から流入してくる難民・移民の数が急増しています。その他南アジアや中東地域等様々な国からも難民が押し寄せており、イタリア政府はその対応に追われている状況です。ローマ市内にあるJoel Nafuma Refugee Centerでは、そういった難民達に対して職業訓練や言語指導、煩雑な申請書類の作成支援や法律相談を提供している他、精神科医や心理士・インターンの学生達で形成される心理社会的支援チーム(Psycho Social Support Team)がメンタルヘルスの維持・促進業務を担っています。
難民のメンタルケアというと、トラウマやPTSD治療を最初に思い浮かべる人も多いと思います。もちろん重篤なうつ症状やPTSD等の精神症状が見られる場合には、専門機関へのリファーを行う場合もあります。ですが、難民センターのようなその日誰が来るか分からないという不確定な要素が多い場所においては、クローズドな治療的アプローチを日常的に行うことには限界があります。トラウマや脆弱性といったイメージが想起されやすい難民の人達ですが、実際には能力やもともとの健康度が高い場合も多いです。新しい土地への適応を促し、生活を支援していくには、彼らのレジリエンスを支持し、エンパワメントしていくことが大切です。そういった意味で、多職種が連携してレジリエンスの向上や社会適応の促進を支援していく心理社会的支援という視点が重要となります。
心理士としての役割や難しさ
そうした背景を念頭に置きながらの活動になりますので、普段は基本的に心理的負荷の少ない手芸やコラージュ等のアクティビティを、インターンの学生さん達と相談しながらグループで行っています。その中で日常的なお話をしながら必要があれば他の支援に繋げたり、職員に情報を共有したりします。また、ニーズがあれば個別のカウンセリングを実施することもありますし、状況に応じてストレス反応やトラウマ症状に関する心理教育を行うこともあります。文化的背景によってはカウンセリングや精神科といったものに拒否反応を示す方もいらっしゃいますので、まずは居場所作りということを意識しています。
インターンの学生さん達はとても熱心で、時に私のカウンセリングの通訳をしてくれることもあり、心強い存在です。ですがやはり専門が違ったり、主張の強い国民性だったりすると、協力体制を築くのに苦労することもあります。例えば心理士として普段から臨床場面で描画を使うことがある人であれば、メンバーが流動的で、活動の後にしっかりと気持ちを話す時間が確保できない可能性のある場合には、大きな紙に絵の具を使って絵を描くといった退行を促すような活動は避けるのではないかと思います。ですが、そのことを心理系以外の学生さんや、職員の人に説明するというのはなかなか骨の折れる作業です。特にアート系の学生さんであれば作品的要素の強い活動を好みますし、施設側としては「心理社会的支援」の名目で支援金が入ったりするので、支援者に説明材料として分かりやすい描画が必要なこともあるのです。様々な事情とそれぞれの考えがありますので、その時々のメンバーのエネルギーや健康水準を見ながら、活動内容を決めています。
また個別に話を聞く際、一般的な流れであれば始めにその方の年齢位は確認すると思うのですが、アフリカ出身の方の場合、高齢の方ですと自分の生年月日を知らないという方もいらっしゃいます。生活歴のアセスメントとは何かというのを根本から考えさせられるような経験でした。更に日本ではあまり想像できないことかもしれませんが、祖国の情勢によってはどうしても同じテーブルにつけない国の人同士というのもいますので、気を配る必要があります。そのため移民関連や紛争地域の情報については、幅広く頭に入れておくようにしています。
そして、やはり難民の人達の中には戦禍を逃れて家族と離れてしまった方や、海を渡る途中にボートの上で亡くなっていく人を何人も見たという方もいます。そういった話を学生さんが聞くというのはとても負担が大きいですので、スタッフの側のメンタルを守るためにも、心理的負担が大きい時には心理士を呼ぶように伝えています。インターンの学生さんや他のボランティアの人達に適切な対応についてコンサルテーションを提供することも、心理士としての重要な役割です。
どうにもならない不平等を前にして絶望的な気持ちになる時もありますが、学生の頃にある難民の方から言われた「目の前の人や家族に愛を伝えてあげて」という言葉が支えになっています。私達にとってこれからますます身近になってくる難民の人達と、コミュニティで共に生活していくために心理士として何ができるかということを、今後も考え続けていきたいと思っています。