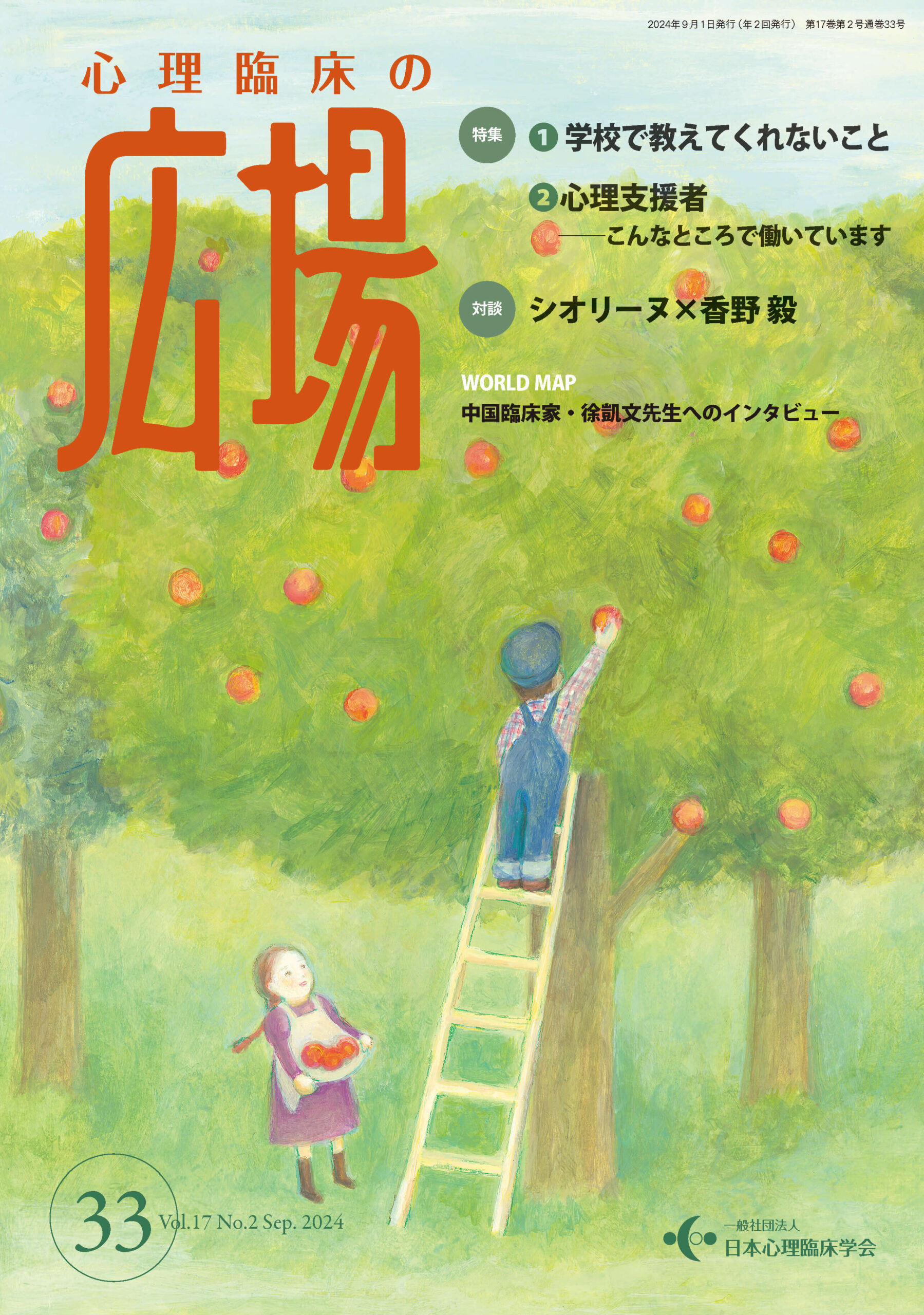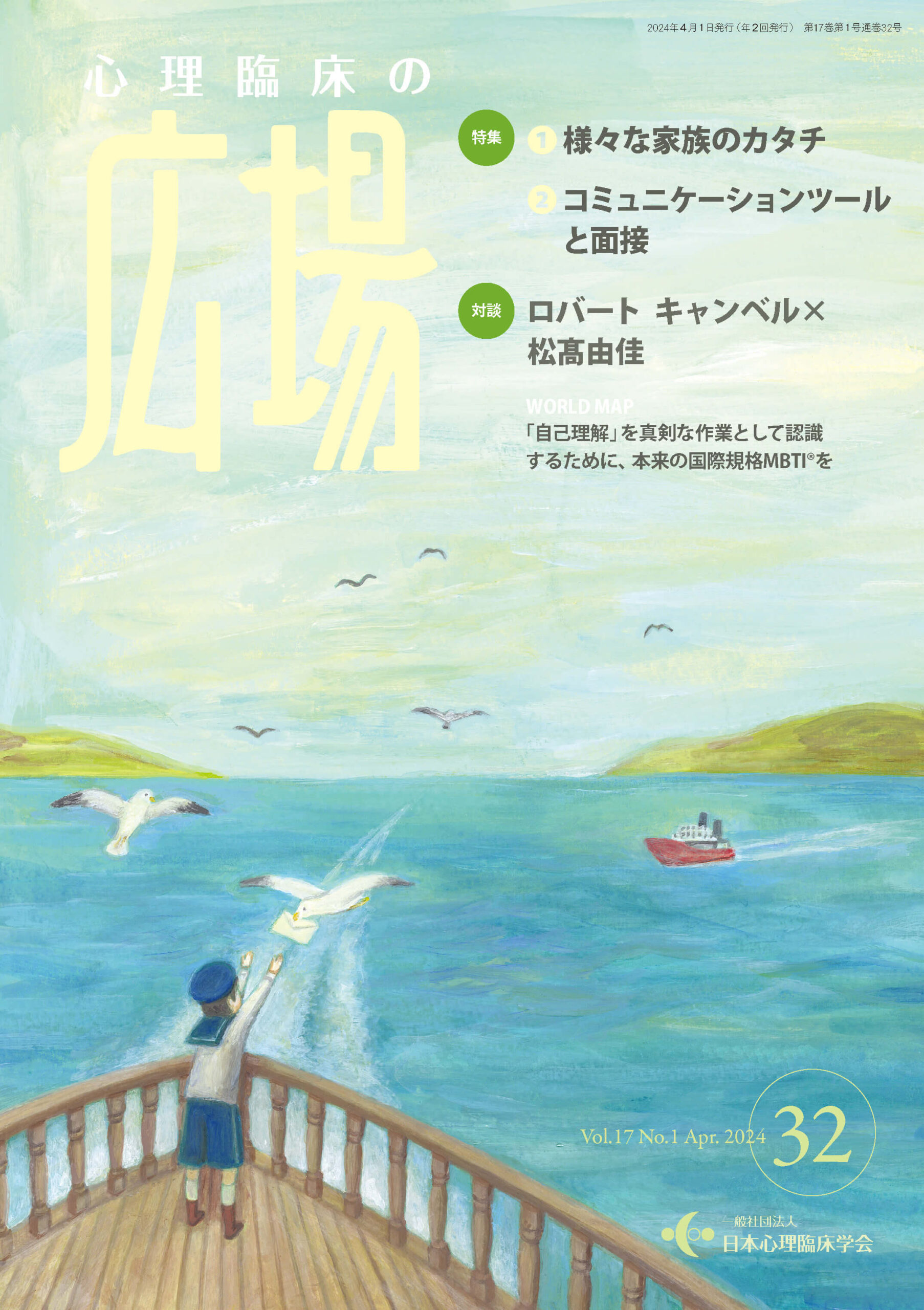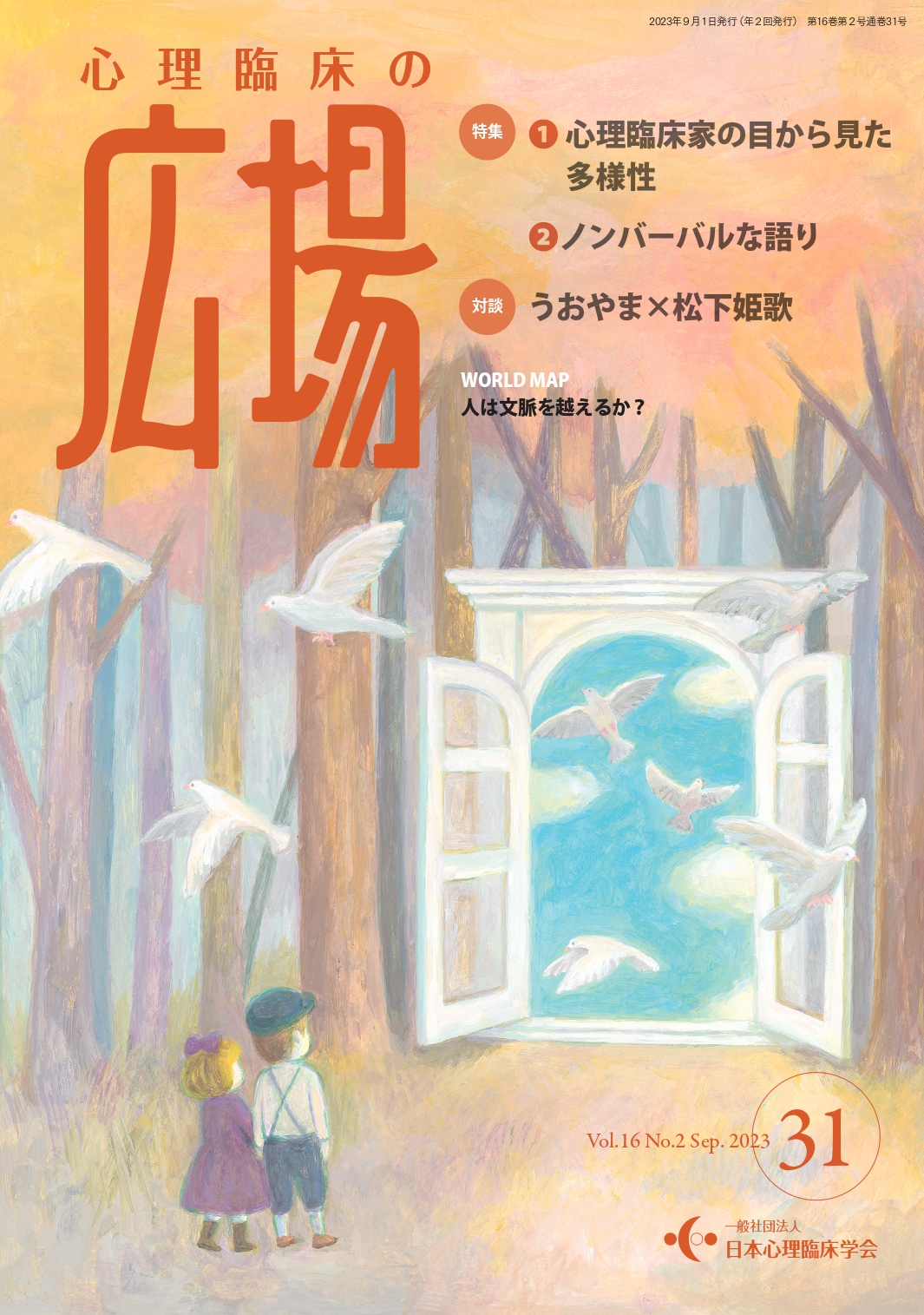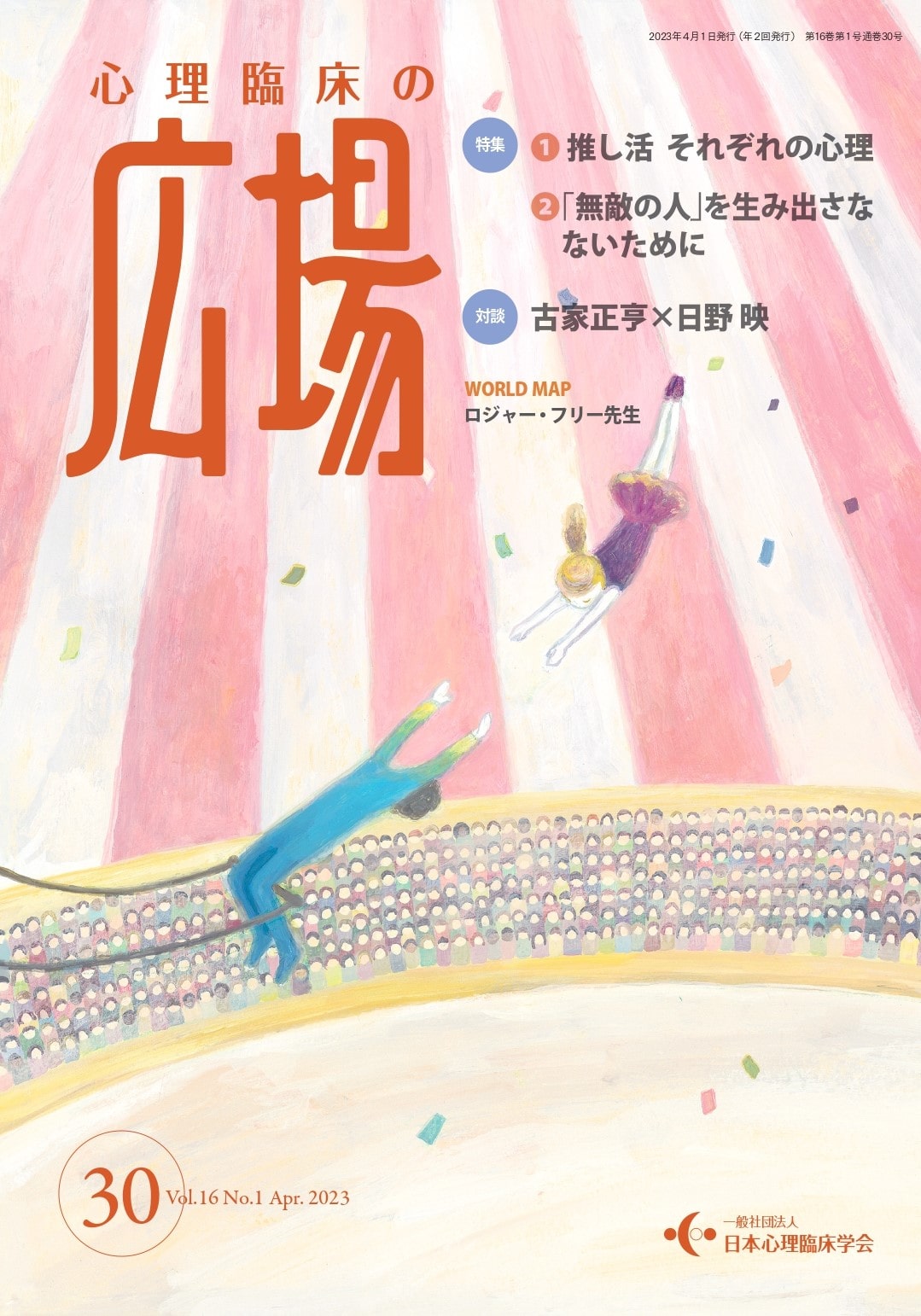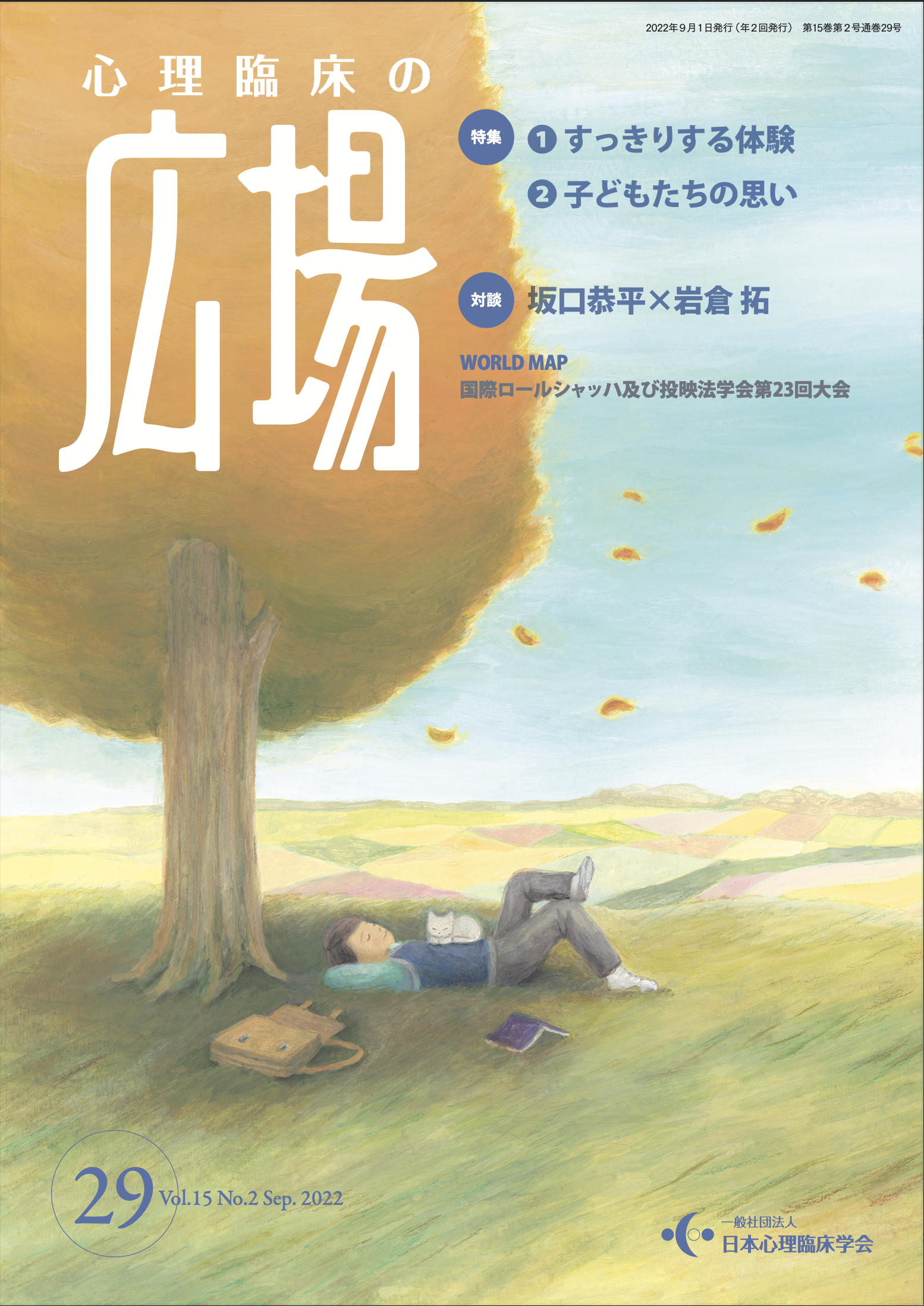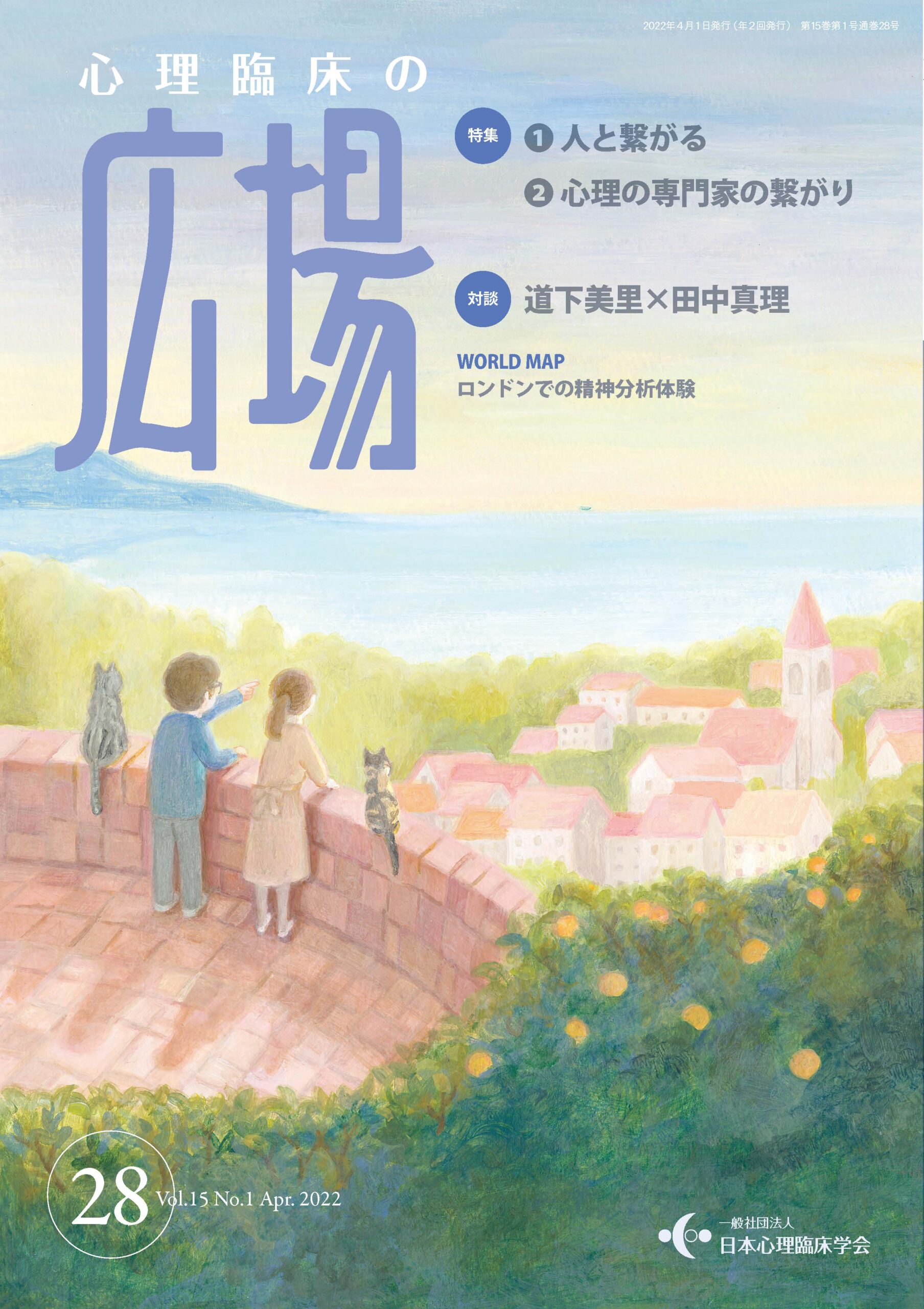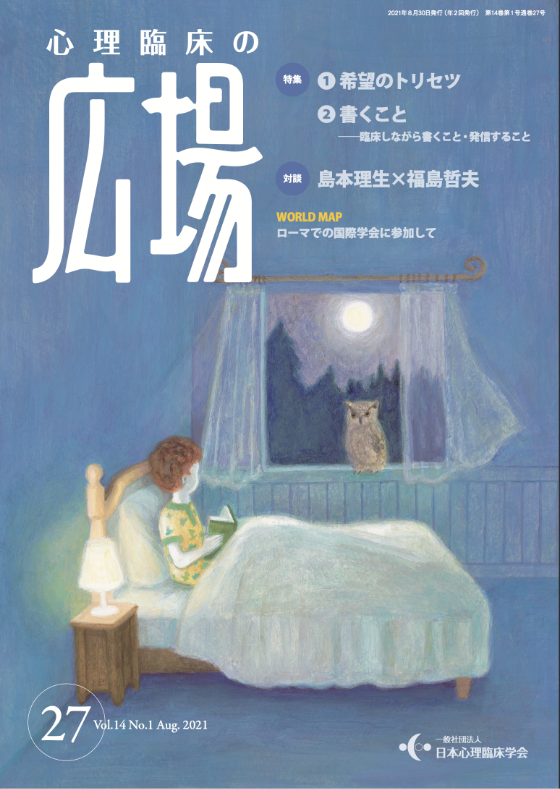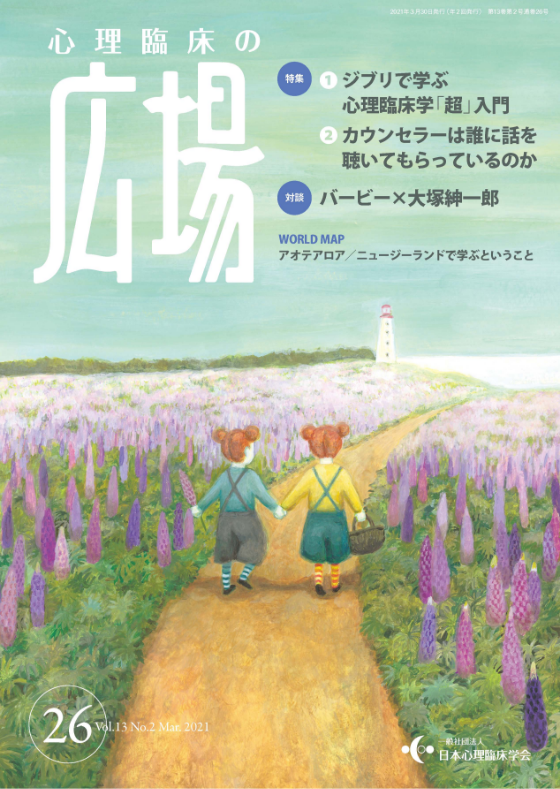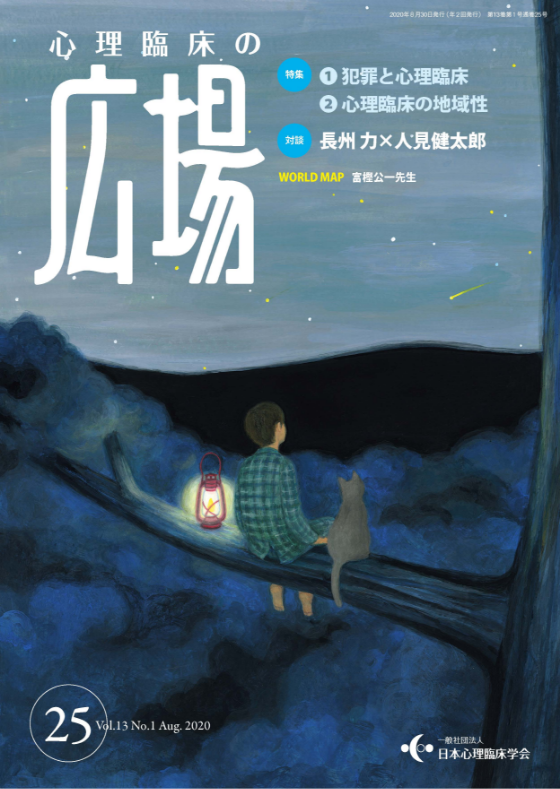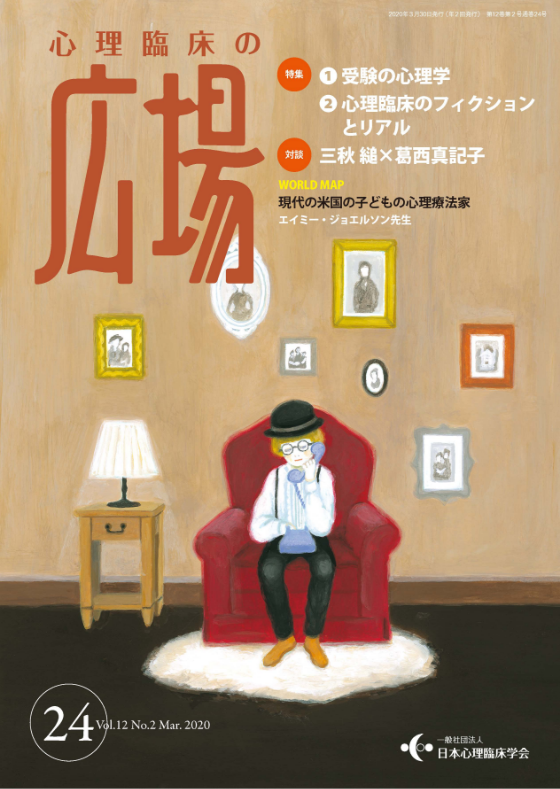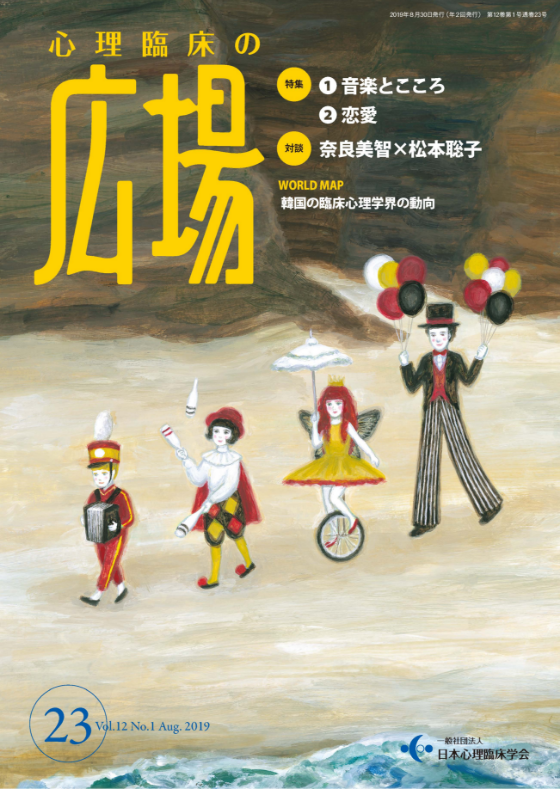Serial Articles 初心者のためのブックガイド『治療者としてのあり方をめぐって――土居健郎が語る心の臨床家像』
紹介者 札幌学院大学心理学部 斉藤美香
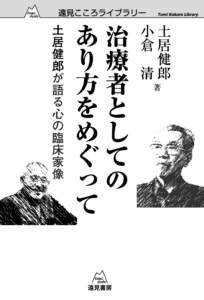
本書は1970年代にベストセラーになった『甘えの構造』の著者である精神科医・精神分析家の土居健郎先生、そして土居先生とゆかりの深い児童精神科医の小倉清先生という、50代以上の心理臨床に携わる人にとっては、知らない人がいないだろうというほどの著名なお二人による対談集です。第1部がお二人の対談で、第2部は小倉先生のアメリカ留学中の経験談などから構成されています。お二人の対談を通じて、治療者(著者が精神科医なので「治療者」「患者」という表現になっています)としての心構えや、治療者としてどうあるべきかなど、幼少時からの体験も織り交ぜながら語られています。
本書は1995年に別の出版社から刊行され絶版となった初版本を底本として再刊されました。私が初心者の頃から、自分の原点に立ち返らせる機会として、初版本を幾度となく読んできました。初心者にとっては、正解やマニュアル的なものを求めがちですが、本書の中では、「きちんとしたトレーニングを受ければ、きちんとした治療者ができるとは限らない」「制度化すると中身が乏しくなってくる」「ハプニングが大事」と述べられており、システマティックなスキル習得とは対極にあると述べられています。本書が提示する視点は、心理臨床の営みは「自分自身のあり方」と切り離せないというものです。「人間にはオムニポテンスに対するあこがれがいつもある」前提で、治療者は全能感(オムニポテンス)に対する憧れに気づき、抗い、とことん自分を突き詰めるという厳しさに耐えていく必要性とともに「不安定なまま」で良いとも示しています。
本書の魅力は、対談形式で読みやすいことです。ぶっつけ本番でユーモアに満ちた語り合いがそのまま掲載されているので、初心者にとって理解しやすい内容です。そして、最近の心理臨床では見過ごされがちな視点について述べられています。それは治療者自身の姿勢がいかに患者との関係性に影響を与えているかであり、技法とは異なる心理臨床の根本に関わる重要な視点といえるでしょう。お二人の先生の幼少時からの様々な体験や縁によって「治療者としての自分」が創られてきたことが生き生きと語られています。自分のこれまでの体験を踏まえた人間観、価値観など、自分の軸となるものが専門家としての幹であり、枝葉の広がりに通じているものでしょう。
心理専門援助職をめざして、学び始めたばかりの大学生や大学院生にとっては、専門的な知識を身につける以前に「心理援助専門職とは何か?」を深く考える良い機会になるはずです。臨床心理学の世界をより広い視点で捉えたい人、心理臨床の奥深さに触れたい人にぜひおすすめしたい一冊です。この本が、心理臨床を志す皆さんの視野を広げるきっかけとなりますように。