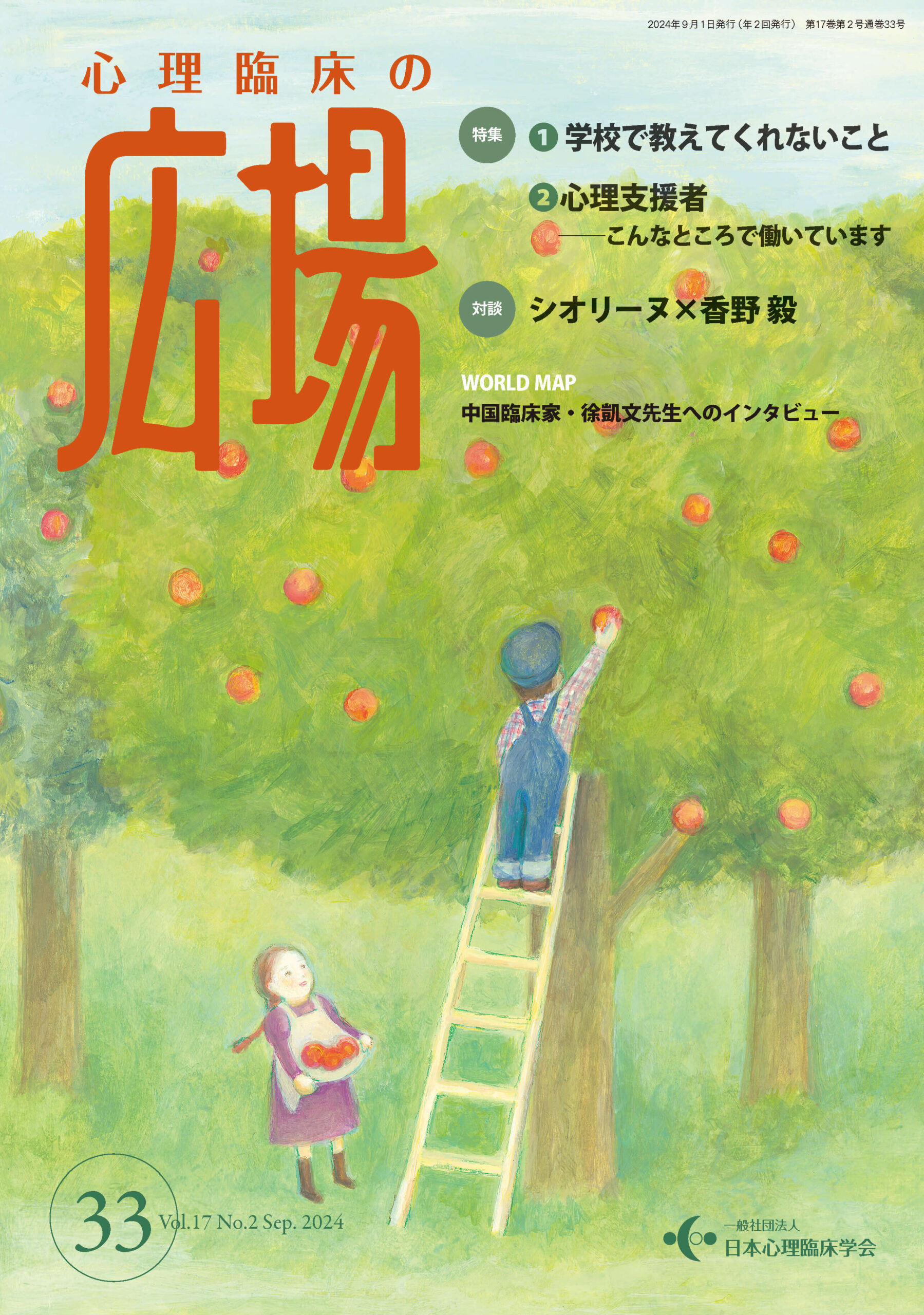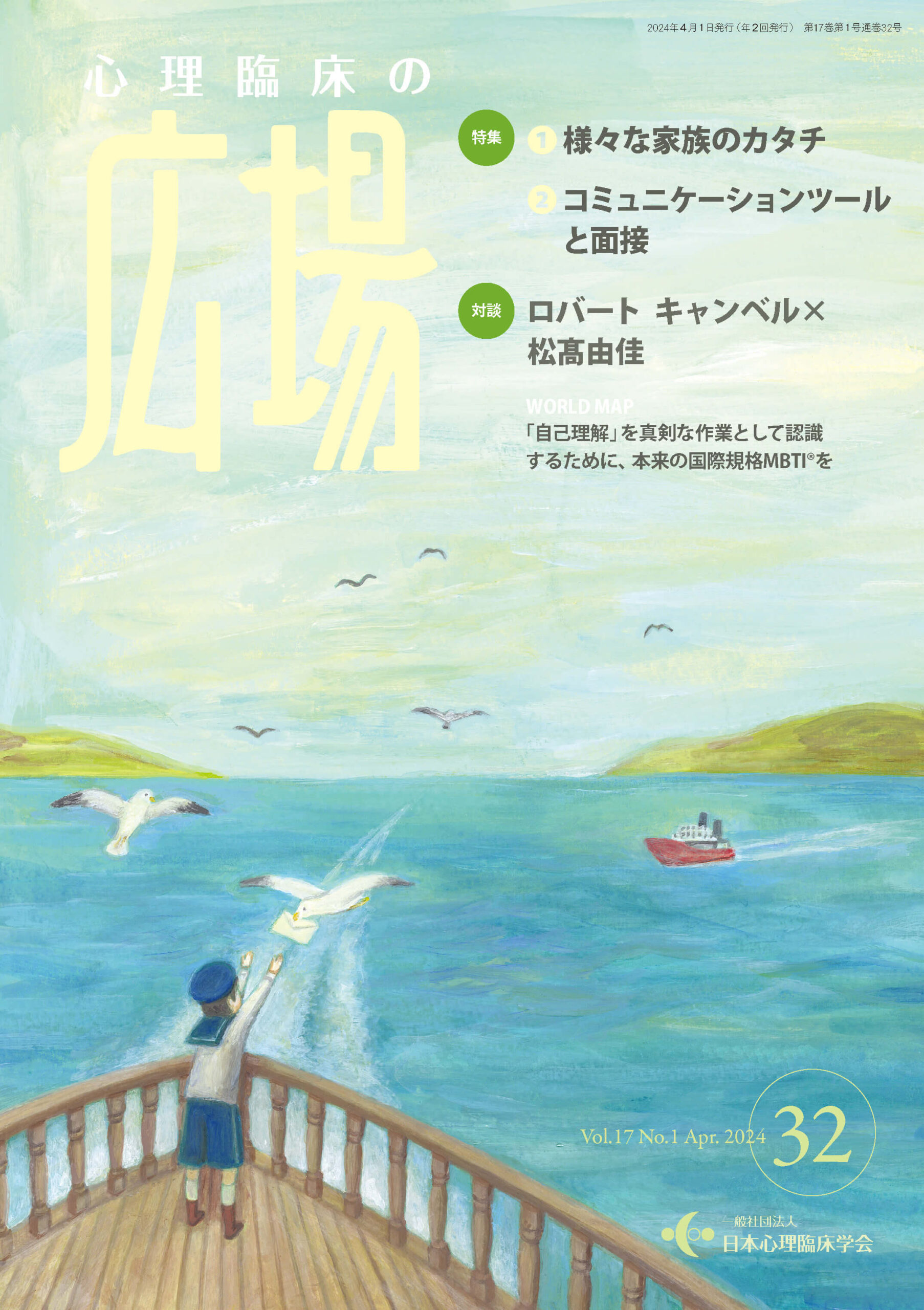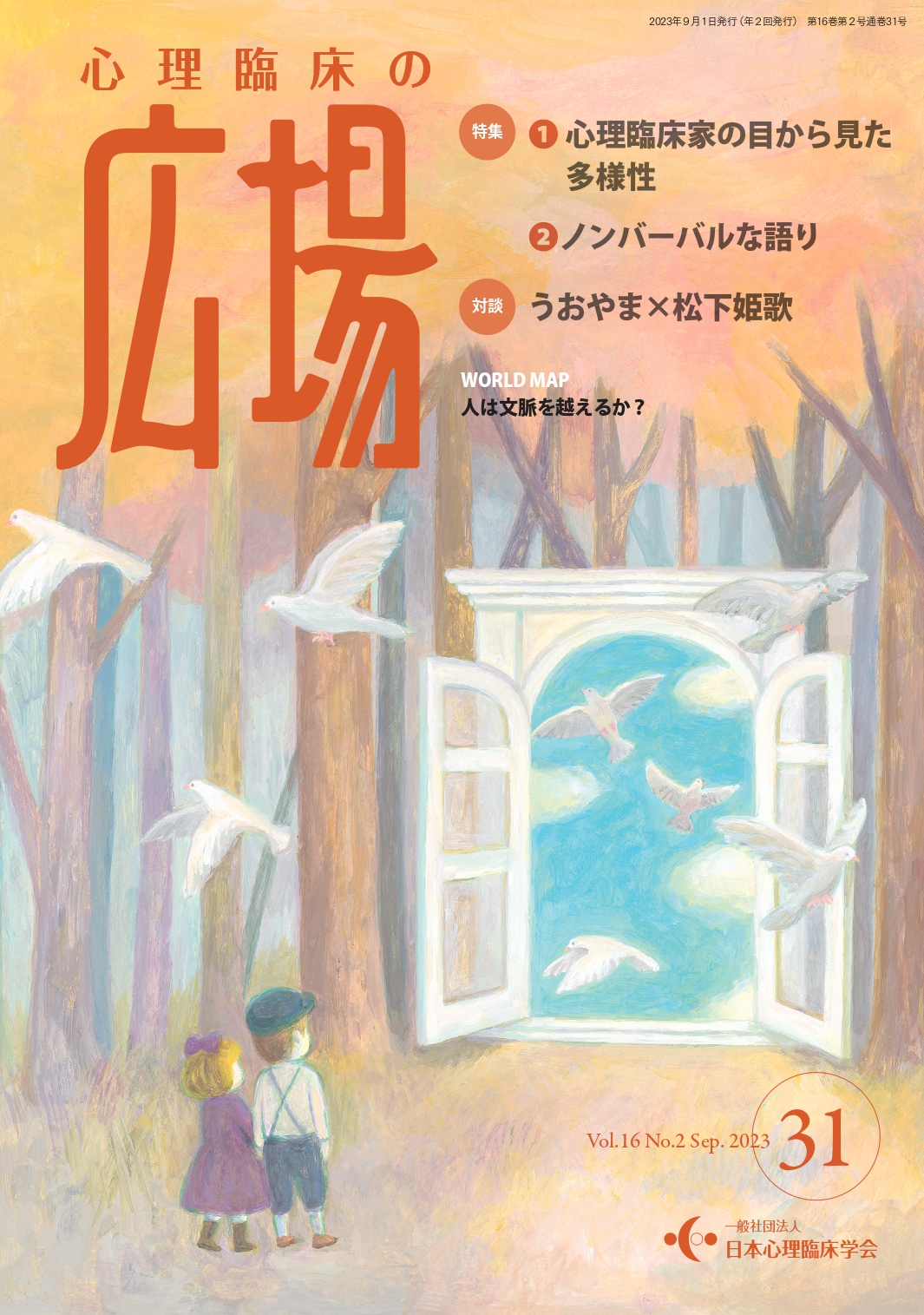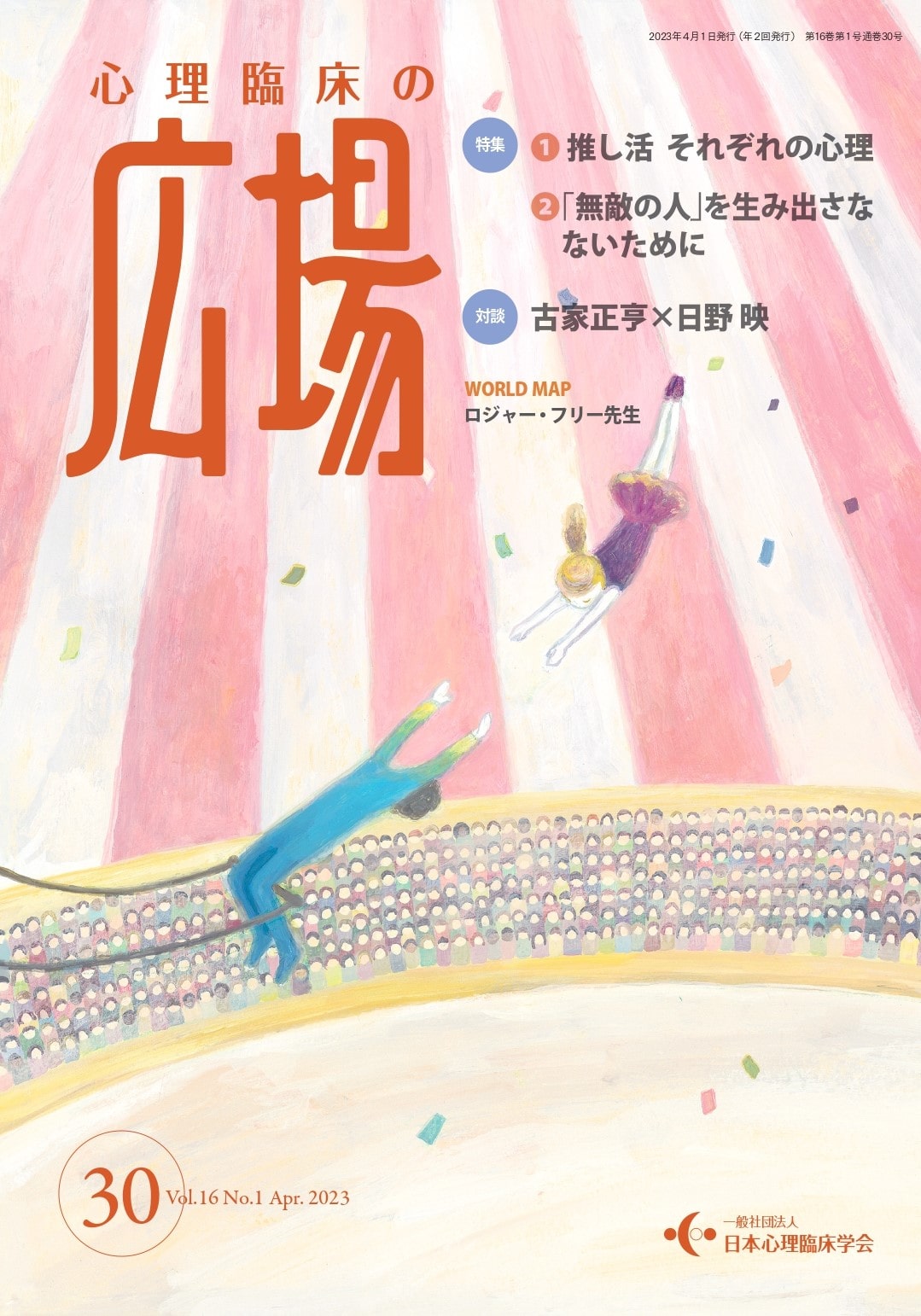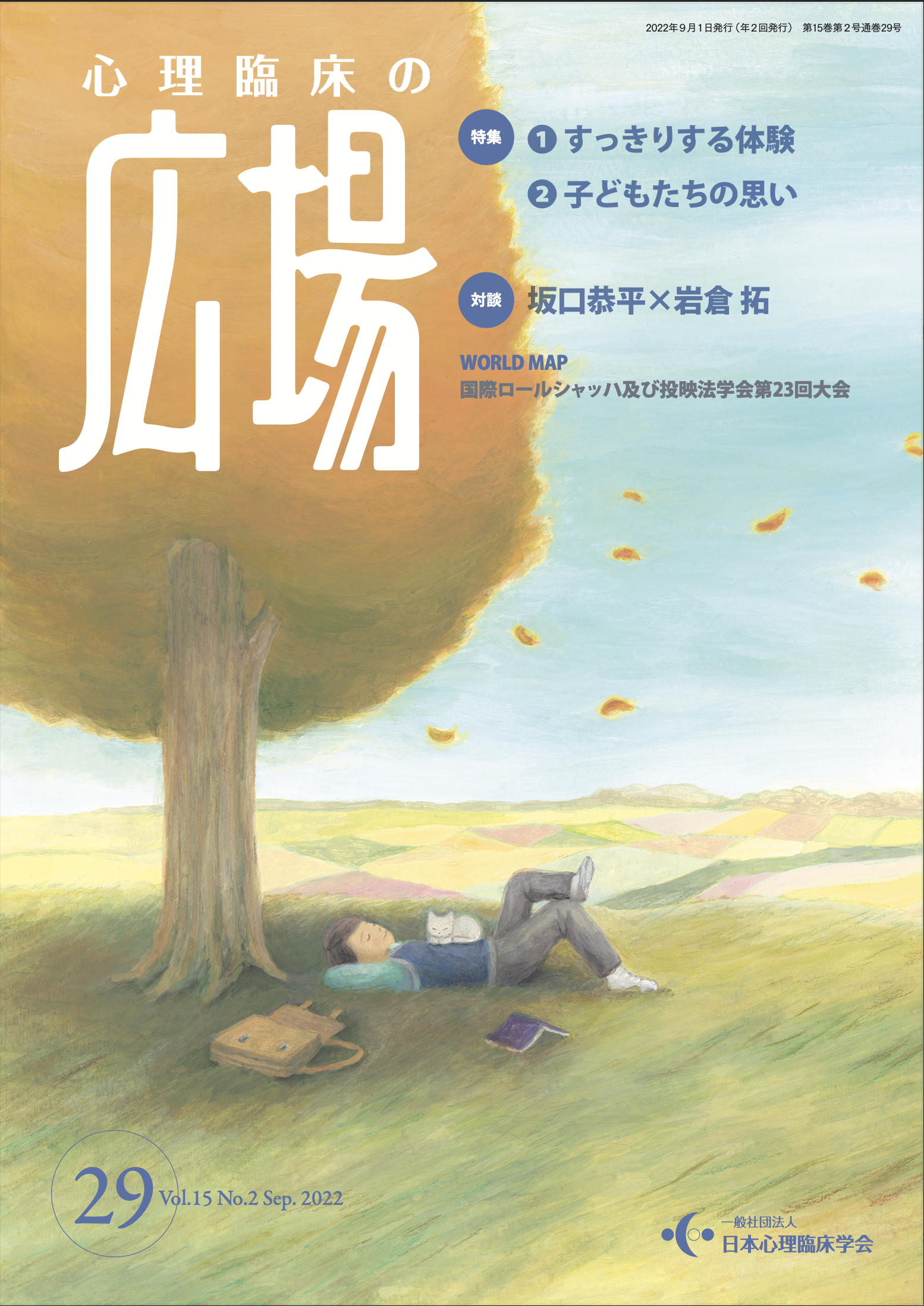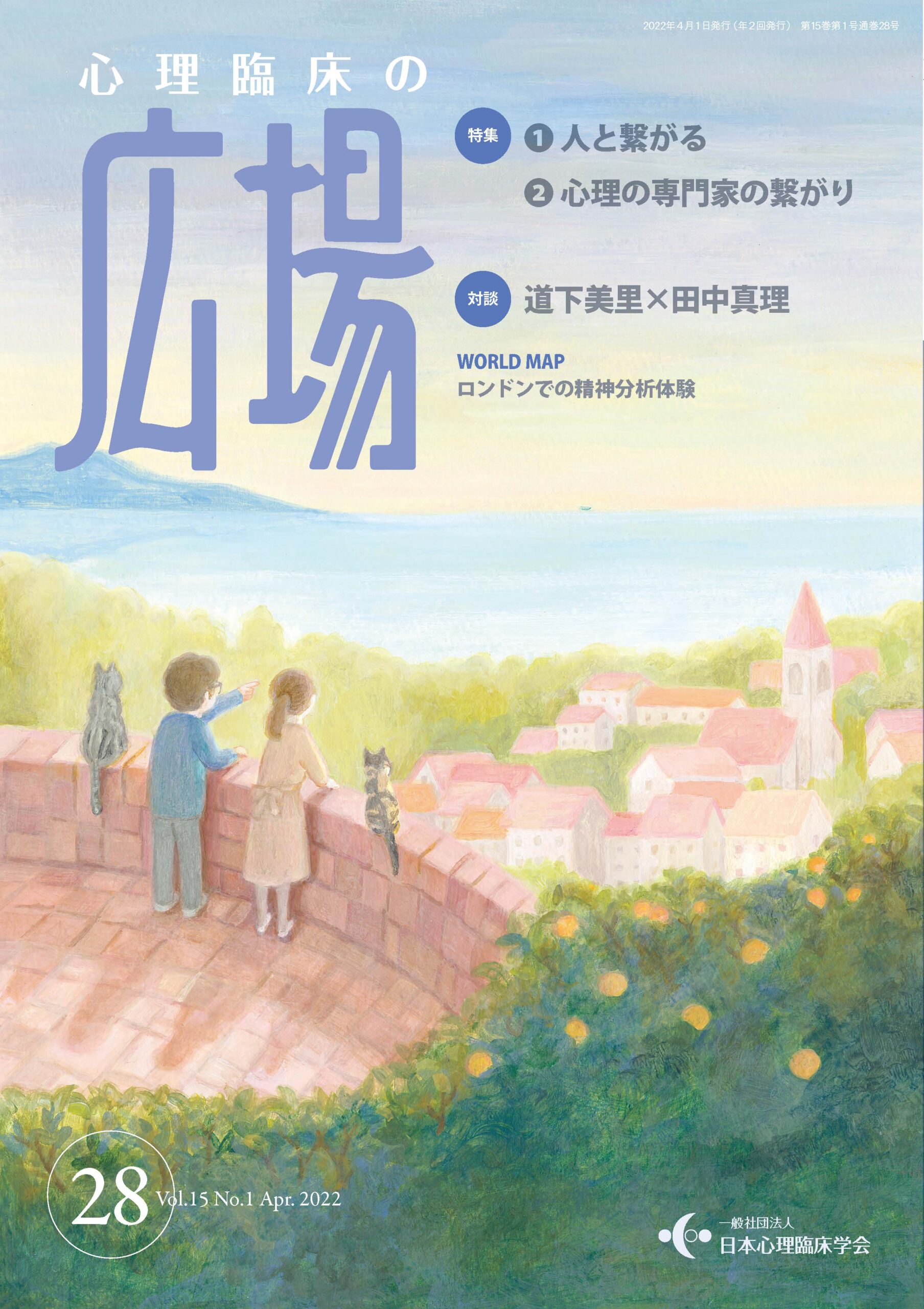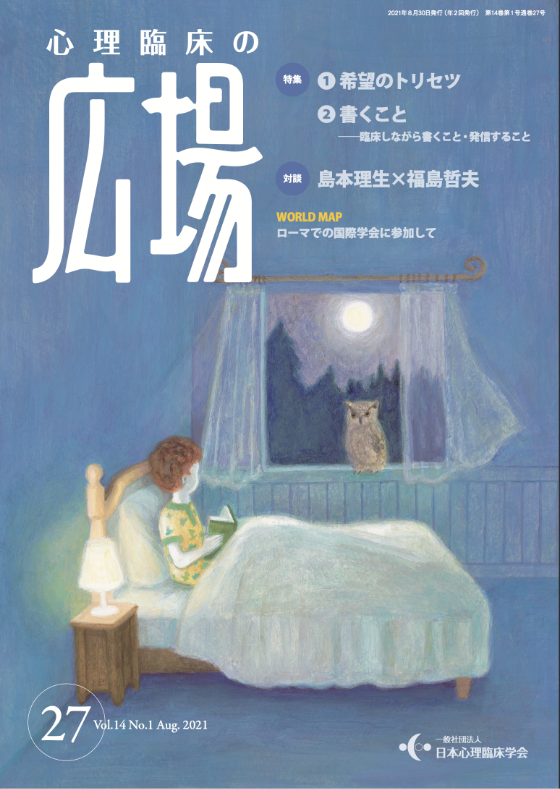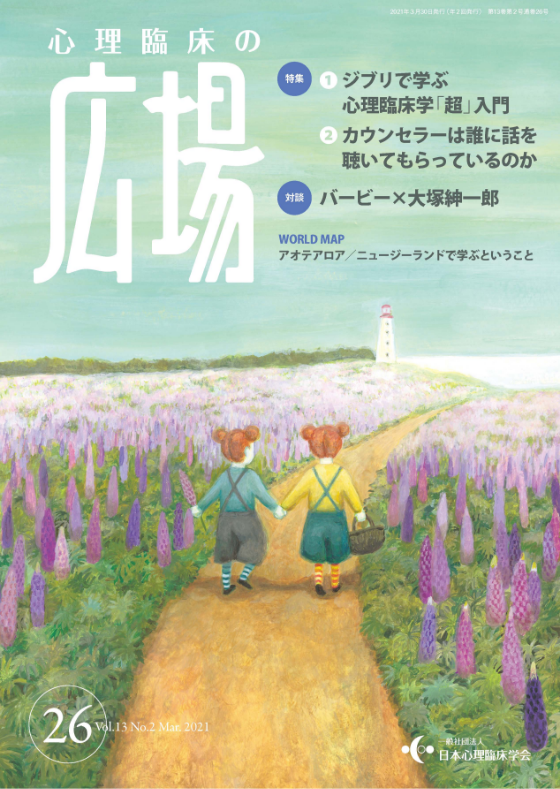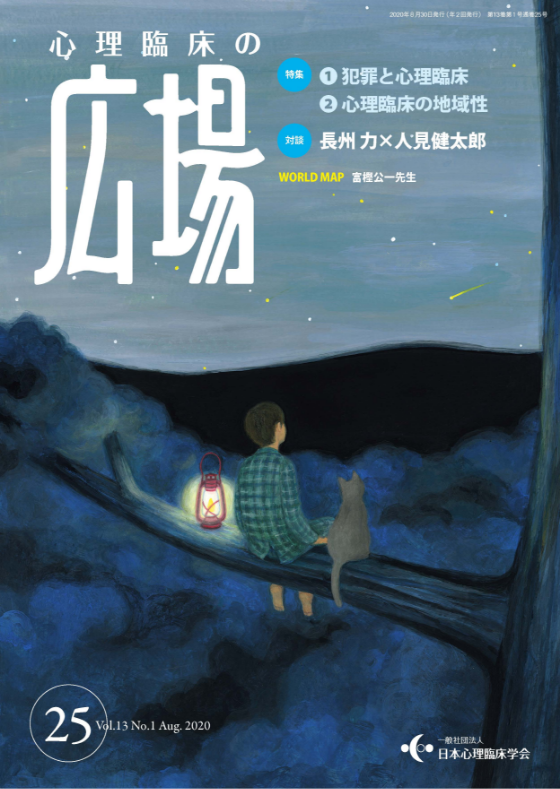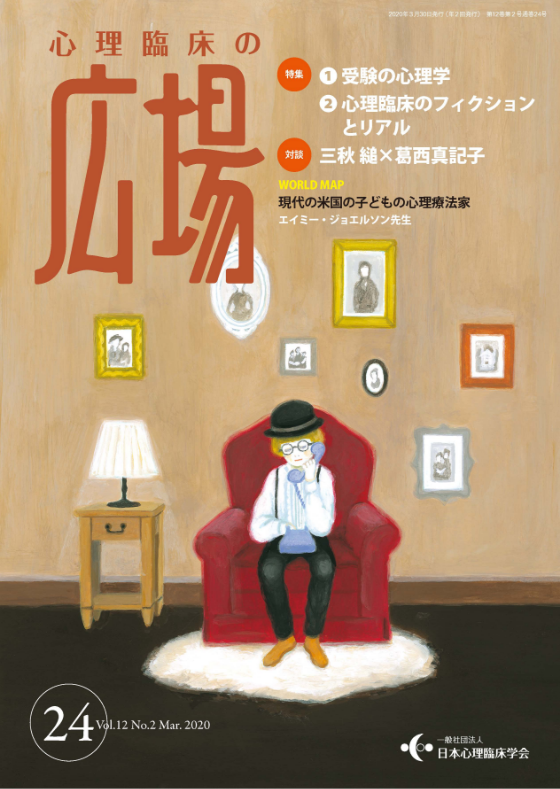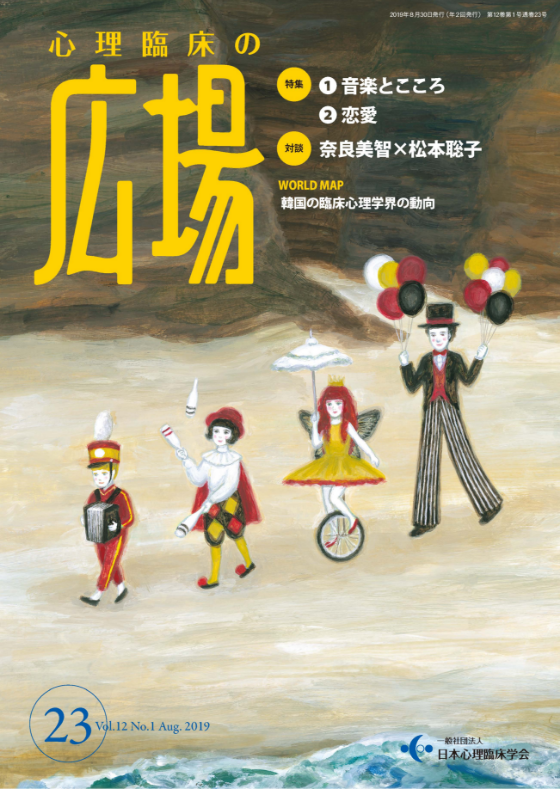概要(歴史)
日本大学は、1889(明治22)年に創立された日本法律学校を前身とします。1903(明治36)年には「日本大学」と改称し、1920(大正9)年の大学令により大学となりました。
学祖である山田顕義(1844〜1892)は、1844(弘化元)年に現在の山口県萩市で生誕し、吉田松陰の松下村塾に入門しました。西南戦争後には陸軍中将に任ぜられ、1885(明治18)年に内閣制度が発足して、初代の司法大臣に就任しました。
心理学科は、1924(大正13)年に日本大学「法文学部文学科心理学専攻」として出発しました。1949(昭和24)年、新制大学の発足にともない「文学部心理学科」に発展しました。その後、大学院の修士課程に加えて博士課程も設置されています。1958(昭和33)年、文理学部の発足に伴い、「文理学部心理学科」と改称し、研究室が東京都の世田谷区桜上水へ移転しました。現在も同地にあり、校舎の周りの桜が本当に見事です。
日本大学文理学部心理学科の創設者は、渡辺徹(1883〜1957)です。東京帝国大学を卒業後、1914(大正3)年から日本大学で講義を始めました。1920(大正9)年に教授となり、前述のように1924(大正13)年に、私学では最初(東京大学、京都大学、東北大学に次いで日本では4番目)の心理学専攻課程を日本大学に創設しました。
2024(令和6)年には心理学科創設100周年を迎え、現在、101年目を歩んでいます。このように、日本大学文理学部心理学科は、心理学の伝統校です。
文学研究科心理学専攻「臨床心理学コース」
公認心理師と臨床心理士(第一種指定校)の両方の養成校です。定員は修士課程で10名です。日本大学と聞くとマンモス大学をイメージすると思いますが、臨床心理学コースは少人数です。現在、専任教員7名(教授5名、准教授1名、助教1名/全員が公認心理師と臨床心理士の有資格者)と多くの非常勤講師が指導に当たっています。
心理臨床センター
臨床心理学コースの学内実習機関としての「心理臨床センター」は、学部正門の正面にある百周年記念館の中にあります。面接室5、プレイルーム2、集団面接室1、待合室1、研修員室1、事務室1があり、月曜日〜土曜日まで(木曜日を除く)、午前10時〜午後5時まで開設しています(電話受付は午前9時半〜午後4時半)。スタッフは、18名の公認心理師・臨床心理士がおり、特定のアプローチに偏らず、幼児から高齢者まで幅広く相談を受け付けています。駐車場や駐輪場は無料で、人とできるだけ接触したくない来談者のための動線も確保されています。年間のべ1500名程の来談者があり、近隣の区だけでなく各地から来談されています。
また、桜っ子カフェという、0歳〜3歳のお子さん達をもつ親御さん向けの子育て支援グループも行っています。小さな子ども達と年間を通して過ごすことは大学院生にとって意味あることです。
学内・学外実習
臨床心理学コースの大学院生は、修士1年次の夏休みから心理臨床センターで実習を開始し(学内実習)、この学内実習は修士課程が修了するまで続きます。修了後も続けてケースを受け持ち、センター内で、無料で指導が受けられる研修生制度があり、実際に修了生が通っています。学外実習先は、日本大学は医学部を有しますので、精神神経科、心療内科、小児科のほか、他大学病院のメンタルヘルス科、単科精神科病院といった医療領域の学外実習を修士2年生の1年間を通して行います。医療領域とは別に、文理学部が世田谷区と地域連携をしている関係で、世田谷区内の公立小・中学校に半年、学外実習に出られます(教育領域)。また、産業領域、矯正領域、福祉領域の見学実習も用意されています。
臨床心理学コースの特徴
どのようなアプローチや技法を駆使するとしても、基礎体力にあたる臨床実践の実力がなければ絵に描いた餅になります。本学では、修了後、どの領域で働いたとしても臨床家としてやっていける基礎を培うことに主眼をおいています。公認心理師も臨床心理士も合格率は全国平均をはるかに上回っています。
また、東京にある大学というと都心のイメージをもつかもしれませんが、桜上水という落ち着いた土地で、コミュニティの中の1つの施設として心理臨床センターは機能しています。その証拠に、近隣のメンタルヘルス科からのご紹介に留まらず、近隣の身体科(内科等)からのご紹介も少なくありません。今後とも、コミュニティに信頼されるセンターとして活動を続けていきたいと考えています。