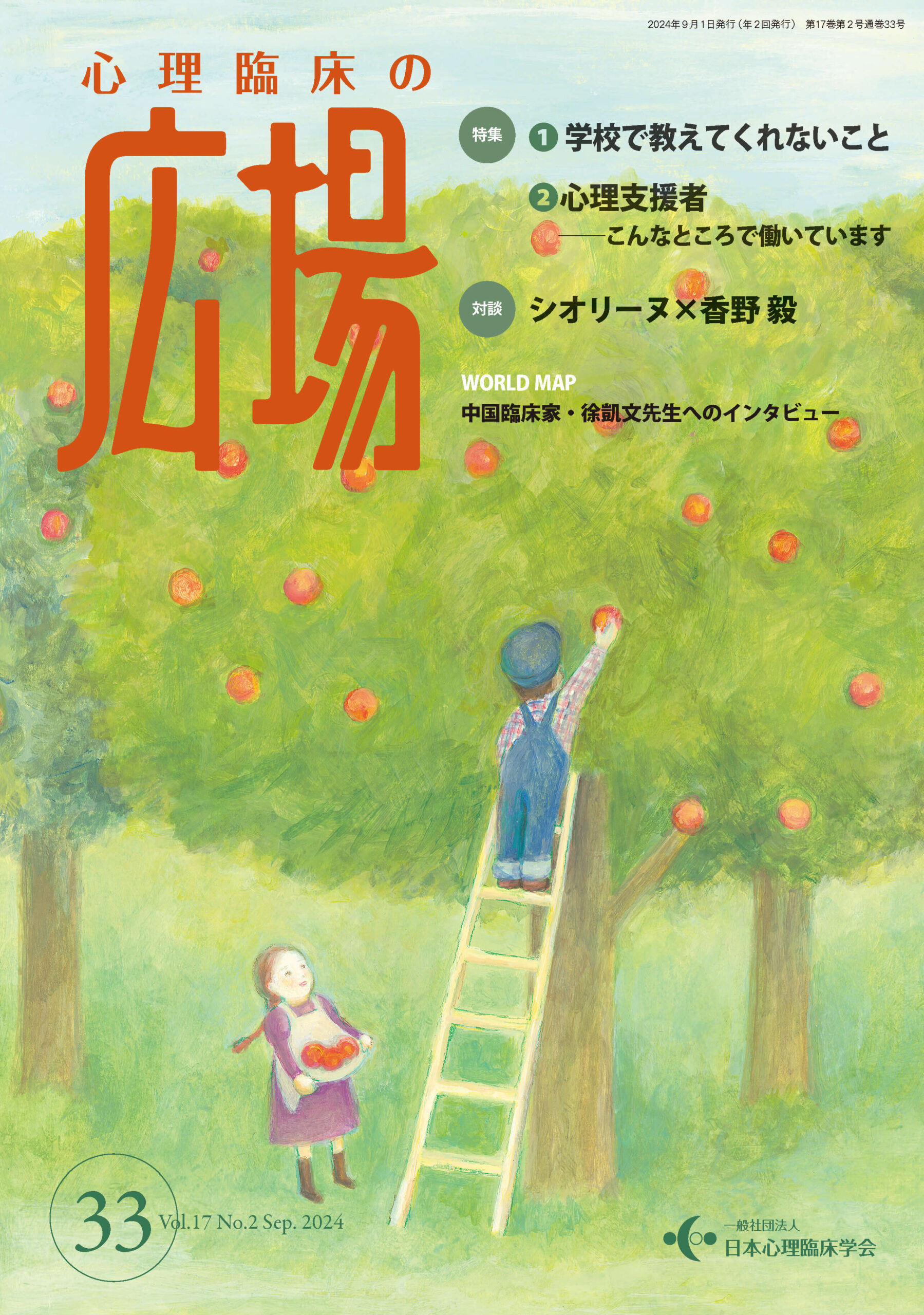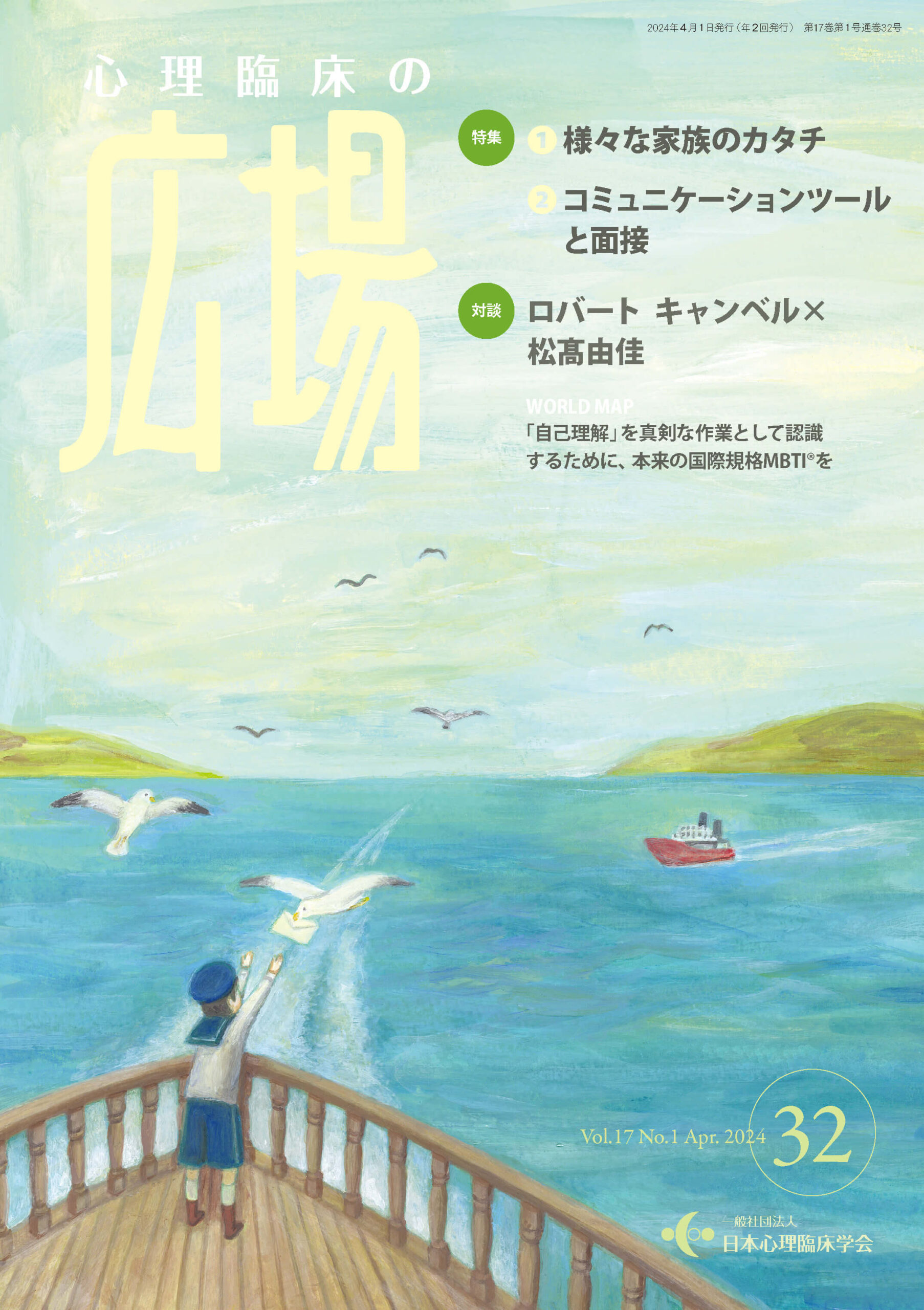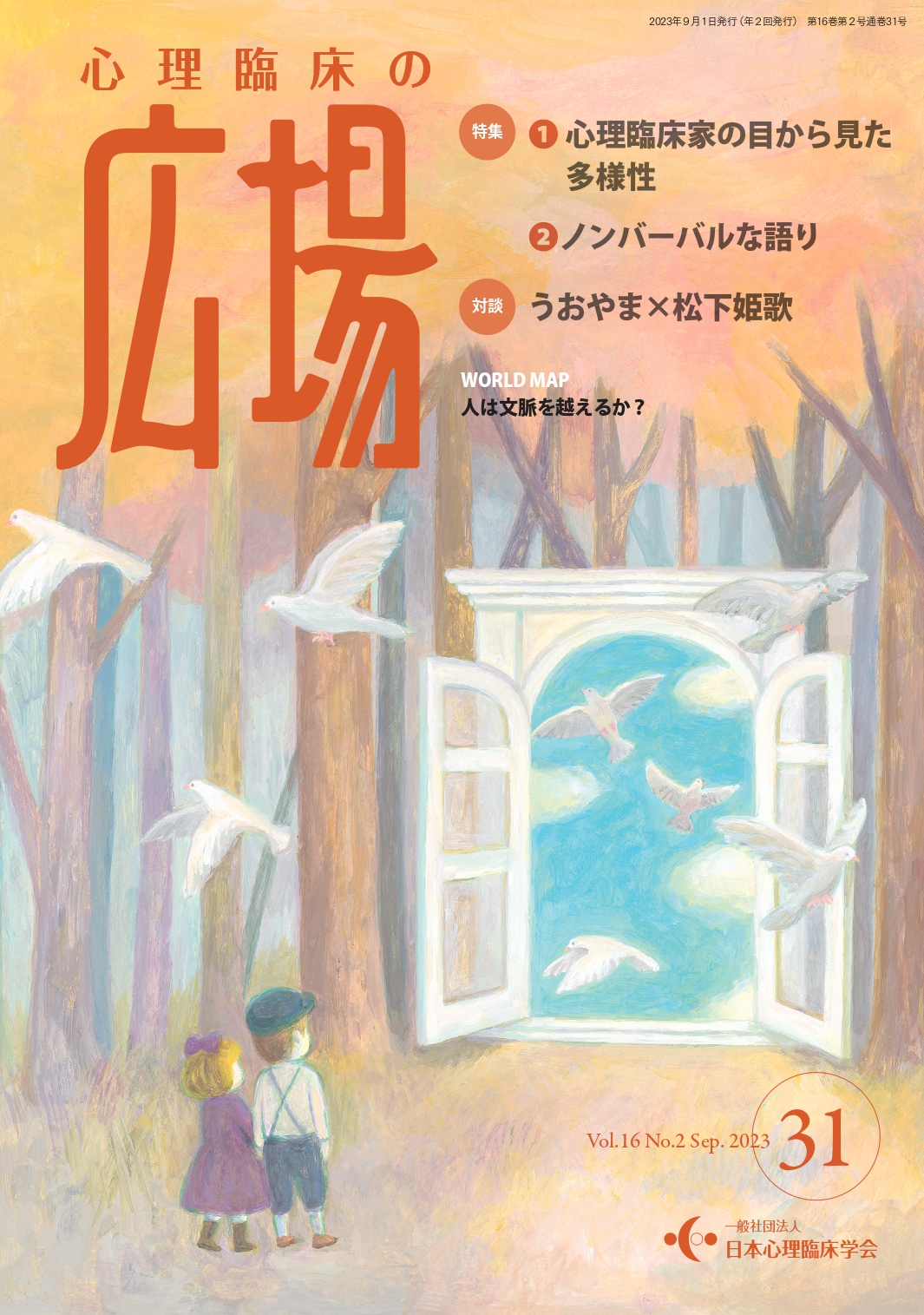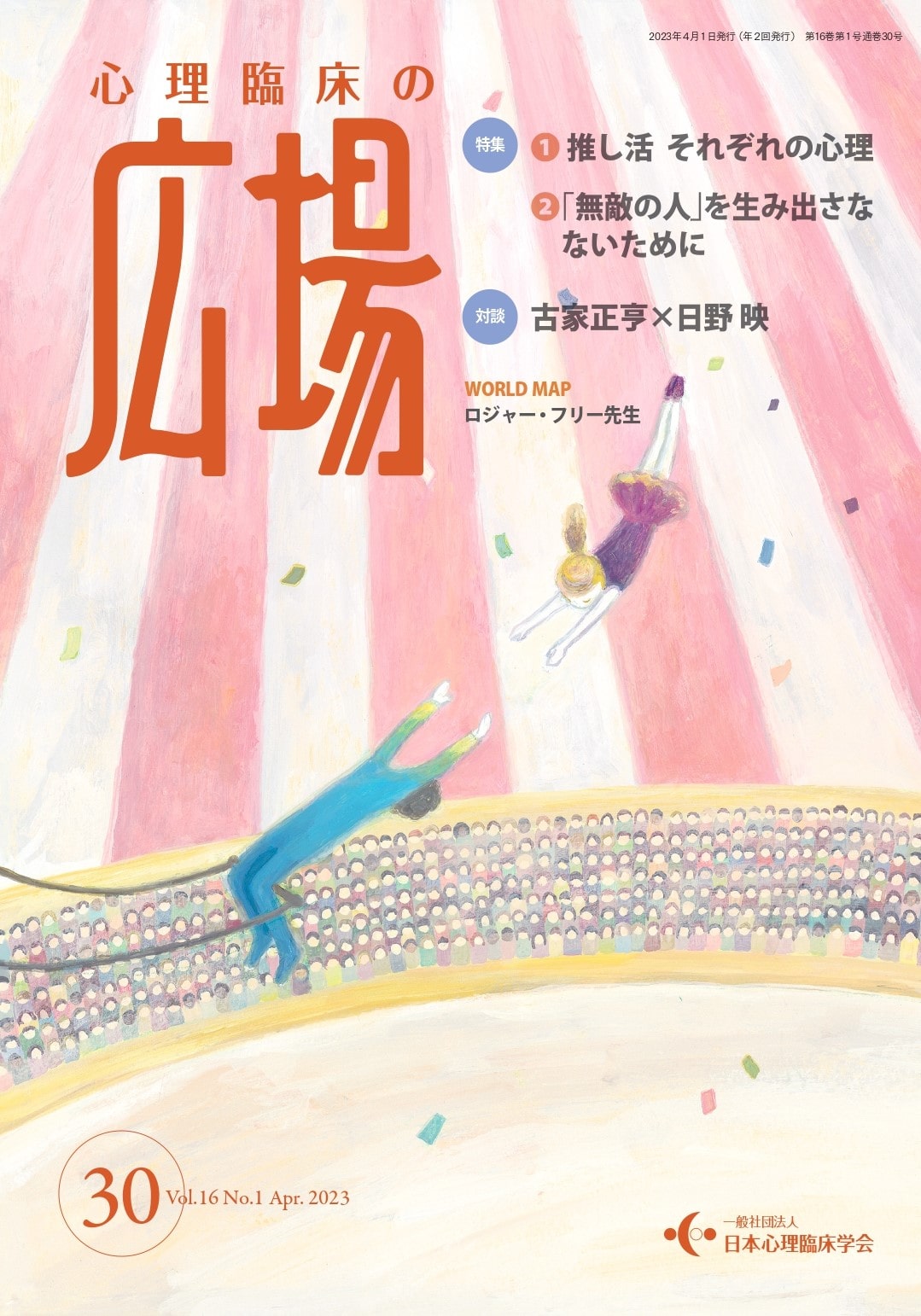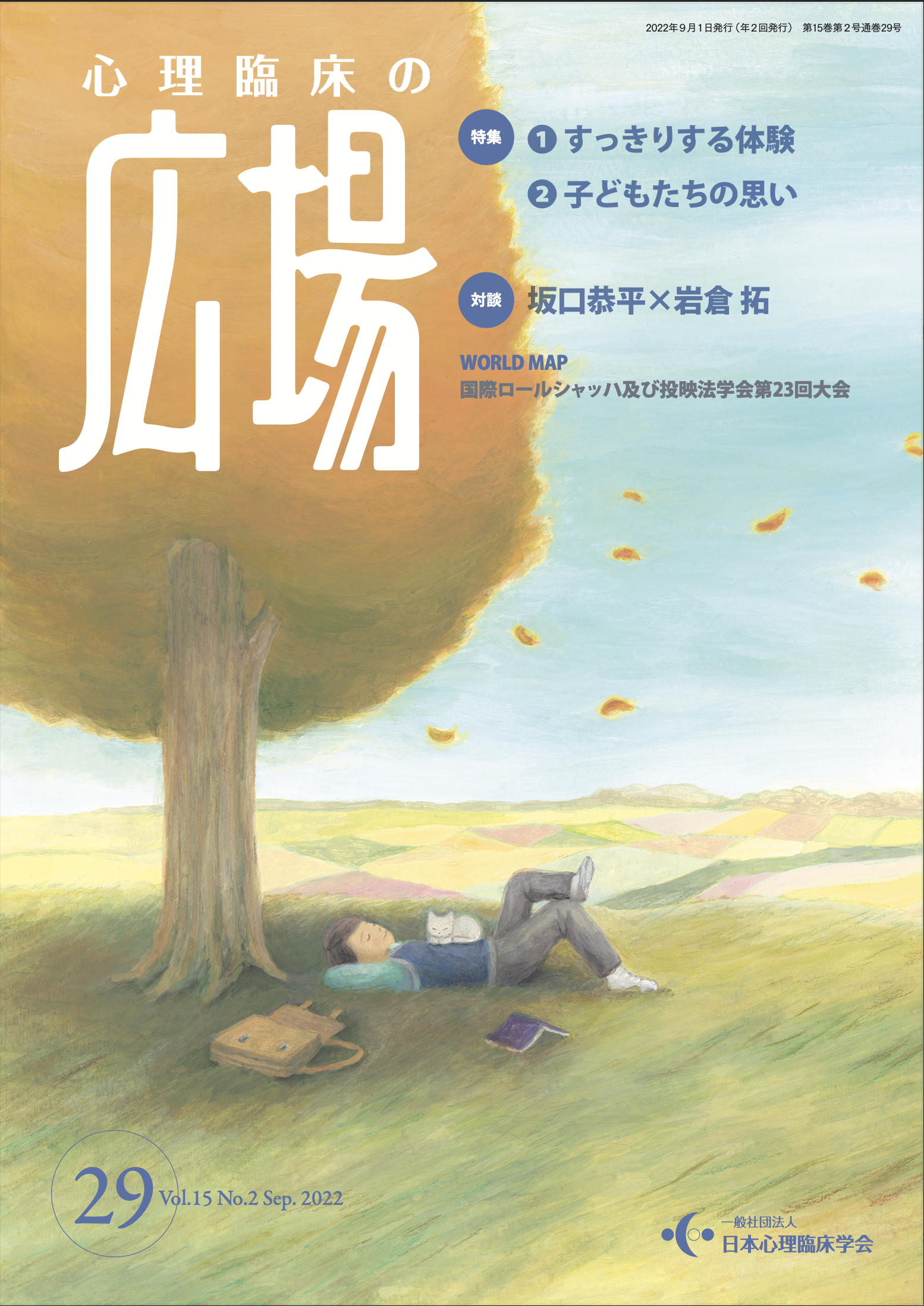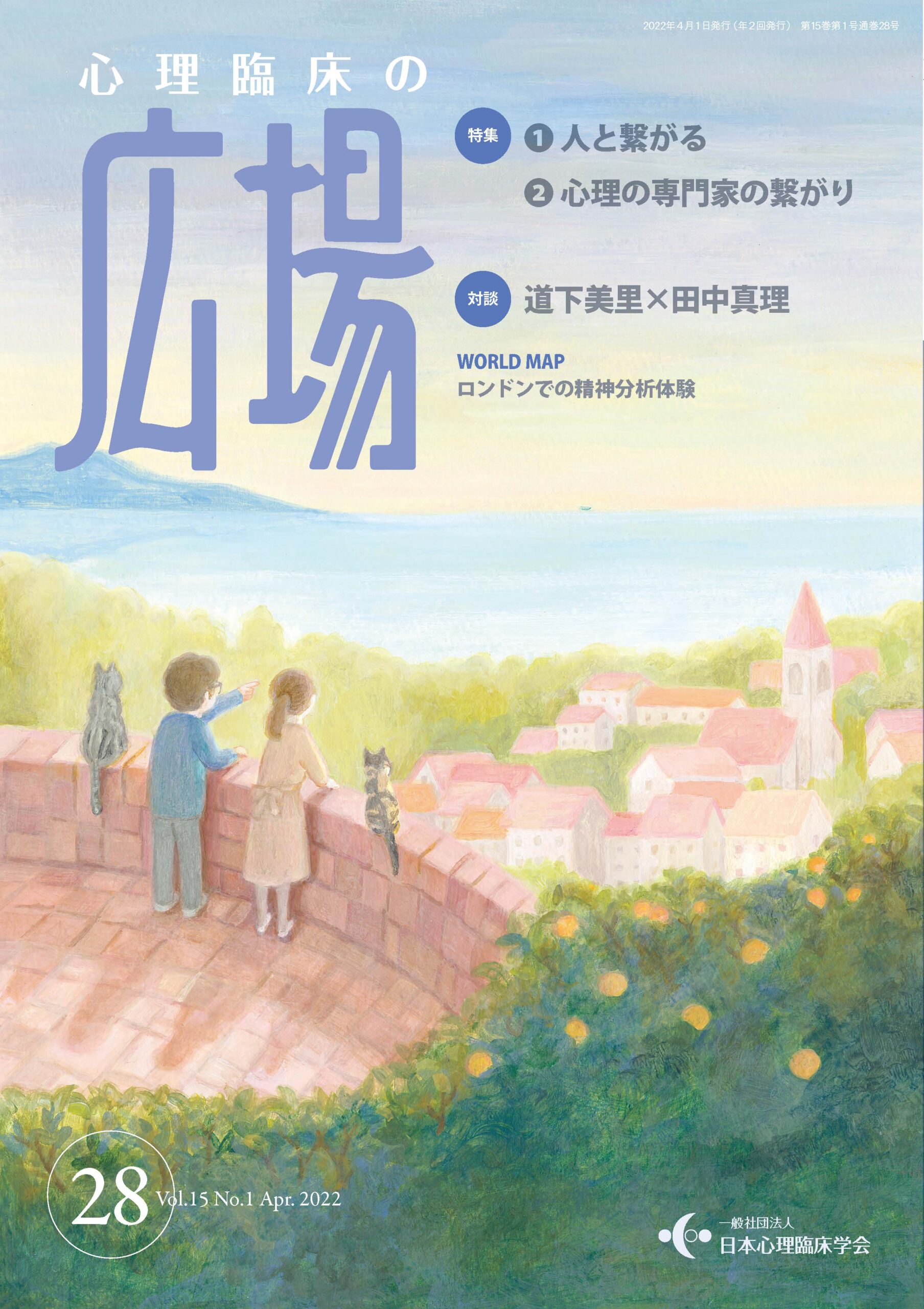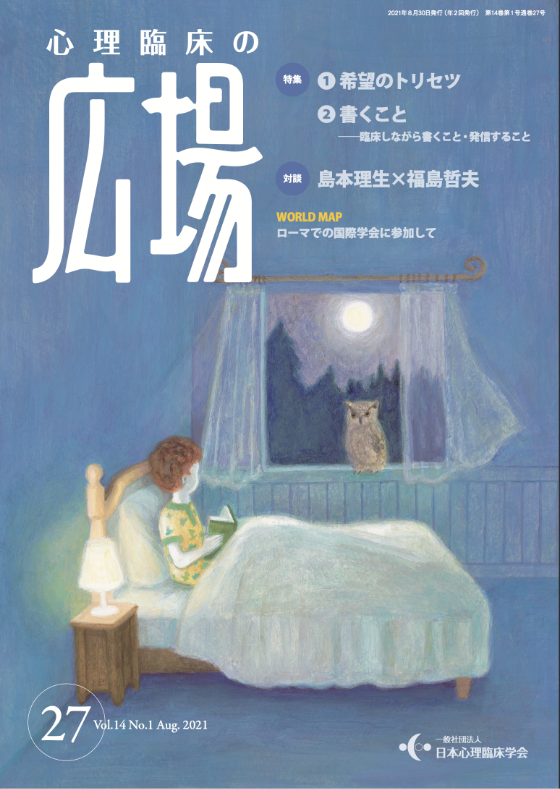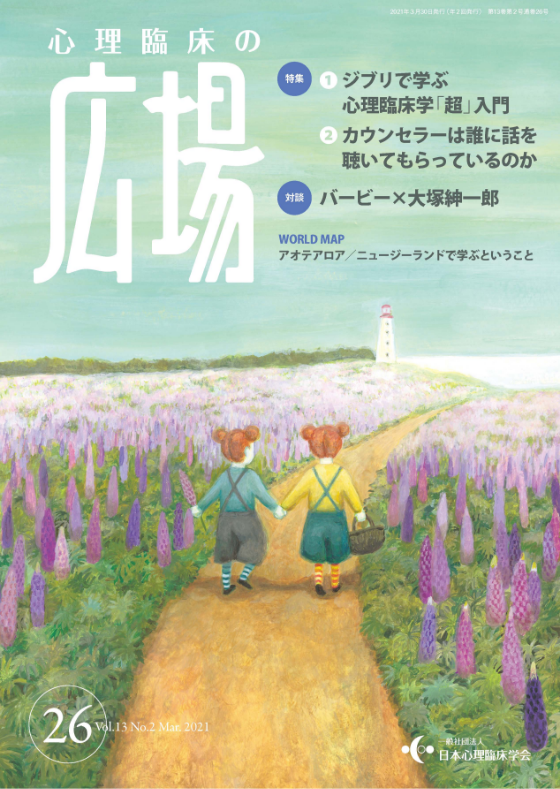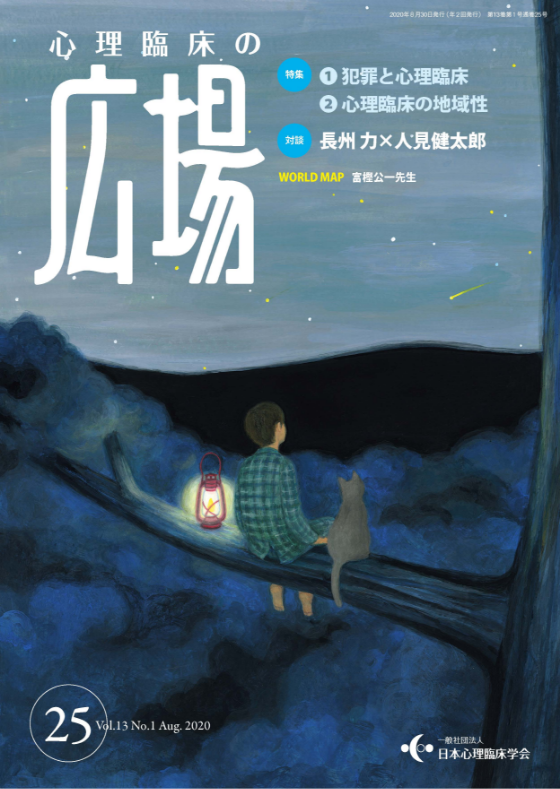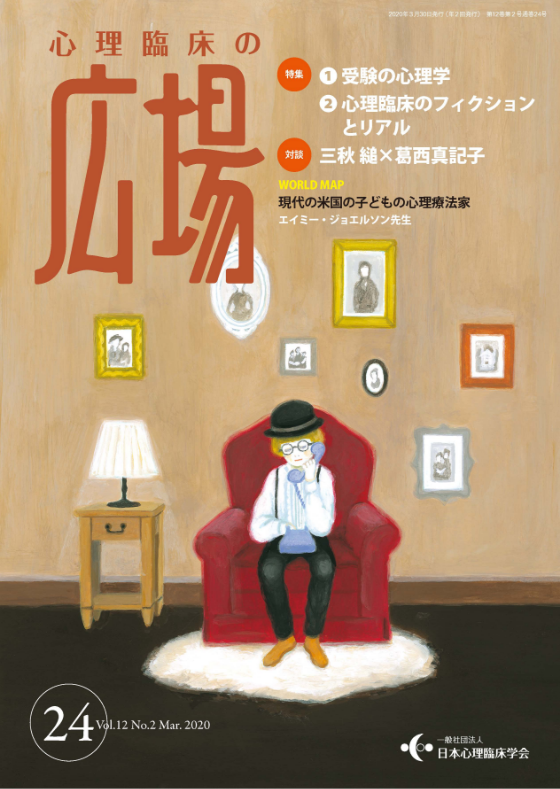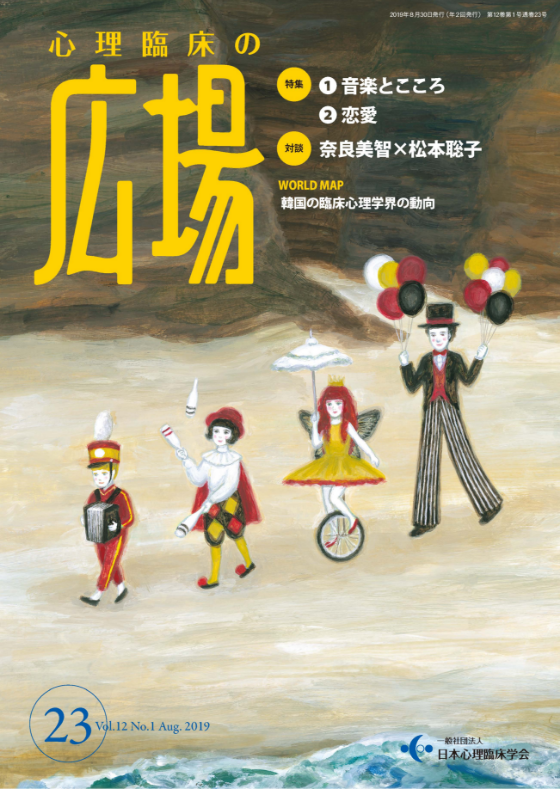「恥ずかしい!」「あんなこと言わなければよかった…」――恥ずかしさとは小さい子からお年寄りまで抱く感情(気持ち)で、生活の中のさまざまな状況で現れます。
何の役に立っている?
恥ずかしさという感情は、本当にわずらわしいものです。友達の前で失敗したとしても、この気持ちさえなければもう少し辛くないかもしれませんし、失敗にさえ気づかないかもしれません。感情には「機能」があると心理学は考えています。少しおおげさにいうと、うまく生きていくことができるように、長い人類の歴史の中で感情という心理現象が生じるようになったと考えられています。例えば、失敗せずに何かできたとしても、「うれしい!」という感情が生じなければ、それ以上努力することはないでしょう。いろいろな気持ちにそれぞれの役割があるのなら、恥ずかしさの役割は何だと思いますか?恥ずかしさは「自己意識的感情」であることがヒントです。
かしこさの裏側にあるもの
さらに、未来を予測するという人間のかしこさが今回のテーマに関わっています。恥ずかしい気持ちになったことがある人なら、似たような状況には「恥をかくリスク」があると感じることでしょう。この感じ取ったリスクに対して、自然に生じてくる気持ちが「不安」なのです。一度不安な気持ちになるとさらにリスクに目が向いて、より不安が高まるという悪循環におちいりがちです。そうなると、不安で不安で他のことに手がつかなくなったりして、生活に支障が出てきます。これが「不安症」といわれる強い不安状態です。過去にとらわれるのがうつ病なら、不安症は未来へのとらわれといえます。
リスクと実害
さて、ここでリスクに目を向けてみましょう。はたして「恥をかくリスク」を0にすることはできるでしょうか?恥をかくリスクを下げるためには、練習をしたり、失敗しそうだと友達に先に言っておいたりなど、いろいろな策を講じることはできます。しかし、未来に何が起こるかどうかは誰にもわかりません。多かれ少なかれ必ずリスクは残ります。不安が強い方は、リスクの大きさを現実よりも高く見積もったり、そのことが重大な結果につながると考える傾向にあるといわれています。そして、リスクがあると感じていることが本当に現実に起こるかどうかはその時までわかりません。そうしたことにあたふたとあわてすぎるとしたら、まだ生じるかどうかわからない害とは別に、不安に大きく振り回されるという実害を自分に引き込んでしまいます。このパラドックスが不安のちょっと怖いところなので、リスクには対処しつつ、不安に振り回されすぎないというスタンスが重要です。
自動的処理 vs 能動的処理
リスクと不安で自動的に安全志向になるのは生き残るためには便利である一方、長期的には悪循環におちいる可能性があります。認知行動療法とは、自分の頭や行動を使って、いわば「能動的処理」で不安になりすぎないよう、じわじわとりくんでいく心理療法です(心理職と一緒にするのがおすすめです)。不安になれてゆく、考えていることを客観的に分析する、など不安を下げる方向性に加えて、不安な状況でも安心材料に目を向けることが大事であることがわかってきました(制止学習)。不安に振り回されすぎなくすることができれば、人よりも敏感にリスクをみつけることができるという不安の力をより自分や身の回りの人に活かしていくことができるでしょう。