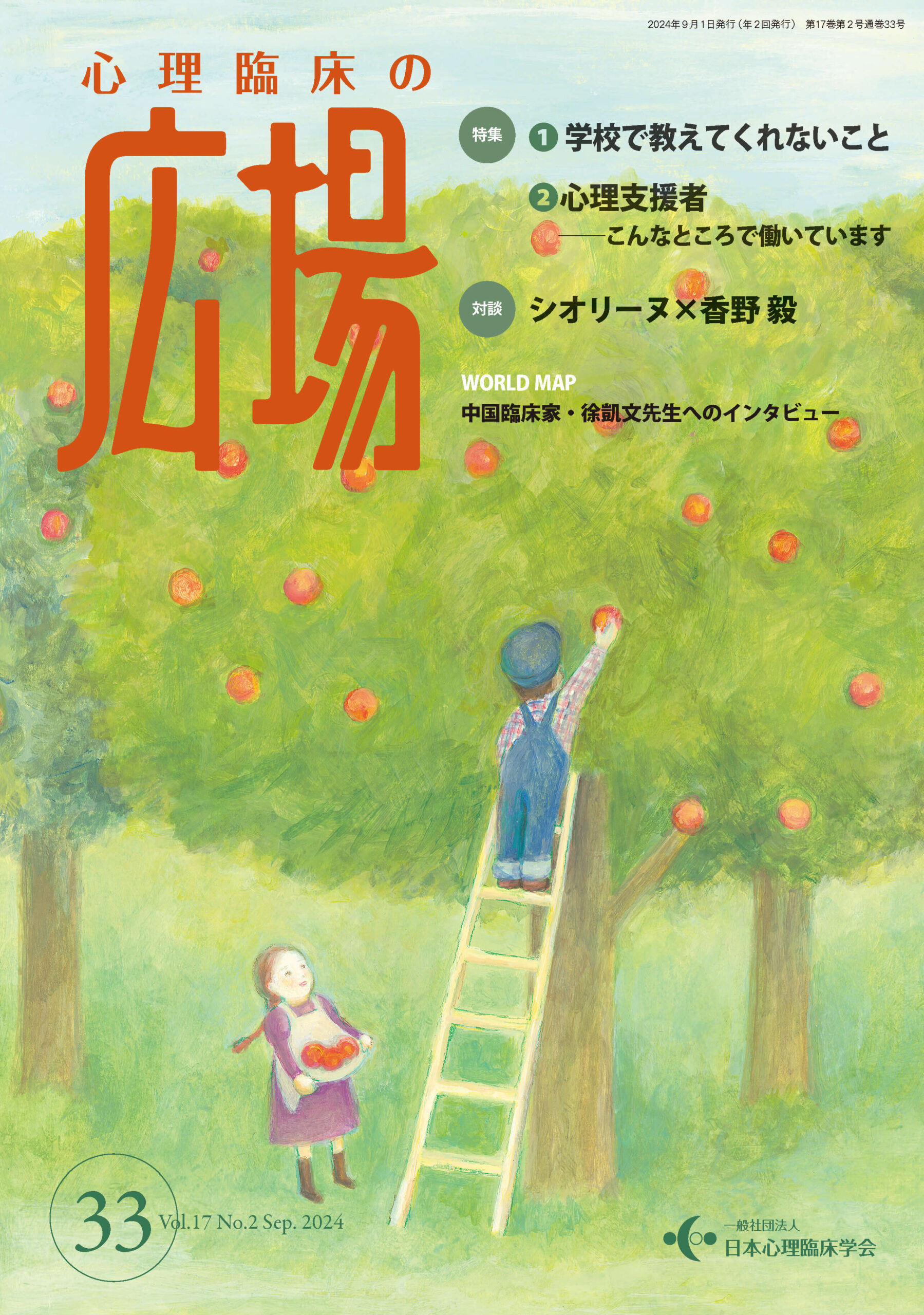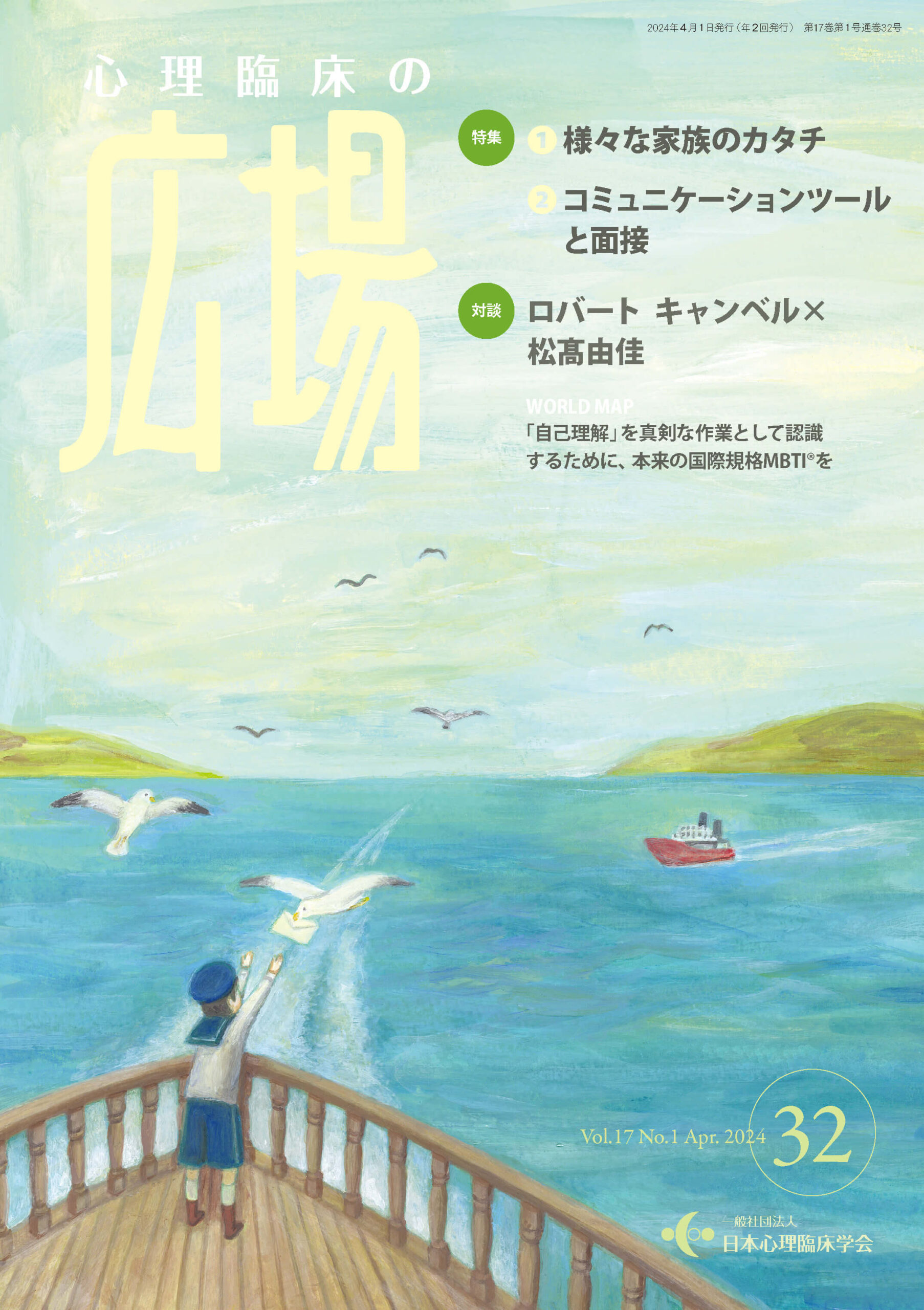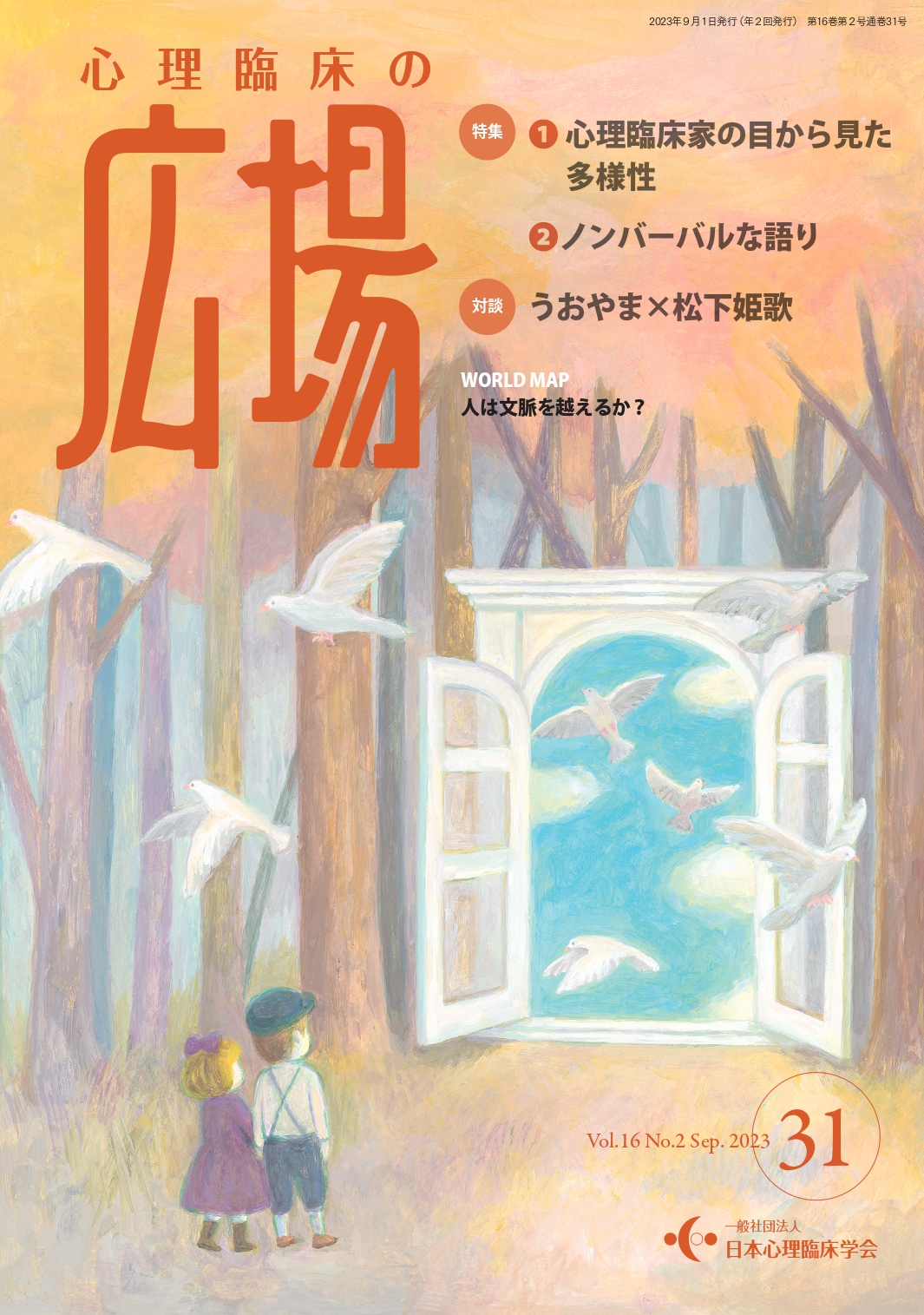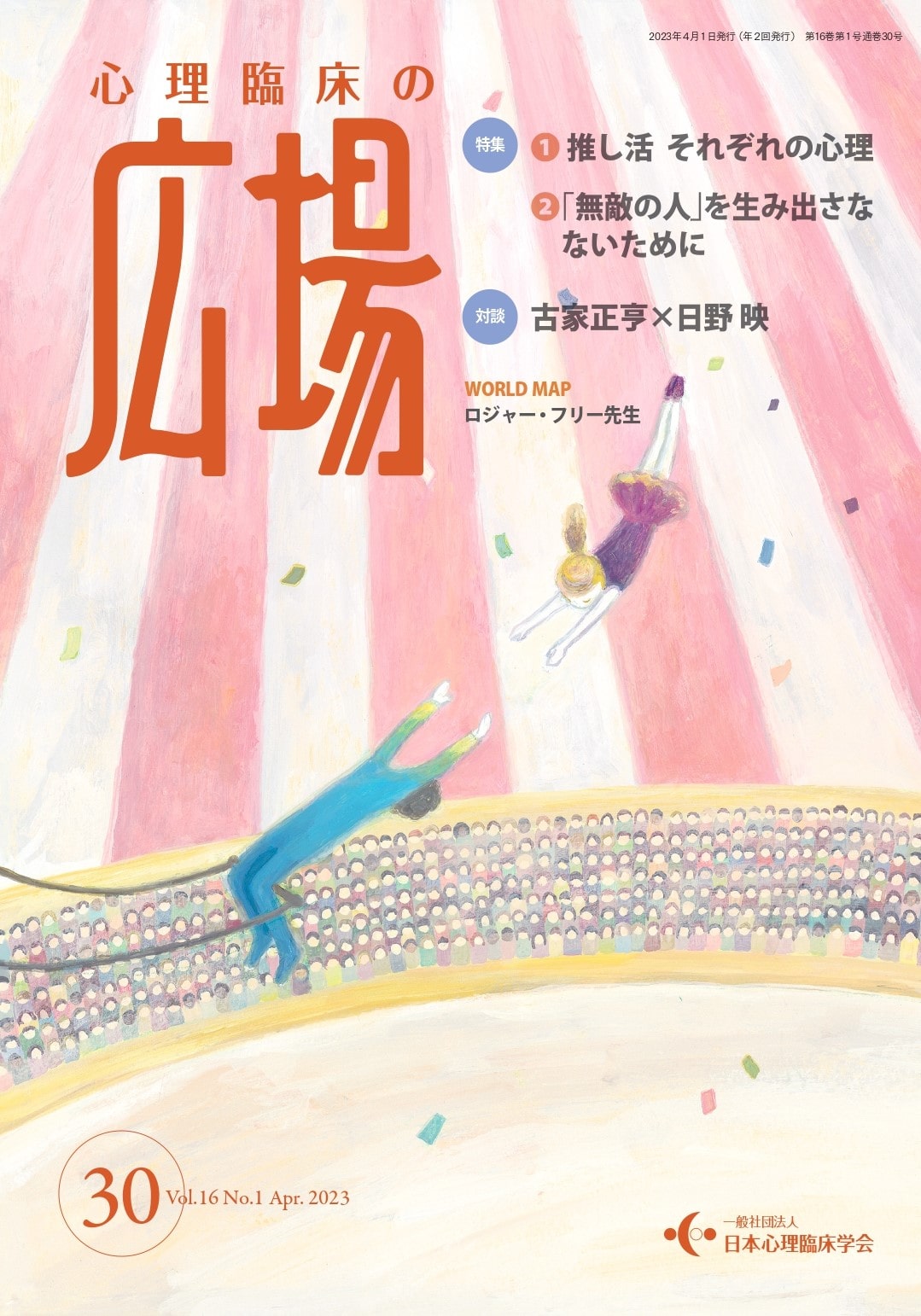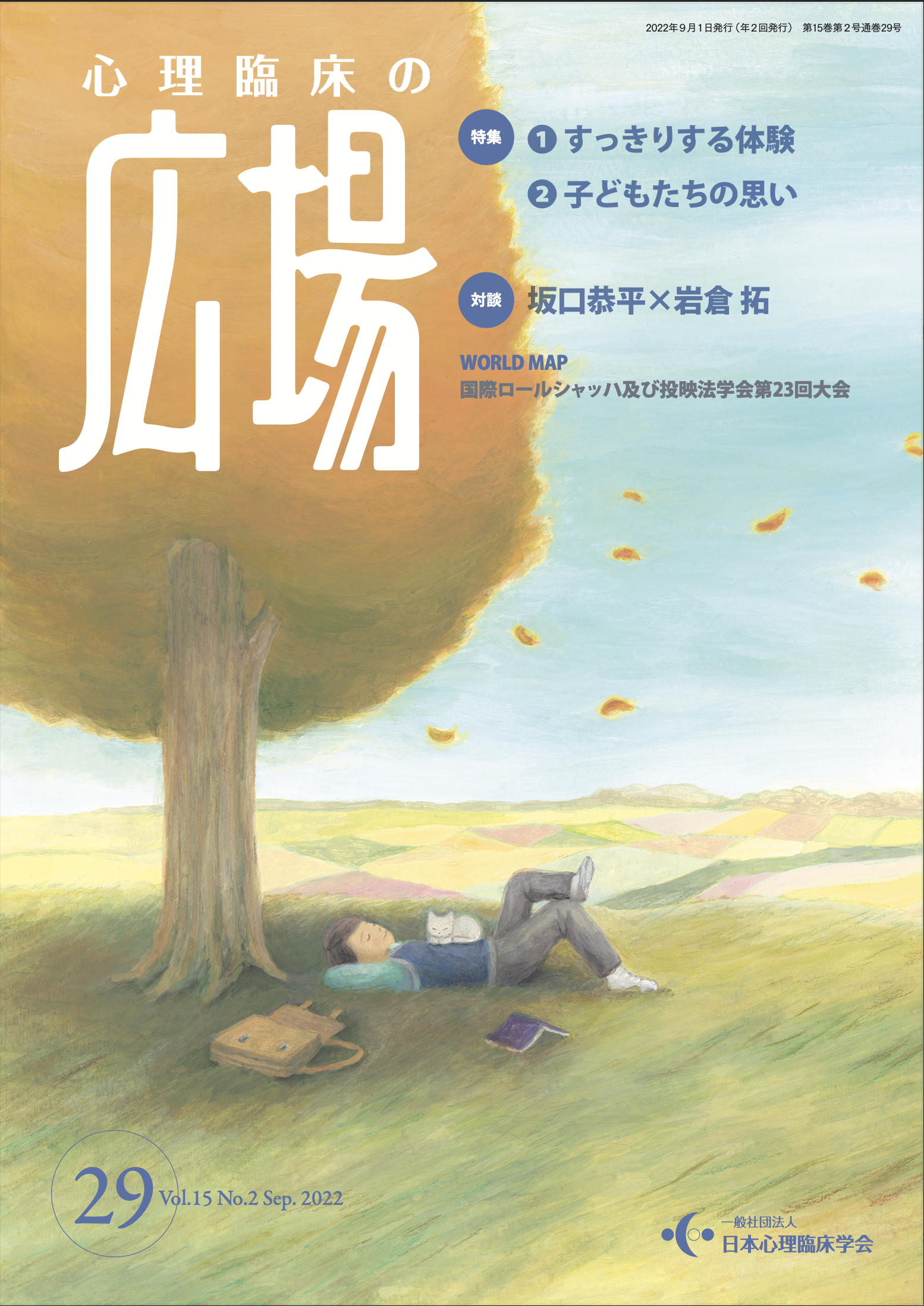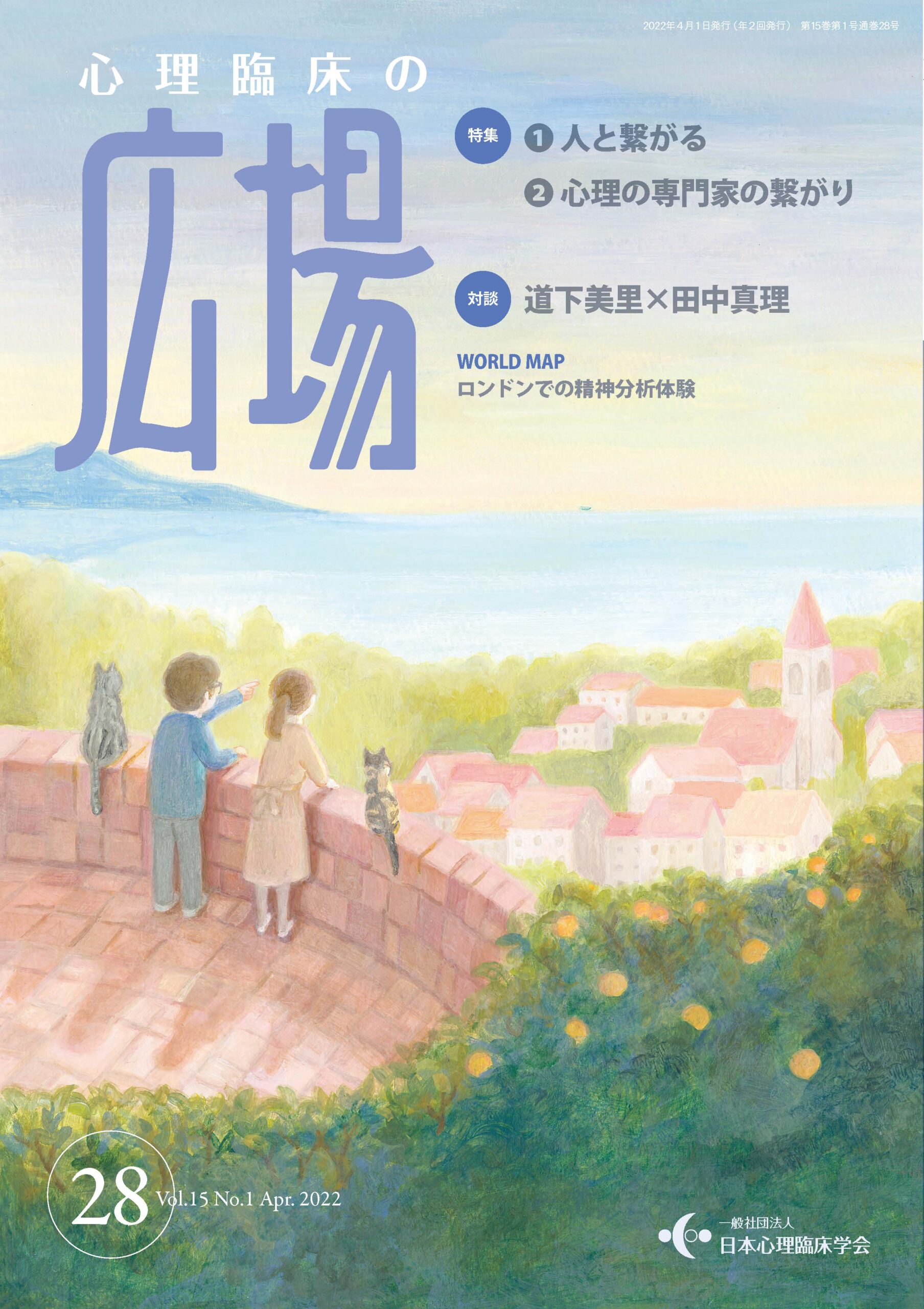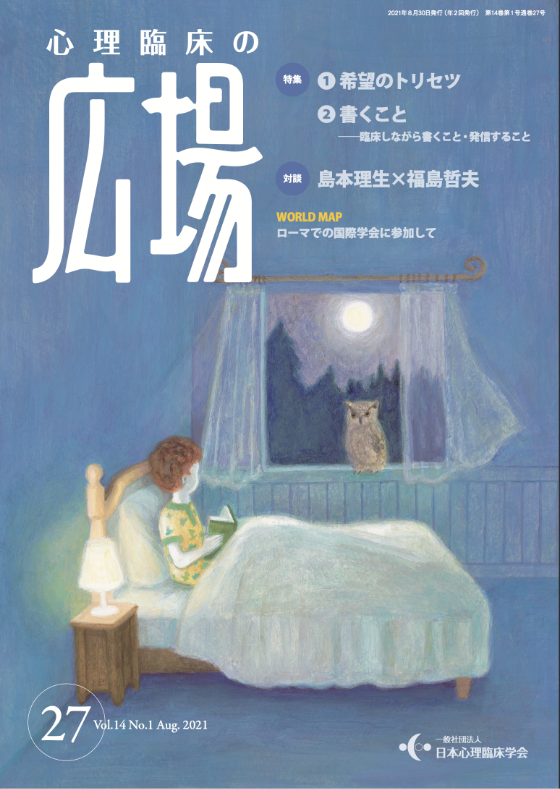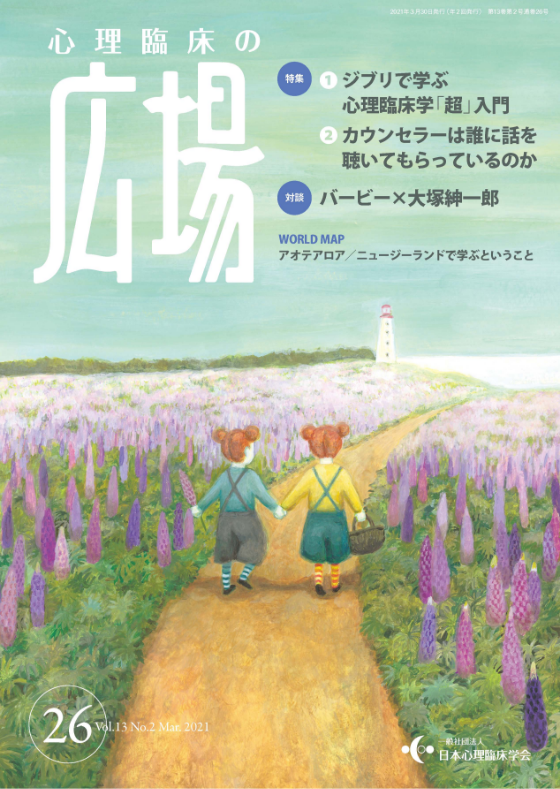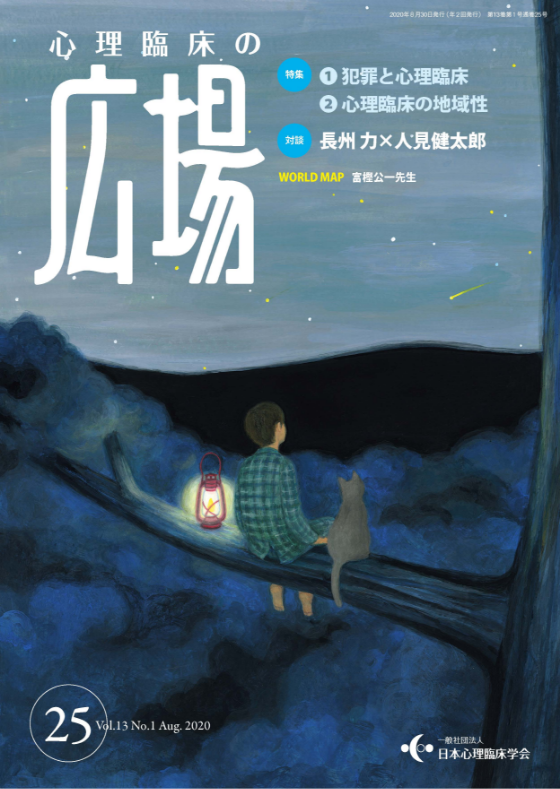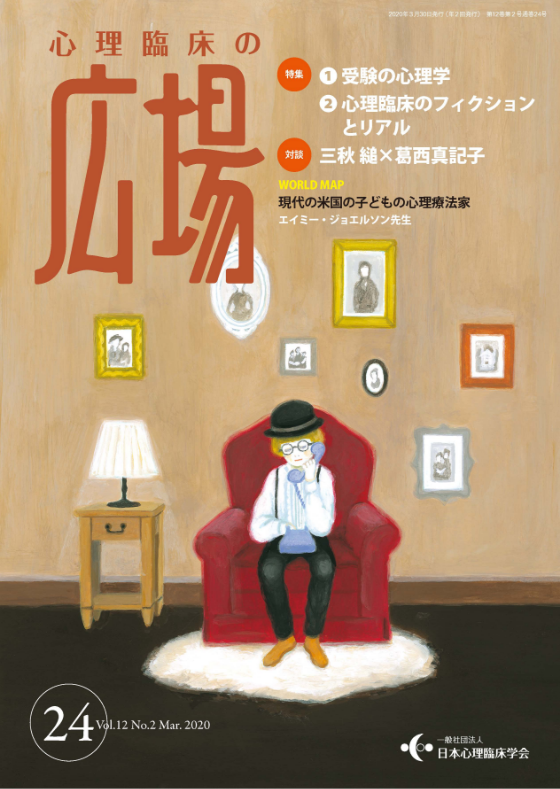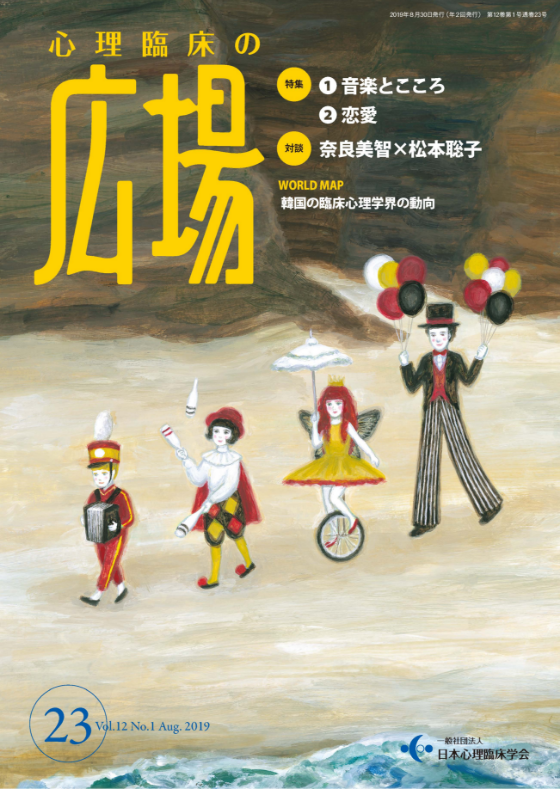人間関係の悩みはどれも大変つらいものです。しかし集団の中にいるにもかかわらず、自分だけが違う時空間に取り残されたような孤独を感じることや、息を潜めて俯いたまま顔をあげられない「恥」の状況に追い込まれることは、その中でもかなりの苦痛を伴うものなのではないでしょうか。
それは今も昔も変わりません。1900年頃に活躍したアメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズの言葉(一部改変)を紹介しましょう。「人は元来、人から注目され好意的に見てほしいという傾向があります。もし人が社会生活を自由に送りながら、全ての人から全く注目されない状態におかれるとしたら、それほど残酷な仕打ちはありません。」
みんなは友達を作れたり、話せたり、遊べたりするのに、自分だけができていない。みんなからあの子は違うと思われている。みんなが普通で、自分は違う。そのような状況です。
一人でいること自体は、それほど悪いものではありません。究極的に言えば、人はみんな一人だという感覚を持っていますから、誰しもが多少なりとも孤独です。孤独を楽しめる人だっています。静かに一人で居られる穏やかな時間も、ひっそりと過ごせる空間もいいものです。そんな風になれたらいいと思いますが、言葉でいうほど簡単なものではありません。通常は社会生活を営むために、集団に属する必要があるからです。そして集団の中で生活をしているのにもかかわらず、いじめられたり、疎外されたり、差別されたり、無視されたりすると、とてつもない苦痛です。それが集団の中での恥の感情です。
『スイミー』という絵本を覚えていますか。もう半世紀近く小学2年生の国語の教科書に載っています。黒くて小さい魚スイミーは赤いきょうだいたちと過ごしていますが、ある時みんなは大きな魚に一口で飲み込まれてしまいます。孤独になったスイミーは世界を旅し、再び自分とそっくりの赤いきょうだいたちを見つけます。そしてその仲間と一緒に泳いで大きな姿に見せかけ、大きな魚を追い払うというお話です。
この話の中でスイミーは、赤い小さなきょうだいたちの中で楽しく暮らしたり、遊んだりして過ごしています。新しく出会った赤い仲間たちからも一匹だけ黒いからという理由でいじめられたり、除け者にされたりすることはありません。スイミーは泳ぐのが早く、むしろみんなのリーダーのようで明るく前向きです。
このスイミーの話は、恥の感情で苦しんでいる子どもたちの集団療法に用いられることがあるようです。自分だけが他のみんなと違う、自分の悩みは誰もわかってくれないという思いを抱いている子どもたちは、スイミーをどのように読み、スイミーに何を重ねるのでしょう。
スイミーはみんなと違う色をしていても、仲間をなくしても、またきょうだいを探しにいき「みんなであそぼう」と誘います、自分と同じ色の魚はいませんが、色の違いを活かしてみんなと協力して生きていきます。
人を孤立させ、恥の感覚を植え付けるのも集団ですが、自分は一人ではないと思わせてくれるのもまた集団です。自分が自分らしく居ることができ、楽に話ができる集団に出会えると、恥の感覚は癒されます。協力して助け合えると思える集団やコミュニティがあると、いつかの孤立感や恥の感情も、包み込まれていくはずです。私たちはスイミーのように、いつも心のどこかに、そんな集団を探し求めて生きていると思います。