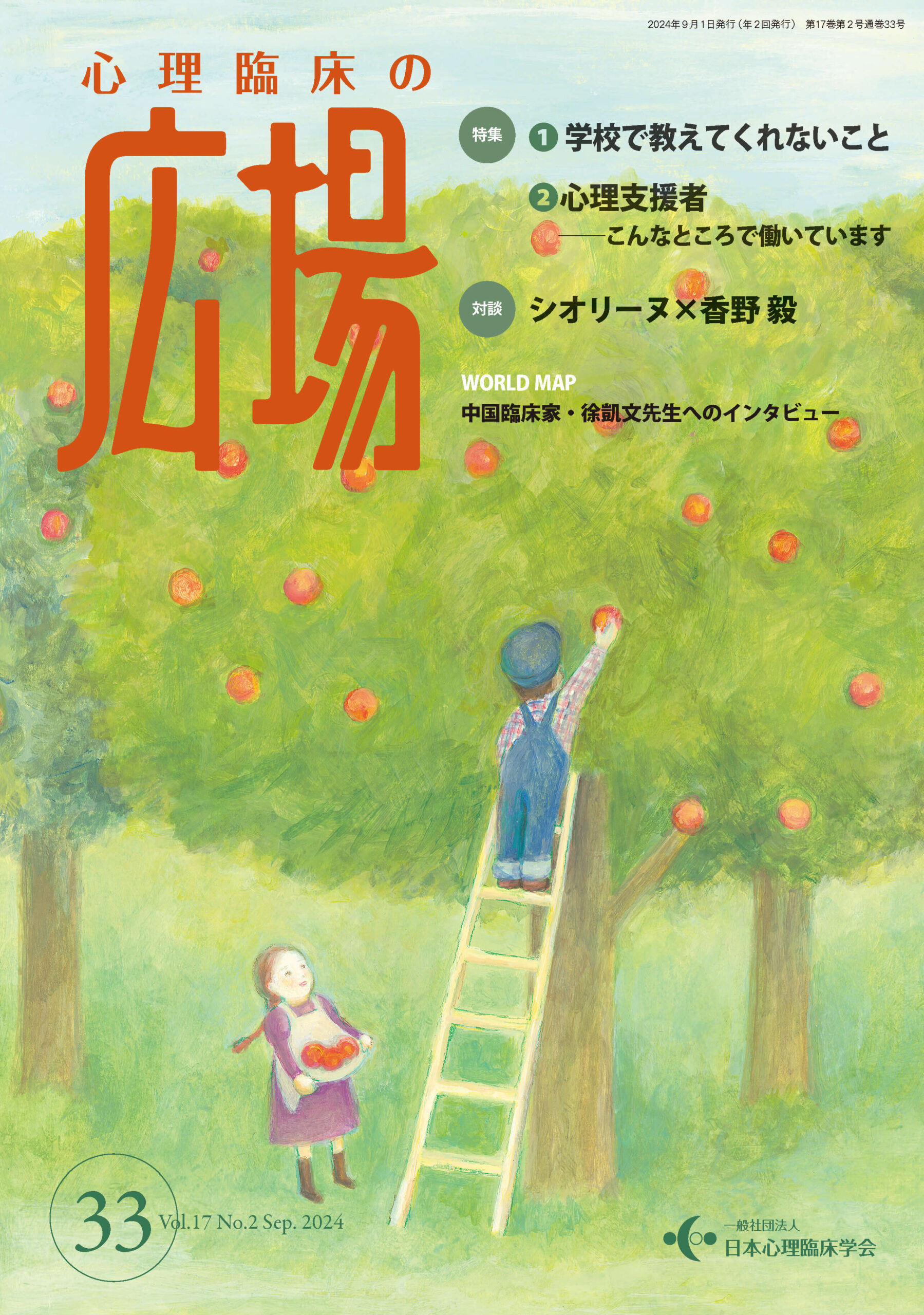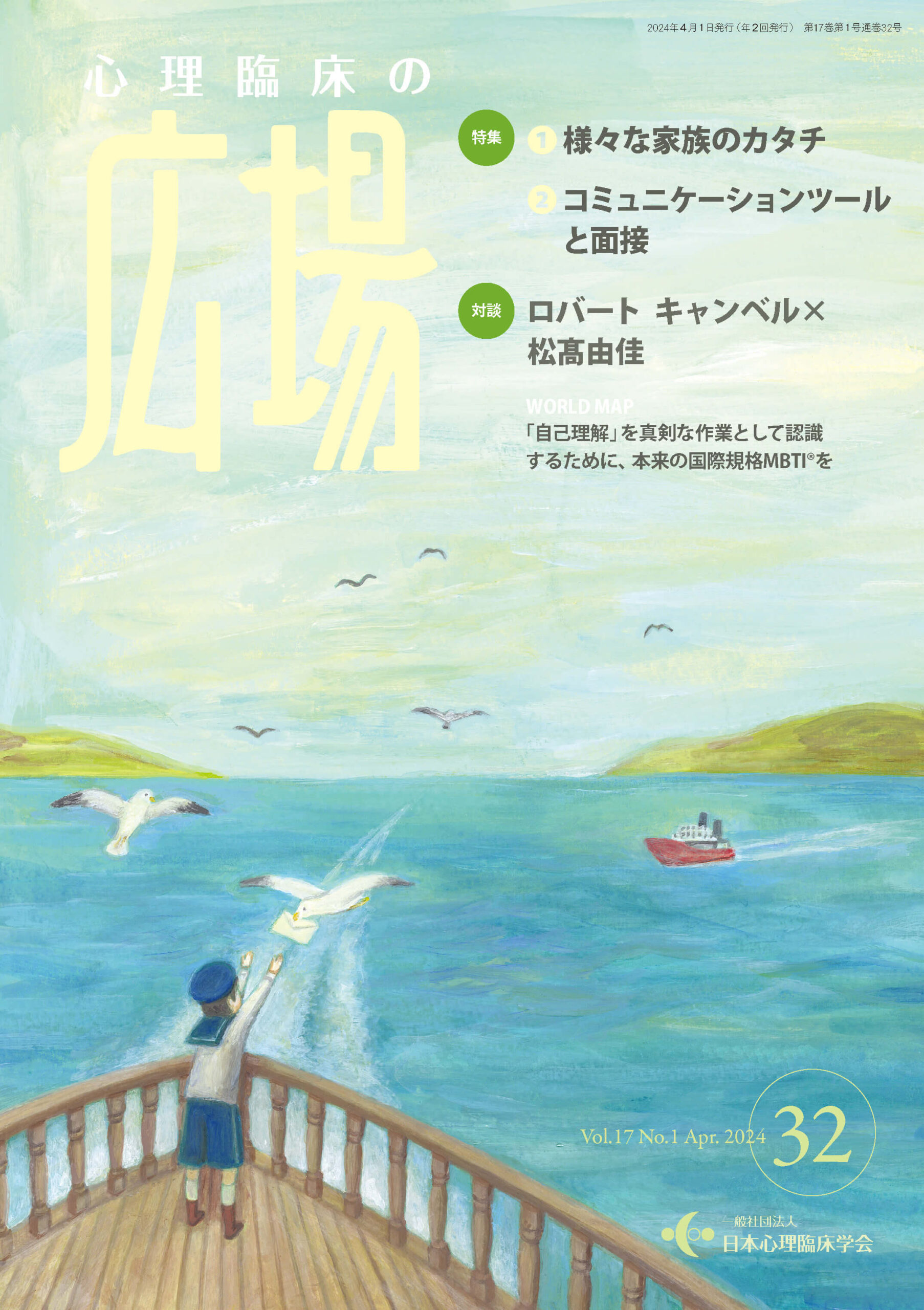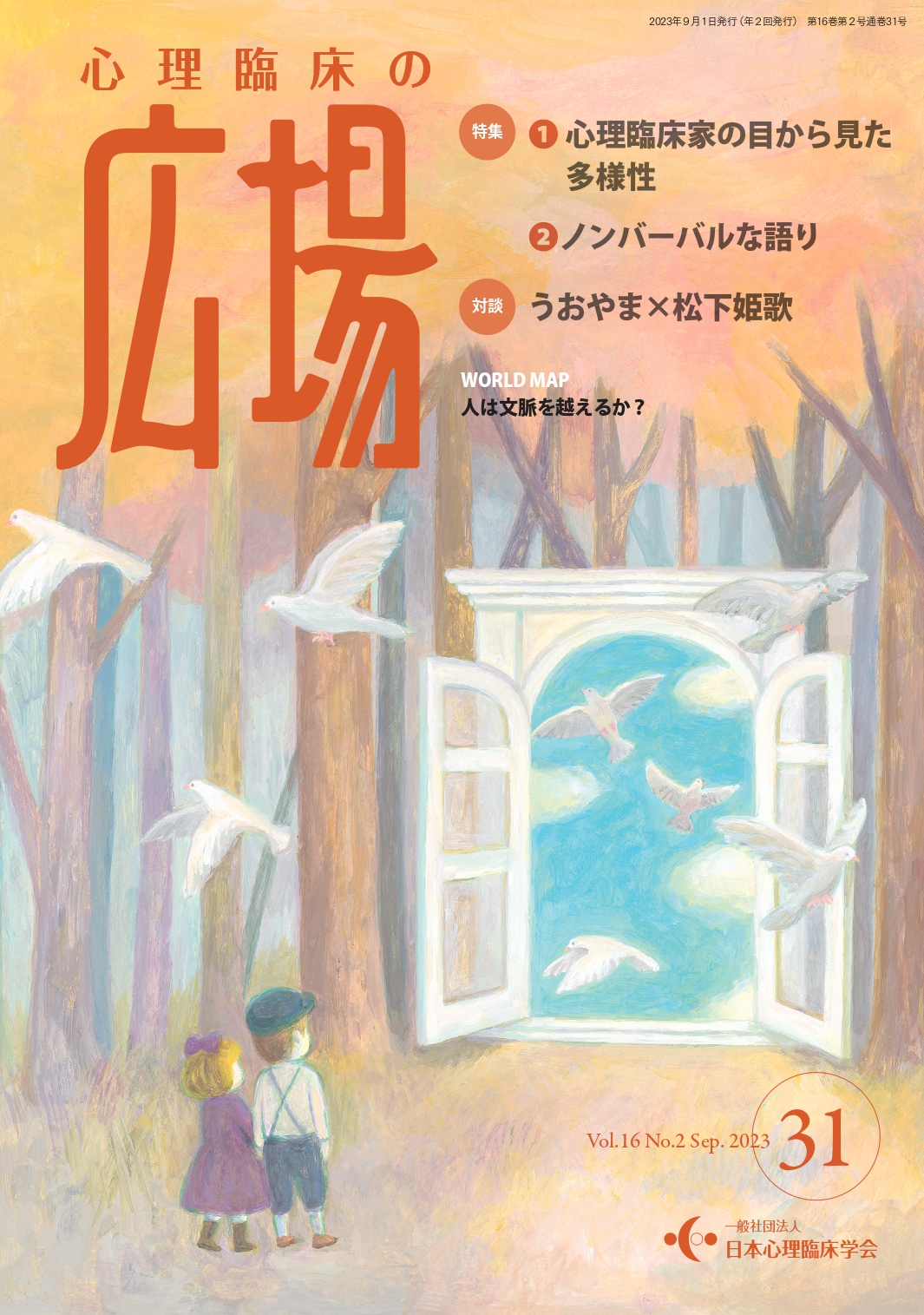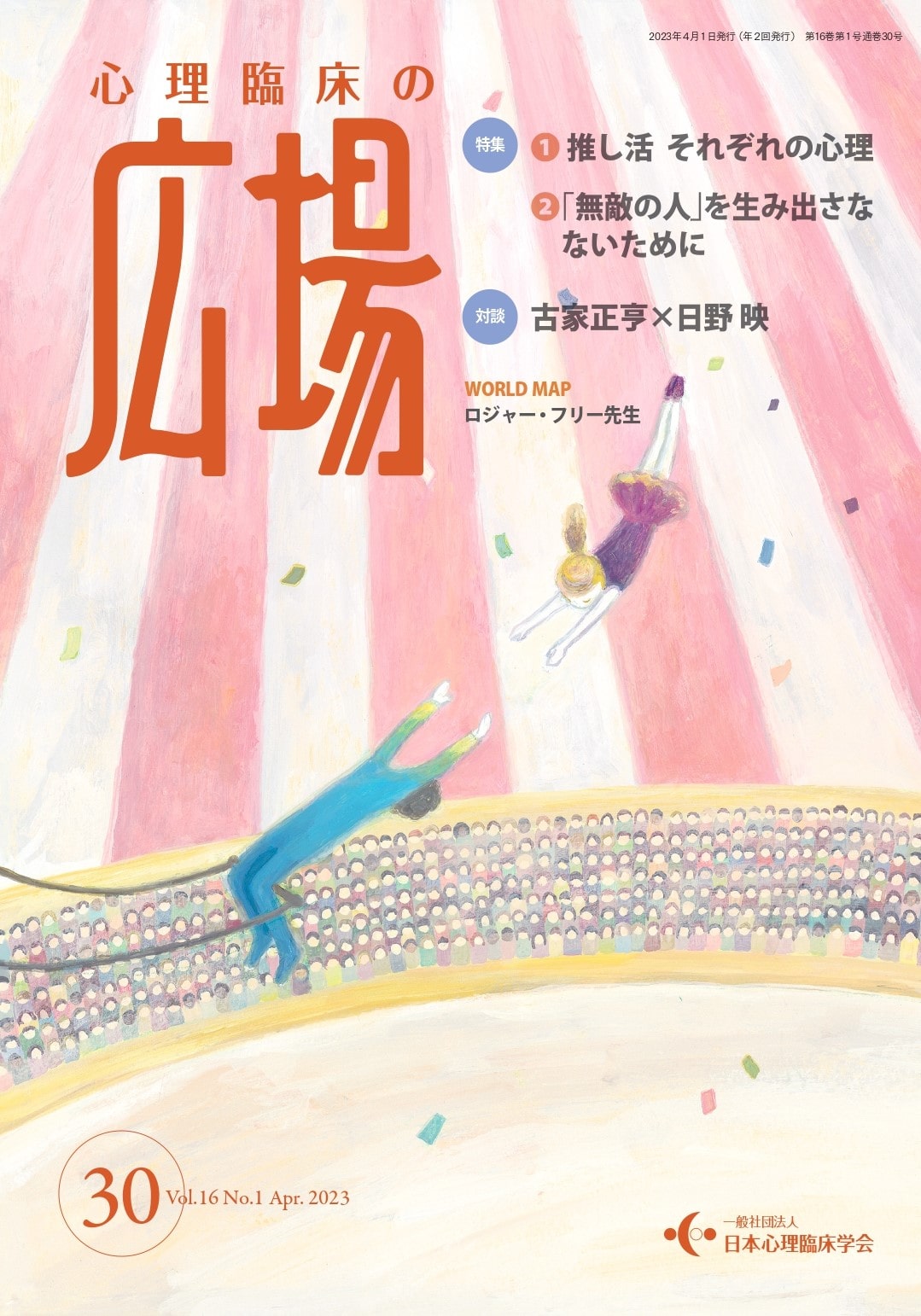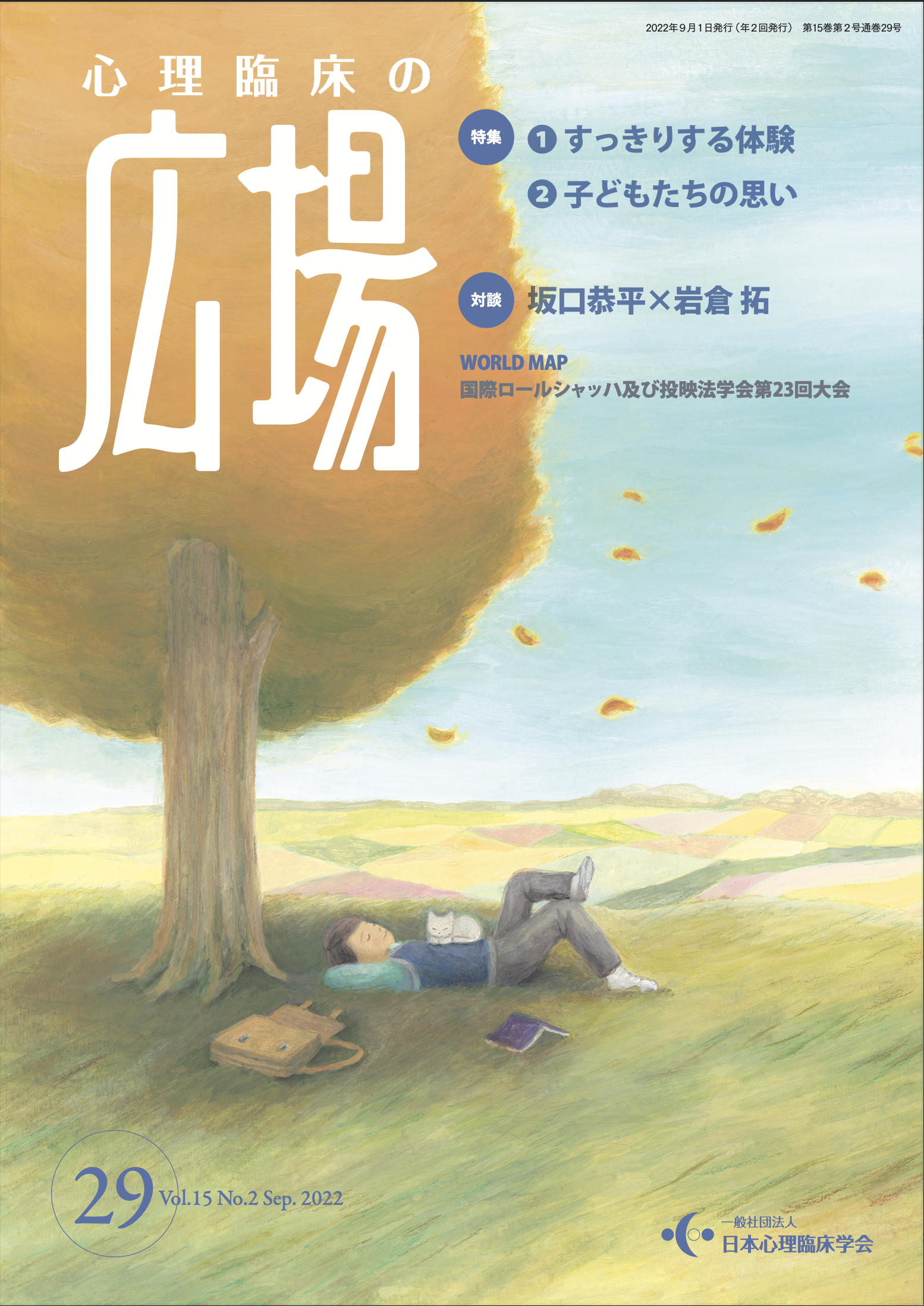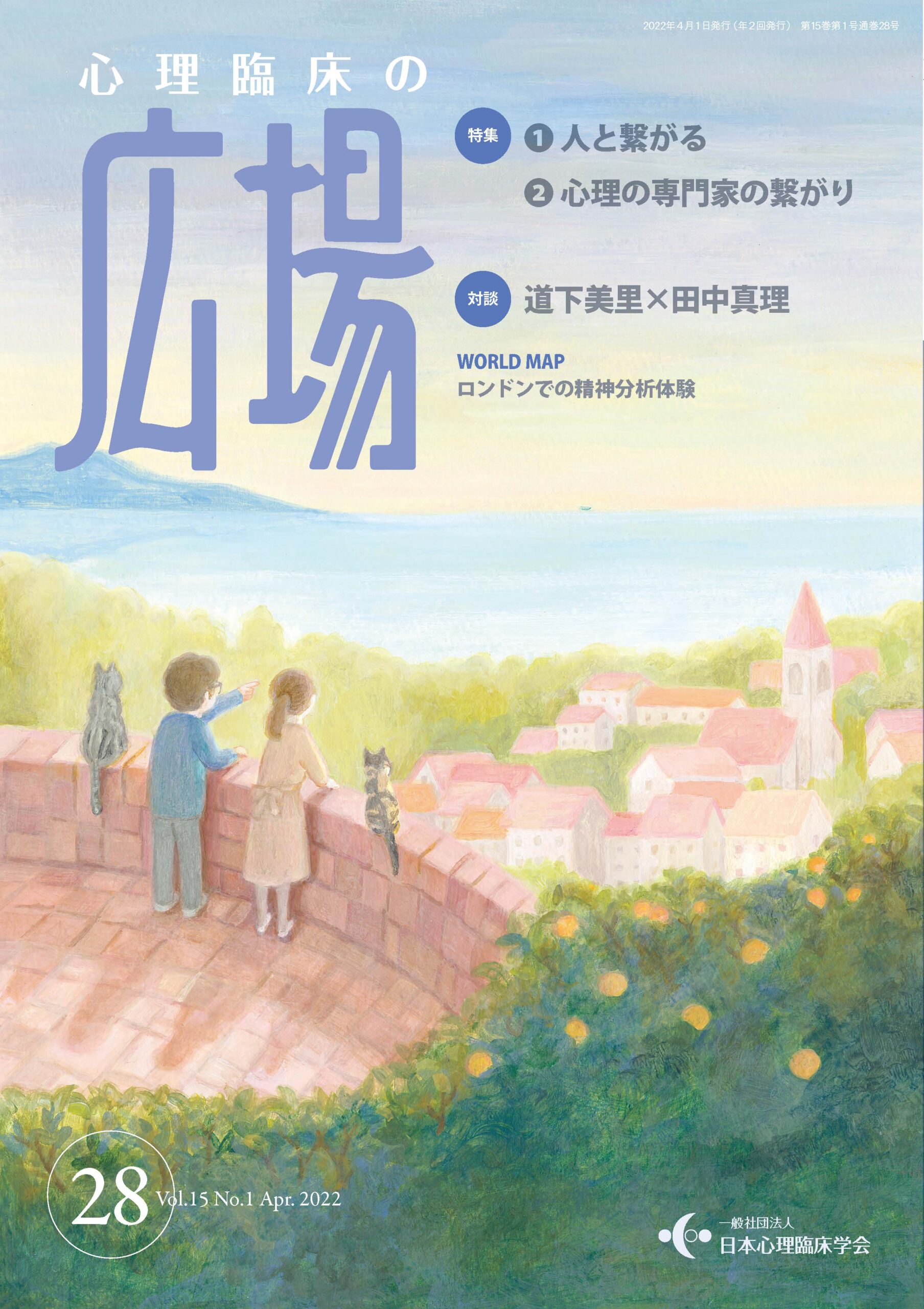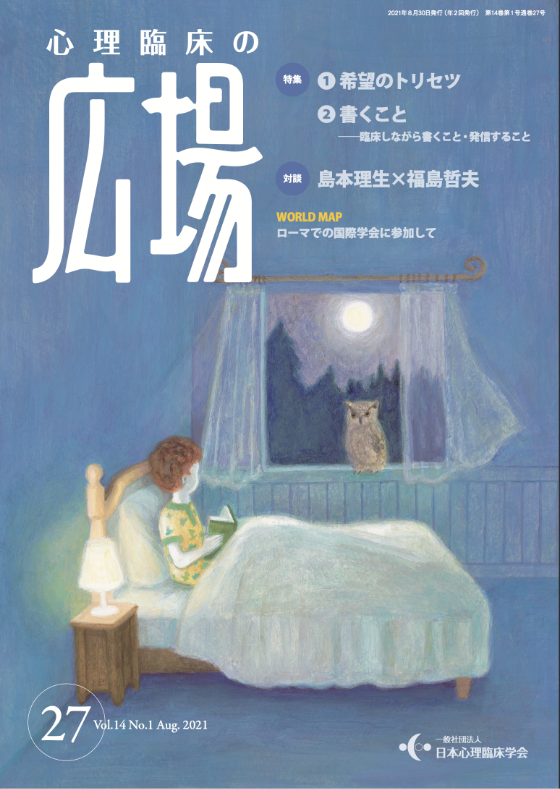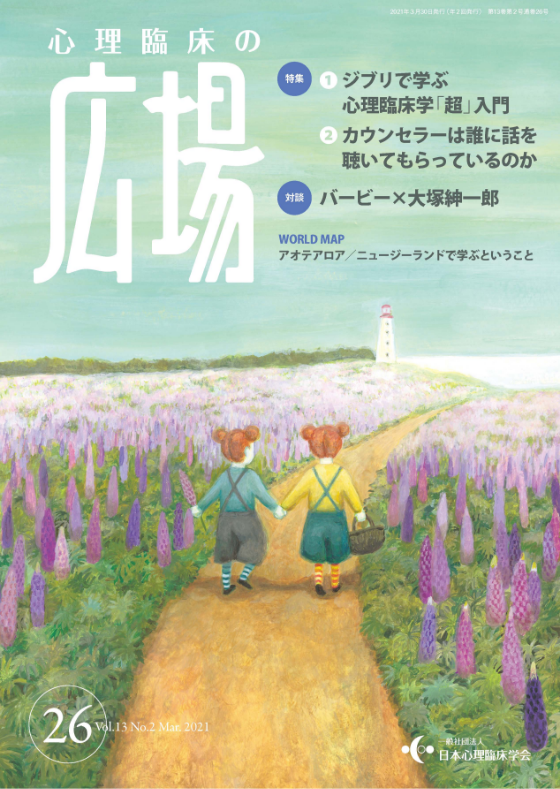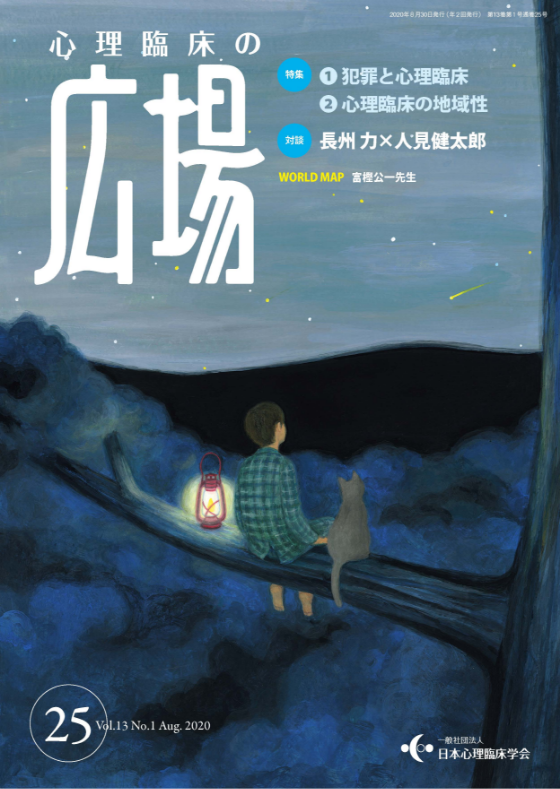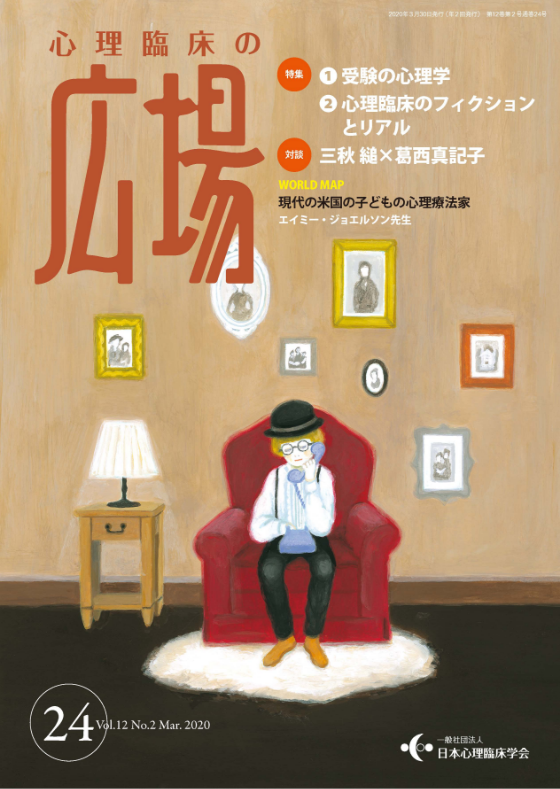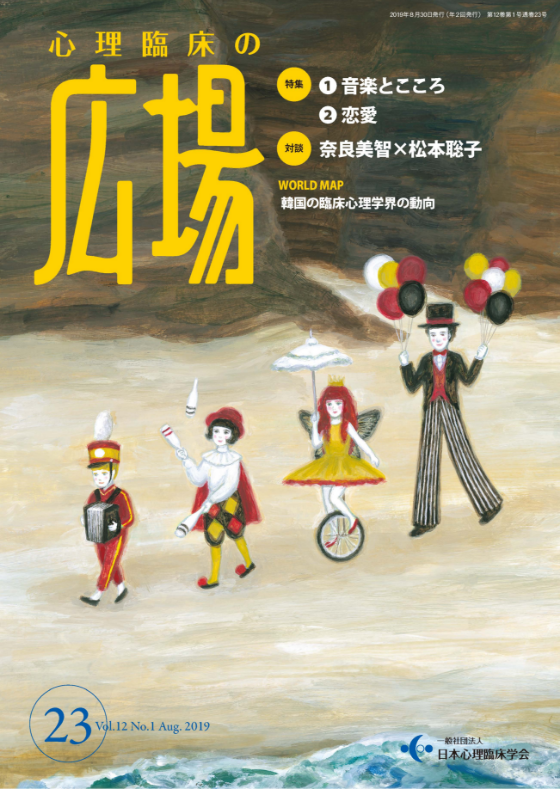当事者に役立つ心理教育 人に知られたくないことがある――恥と秘密
著者 島根大学こころとそだちの相談センター/臨床心理相談室にしきまちオフィス 岩宮恵子
「ぼっち」が恥になる時代に
「ひとりでいるところを見られたくない」と話す思春期の子どもたちがいます。誰とも一緒にいない状態を知り合いに見られることを、恥ずかしいと感じてしまうのです。そこには「ぼっち恐怖」と言ってもいいほどの怖さがある場合もあります。
SNSによって人間関係が可視化されるようになった今、集団からの逸脱がはっきりとわかることも増えてきました。思春期の「恥」は、個人的な問題や振る舞いや失敗に対するものに加えて、一緒にいる人がいないという「空白」が露呈することへの不安からくることもあります。だからスマホで武装して、あたかも誰かとつながっているふうを装って、その場に“居る”自分を守ろうとすることもあります。でもそれが演出だと周囲に気づかれたときには、とてつもない居心地の悪さが襲ってくることになります。
そしてこの「つながりの演出」をしなくてはならないほどの想いは、自分自身の存在の根拠を問い直すような、深いレベルの不安とも結びつくことがあります。その演出が破綻したときの恥の感覚は、もはや他者にどう思われるかというレベルを越えて、自分が生きている意味ってなんなんだろうというような、自分自身の実存をめぐる問いになることすらあるのです。
語れない心と、物語に託される感情
「恥」の感情は、しばしば「人に知られたくないこと」として心の奥に沈殿していきます。それは単なる隠したい秘密ではありません。語りたくても言葉にならないとか、それを人に分かってもらう資格など自分にはないと感じていることもあります。「べつに」「わかんない」としか言えない言葉の奧には、まだ形を持たない深い想いが潜んでいることもあるのです。
そんなとき、アニメや漫画やゲームといったサブカルチャーが大事な避難所になることがあります。なぜならサブカルは、怒りや恐怖、絶望や希望や喜びといった複雑な感情を安全に投影する舞台となるからです。
そんななかで「推し」も重要な意味を持ちます。ただ「推し」の存在は、自分の内面と深く共鳴しているため、誰にどの程度話すのかというその語りには繊細な選別が働くことがあります。推しているのに語られることのない「推し」には、語られないだけの理由があり、語らないことで内面の秩序が守られていることもあるのです。
恥と秘密を暴かず、そっと尊重するということ
「恥ずかしがらずに言ってごらん」「秘密はないほうがいいよ」と言葉をかけられることがあります。それは善意からきている言葉ですが、時に追い詰められるような気持ちになることもあります。「話さないとわからない」と言われると、ますますどうしていいかわからなくなりますよね。
語れないことにも意味があるということを知っていて、「無理に話さなくてもいいよ」「話さなくても嫌いにならないよ」という関係性を提供してくれる人との間でこそ、言葉になっていないかけがえのない心の風景がうっすらと見えてくることがあります。
恥や秘密は、その人の感性と生の実感がしみ込んだ、守られるべき領域です。それを無理に開かせようとせず、そこに大事なものがあることを信じ、そっと受け止めるまなざしが、つながりの可視化が進む今ほど必要とされている時代はありません。自分の「語れなさ」すらも尊重してくれる誰かの前で、「言葉にできるかもしれない」と感じる日が来るでしょう。ここは、安全だと深く確信できた、そのときに。