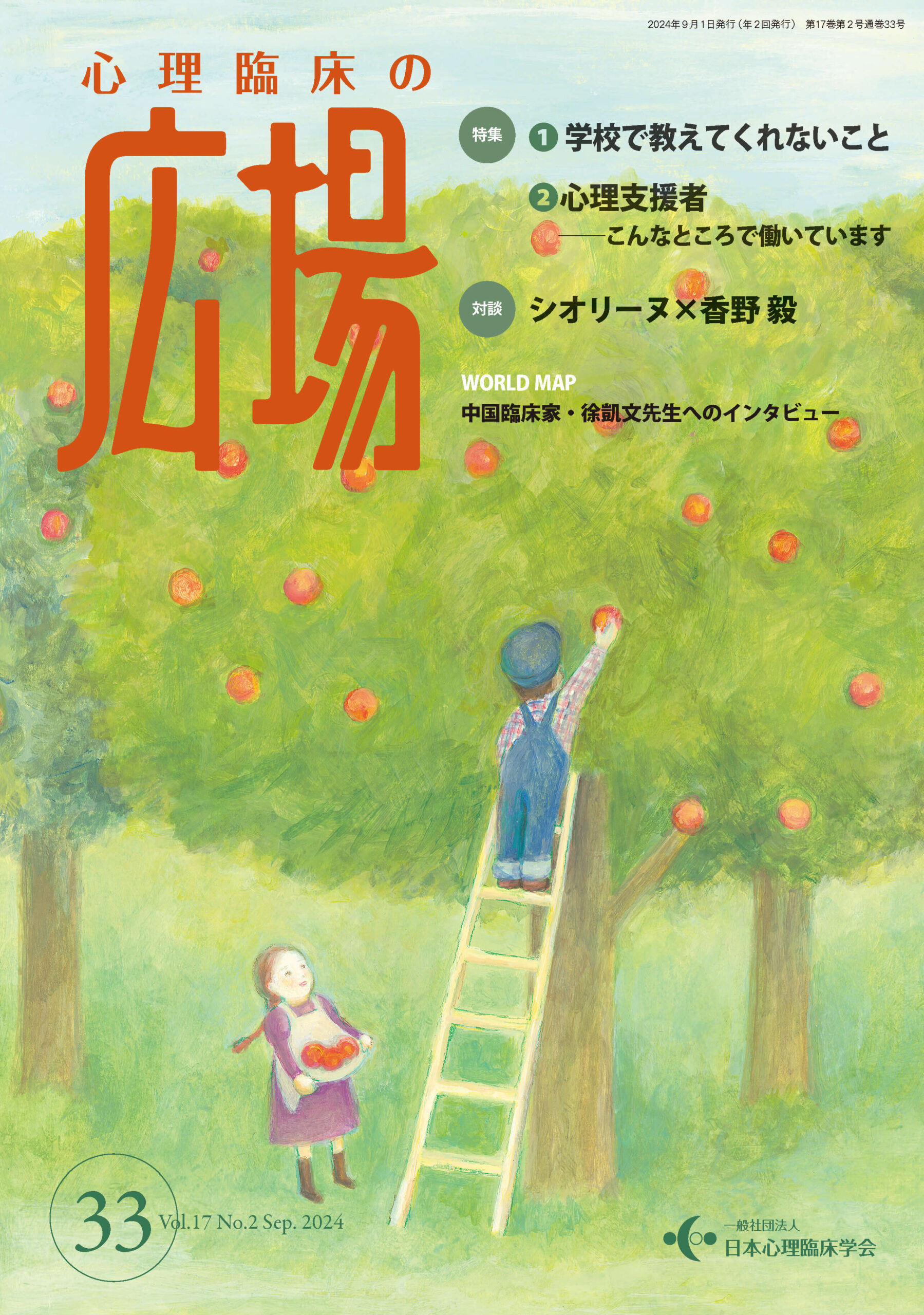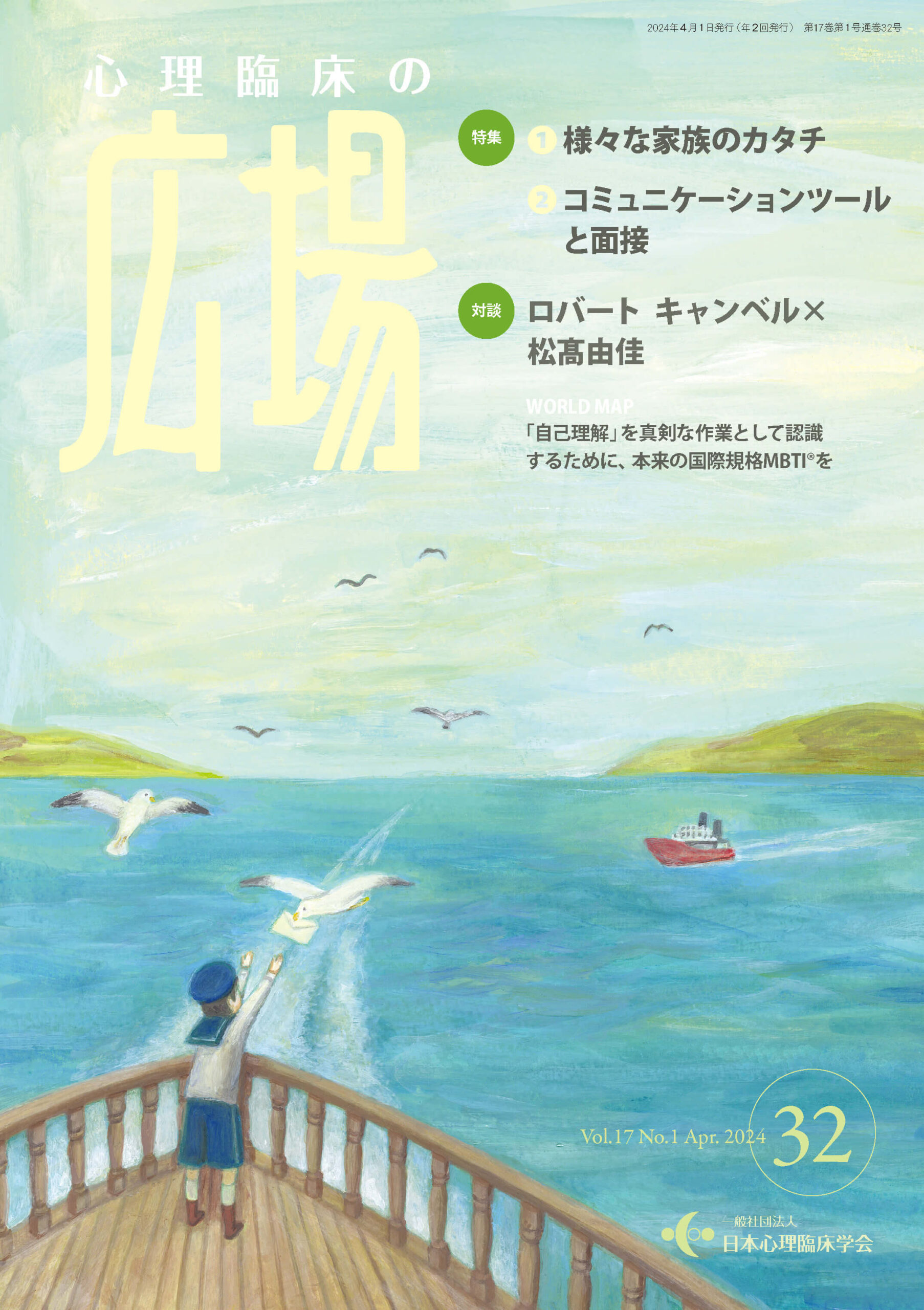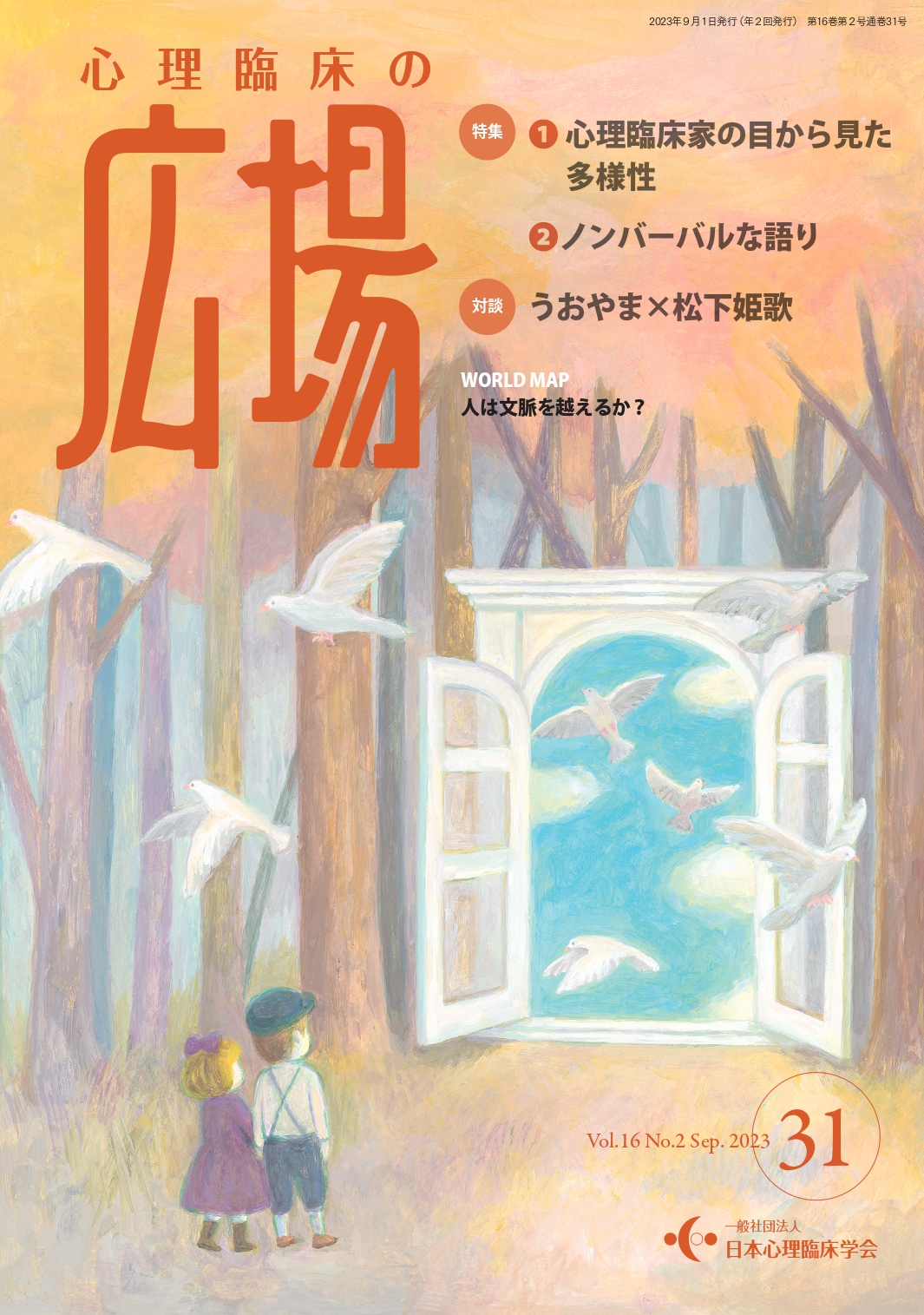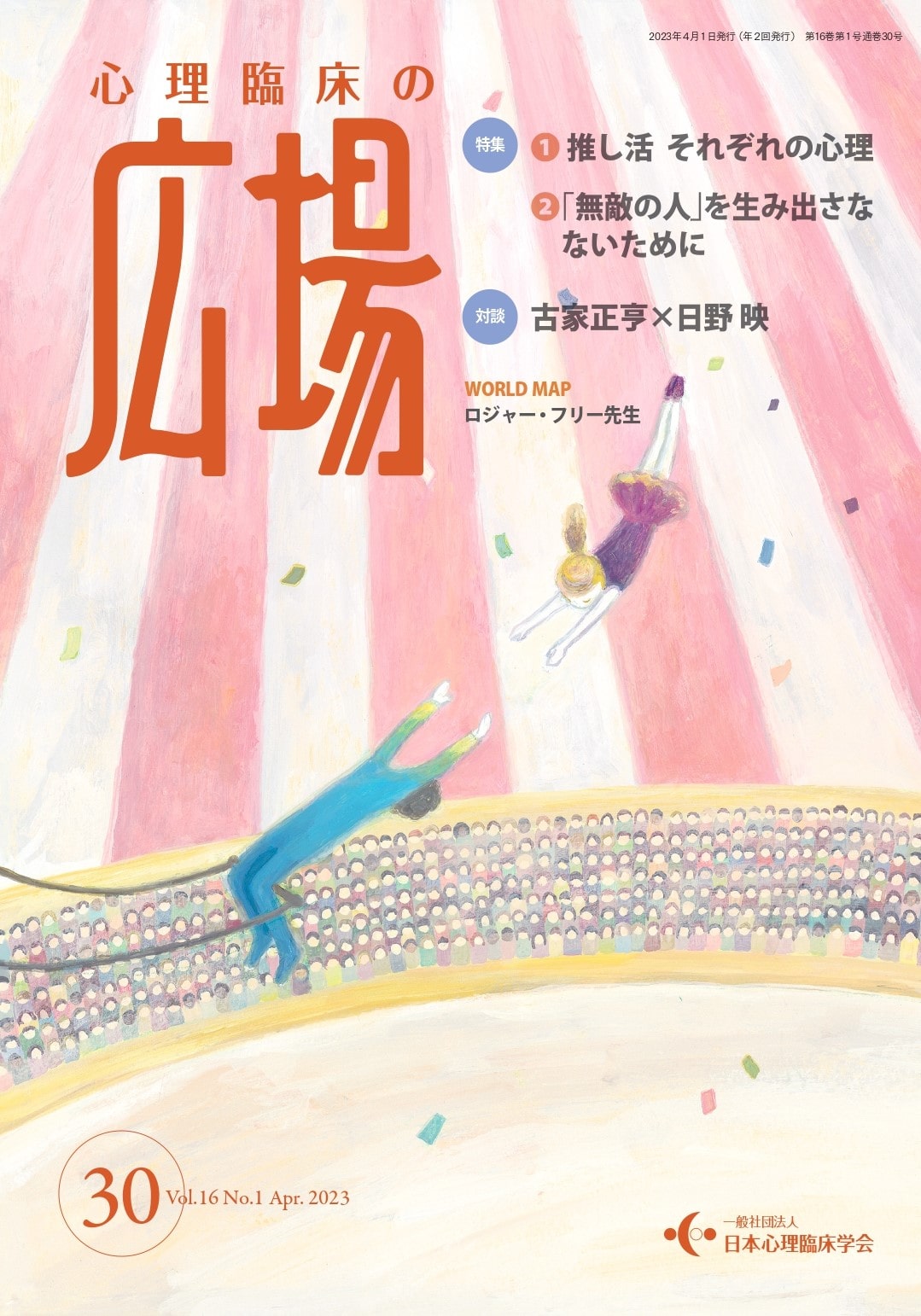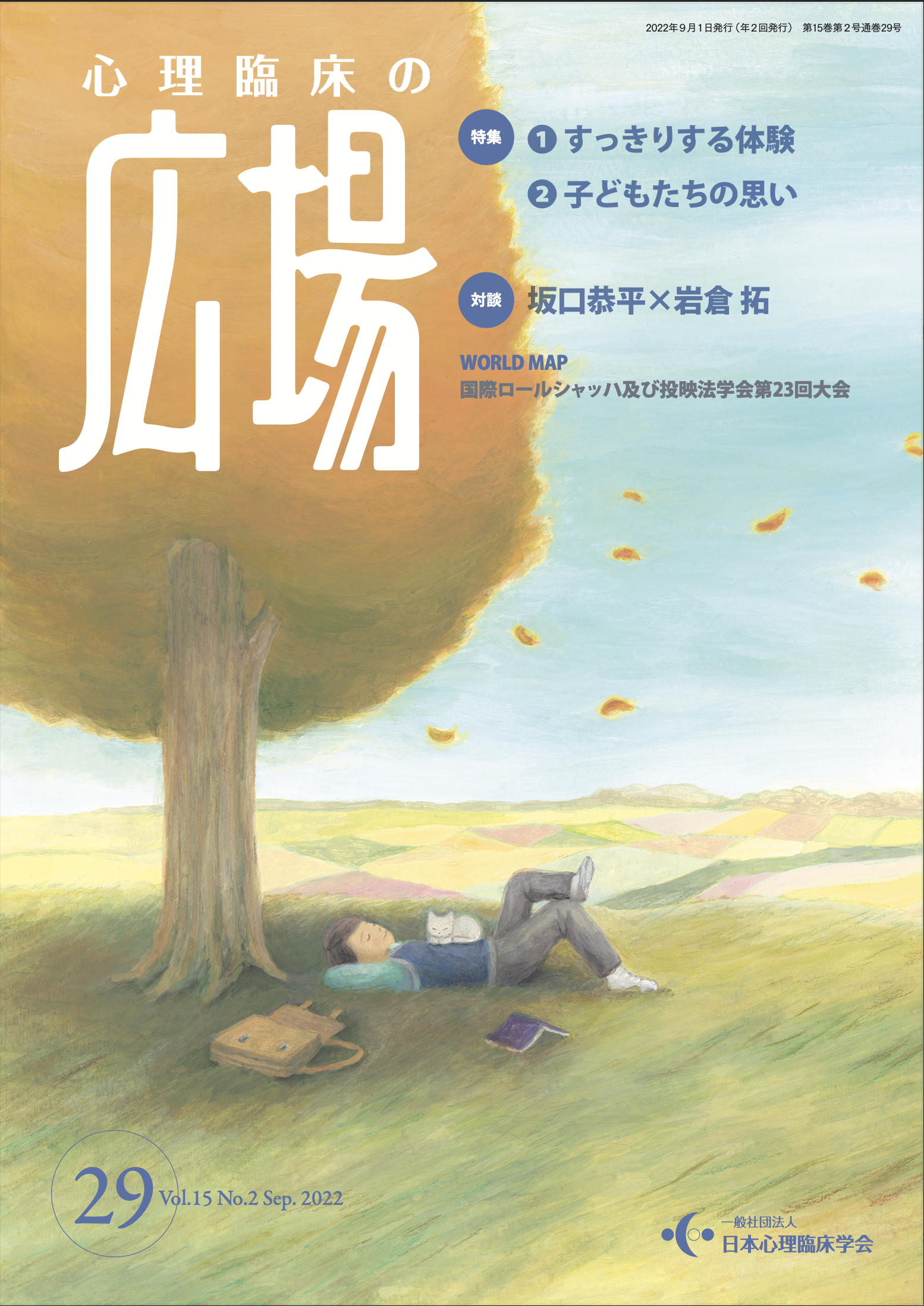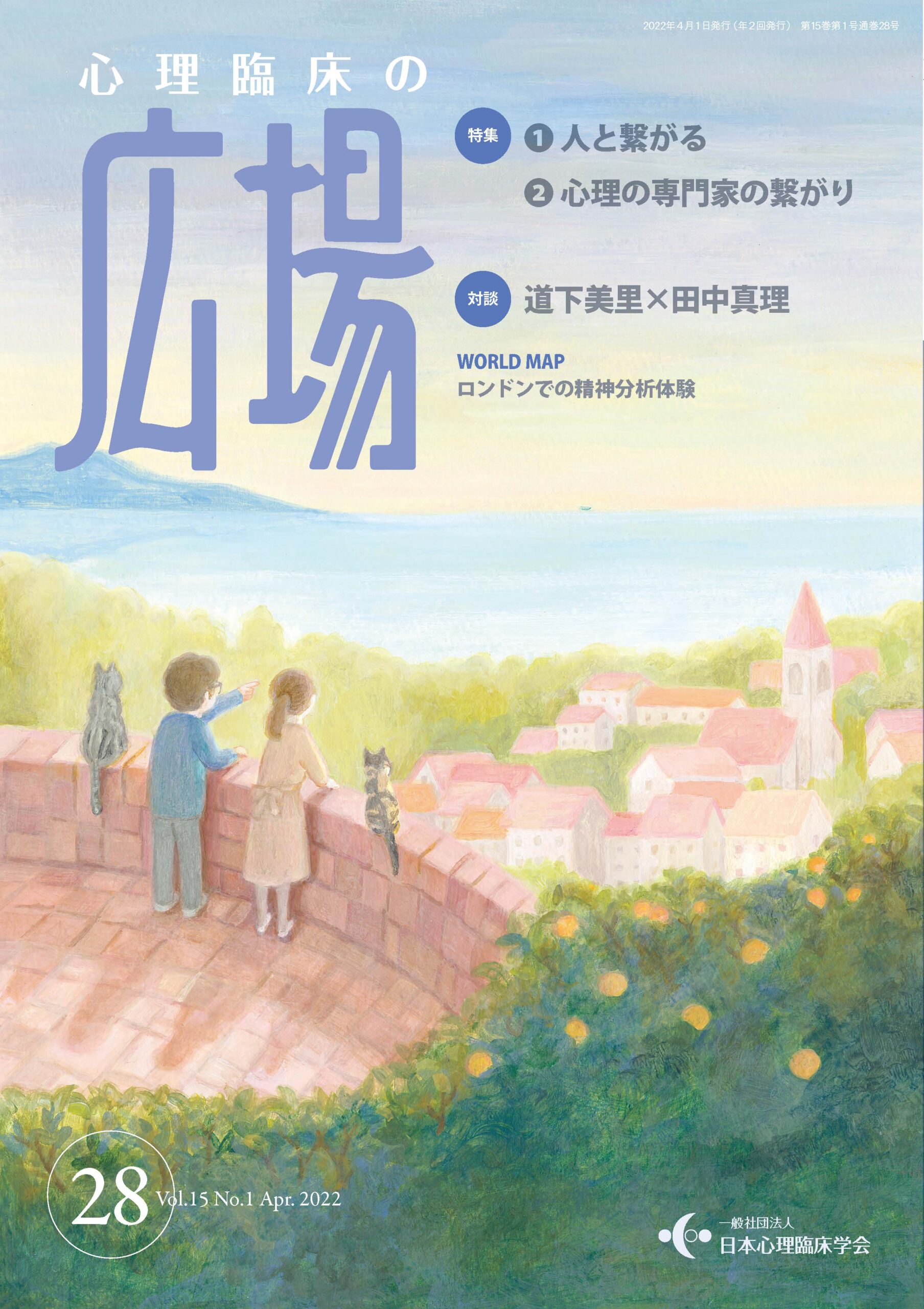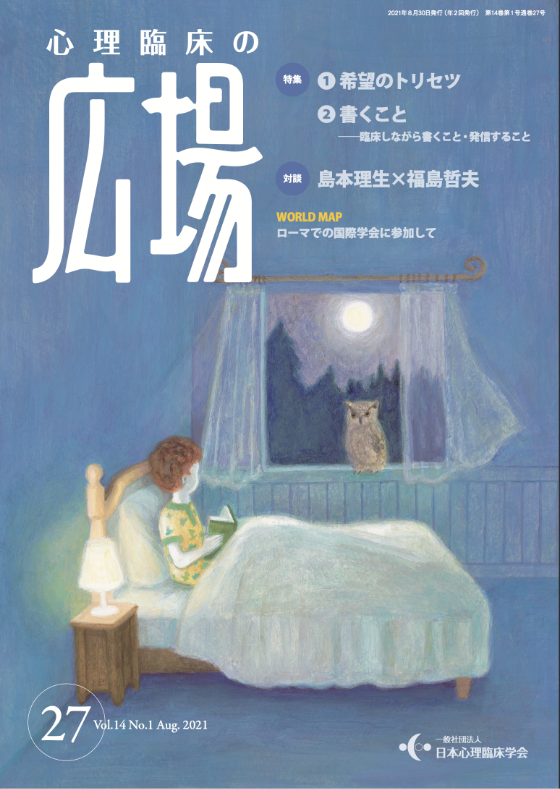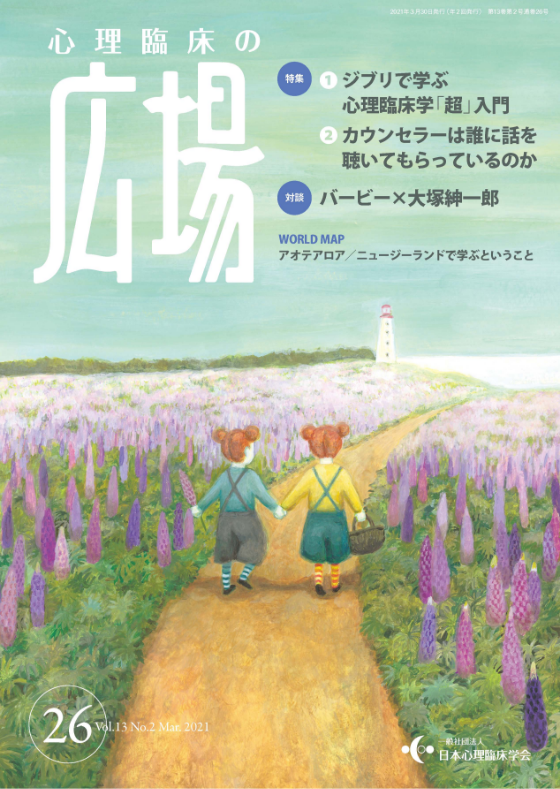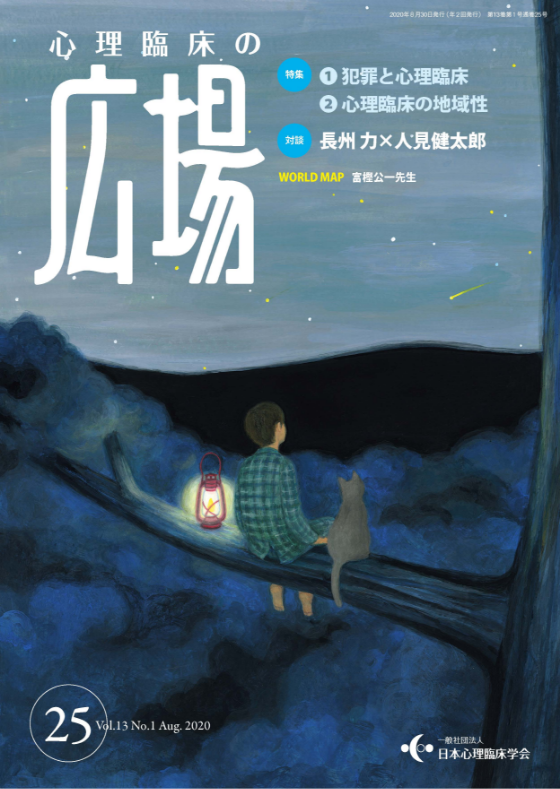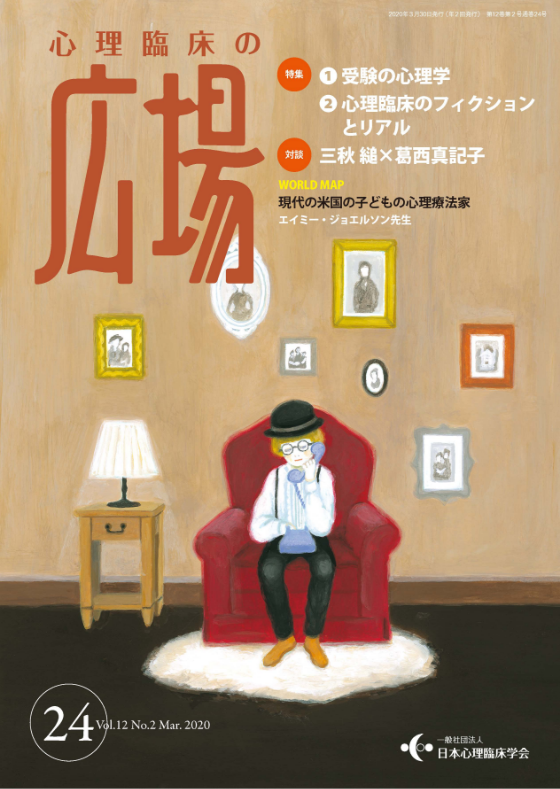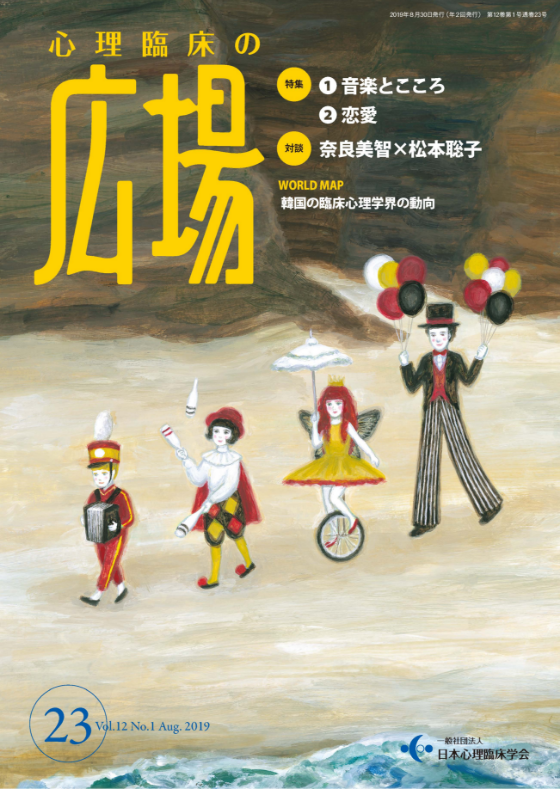家族としての犬と猫
一般社団法人ペットフード協会の全国犬猫飼育実態調査(2023)の推計値によると、現在飼育されている犬は約684万4千頭、猫は約906万9千頭。合わせて約1591万3千頭なので、東京都と香川県と佐賀県の人口を足した以上のワンコとニャンコが、飼い主の大切な家族になっています。メダカ、小鳥、ハムスターなども含めると、過去10年間にペットを飼育した経験のある人は38%。ちなみに筆者は子ども時代に雑種の室外犬と、大人になった現在はトイプードル2頭とヘルマンリクガメと暮らしています。本稿はそういったこころにペットがいる方たち、そしてこれからそうなるかもしれない方たちに向けたエッセイです。
愛し愛されて生きるのさ

そもそもなぜ犬は人と暮らすようになったのでしょう?諸説ありますが、心理学でよく引用されるダーウィン的な思考をしてみると、祖先にオオカミを持つ犬が生存のために牙を使わなくなり、かわりに愛される術を本能として覚えた…となるのかもしれません。近代では番犬として、つまり危険を知らせる役割をがんばったから一緒に暮らすようになった、と考えることもできそうです。進化心理学的な適応論とも言えます。
しかし筆者は、そのような淘汰・機能論だけでは納得できません。なぜならわたしたちが犬を見るとき、犬もまたこちらを見ているのである…といきなりニーチェのナラティヴ的にぴんぼけの援用になるのですが、半分本気です。トイプードルも雑種犬も、人間に受動態として愛されるために尻尾を振るようになったのではなく、むしろ人間を能動態で無条件に愛しているからともに暮らすようになったのでは、と思えてならないのです。眼差しが交差すると、小沢健二の1994年のヒット曲のように「いつだって可笑しいほど誰もが誰か愛し愛されて生きるのさ それだけがただ僕らを悩める時にも未来の世界につれてく」のだと、犬との暮らしは実感させてくれます。「お散歩いく?」と話しかけてハーネスを手にとった時のはしゃぎよう、人の腕にアゴを乗せてくつろぐ姿、疲れて寝転んでウトウトすると足元からこちらを見てくれている…。気持ちが通じ合っていると感じます。
愛犬との交流は心理的な苦痛を和らげる
その根拠として、アメリカ心理学会のジャーナル「Emotion」に掲載された論文「愛犬との交流が心理的な苦痛に及ぼす影響; The Influence of Interactions With Pet Dogs on Psychological Distress」(Matijczak et al., 2024)を紹介します。この研究に参加した飼い主は73名で、愛犬はいわゆる盲導犬のような専門的訓練を受けたセラピードッグではなく、普通の犬です。手続きとして、まず飼い主がランダムに①リードを付けずに自由に愛犬と触れ合うグループ、②ストレス低減のうたい文句でベストセラーとなった「大人の塗り絵」を行う期待コントロールのグループ、③何もしない待機コントロールのグループに割り当てられました。
そして、ストレスを人為的に誘発するために用いられるPASAT-Cという継時的な足し算課題に回答し、直後に介入として①②③のいずれかを体験したわけです。その結果、①愛犬と触れ合うグループの飼い主は②③と比較し、有意に肯定的な感情の増加と不安の減少を示しました。そこでさらに飼い主と愛犬が触れ合う様子を撮影したビデオの分析を行ったところ、「愛犬へのポジティブな言葉」「身体接触」といった交流の総和が多くなるほど、否定的感情の減少が予測されました。この研究は、飼い主と愛犬の組み合わせを対象に実施された点が画期的です。毎日の仕事や勉強で疲れて帰宅し、玄関のドアを開けると愛犬がクルクル回りながら喜んで出迎えてくれる。「お留守番がんばったね」と声をかけると、「撫でて? 撫でて?」と言うかのように無防備にお腹を上に向ける。そういった再会が研究手続きに再現されているのです。愛犬の心をメンタライジングすると「ご主人さま、足し算課題お疲れさまでしたワン!」という声が聞こえてくるようです。それは大人の塗り絵よりも癒されるでしょう。

犬は人を信じる
このように動物心理学、動物行動学、イヌ学は近年注目を浴びています。犬から人への揺るぎない信頼について、行動実験やMRIといった科学的手法を用いて包括的に解析したWynne(2019)は、「人間社会でイヌをこれほど繁栄させたものは、なんであれ特殊な知能などではなく、温かな心の絆を結びたいというイヌの欲求なのだ」とまで述べています。
筆者の生活を振り返っても、心理臨床を通して垣間見える世間の理不尽を感じた夜はとくに、飼い主を評価せずありのままに気持ちを理解しようとしてくれる愛犬からの関わりにホッとします。SNSはフェイクニュースと揚げ足取りばかりで、チクチク言葉にこころを削られますが、そういった言葉の世界から離れモフモフの世界に身を投じることで、生の実感を取り戻すのです。ソファでじゃれつくトイプードルの群れに、筆者が「大型犬」として仲間になる、こころから癒され、リフレッシュされる瞬間です。
猫も杓子も、リクガメも
猫派のみなさんについても想像で書く挑戦を考えていたのですが、幸運なことに文字数が尽きてしまいました。先住亀のヘルマンリクガメにも筆者は癒されていて、何がいいかと言うと黙々と葉物野菜を食べてくれるのです。爬虫類はなつかない? そんなことはありません。カメの顔に顔を近づけると、にょきっと首を伸ばして挨拶してくれます。
猫も杓子も、リクガメも。もちろんワンコも、同じいきものとして、わたしたちは互いに愛着をもつことができる。そう考えるとちょっとだけ幸せになれる気がするのです。

◦参考文献
一般社団法人ペットフード協会(2023)「令和5年全国犬猫飼育実態調査」https://
petfood.or.jp/data/chart2023/index.html
Matijczak A, Yates MS, Ruiz MC, Santos LR,Kazdin AE, Raila H. (2024). The influence of interactions with pet dogs on psychological distress. Emotion, 24(2):384-396.
小沢健二(1994)「愛し愛されて生きるのさ」東芝EMI
Wynne, C. D. L. (2019). Dog is Love: Why and how your dog loves you. Mariner Books.
梅田智世訳(2022)『イヌはなぜ愛してくれるのか——「最良の友」の科学』ハヤカワ文庫NF