巻頭対談: ロバート キャンベル×松髙由佳

松髙 こういう対談は初めてで、とても緊張してます。
キャンベル わかります(笑)。緊張しない人はいませんから。
松髙 私は今、県立広島大学というところで学生相談の仕事をメインにしています。肩書は室長ですが、実際の相談もたくさん受けていますし、その中にLGBTQの方もときどきやって来られます。ただ、カウンセラーでも心理の専門職でも、性に関して正しい知識を学んだり、どういうふうに対応したらいいかといった教育を受けてきてない人が多いんですね。私自身は特に多様なセクシュアリティについて関心があって、いろいろ調べたり研究したりしながら支援や現場に関わっています。LGBTQもそうですが、最近になって「 SOGI(Sexual Orientation and Gender Identity)」という言葉がようやくポピュラーになってきたと感じています。
キャンベル 確かに市民権を少しずつ得ていますよね。
松髙 認知度が上がってきてはいるんですが、その一方で、当事者自身のしんどさというか、なかなか自分を外に表せないといった問題も今なお大きいと感じています。そういう状況について、キャンベルさんはどのように感じておられますか?
キャンベル 私自身、身体的に目立つということもありますが、メディアで活動しているので、私の名前と顔が一致する人からすれ違うときに軽く会釈をされることがあるんですね。ただ、東京の人はあんまり驚かない人が多いですけど(笑)。僕の日常の中には、そういうことが普通にあって、それと僕がカミングアウトしているということが合わさって、面識がない人から声をかけられたり、相談というと大げさですが、自分の経験を私に話してこられる方がいます。そうした体験から、あくまで皮膚感覚としてですが、セクシュアリティのことを考えている人たちが増えている印象があります。
今『虹クロ』というNHKのテレビ番組に出演していて、視聴者の方からフィードバックをいただくことがありますが、当事者の人たちだけではなく、その人たちと繫がっている人——つまり「ほとんどの人」ということになるわけですが、そういう人たちが実はセクシュアリティに限った話ではなく、私が発した言葉や番組内で話し合われたことが、家族や社会の中で自分が感じている生きづらさに、そのままパラレルに通じるという声を聞くことがとても多いですね。
松髙 ああ、そうなんですね。
キャンベル SOGIやLGBTのことに限定して言うと、もちろん当事者たちにとっては非常に深刻なことです。なぜなら、自分の健康に直結することでもあるわけですから。ただ、そこにはいろいろなグラデーションがあって、それは色が薄くなっていくイメージではなく、別の意味、別の意義として、自分たちのことや今この生きている社会の中がどうなのか、自分はその中で何者になろうとしているのか。特に若い人たちが、そうしたことを一つの起爆剤になるようなレベルで考えてくれているように感じます。
日本でもある程度は取り組んでいると思いますが、ヨーロッパやアメリカでは当事者の意識に関するアンケート調査を徹底的にやるんですね。それはLGBTがどこに何人いるか、に限らず、その人の職業であったり、どういう生き方をしているのかを問うわけです。例えば、法律や自治体の仕組みのような大きな枠組みを改善していくためには、そういうデータの積み上げが不可欠なんです。
今申し上げていることが、少し特殊な属性を持った一人の市民としての印象ですね。著しい変わり目というか、私たちは今、分岐点という塀の上にいるような感じがしますね。
自分の「身近な層」にある問題
松髙 そういう感覚をキャンベルさんはおそらく何年も前から感じられていたんですね。特にここ最近は、そういうふうに自己開示というか、自分の言葉で自分のことを語る方が増えた感じなんでしょうか?
キャンベル 私もそうですけれども、自分のあり方を言語化したり、あるいは可視化されたりすると安心できるんですよね。特に日本社会においては、対立を回避することや、できるだけ否定するような場をつくらない力が、日本語という言語そのものや、教育制度をはじめさまざまな仕組みの中で働いているわけです。良く言えば、相手のことを慮って、相手が不愉快にならないように、あるいは不愉快というよりも戸惑わないように話をする。そういうことを常に意識しながら生きていると思うんですね。
そう考えると、相手がどういう立場にあるのかわからない中で、特にセクシュアリティという「違和感」を生み出しかねないトピックに関しては、若い人も、あらゆる世代の人も、まだ公言することは難しい社会だと思います。また、もう一つ感じることは、いわゆる当事者の方たちには、バイセクシュアルの人、ゲイ、レズビアンの人、トランスジェンダーの人というように、ものすごくいろんな幅があるんですね。それぞれさまざまなニーズというか、社会的な課題が異なる部分であると思うんです。このことは前からわかってはいたけれども、具体的に差別をされることによって、あるいは社会の中で与えられて当たり前のものについて、どれだけ妥協しながらそうした人々が生きているかということが、とてもよく見えてきたような気がします。例えば、長年連れ添ったパートナーが入院をしたときに身元保証人にもなれず、場合によっては病室にも行けず、生死に関わる重大な医療判断の場に参画することができない。それは今この瞬間にも起きていることです。
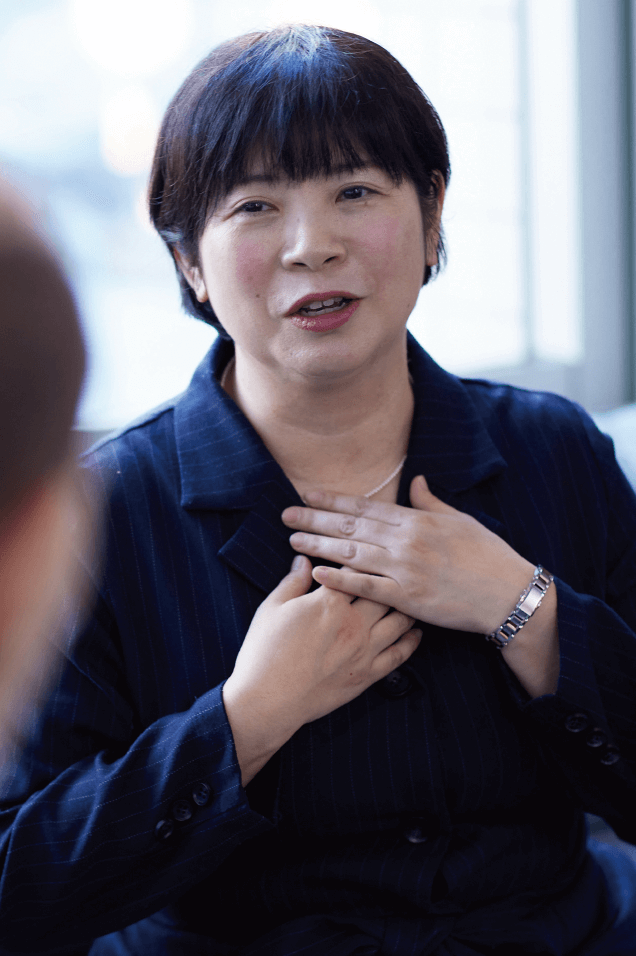
そういうことが、一人や二人ではなくて、波紋のように広がって可視化されてきています。先ほど申し上げたように、まだデータとしては十分ではないかもしれませんが、そうした問題について、何が必要なのか。それはお金なのか、法律の改正なのか、もしくは人々の心の問題として捉えるべきなのか。最初の話に戻しますと、やっぱり一つ一つの事柄に言葉が連結して、繫ぎ合わさって、そのことによって人々の心というものが開く。今はそういう動きや作用が伝わっている真っ只中という感じがしますね。
松髙 思いが表現されて、それが人に伝わって共有されていく…。確かに当事者の方がどういうことに困っているとか、差別をされたとか、「これはおかしい」とか、本当にそういう声をどんどんと上げるようになってきて、それで実際に変わってきたところもあると思いますし、その声を周りの人が受け取って「じゃあ、こういうことに繫げていこう」とか、いろんな動きに繫げていったりしています。私たちも、例えば、心理職にどういう教育訓練をするか、セクシュアリティに関するトピックをどう伝えていけばいいのか、そういうことを常に考えているわけなんです。
ただ、先ほどまさに「心の問題」と言われましたが、声を上げられるようになった一方で、そのことでSNSの世界で叩かれたり、考えが折り合わないと思う人が、ヘイト的な発言をしたりすることがあると思うんです。論争までは行かないにしても、そこでまた傷つきがあったり…。

キャンベル 今、話をお聞きしていて思い出すのが『虹クロ』のことです。この番組にはリモートで参加される方もいますが、さまざまな地方から実際にスタジオまで足を運んで、本当に皆さんすごく勇気を振り絞って出てくださっているんですね。何かをそこで伝えたい、悩みを聞いてほしいという若い人たちが、毎回、私たちの目の前に現れるわけです。当然、一人一人が置かれている状況や環境は違うので、あまり公約数的に、これがすべての方に通じているとは言えないのですが、一つ感じることは、自分の周りにいる人に自分の話をしてもいいけれど、気を遣われることが嫌だという人が多いんですね。
そういう言葉が重なっていくうちに、これは深いなというふうに思いました。何歳であろうと、自分のことをカミングアウトすることはとてもリスキーなことです。今の若い人たちの多くは、わりと周囲に知ってくれている友だちがいたり、家族がセーフティネットになっていたりするんです。でも、それでもなぜ言わないかというと、言うことによって周りの人たちに気を遣わせることになる。昔から親を悲しませたくないから言わないということがありましたが、これは本当で、母の顔とか父の顔を想像すると怖気づいてしまいます。大好きなお祖母さんがすごく悲しむ、と思えば、お祖母さんを失望させたくないので、沈黙します。
この前会った子もそうでしたけれども、お祖母さんから振り袖の着物を買ってあげるよと言われ、いや、それは着たくないけどそう言い出せない。それを言うことによってお母さんやお祖母さんを悲しませたくないということがありました。
あと今の若い人たちは承認欲求がとても高くて、「いいね」の数やフォロワー数、SNSでどれぐらい自分が人と繫がっているのかが大事ということがありますよね。その中で、もし自分が今まで投稿してきたことと違うことを言ってしまったら、それまでの全部が崩れて周りの人たちが引いてしまうのでないか。引かないにしても違う目で自分を見るのではないか。これってやっぱり日本流の言い方かもしれませんけれども、気を「遣わせて」しまう。どうやって人に気を遣わせないかの方が大事なんです。
それに対して「そんなこと心配しなくてもいいよ」と言うのは簡単ですけれども、私はその気持ちがわかる気がするんですね。自分が差別を受けるとか、アパートが借りられないとか、ローンが組めないとか、好きな人と一緒に組めないということは、それは現実としては大変なんだけれども、この「気を遣わせてしまう」ことも日常的な悩みだということです。
松髙 具体的な、現実的な問題もあるにはあるけど、もう一つの層というか、人間関係や関係性が変わってしまうことの方が大きいわけですね。
キャンベル 例えば、会社に入ると上司がどういう人なのかということはすごく大事なことですね。部長や専務、社長クラスになると、インクルーシヴな人が増えて、企業が大きくなればなるほどそういう取り組みをしたりするんですけれども、直属の管理者がどうなのかによって自分の日常がもう180度変わるわけです。
一方で、先ほど申し上げたようなSNSもそうですし、ゲームもソーシャルゲームが基本になって、不特定多数の人との緩やかな関わりの中で自己表現をしたり、自分を確立していくということがあります。一つの場ではなく複数の場で、それぞれその都度名前を変えたりするということが普通にあるわけですね。そうすると、特に若い人たちの自我の同一性というものが、どう折り合って
いくのか。どういうふうにして整合性が保たれているのかが問題になるわけです。
僕もTikTokをやりますけれども、YouTubeをやったりTikTokをやっている人たちが今はもう普通にいっぱいいるわけですね。で、例えば30秒や1分の短い動画であっても、そこには間違いなく自分の、その時点で表したい自己というものが投影されているわけです。そうすると、今どういうセクシュアリティが自分の性質であるのか、そしてもしそれを抑制している自分がいたとして、その抑制を取り払ったときに何が起きるのか。それまでつくってきた自分との乖離というものが、できるのかできないのかというところが非常に大事な気がします。ちなみに私の周りには、結局最後は親の顔とか上司の顔ではなく、フォロワーたちがどう思うかだという人がいたりします。
ただ、セクシュアリティについては、これは決して軽いものではないし、ある年齢になって、ある人生のステージになって、自覚的になってから誰であっても悩むものだと思うんです。それを自分から公言をするかどうかというときに、5年前や10年前とはやはりもうすでに違う状況があって、その乗り越えるべきハードルが違っている。むしろハードルがどうと言うよりも、そのハードルを越える場所が違う感じがしているんですね。

松髙 そのハードルを越える場所の一つに、フォロワーの反応があったりするわけですか?
キャンベル 今はもうLGBTをキャラ化することが求められるようになっています。それによって登録者数やビュー数が積み上がっていく。つまり承認されて成功に繫がっていくんですね。それはそれでいいと思うのですが、でも、いつの間にか、そのグループの中で自分がレズビアンの代表みたいになって、何かが起きたときにすべて自分が対応しないといけないとか、あるいはレズビアンならではの感性を求められるとか、こういうことがすごくあるんですね。
松髙 何かこう、役割を負わされるというか。
キャンベル 金水敏さんという著名な言語学者が日本語には「役割語」があるとおっしゃっているんですね。例えば「博士語」や「田舎のおかみさん語」みたいなものがあると。役割で言うと、「女性ならではの感覚や感性」を求められるのも女性が担わされている役割ですよね。同じように、今ではかなりなくなりましたけれども、昔は「外国人」もそうだったんですね。私のように前近代の日本文学を研究する外国人は、日本人では気づかないような、外国人ならでは目を通した新しい発見ができるはずだ、だからそれを我々に与えてくださいというふうに20代の頃からずっと言われて、それがすごいストレスでした(笑)。
「聴ききる」ことで得られる深い理解

松髙 そういうふうに外側から言われる、押しつけられると、いや、そうじゃないんだけど…と言いたくなりますよね。
キャンベル 押しつけられると、自分の個性や自我というものが、完全にうち消された感じがするんですね。役割を与えられてそれで安心できる人もいるし、すべて悪いというわけではないんですけど、女性であるとか、レズビアンであるとか、ゲイであるとかということが、一つの役割のようなものになると、本人たちは躊躇しますね。そういうことはあると思います。
松髙 私たちも心理職として、あるいは一般人としてもそうかもしれないですが、わかりやすいイメージだったり、先入観みたいなものからなかなか自由になれないことがあります。私はカウンセラーが抱えるバイアスについての研究を博士号のときにしていたんですが、自分が研究する立場にいても、つい思い込みというか、そうと気づかずに「ゲイの人というのは大体こうだよね」みたいなふうに言ってしまって、「いや、そうじゃないんですけど」と言われたりしたことがあって。なかなかそういうものから自由になれないということは本当にあるし、気をつけなければと思っています。
キャンベル 松髙先生と同じように、僕もすごくたくさんの人にインタビューをしたり、話を聴いたりしますが、やっぱり「聴ききる」ということが非常に重要です。日本語のこの「聴く」「聴ききる」「傾聴する」ということの中には、どこかで判断を留保する姿勢が、善し悪しはちょっと置いておいて相手の立場を共感まではしなくてもそのまま受け取るような態度がありますよね。僕はそこに日本社会の蓄積があると思っていて、聴ききることが美徳というか、評価される社会であると感じています。
そういうふうに最後まで聴ききった後に質問をする。あるいは自分の立場を伝える。そこから初めて対話が始まると思うんですね。そして、セクシュアリティに関しては、まずは基本的な知識を持っていることが必要です。どういうことかと言うと、今の私たちが生きている社会の中で、その人たちはどういう状況に置かれているのか。権利と義務、あるいはどういう「制限」に縛られているのかということを、自分の中で整理できていないと、まず聴くことができないと思うんですね。
ただ、最初に私の皮膚感覚から申し上げたように、今この社会の中で生きている人たちの中で、本当に加速度的に意識が変わっていっています。「あなたは私とどういうふうに繫がっているのか。これから一緒にどういうふうにやっていくのか」ということがやっぱり大事だと思っている人たちが増えているように思います。
ウクライナでの出会い
キャンベル 去年の6月にウクライナに行く機会があって、そのときにLGBTのシェルターを訪ねたんですね。そこに身を寄せている10代の人たちがたくさんいて、施設の担当者から話を聴いたんですが、早い話が今日生きるか死ぬかわからない中で、自分が誰と寝ているかとか、誰を対象に恋い焦がれているかということは、本当に小さいことだと彼ら自身も感じていると言うんですね。旧ソ連の地域もほぼそうであるように、セクシュアリティに関してウクライナは非常に保守的です。そんな中で戦争が起きて、志願兵の中にはゲイもレズビアンもトランスヴェスタイト(transvestite)の人たちがたくさんいます。中にはレインボーの腕章をつくって、それをつけている人たちがかなりいるんです。そして、戦争で銃器を持つ人たちだけではなく、多くの人がボランティアになって、自分の仕事以外のことに関わっているんですね。
例えば、リビウのシェルターにいる若いLGBTの人たちは、土日にボランティアで犬の散歩をしていると聞きました。飼い主を失った犬が大量にアニマル・シェルターにいて、彼らは15人ぐらいのグループでそこに行って、毎週二時間ぐらい犬に散歩させたり、動物と触れ合ったりしています。また、それぞれの拠点には心理カウンセラーがいて、医者もいて、HIVカウンセリングを行うスペシャリストがいます。そんなふうに、いろんな従事者たちがいるけれども、みんなが社会に出て見えるような形で貢献をするわけです。いろんなところでそうした状況が起きていて、彼らとしては非常に生きやすくなったというふうに言っているんですね。
災害が起きたり戦争が起きたりすると、ある種のユートピア状態になることは、これはよく言われることです。平和な状態になったらどうなるのか、また前の状態に戻ってしまうということもありますが、そうやって見えるような形で社会に関わっていける、そういう場や契機があるということが重要だと思います。
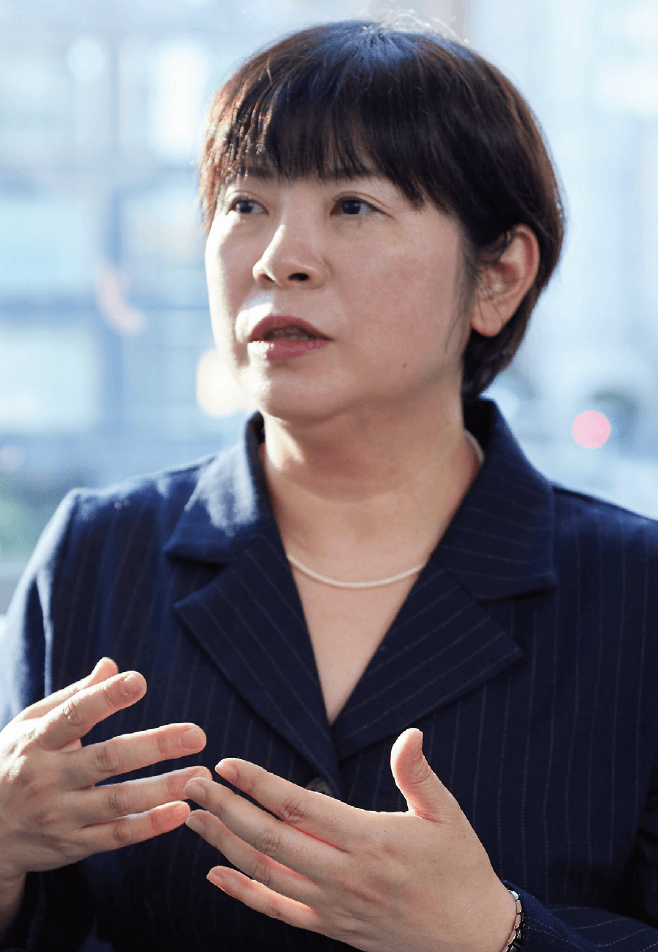
松髙 やっぱり状況が違えば、セクシュアリティの扱いというか、世の中の見方や当事者の中での感じ方が違ってきますよね。ウクライナという極限状態の中で、そういうことが起きることもあるし、日本の若者を取り巻くSNSの状況も実は何かがすごく変化する契機なのかもしれません。個人の中で変化することも大事ですが、コミュニティだったり、それよりも大きな社会状況との兼ね合いで影響を受けるものだということを改めて感じました。
キャンベル 2週間余りの滞在でしたが、朝から晩まで、とにかくたくさんの人と話しました。本当に信号待ちをしている間とか、エレベーターを待っている間に話しかけてきて、私が日本から来たということがわかると、「来てくれてありがとう」と手を取って言うんですね。そして自分の精神状態を堰を切ったように打ち明けてくれるわけです。以前は精神安定剤を飲んでいることは隠すべきことだったのが、今はもうみんなでどういう薬を飲んでいるか見せ合いっこをしたりしていると。それが自分たちの武器なんだと。自分は銃器を持てないから、せめて心を穏やかにできるようにしている、だからこれは大切な薬だというふうに言うんです。
私が会ったLGBTの当事者たちは、社会の中で自分の新たな役割を見つけたり、それを拡張したんですね。自分たちが活動できる部分というものが、悲しいことに、不幸の中にあったわけです。
〈社会〉をサポートする視点
松髙 少し話が離れてしまうかもしれないんですけども、カウンセリングではそうしたことを大事にしたいと思っているんです。「自分はこうなんだ」と言えることが本当に重要で、それができないことの大変さというか、ただそこにはできない理由が、しない方が安全かもしれないとか、そういうこともあって…。本当に一概に何がいいとは言えないと思うのですが、一人一人、その人が置かれた状況の中で、何がその人の意思決定において大事なのかというところを丁寧に聴いていくしかないのかなというふうに思います。
キャンベル 松髙先生たちがなさっていることは、とても尊い、重要なお仕事ですし、一対一、一人一人と向き合ってされているわけですよね。おっしゃる通り、そこにはそのときの状況やそれぞれの判断があると思います。ただ、我々がやっぱり心がけるべきことは、そこにいない人たち——それはその人の保護者であったり、同僚であったり、近所の人たちであったりするわけですが、そうした周囲の人たちが当事者と繫がりを持っているということを自覚することから始めないといけないと思うんです。
特にここ最近は『虹クロ』という番組に出て、そのフィードバックを聞いていると、とても遠いところにいるはずの人たちの気づきを感じる機会が多いんですね。「遠いところ」というのは、自分の息子や娘は当事者ではない、自分は関係ないと思っている人たちのことです。そうした人から「ああ、私に気を遣わせたくないから子どもは大事なことを言っていないんだ」という声が届く。「そう考えると、俺も仕事を選ぶときにこういうことがあって失敗した」とか「私が子育てしているときに職場でこういうことがあった」と、一見全然違うトピックに見えるものが実は繫がっていて、「ああ、そういう立場や状況に、彼ら彼女たちがいるんだ」と気づく。僕はそれは大事な、とても大きなスイッチだと思うんですね。そのスイッチをやっぱり大切にしないといけない。
これは、カウンセリングの場では異なる話になるのかもしれませんけれども、そのスイッチに対してもっと私たちが自覚的になってやっていかないと。そうすれば、みんなが息をつきやすくなるというか、空気がおいしくなるというか、そういうことがきっとあると思うんです。

松髙 本当に関係ないと思っていた人たちがそういうことに気づいて、それがうねりとなって社会の制度を動かしていって、その中で当事者の人も、そうではない周りの人も変わって、認識がしやすくなって息がしやすくなることは確かにありますよね。
みんながハッピーになる、と言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、ハッピーになる人たちが増えるのは確かだと思うので、私たち心理職の人間は個別の関わりを重視してはいますが、一方でキャンベルさんがおっしゃるようなマクロの視点を大事にしなければと思います。
キャンベル もう一つ、私の知人や友人に当事者で子育てをしている人たちがいるんです。本当にその人たちは毎日大変さを嚙み締めながら覚悟を持って育てているんですが、一方でその子どもたちは、この日本社会の中で、やっぱりどこか影のようなものの中に生きているんですね。そこには抜けるような青空はないんです。例えば、自分にはお父さんが二人いる。お母さんが二人いる。どうして二人は結婚できないのか。こうしたことは子どもの福祉に本当に直結するんですよ。
僕の周りには、わりと立場も恵まれて、それなりにサポートがあって、お祖父さんやお祖母さんの理解やスタッフの助けがあったり、あるいはしっかりそういうことがわかっている学校に子どもを通わせるような場所に住んでいる人たちがいます。そうした人からはそこまで悲壮な話は聞きませんけれども、特に地方にいる人たちは容易なことではないんですね。自分たちで安全なバブルをつくらないと、子どもを守ることができません。それはいじめもそうだし、教育環境や部活のこともあります。彼彼女らから話を聞くと、これはやっぱりマクロで物事を考えないといけないなと思います。
そうしたマクロな視点を、心理の先生たちがどのように一対一の臨床現場の中に織り込んで、生かせるかということが重要な点であるように思いますね。
松髙 最近ずっと「家族」にどういうサポートができるのかという研究をしたいと考えていたので、本当に今の話と繫がる気がしています。私は広島で活動していて、子育て支援の関係者と話をする機会がありますが、やっぱり同性のカップルに会ったことがないという人がほとんどだったりするんです。そういう人たちにも認識を持ってもらえるように、何かしていかなければいけないと思っています。
キャンベル あと、子育てに関することで言うと、ひとり親世帯を含めて貧困の問題がありますよね。例えば、貧困について国や自治体からサポートを受けることは恥ずかしいことでも何も悪いことでもないんですけども、セクシュアリティについては、特に子育てということになると、自分たち親自身のことはいいけれども、特に子どものことになると、さまざまなハードルがすごく高くなってしまうことは当然あると思っています。
松髙 もうセクシュアリティのことだけではなくて、私たちの中にある多様性やさまざまなニーズをもっと明らかにしていかないといけないですね。
キャンベル いわゆるセクシュアリティのことでマイノリティになっている人たちの中には「放っておいてよ」と言う人たちもいますし、決して一枚岩ではないわけです。そういうことはあるわけですけれども、ただ、やっぱり先ほど言ったように、それでも「聴ききる」ことはできます。自分の状況を整理したり、自分の周りがどういうふうに実際になっているかをしっかり把握すること。安心して自分はこうだと言えるような、まず小さい空間をつくっていくということが大事ですね。

松髙 そうですね。市井の中に自分がいて、どうやってコミュニティをつくっていくか。本当はもっとお話をお聴きしたいんですが、残念ながらお時間が来てしまったようです…。
キャンベル ありがとうございます。ちょうど日が暮れたところで終わりですね(笑)。
ロバート キャンベル
ニューヨーク市出身。日本文学研究者。専門は江戸・明治時代の文学、特に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などに関する研究を行う。早稲田大学特命教授、早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)顧問、国文学研究資料館前館長、東京大学名誉教授。主な編著に『戦争語彙集』(岩波書店)、『よむうつわ』(淡交社)、『日本古典と感染症』(角川ソフィア文庫、編)、『井上陽水英訳詞集』(講談社)、『東京百年物語』(岩波文庫)等がある。
松髙由佳(まつたか・ゆか)
2007年広島大学大学院教育学研究科人間科学専攻博士課程後期修了。博士(心理学)。臨床心理士・公認心理師。現在、県立広島大学広島キャンパス学生相談室長、准教授。広島県、広島市HIV派遣カウンセラーとしても活動中。















