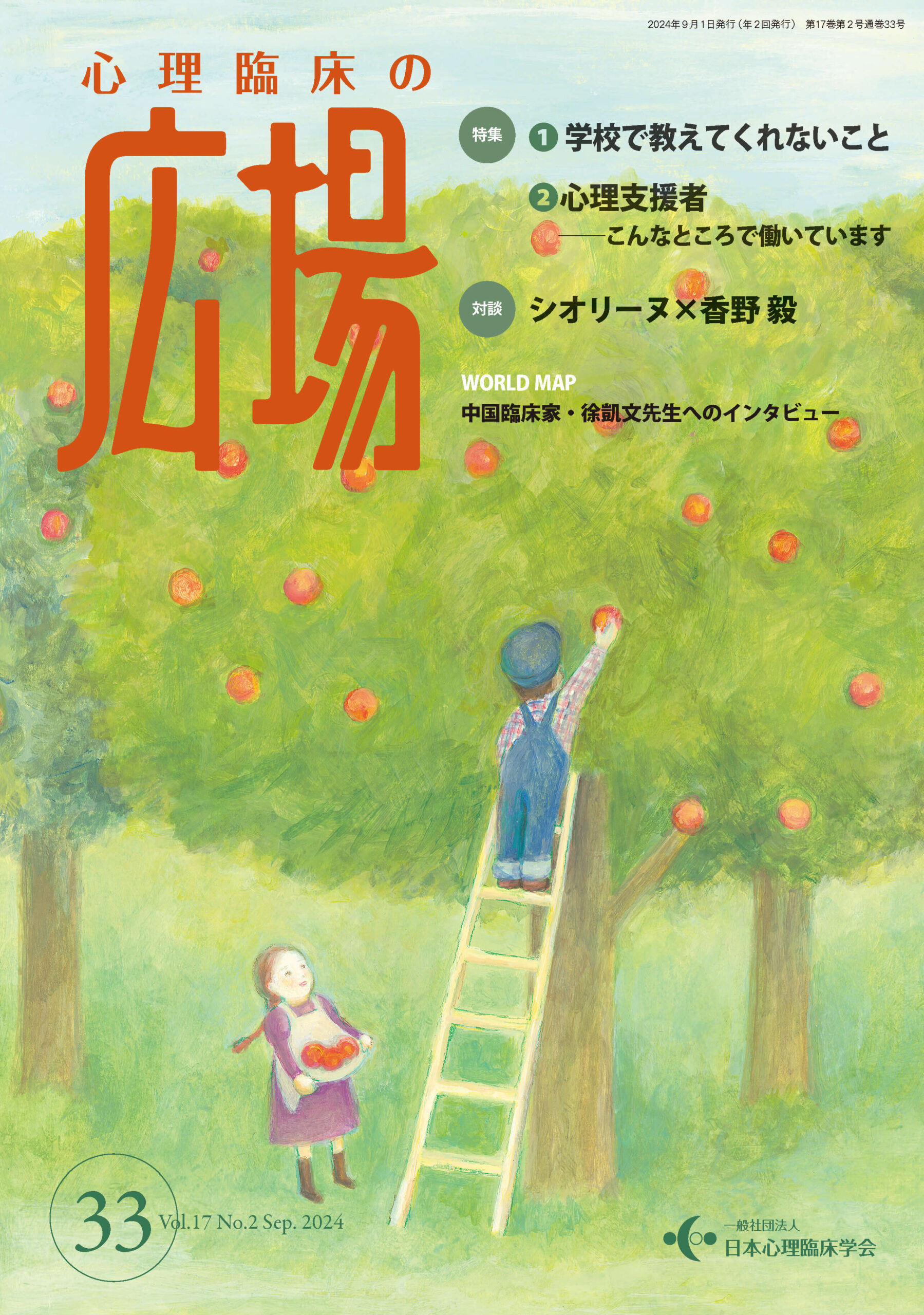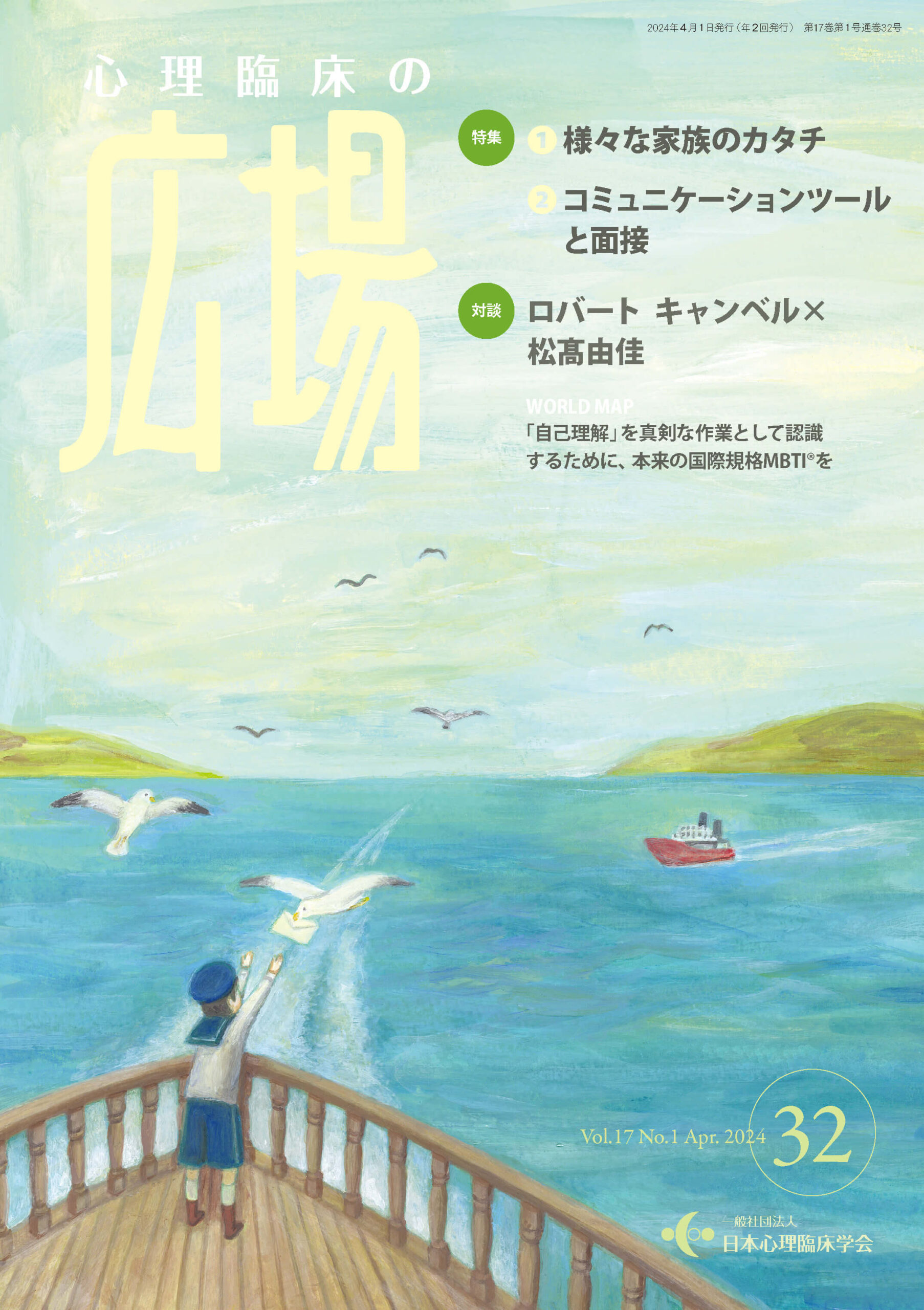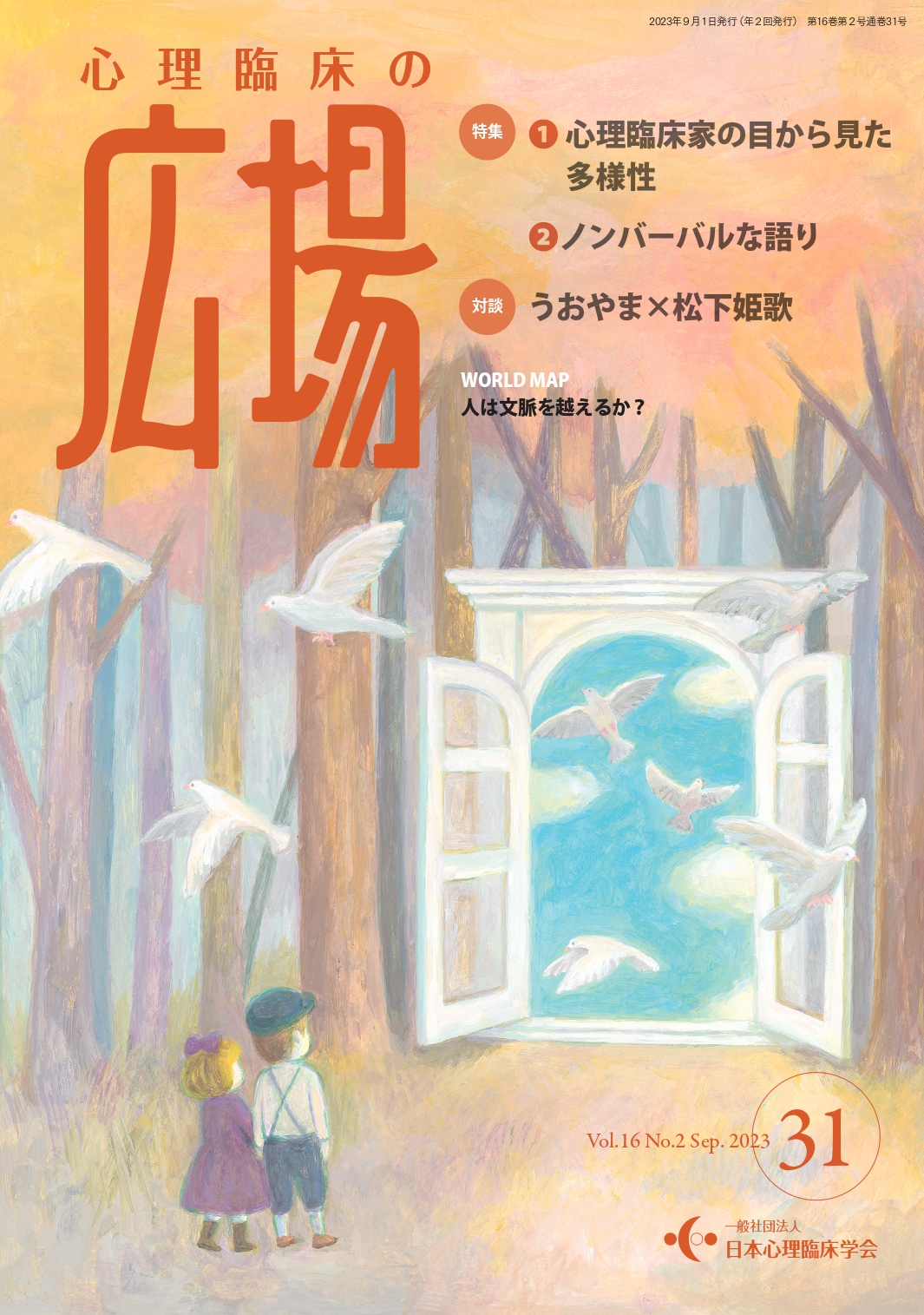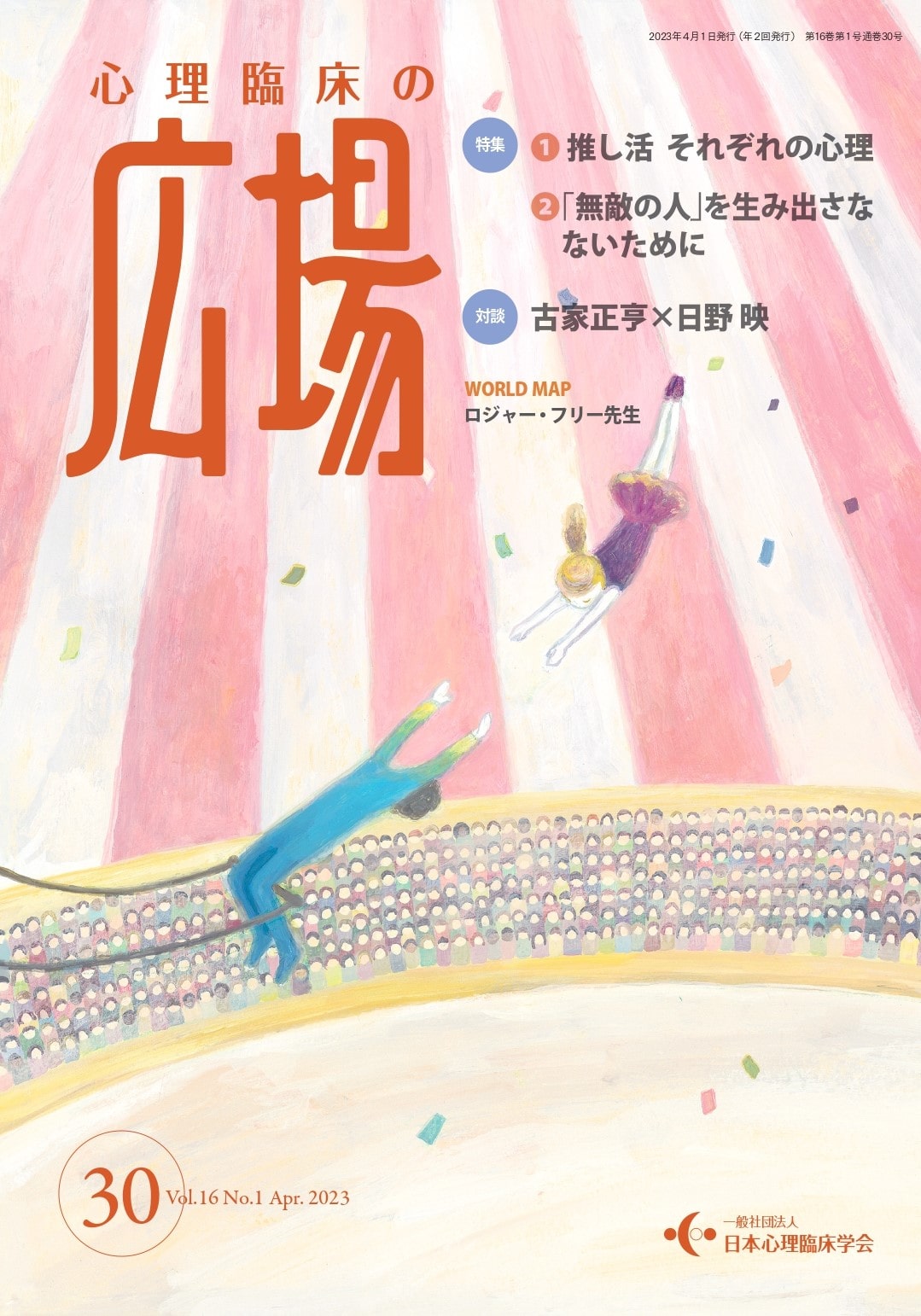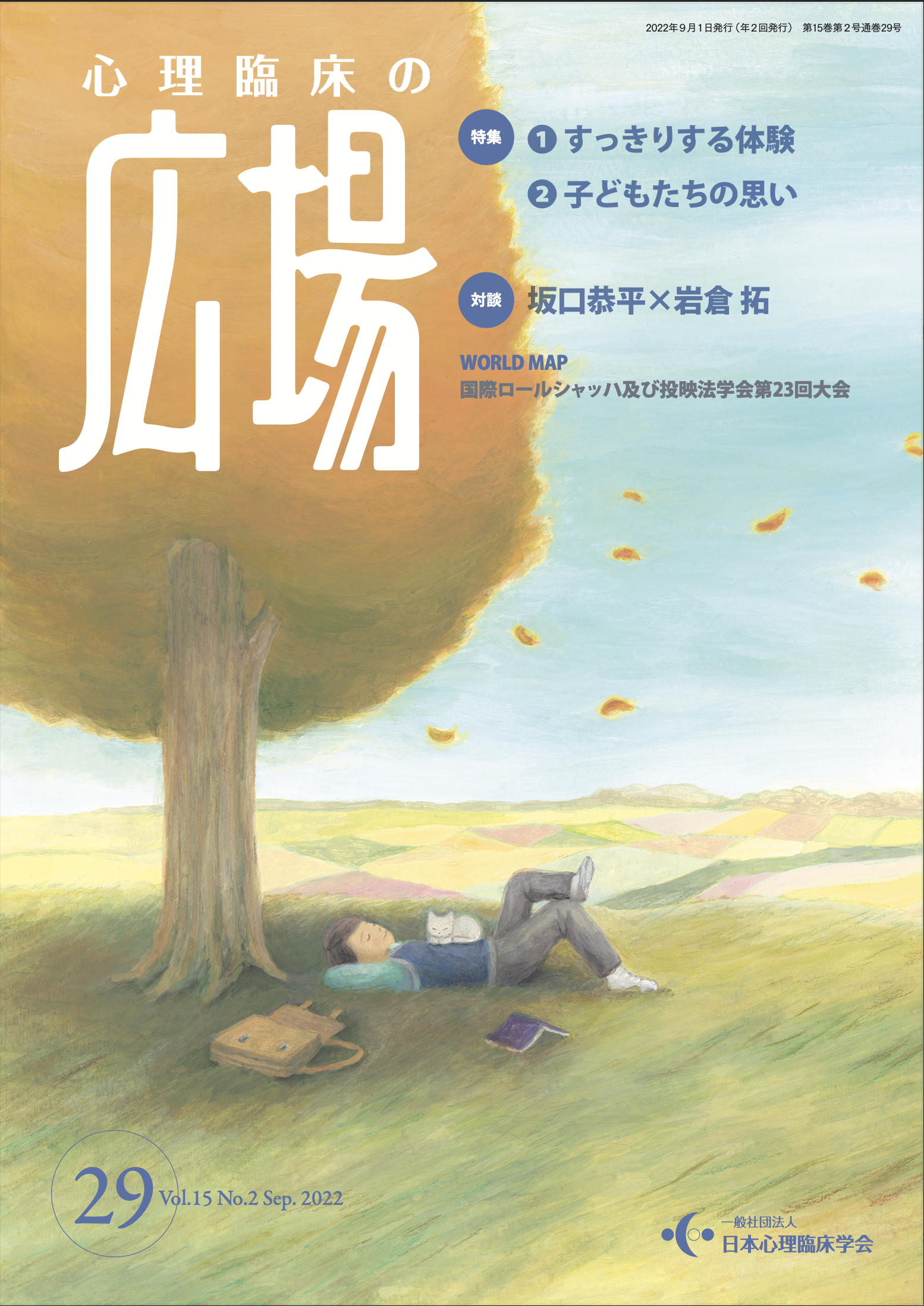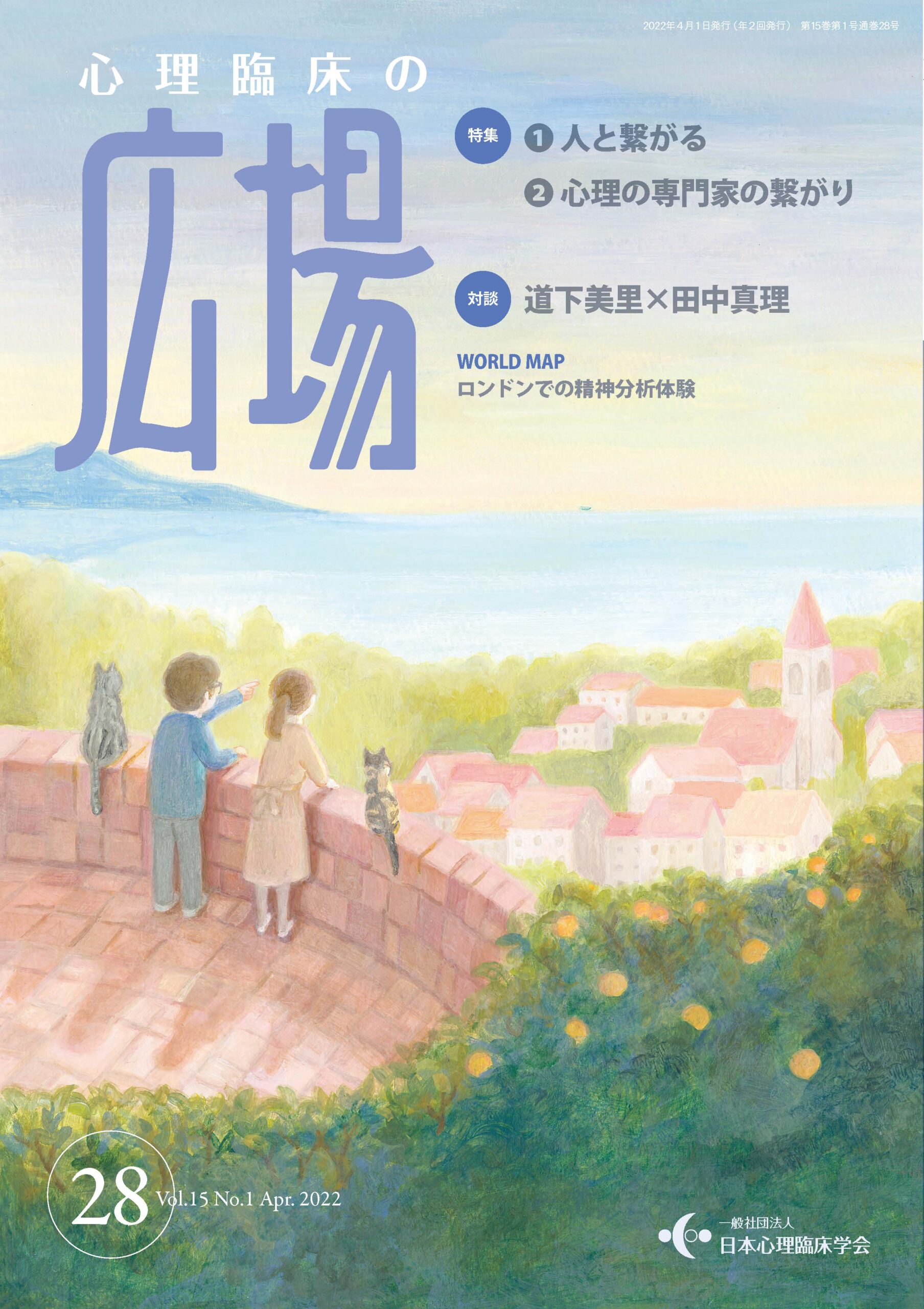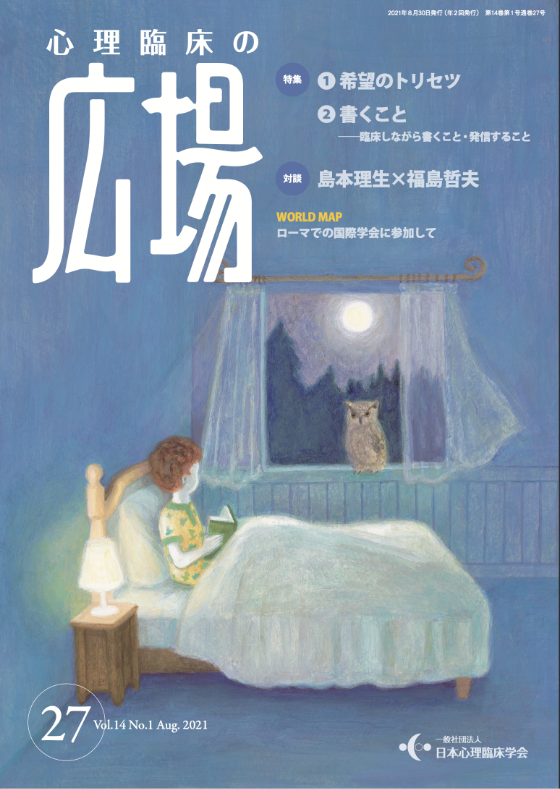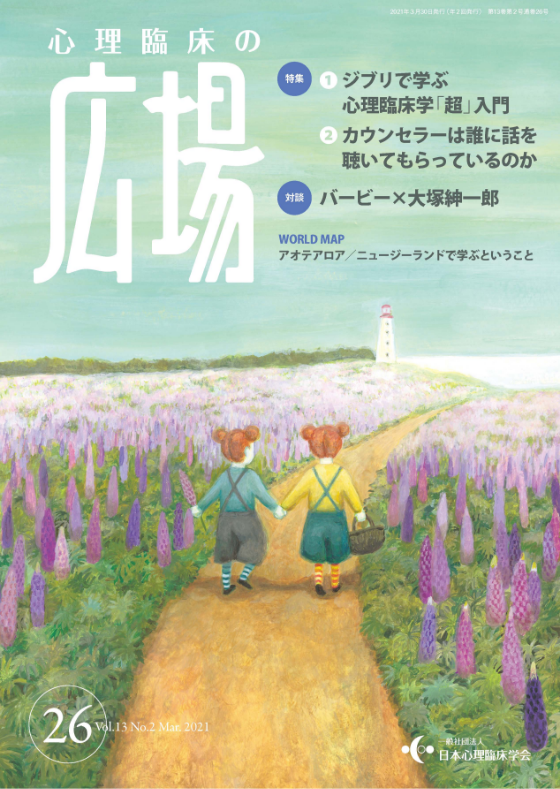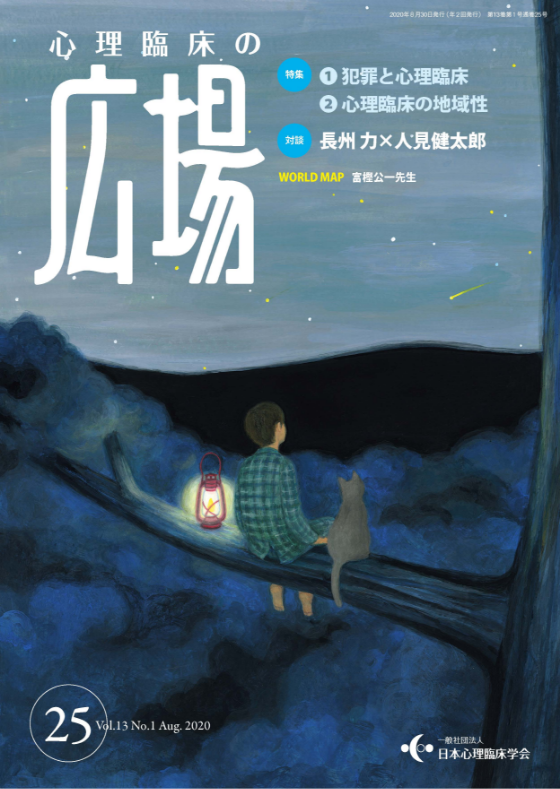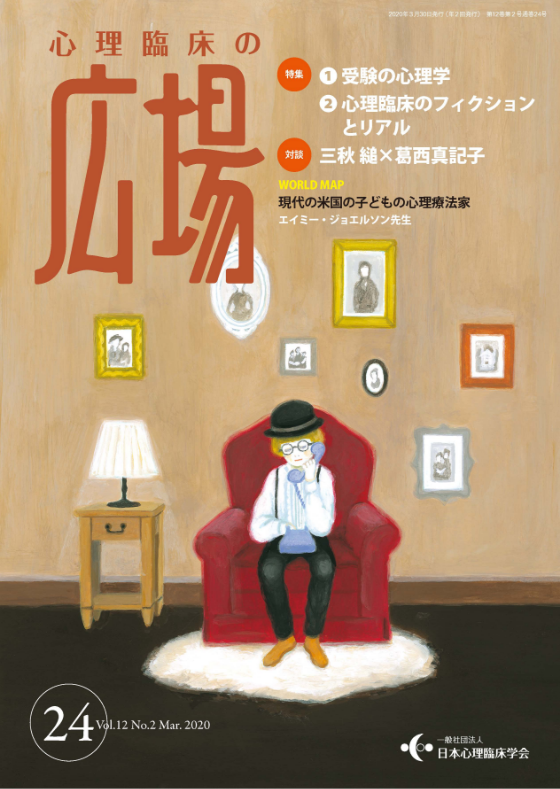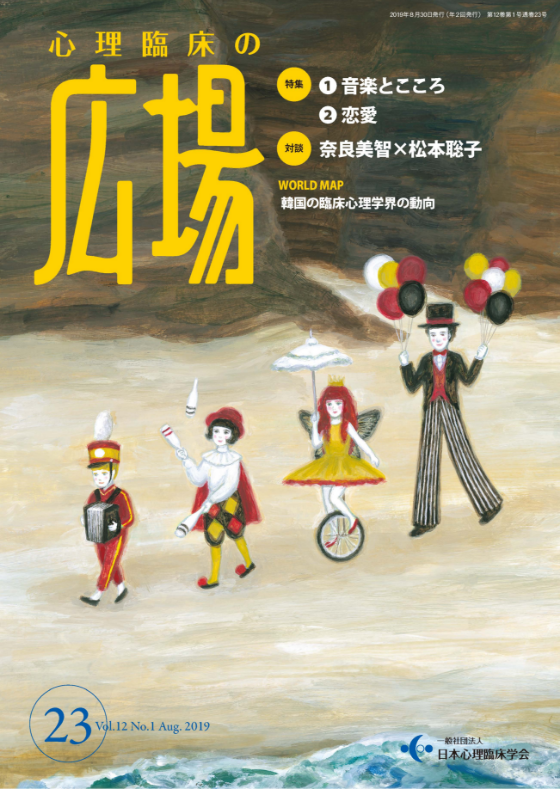私に何ができるのだろうか…
保育の世界に足を踏み入れたのは、大学4年生の4月でした。当時、私は臨床心理士になるべく学びつつ、不登校や発達障害の小中学生と関わる機会があり、「もっと早く支援があればよかったのに」とか「この子たちの幼児期はどんな感じだったんだろう」ということを考えていました。そのようなときに、ご縁あって幼稚園での心理士見習いとして、有償でのインターンシップをさせていただけることになりました。保育の手伝いをするのではなく、子どもたちの様子を見た上で保育者と話をする、コンサルテーションもどきのような任務までいただきました。いざ現場に入ってみると、園の先生方が一人一人の子どもたちと真剣に向き合い、一生懸命に関わっている姿に感動する一方、そこで自分が何をできるのかがわかりませんでした。保育科の学生が来る方がよいのではないかとも思いましたが、先生方の姿に何度も感銘を受ける中で、少しでもお役に立ちたいという想いが強くなっていきました。
その後、心理士養成課程の大学院へ進み、試験を受けて保育士の資格を取得した上で、現在も心理士として保育現場で働いています。また、保育者養成にも携わるようになりました。最初にお世話になった園とは現在もご縁が続いており、何かしら役に立てるようになれたようです。今回は、大学4年生の私の悩みに立ち返り、保育者と保育現場で働く心理士の違いから、保育現場で心理職ができることを考えてみます。
子どもへの関わり方の違い
本題に入る前に、保育の仕事をする人の資格・免許について紹介します。保育の資格は少し複雑で、主に保育所で働く「保育士」資格と幼稚園で働く「幼稚園教諭」免許状があります。また、それら2つを持って認定こども園で働く人は「保育教諭」と呼ばれます。しばしばこれらを区別せず全て「保育士」と呼ばれたりしますが、実は資格・免許や働いている場所によって呼び方が違うのです。保育の世界では、これらを総称して「保育者」と言います。名前だけでなく細かな違いも色々ありますが、今回はその区別はせずに、「保育者」と乳幼児と関わる心理職の仕事を見比べてみます。
まず、保育者の仕事である保育には「養護care」と「教育education」の2つの側面があります。養護とは、子どもの心身を安心・安全に守るような関わりのことです。保育における教育では、お勉強というよりも遊びや生活の中で主体的な経験を通しての学びが重視されます。実際の保育では、一緒に歌を歌ったり、鬼ごっこをしたり、食事をしたり、トイレに行ったりと、日々の遊びや生活を共にしていきます。また、多くの子どもたちが園に来ているので、子どもたちと集団の中で関わっていくことになります。保護者とは、送迎時や連絡帳を通して、日々情報を共有していきます。
一方、心理職については、私自身が実践しているキンダーカウンセリング(スクールカウンセリングの幼稚園版のようなものですが、保育現場ならではの部分もあります)を例に挙げると、通常月1回程度の頻度で園を訪れて、子どもの保育中の様子を観察し、その後に保育者とコンサルテーションを行い、子ども理解や援助の仕方について話し合います。保護者と話すのは、子どもの発達や子育てについて、何かしらの悩みがあって「相談」に来られたときが中心です。園外では(時には園内でも)、心理職が幼児と一対一でプレイセラピーや発達検査を行うこともあります。1回1時間程度、継続的に行うとしても週1回程度の頻度であり、保育者と比べてとても限定的な関わりです。
保育者は子どもたちと毎日の生活の中で関わっていく一方、心理職はよりピンポイントな「心理」に特化した関わりを行っていると言えそうです。また、保育は子どもたちの「集団」で行われますが、心理職の場合は一人の子どもを観察したり、一対一で関わったりと、より「個人」に注目しています。
学びと専門性の違い
このような違いは、学んできた内容や専門性の違いと関連しています。保育者の学びは多岐に渡っており、実践については保育のいわゆる5領域(健康、人間関係、環境、言葉、表現)のそれぞれについて「指導法」を学びます。例えば表現に関する科目では、ピアノを弾いたり、歌を歌ったり、絵を描いたりをします。また、座学も多様で「保育や教育」に関する理論や制度はもちろんのこと、「福祉」や「健康」、「法律」等についても学びます。「心理学」もその中の一つで、主に乳幼児の発達について学びます。保育科の学生は、保育士と幼稚園教諭の2資格(免許)の取得を目指すことになりますが、最短だと高校卒業後に短大に通って2年間で両資格を取得し、働くことが可能です。
一方、臨床心理士や公認心理師は、基本的には大学院卒業が前提となっており、高校卒業後6年以上と、保育者と比べて資格取得までに時間が掛かります。学習内容としては、心理臨床に関する様々な分野や実践について学んでいきます。子どもの領域で言えば、プレイセラピーやカウンセリング・心理療法や心理検査・発達検査について学んでいきます。ただ、心理士(師)の資格取得を目指す場合、乳幼児だけについて学ぶのではなく、学齢期〜高齢者まで幅広い年齢の心理や支援について学んでいきます。
比べてみると、少し大雑把な見方ではありますが、保育者は子どもに関して「幅広く」学びその中に心理学もあるのに対し、心理職の場合は心理臨床や心理学に特化して「より深く」学ぶと言えるかもしれません。
違いを活かして
このように保育者も心理職も子どもと関わる職種の一つですが、立場によって関わり方や役割は異なります。しかし、どちらも同じくらい「子どもたちのために!」という強い想いを持っているはずです。そのため、それぞれの保育者と心理職の強みを活かした連携・協働を行うことで、子どもたちの育ちを力強く支えることができます。例えば、心理職の立場から見て、発達障害やアタッチメントの問題を抱える子どもについて、「日々こういう関わりがあるとよいな」ということを考えたとしても、1週間の中で関わることができる時間は限られています。日々の関わりについては、子どもたちの日常に近い保育者の方が得意分野です。そこに、心理職の見方をお伝えすることで保育者の力になることができるはずです。
違う専門性だけど、同じ想いで。それぞれの専門性を活かして、協力して子どもたちの育ちを支えていきましょう。